船井学術賞受賞者
第24回 2024年度
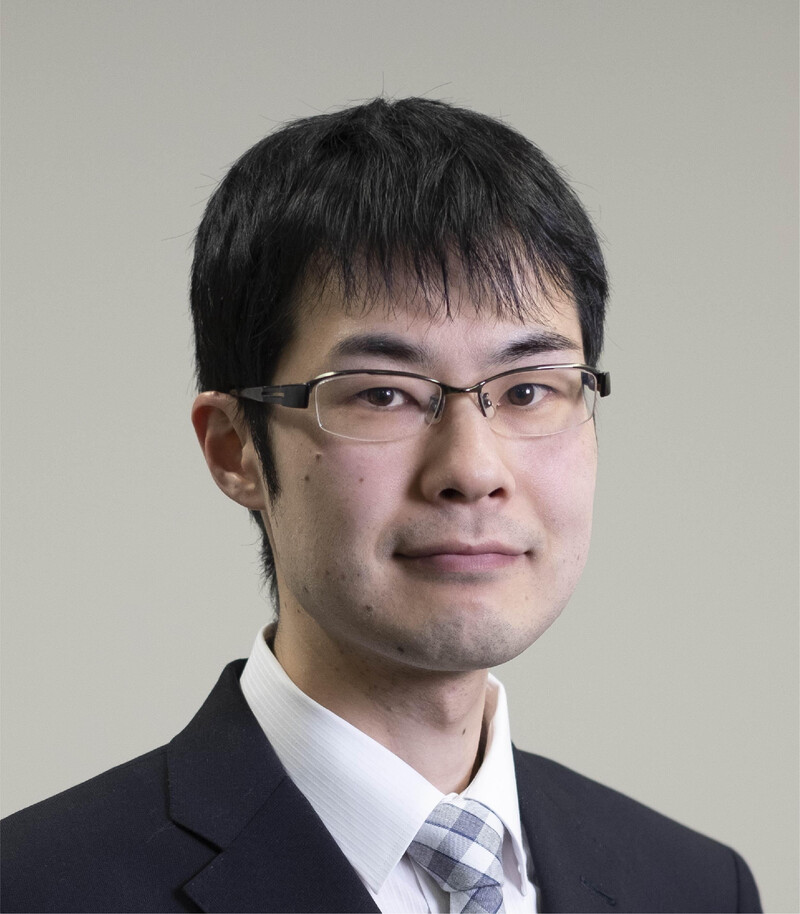 速水賢はやみさとる北海道大学准教授トポロジカル遍歴磁性体の機構解明と機能性開拓トポロジーと磁性の密接な絡み合いから生まれるトポロジカル磁性体は物性物理学における豊潤なフロンティアであり、従来の磁性体とは一線を画する多彩な物性現象の発見が相次いでいる。これらのトポロジカル磁性体は不純物や外部からの攪拌に対して堅牢であるため、その性質を利用した高速・省エネルギー・安定な動作性をもつ磁気デバイスへの応用が可能であり、次世代のスピントロニクス産業の観点からも大きな注目を集めている。速水氏は、そのようなトポロジカル磁性体の発現機構や機能性開拓を基軸とした物性理論研究を推進してきた。特に、2017 年に空間反転対称性を有する遍歴磁性体における磁気スキルミオンの微視的機構を理論的に明らかにし、研究の新しい方向性を開拓することで、2019年以降における高密度スキルミオン物質の実験観測の基盤を築くと同時に高効率情報担体としてのスキルミオンを用いたスピントロニクスへの道を切り拓いた。
速水賢はやみさとる北海道大学准教授トポロジカル遍歴磁性体の機構解明と機能性開拓トポロジーと磁性の密接な絡み合いから生まれるトポロジカル磁性体は物性物理学における豊潤なフロンティアであり、従来の磁性体とは一線を画する多彩な物性現象の発見が相次いでいる。これらのトポロジカル磁性体は不純物や外部からの攪拌に対して堅牢であるため、その性質を利用した高速・省エネルギー・安定な動作性をもつ磁気デバイスへの応用が可能であり、次世代のスピントロニクス産業の観点からも大きな注目を集めている。速水氏は、そのようなトポロジカル磁性体の発現機構や機能性開拓を基軸とした物性理論研究を推進してきた。特に、2017 年に空間反転対称性を有する遍歴磁性体における磁気スキルミオンの微視的機構を理論的に明らかにし、研究の新しい方向性を開拓することで、2019年以降における高密度スキルミオン物質の実験観測の基盤を築くと同時に高効率情報担体としてのスキルミオンを用いたスピントロニクスへの道を切り拓いた。 今泉允聡いまいずみまさあき東京大学准教授大自由度データ駆動系の数理開発とニューラルネットワーク解析深層学習・人工知能などの、データを活用して膨大なパラメータを学習させる技術が発展している。しかし、この技術を効率的に理解・制御するための数理的・基盤的な理論はまだ発展途上である。申請者は、大自由度かつデータ駆動系を記述するための基礎的な数理基盤の開発を行い、さらにそれを応用した深層学習の原理解析を推進した。具体的には、大自由度モデルの学習を高次元・無限次元空間における確率的な変動として表し、さらにそれらをデータ行列のスペクトルや物理的方程式を用いて記述することでデータに基づく学習の様子を記述した。かつそれらをニューラルネットワークの更新や予測能力の獲得の過程に応用し、深層学習や人工知能技術の原理に対して解釈を与える数理的な理論を構築した。これにより、深層学習・人工知能によるデータ固有構造の抽出や汎用的知識の獲得といった現象を数学的に発見し、今後の人工知能理論の発展に寄与した。
今泉允聡いまいずみまさあき東京大学准教授大自由度データ駆動系の数理開発とニューラルネットワーク解析深層学習・人工知能などの、データを活用して膨大なパラメータを学習させる技術が発展している。しかし、この技術を効率的に理解・制御するための数理的・基盤的な理論はまだ発展途上である。申請者は、大自由度かつデータ駆動系を記述するための基礎的な数理基盤の開発を行い、さらにそれを応用した深層学習の原理解析を推進した。具体的には、大自由度モデルの学習を高次元・無限次元空間における確率的な変動として表し、さらにそれらをデータ行列のスペクトルや物理的方程式を用いて記述することでデータに基づく学習の様子を記述した。かつそれらをニューラルネットワークの更新や予測能力の獲得の過程に応用し、深層学習や人工知能技術の原理に対して解釈を与える数理的な理論を構築した。これにより、深層学習・人工知能によるデータ固有構造の抽出や汎用的知識の獲得といった現象を数学的に発見し、今後の人工知能理論の発展に寄与した。 江崎貴裕えざきたかひろ東京大学先端科学技術研究センター特任講師ネットワーク型物流システムの基礎理論の構築多数の事業者によって運営される物流システムを統合し、一つのネットワークシステムとしてリソースを共有化することで抜本的な効率化と持続可能性の向上を目指すアイディア(フィジカル・インターネット)が物流システムの危機を救う方策として国際的に注目を集めている。こうして出来上がった複雑なネットワークの上でモノや情報のながれがどのように生じるのかを明らかにすることは、実現可能なシステムの設計指針を考える際に必須となるが、ボトムアップ的な理解を与える研究は皆無であった。応募者は、複雑ネットワーク科学の知見と渋滞学モデリングの技術を物流システムに応用し、頑強な物流ネットワークを実現するためのトポロジカルな要件および、リンク重要度の定量化、統合の際に相乗効果が得られやすいネットワーク構造の同定、数十億件の実データ解析による定量的な効果の実証といった、ネットワーク物流の理論的基礎をなす一連の成果を上げた。
江崎貴裕えざきたかひろ東京大学先端科学技術研究センター特任講師ネットワーク型物流システムの基礎理論の構築多数の事業者によって運営される物流システムを統合し、一つのネットワークシステムとしてリソースを共有化することで抜本的な効率化と持続可能性の向上を目指すアイディア(フィジカル・インターネット)が物流システムの危機を救う方策として国際的に注目を集めている。こうして出来上がった複雑なネットワークの上でモノや情報のながれがどのように生じるのかを明らかにすることは、実現可能なシステムの設計指針を考える際に必須となるが、ボトムアップ的な理解を与える研究は皆無であった。応募者は、複雑ネットワーク科学の知見と渋滞学モデリングの技術を物流システムに応用し、頑強な物流ネットワークを実現するためのトポロジカルな要件および、リンク重要度の定量化、統合の際に相乗効果が得られやすいネットワーク構造の同定、数十億件の実データ解析による定量的な効果の実証といった、ネットワーク物流の理論的基礎をなす一連の成果を上げた。 金井駿かないしゅん東北大学電気通信研究所准教授スピンダイナミクスの新概念素子応用に関する研究社会のIoT化やAIの汎用化による情報通信・計算量の急増に伴い、限られた計算・電力リソース下での高度な情報処理が必須となっている。応募者は物質をナノメートル程度へ微細化することにより顕在化する電子の電荷とスピン両方が密接に関わる諸現象を利用し、省リソースでスピンダイナミクスを制御する次の新概念素子について特筆すべき成果を上げた。【古典ビット】待機電力が不要な不揮発性磁気抵抗メモリ向け磁気トンネル接合素子の開発とその半導体メモリ並みの省動作電力書き込み方式を開発した。【確率ビット】確率論的コンピュータ向け磁気トンネル接合素子の動作速度を10万倍向上した。【量子ビット】量子コンピュータ向けスピン中心材料の最重要特性(位相緩和時間)の即時予測手法を発見した。一部成果はすでに量産化技術の核として実用に供され、現代のコンピューティングにおける頭書課題を解決する、新概念スピン素子の基盤技術・学術基盤として高く評価されている。
金井駿かないしゅん東北大学電気通信研究所准教授スピンダイナミクスの新概念素子応用に関する研究社会のIoT化やAIの汎用化による情報通信・計算量の急増に伴い、限られた計算・電力リソース下での高度な情報処理が必須となっている。応募者は物質をナノメートル程度へ微細化することにより顕在化する電子の電荷とスピン両方が密接に関わる諸現象を利用し、省リソースでスピンダイナミクスを制御する次の新概念素子について特筆すべき成果を上げた。【古典ビット】待機電力が不要な不揮発性磁気抵抗メモリ向け磁気トンネル接合素子の開発とその半導体メモリ並みの省動作電力書き込み方式を開発した。【確率ビット】確率論的コンピュータ向け磁気トンネル接合素子の動作速度を10万倍向上した。【量子ビット】量子コンピュータ向けスピン中心材料の最重要特性(位相緩和時間)の即時予測手法を発見した。一部成果はすでに量産化技術の核として実用に供され、現代のコンピューティングにおける頭書課題を解決する、新概念スピン素子の基盤技術・学術基盤として高く評価されている。 金澤直也かなざわなおや東京大学生産技術研究所准教授実空間と運動量空間のトポロジーを融合した新奇量子相の創出とスピン機能開拓欠陥の分類学や量子ホール効果の発見を契機として発展してきた「物質中のトポロジー」の概念は、物性物理学のみならず、その応用面にも大きな影響を与えてきた。応募者は、このトポロジーを実空間(スピン構造)と運動量空間(バンド構造)の両面から制御し、新しい量子相の発見やスピン機能の開拓を進めてきた。具体的には、キラル磁性体に着目した実空間トポロジカルスピン構造の設計・制御により、スキルミオンやヘッジホッグ格子などのナノ磁気粒子を実現し、巨大トポロジカルホール効果や高効率熱電変換など多彩な創発電磁場現象を解明してスピントロニクス応用への基盤を築いた。さらに、運動量空間(バンド構造)のトポロジーとしてZak位相に注目し、従来のトポロジカル絶縁体とは異なる新たな表面量子相を発見した。特に、ありふれた元素からなる化合物FeSiでは、界面エンジニアリングによって2次元強磁性や巨大スピン軌道結合効果を室温かつ大気中で実現し、磁化の電気的制御や高次非線形伝導特性を含む先進的なスピン機能を実証した。現在は、これら実空間と運動量空間のトポロジーを融合し、次世代の省電力磁気メモリや非従来型コンピューティングへと繋がる基盤技術を構築している。
金澤直也かなざわなおや東京大学生産技術研究所准教授実空間と運動量空間のトポロジーを融合した新奇量子相の創出とスピン機能開拓欠陥の分類学や量子ホール効果の発見を契機として発展してきた「物質中のトポロジー」の概念は、物性物理学のみならず、その応用面にも大きな影響を与えてきた。応募者は、このトポロジーを実空間(スピン構造)と運動量空間(バンド構造)の両面から制御し、新しい量子相の発見やスピン機能の開拓を進めてきた。具体的には、キラル磁性体に着目した実空間トポロジカルスピン構造の設計・制御により、スキルミオンやヘッジホッグ格子などのナノ磁気粒子を実現し、巨大トポロジカルホール効果や高効率熱電変換など多彩な創発電磁場現象を解明してスピントロニクス応用への基盤を築いた。さらに、運動量空間(バンド構造)のトポロジーとしてZak位相に注目し、従来のトポロジカル絶縁体とは異なる新たな表面量子相を発見した。特に、ありふれた元素からなる化合物FeSiでは、界面エンジニアリングによって2次元強磁性や巨大スピン軌道結合効果を室温かつ大気中で実現し、磁化の電気的制御や高次非線形伝導特性を含む先進的なスピン機能を実証した。現在は、これら実空間と運動量空間のトポロジーを融合し、次世代の省電力磁気メモリや非従来型コンピューティングへと繋がる基盤技術を構築している。 関根智仁せきねともひと山形大学大学院有機材料システム研究科准教授有機複合材料の精密機能化による高性能デジタルスキンデバイス技術の開拓候補者は、これまでヒトの触覚機能を高度に再現できるインプランタブル(埋め込み可能)なウェアラブル触覚センサである「デジタルスキンデバイス」を独自の有機材料合成から実現した。これらの機能化されたセンサ群をワンチップ上に統合し、マルチモーダル化を基軸とするAI自動認識機構との一体化によって、高性能化・高環境安定化・広域システム化を全担保したやわらかくしなやかな高精度触覚センサを実現した。本成果は学術分野以外にも国際的な産業応用を見越したプロトタイプ試作にも展開されており、世界的にも大きなインパクトを与えた。また、関連成果は数々のトップ国際論文誌や国際会議などで発表し、国内外で著名な賞も受賞してきた。
関根智仁せきねともひと山形大学大学院有機材料システム研究科准教授有機複合材料の精密機能化による高性能デジタルスキンデバイス技術の開拓候補者は、これまでヒトの触覚機能を高度に再現できるインプランタブル(埋め込み可能)なウェアラブル触覚センサである「デジタルスキンデバイス」を独自の有機材料合成から実現した。これらの機能化されたセンサ群をワンチップ上に統合し、マルチモーダル化を基軸とするAI自動認識機構との一体化によって、高性能化・高環境安定化・広域システム化を全担保したやわらかくしなやかな高精度触覚センサを実現した。本成果は学術分野以外にも国際的な産業応用を見越したプロトタイプ試作にも展開されており、世界的にも大きなインパクトを与えた。また、関連成果は数々のトップ国際論文誌や国際会議などで発表し、国内外で著名な賞も受賞してきた。
第23回 2023年度
- 吉田悠一よしだゆういち国立情報学研究所教授アルゴリズムの平均感度解析の創始と発展アルゴリズムを用いた意思決定と知識発見では、入力データに対するノイズの影響で出力が不安定になることが多い。この不安定性は、資源配分のコスト増、ユーザーの信頼の毀損、安全性、結果の再現性の如などの問題を引き起こす。応募者は、この問題に対処するため「平均感度」という概念を提唱し、アルゴリズムの解の安定性を数理的に分析することを可能にした。次に、基本的なグラフの問題や動的計画法で解く問題に対して平均感度と近似性能のトレードオフを理論的に明らかにした。平均感度は他のアルゴリズム分野とも関連があり、これらの結果はそれらの分野に対しても新しい結果を与えている。さらに、決定木学習のような実用的に用いられる問題に対して、平均感度の小さいアルゴリズムを提案し、その有用性の実証も行った。このように応募者は、アルゴリズムの不安定さから生じる問題を解決し、アルゴリズム分野の発展に貢献している。
 五十部孝典いそべたかのり兵庫県立大学 大学院 情報科学研究科教授超高性能暗号の設計と実社会展開暗号技術は情報セキュリティの基盤技術である。応募者は「IoT用」や「Beyond 5G用」など実装や安全性要求の極めて厳しいアプリケーションに向けたの超高性能暗号を世界に先駆けて開発した。
五十部孝典いそべたかのり兵庫県立大学 大学院 情報科学研究科教授超高性能暗号の設計と実社会展開暗号技術は情報セキュリティの基盤技術である。応募者は「IoT用」や「Beyond 5G用」など実装や安全性要求の極めて厳しいアプリケーションに向けたの超高性能暗号を世界に先駆けて開発した。
IoT機器向けの暗号としては、低回路規模、低消費電力、低遅延性能において世界一の性能を達成した暗号を設計し、ハードウェア資源の乏しいIoTでの強固なセキュリティ確保を可能とした。
B5G向けの暗号としては、要件である100Gbps超のスループットと量子計算機に対する安全性の両立を世界で初めて達成した暗号Roccaを開発した。
これらの暗号の設計理論や安全性評価に関する論文は、暗号分野のトップ会議・論文誌に50本以上採録されている。また、国内外で数多くの著名な学術賞や論文賞を受賞しており、当該学術分野を世界をリードしている。
学術成果のみではなく、開発した暗号の標準化やOSS化も企業と連携して進めており、技術の社会実装にも貢献している。国産での暗号開発は経済安全性保証の観点でも重要であり、我が国の安心安全な社会の実現に大きく寄与している。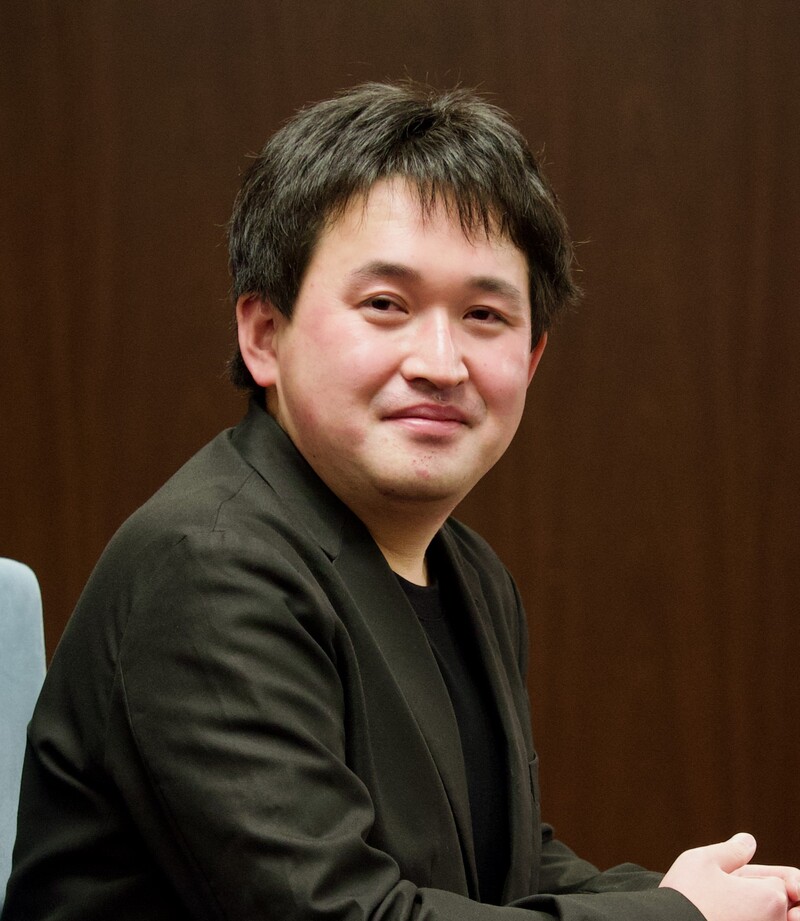 金子健太郎かねこけんたろう立命館大学 総合科学技術研究機構教授新しい酸化物半導体の開拓とパワー半導体応用電力機器のエネルギー高効率化のキーとなる超ワイドバンドギャップ半導体(UWBG)が注目されている。金子氏は酸化物UWBGにおける困難な課題の一つであるp型伝導の実現に取り組んできた。p型伝導が困難である酸化ガリウムにおいて、酸化イリジウムおよび酸化イリジウムガリウムという新しいp型半導体の提言とその薄膜合成、およびp型伝導に関する基礎的な研究を行ってきた。一方で、このようなヘテロ接合構造よりも、同じ材料でのpnホモ接合型の実現が社会実装において重要であると考えた。そこでp型とn型の両伝導制御が理論的に予測されていたルチル構造二酸化ゲルマニウムに着目し、薄膜合成が困難な材料であったが、低結晶性領域を含みながらも薄膜の合成に成功し、さらに混晶作製による新しい半導体混晶の提言も行った。これらの成果はUWBG酸化物のp型伝導という新しいエレクトロニクス分野において大きく貢献した。
金子健太郎かねこけんたろう立命館大学 総合科学技術研究機構教授新しい酸化物半導体の開拓とパワー半導体応用電力機器のエネルギー高効率化のキーとなる超ワイドバンドギャップ半導体(UWBG)が注目されている。金子氏は酸化物UWBGにおける困難な課題の一つであるp型伝導の実現に取り組んできた。p型伝導が困難である酸化ガリウムにおいて、酸化イリジウムおよび酸化イリジウムガリウムという新しいp型半導体の提言とその薄膜合成、およびp型伝導に関する基礎的な研究を行ってきた。一方で、このようなヘテロ接合構造よりも、同じ材料でのpnホモ接合型の実現が社会実装において重要であると考えた。そこでp型とn型の両伝導制御が理論的に予測されていたルチル構造二酸化ゲルマニウムに着目し、薄膜合成が困難な材料であったが、低結晶性領域を含みながらも薄膜の合成に成功し、さらに混晶作製による新しい半導体混晶の提言も行った。これらの成果はUWBG酸化物のp型伝導という新しいエレクトロニクス分野において大きく貢献した。 川上恵里加かわかみえりか理化学研究所理研白眉研究チームリーダー真空中に浮いている電子の量子状態の読み出しと量子コンピュータ実現への展開応募者は電子を量子ビットとして用い、量子コンピュータを実現するための研究を開拓してきた。最近では、
川上恵里加かわかみえりか理化学研究所理研白眉研究チームリーダー真空中に浮いている電子の量子状態の読み出しと量子コンピュータ実現への展開応募者は電子を量子ビットとして用い、量子コンピュータを実現するための研究を開拓してきた。最近では、
液体ヘリウム表面上の真空中に浮いている電子の量子状態を読み出す新たな方法「鏡像電荷検出」を理論的に
提案し、また実験的に実証した。真空中の電子は、半導体などの固体中の電子と異なり、結晶の欠陥や不純物
の影響を受けないため、より高い信頼度を持つ量子ビットの実現が期待される。しかし、電子が真空中に存在
するため、電子へのアクセスが難しく量子状態の読み出しは困難であり、これまで研究が進展してこなかった。
応募者はこの新たな読み出し方法を基盤に、真空中の電子を量子ビットとして集積化し、量子コンピュータを
実現する方法を理論的に提案し、真空中の電子を量子コンピューティングに利用する道を切り開いた。
また、この新たな読み出し方法を用いて、高エネルギー準位への励起や量子状態の緩和時間を測定し、
液体ヘリウム表面上の電子の物性の解明にも貢献した。 月﨑竜童つきざきりゅうどう宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所准教授小惑星探査機はやぶさ2を実現したマイクロ波イオンエンジンの研究プラズマを電磁気的に加速するイオンエンジンは、従来の化学推進機と比較し燃料は10分の1程度で済む反面、低推力で長時間運転が要求されることが課題だった。特に、小惑星探査機「はやぶさ2」の主推進機のマイクロ波イオンエンジンは、推進性能により軌道が律速されるなど、研究開始時点ではミッションの実
月﨑竜童つきざきりゅうどう宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所准教授小惑星探査機はやぶさ2を実現したマイクロ波イオンエンジンの研究プラズマを電磁気的に加速するイオンエンジンは、従来の化学推進機と比較し燃料は10分の1程度で済む反面、低推力で長時間運転が要求されることが課題だった。特に、小惑星探査機「はやぶさ2」の主推進機のマイクロ波イオンエンジンは、推進性能により軌道が律速されるなど、研究開始時点ではミッションの実
現が困難な状況だった。この課題解決のため、絶縁体でマイクロ波電磁場を乱さない光ファイバに着眼し、レーザを組み合わせたプラズマ診断手法を確立した。この内部診断により、高電圧に印加された運転中のエンジンの内部のプラズマ状態を非破壊で精密に解明し、設計に活かすことで推力が50%向上した。さらに宇宙
運用を通じ、地上の研究開発では特定不可能な宇宙空間特有の寿命律速要因を発見した。この成果は、小惑星Ryuguのサンプルリターンを実現しただけでなく、さらに複数の小惑星を探査する拡張ミッションを実現し、設計寿命を超え、現在も深宇宙航行中である。 横矢直人よこやなおと東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授多次元高分解能衛星画像解析のためのデータ融合技術の研究横矢氏は,異なる衛星で得られる画像データを統合的に解析することで,地表の詳細な特性や変化を把握するデータ融合技術を創出した.物理現象の知見を数理最適化や機械学習と組み合わせることで,教示データ不足の問題を克服し,画像の取得と理解の両面において,時間・空間・波長の分解能について既存技術の限界を超える新機軸を確立した.具体的には,高空間・高波長分解能画像の取得を実現する画像再構成や,高空間・高時間分解能での土地被覆地図作成・変化認識に関する先駆的成果を挙げてきた.これらの技術を災害把握や環境評価に応用し,社会問題の解決に資する研究に活発に取り組んでいる.さらに,国際的なリーダーシップを発揮して,データ融合に基づく画像解析のためのベンチマークデータを,海外の研究機関や民間企業と協力して数多く整備してきたことも特筆すべき貢献である.上記成果は分野のトップ論文誌・国際会議で発表された他,国際的に著名な賞を受賞するなど高く評価されている.
横矢直人よこやなおと東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授多次元高分解能衛星画像解析のためのデータ融合技術の研究横矢氏は,異なる衛星で得られる画像データを統合的に解析することで,地表の詳細な特性や変化を把握するデータ融合技術を創出した.物理現象の知見を数理最適化や機械学習と組み合わせることで,教示データ不足の問題を克服し,画像の取得と理解の両面において,時間・空間・波長の分解能について既存技術の限界を超える新機軸を確立した.具体的には,高空間・高波長分解能画像の取得を実現する画像再構成や,高空間・高時間分解能での土地被覆地図作成・変化認識に関する先駆的成果を挙げてきた.これらの技術を災害把握や環境評価に応用し,社会問題の解決に資する研究に活発に取り組んでいる.さらに,国際的なリーダーシップを発揮して,データ融合に基づく画像解析のためのベンチマークデータを,海外の研究機関や民間企業と協力して数多く整備してきたことも特筆すべき貢献である.上記成果は分野のトップ論文誌・国際会議で発表された他,国際的に著名な賞を受賞するなど高く評価されている.
第22回 2022年度
 荒瀬由紀あらせゆき大阪大学大学院情報科学研究科准教授言い換え表現に基づく言語の意味理解推進と言語教育応用に関する研究人間は高度な言語能力を有しており、同一の事象やアイデアであっても多様な言語表現で表すことができる。このような言い換え表現をコンピュータで自動認識し、意味の一致する箇所を明らかにすることで、人間が文を解釈・理解する仕組みを解明する重要な手がかりを得られると期待されている。一方、コンピュータで文を自動的に言い換える技術は、その場に適した表現に自動変換することで、人工知能と人間、また人間同士のコミュニケーションの円滑化に貢献する。さらには非母語話者や学習者に適した平易な文を自動生成することで、言語理解を支援するシステムも実現できる。荒瀬氏はこのような言い換え表現認識・生成研究に網羅的に取り組んでおり、国際的に顕著な成果をあげてきた。またこれら技術を応用し、英語教育学の専門家らと異分野協働することで英語教育支援を行うシステムを開発しており、社会的にも意義深い研究に活発に取り組んでいる。
荒瀬由紀あらせゆき大阪大学大学院情報科学研究科准教授言い換え表現に基づく言語の意味理解推進と言語教育応用に関する研究人間は高度な言語能力を有しており、同一の事象やアイデアであっても多様な言語表現で表すことができる。このような言い換え表現をコンピュータで自動認識し、意味の一致する箇所を明らかにすることで、人間が文を解釈・理解する仕組みを解明する重要な手がかりを得られると期待されている。一方、コンピュータで文を自動的に言い換える技術は、その場に適した表現に自動変換することで、人工知能と人間、また人間同士のコミュニケーションの円滑化に貢献する。さらには非母語話者や学習者に適した平易な文を自動生成することで、言語理解を支援するシステムも実現できる。荒瀬氏はこのような言い換え表現認識・生成研究に網羅的に取り組んでおり、国際的に顕著な成果をあげてきた。またこれら技術を応用し、英語教育学の専門家らと異分野協働することで英語教育支援を行うシステムを開発しており、社会的にも意義深い研究に活発に取り組んでいる。 井手上敏也いでうえとしや東京大学物性研究所准教授ナノ物質における対称性制御と量子整流現象の開拓ファンデルワールス結晶劈開試料に代表されるナノ物質は、薄膜化や電場印加、歪み印加、イオンの挿入等によって結晶対称性や電子状態を変調できると同時に、ナノチューブのような曲率構造や格子整合条件を必要としないヘテロ界面を作製することによって元の結晶にはないユニークな構造を実現することができる。応募者は、そのようなナノ物質特有の対称性の破れの実現や制御を基軸とした物性研究を推進してきた。特に、対称性の破れを反映した物質固有の(接合構造を必要しない単一物質で生じるような)整流現象である、非相反伝導(結晶対称性を反映した電流や超伝導流の整流現象)および光起電力効果(分極を反映した光整流機能)の開拓を行い、その微視的機構を明らかにして、量子力学的整流現象の基礎学理を構築すると同時に省エネルギーナノエレクトロニクスへの道を切り拓いた。
井手上敏也いでうえとしや東京大学物性研究所准教授ナノ物質における対称性制御と量子整流現象の開拓ファンデルワールス結晶劈開試料に代表されるナノ物質は、薄膜化や電場印加、歪み印加、イオンの挿入等によって結晶対称性や電子状態を変調できると同時に、ナノチューブのような曲率構造や格子整合条件を必要としないヘテロ界面を作製することによって元の結晶にはないユニークな構造を実現することができる。応募者は、そのようなナノ物質特有の対称性の破れの実現や制御を基軸とした物性研究を推進してきた。特に、対称性の破れを反映した物質固有の(接合構造を必要しない単一物質で生じるような)整流現象である、非相反伝導(結晶対称性を反映した電流や超伝導流の整流現象)および光起電力効果(分極を反映した光整流機能)の開拓を行い、その微視的機構を明らかにして、量子力学的整流現象の基礎学理を構築すると同時に省エネルギーナノエレクトロニクスへの道を切り拓いた。- 谷口知大たにぐちともひろ国立研究開発法人産業技術総合研究所新原理コンピューティング研究センター研究チーム長スピン異常ホール効果の理論提案とその実証谷口氏はスピントロニクス分野において固体中の電子スピンの生成・制御に関する基礎理論と磁気デバイス・人工知能応用の研究を行ってきた。主な研究成果として新しいスピン流生成現象「スピン異常ホール効果」の理論提案と実証が挙げられる。スピン異常ホール効果は不揮発性磁気メモリに磁界、電界を加えることなくスピン流を注入し、メモリの情報を制御できる画期的な基盤技術となる可能性を秘めている。2015年にアメリカ・フランスのグループと共同で理論提案を行い、2018年には実験グループを指導して世界初となるスピン異常ホール効果の実証に成功した。また2019年には磁気メモリへの書き込みを原理実証するなど産業化を目指した応用研究でも指導的な役割を果たしている。これらの業績を筆頭に、スピンの輸送、ブラウン運動、高周波発振など固体・統計・非線形物理学にまたがる広範な理論研究を行い、スピン物性の基礎学術と産業応用の発展に貢献してきた。最近ではスピンの人工知能応用に取り組むなど常に新しいアイディアを提案し分野を牽引し続けている。
 鄭銀強ていぎんきょう東京大学次世代知能科学研究センター、東京大学大学院情報理工学系研究科准教授知能処理とオプティカルイメージングの融合・創発応募者は,情報科学分野で研究開発が進む知能処理技術と,光学分野で発展する撮像技術との境界を繋ぎ,従来のデジタルカメラの限界を突破する新しい計測技術の開発のみでなく,知能処理に基づく革新的なイメージングシステムの創発を達成し,独創的な学術体系を確立した.これらの研究成果は,コンピュータビジョン(CV)分野の三つのトップ国際会議における計48本の論文採択が示す通り,国際的に非常に高く評価されており,国内では最上位の採択数である.また,国内企業との共同研究を通し,蛍光分光光度計の性能向上や光超音波イメージング装置の製品化に貢献し,産業的にも貢献した.日本の国際的な競争力向上に向けた次世代人材育成にも積極的に取り組んでおり,大学院生・インターン生への指導や優秀留学生の獲得による研究開発力の向上や,人文社会系学生に向けたAI教育プログラムの企画運営などに取り組んでいる.
鄭銀強ていぎんきょう東京大学次世代知能科学研究センター、東京大学大学院情報理工学系研究科准教授知能処理とオプティカルイメージングの融合・創発応募者は,情報科学分野で研究開発が進む知能処理技術と,光学分野で発展する撮像技術との境界を繋ぎ,従来のデジタルカメラの限界を突破する新しい計測技術の開発のみでなく,知能処理に基づく革新的なイメージングシステムの創発を達成し,独創的な学術体系を確立した.これらの研究成果は,コンピュータビジョン(CV)分野の三つのトップ国際会議における計48本の論文採択が示す通り,国際的に非常に高く評価されており,国内では最上位の採択数である.また,国内企業との共同研究を通し,蛍光分光光度計の性能向上や光超音波イメージング装置の製品化に貢献し,産業的にも貢献した.日本の国際的な競争力向上に向けた次世代人材育成にも積極的に取り組んでおり,大学院生・インターン生への指導や優秀留学生の獲得による研究開発力の向上や,人文社会系学生に向けたAI教育プログラムの企画運営などに取り組んでいる. 鳴海拓志なるみたくじ東京大学大学院情報理工学研究科准教授バーチャルリアリティによる身体変容を活用した知覚・認知能力拡張技術の開拓と応用応募者は,人間の感覚情報処理や認知過程における身体の役割を解明する研究に取り組み,その知見に基づいてバーチャルリアリティ(VR)による身体変容を導入することで,状況に応じて適切な知覚・認知能力を発現させることが可能な工学的技術の体系としてゴーストエンジニアリングを提唱し,新たな研究領域を開拓した.ゴーストエンジニアリングのアプローチを視点変換,VRパースペクティブテイキング,変身, 分身/融合の4つに体系化し,これらを駆使することで創造性向上,共感と相互理解の促進,身体能力の増強や獲得,同調圧力低減と議論の質の向上,人から人への効率的なスキル伝達など,多岐にわたる知覚・認知能力を拡張させる成果を挙げてきた.上記成果は分野のトップ論文誌・国際会議で発表された他,国内外で著名な賞を受賞するなど高く評価されている.また,多様な企業との共同研究を通じ,遠隔会議支援システム,運転支援システム,ダイバーシティ研修手法等の幅広い領域でこれらの知見が実用化されている.
鳴海拓志なるみたくじ東京大学大学院情報理工学研究科准教授バーチャルリアリティによる身体変容を活用した知覚・認知能力拡張技術の開拓と応用応募者は,人間の感覚情報処理や認知過程における身体の役割を解明する研究に取り組み,その知見に基づいてバーチャルリアリティ(VR)による身体変容を導入することで,状況に応じて適切な知覚・認知能力を発現させることが可能な工学的技術の体系としてゴーストエンジニアリングを提唱し,新たな研究領域を開拓した.ゴーストエンジニアリングのアプローチを視点変換,VRパースペクティブテイキング,変身, 分身/融合の4つに体系化し,これらを駆使することで創造性向上,共感と相互理解の促進,身体能力の増強や獲得,同調圧力低減と議論の質の向上,人から人への効率的なスキル伝達など,多岐にわたる知覚・認知能力を拡張させる成果を挙げてきた.上記成果は分野のトップ論文誌・国際会議で発表された他,国内外で著名な賞を受賞するなど高く評価されている.また,多様な企業との共同研究を通じ,遠隔会議支援システム,運転支援システム,ダイバーシティ研修手法等の幅広い領域でこれらの知見が実用化されている.- 真栄城正寿まえきまさとし北海道大学大学院工学研究院准教授創薬研究を加速するマイクロ流体デバイス開発に関する研究COVID-19のパンデミック以降、核酸を搭載した脂質ナノ粒子が核酸ナノ医薬品の基盤技術として世界的に注目されている。候補者は、基板上に幅が数十〜数百µmの微細な流路を構築・集積化したマイクロ流体デバイス(iLiNP)を開発し、脂質ナノ粒子の粒径を精密に制御する製造技術を確立した。候補者が考案した独自の流路構造によって、脂質ナノ粒子の粒径を10 nm単位で制御することが可能となった。また、siRNA、mRNA、ゲノム編集酵素、低分子薬剤など、様々な核酸や薬剤を搭載した脂質ナノ粒子作製に成功し、本技術がナノ医薬品開発に応用できることを実証した。候補者が考案したデバイスは、北大発ベンチャー・ライラックファーマ(株)からすでに販売されている。また、iLiNPデバイスを用いた化粧品用リポソーム開発やGMP基準の脂質ナノ粒子大量生産装置の開発など、産学連携によってさらに社会実装を進めている。これらの研究業績は、80報以上の査読付き学術論文で発表しており、生命科学や創薬などの学術分野だけではなく、産業分野にも多大な貢献が期待される。
第21回 2021年度
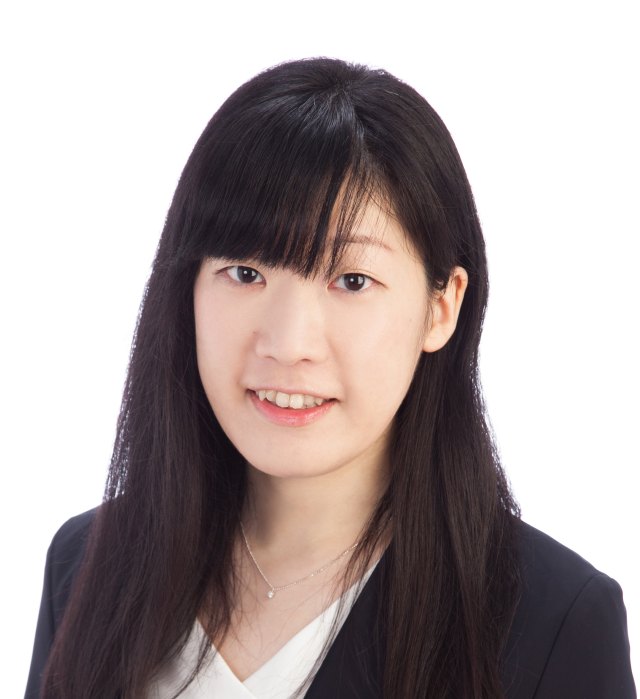 坂上沙央里さかうえさおりハーバード大学医学部博士研究員大阪大学大学院医学系研究科招聘教員大規模ゲノムデータと多層オミクス・フェノタイプデータの 数理学的統合解析手法の開発ヒトの全遺伝情報の解読が終了して20年、ヒトゲノムデータは全世界で爆発的に蓄積している。 しかし当初の期待に反してゲノム情報を疾患の予防や治療に直接役立てる方法論は未だ確立途上である。特に、数百万人・数千万変異規模の巨大データを扱う大規模計算機科学、多層オミクスの生物実験情報と統合解析する情報科学、医療成果へ繋げる臨床医学の学際的研究が求められている。応募者は臨床医学と遺伝統計学のバックグランドを活かし、 ゲノム解析による健康長寿バイオマーカーの発見、ゲノム解析と特異値分解を用いた疾患の再分類の提案、ゲノム情報と機能生物学情報の統合解析手法の解析、ゲノム解析を括用した創薬ソフトウェアの開発など多岐に渡る成果を挙げた。応募者は Nature Medicine、Nature Genetics 等の国際学術雑誌に多数 の筆頭著者論文を発表し、米国人類遺伝学会からの2度の受賞・記者発表など日本人として初の業績を有する。既に数多くの巨大国際ゲノム共同研究コンソーシアムで主要解析者として認知されており、日本のゲノム研究の今後の発展において重要な役割を果たすと期待される。
坂上沙央里さかうえさおりハーバード大学医学部博士研究員大阪大学大学院医学系研究科招聘教員大規模ゲノムデータと多層オミクス・フェノタイプデータの 数理学的統合解析手法の開発ヒトの全遺伝情報の解読が終了して20年、ヒトゲノムデータは全世界で爆発的に蓄積している。 しかし当初の期待に反してゲノム情報を疾患の予防や治療に直接役立てる方法論は未だ確立途上である。特に、数百万人・数千万変異規模の巨大データを扱う大規模計算機科学、多層オミクスの生物実験情報と統合解析する情報科学、医療成果へ繋げる臨床医学の学際的研究が求められている。応募者は臨床医学と遺伝統計学のバックグランドを活かし、 ゲノム解析による健康長寿バイオマーカーの発見、ゲノム解析と特異値分解を用いた疾患の再分類の提案、ゲノム情報と機能生物学情報の統合解析手法の解析、ゲノム解析を括用した創薬ソフトウェアの開発など多岐に渡る成果を挙げた。応募者は Nature Medicine、Nature Genetics 等の国際学術雑誌に多数 の筆頭著者論文を発表し、米国人類遺伝学会からの2度の受賞・記者発表など日本人として初の業績を有する。既に数多くの巨大国際ゲノム共同研究コンソーシアムで主要解析者として認知されており、日本のゲノム研究の今後の発展において重要な役割を果たすと期待される。 清雄一せいゆういち電気通信大学大学院情報理工学研究科准教授プライバシ保護IoTデータ収集・解析基盤の研究様々な人や組織がloTデータを横断的に活用した新たなサービスの構築・普及を考えており、今後これらのデータを流通させ、組み合せて活用していく制度やインフラが整っいくてことが予想される。 しかしながら、どこから個人のプライバシ情報が漏洩するかを予想することが困難になり、プライバシを保護する共通的で強固な枠組みの構築が重要な課題となる。本研究ではIoTデータそのものや IoTデータを用いた機械学習の予測結果に存在する誤差を取り扱い、どのようなデータと組み合わせられてもプライバシの漏洩を防ぐことを現実的な仮定の下で保証するこの分野で極めて重要となる基盤を提案している。またプライバシを保護するのみではなく、プライバシを保護した上で正確な統計的解析や機械学習を行うことのできる仕組みを有す。 安全性の理論的証明及び仮想データでのシミュレーションのみでなく、実際にIoT基盤を構築して個人データを収集し、誤差を含む実データを用いた実験を行って提案基盤の有用性を明らかにしている。
清雄一せいゆういち電気通信大学大学院情報理工学研究科准教授プライバシ保護IoTデータ収集・解析基盤の研究様々な人や組織がloTデータを横断的に活用した新たなサービスの構築・普及を考えており、今後これらのデータを流通させ、組み合せて活用していく制度やインフラが整っいくてことが予想される。 しかしながら、どこから個人のプライバシ情報が漏洩するかを予想することが困難になり、プライバシを保護する共通的で強固な枠組みの構築が重要な課題となる。本研究ではIoTデータそのものや IoTデータを用いた機械学習の予測結果に存在する誤差を取り扱い、どのようなデータと組み合わせられてもプライバシの漏洩を防ぐことを現実的な仮定の下で保証するこの分野で極めて重要となる基盤を提案している。またプライバシを保護するのみではなく、プライバシを保護した上で正確な統計的解析や機械学習を行うことのできる仕組みを有す。 安全性の理論的証明及び仮想データでのシミュレーションのみでなく、実際にIoT基盤を構築して個人データを収集し、誤差を含む実データを用いた実験を行って提案基盤の有用性を明らかにしている。 関真一郎せきしんいちろう東京大学大学院工学系研究科准教授磁気スキルミオンの物質設計と機能開拓関氏はこれまで、系の対称性やトポロジーといった、幾何学的な特徴に基づく物質設計を行うことで、様々な革新的な電子機能の開拓・実証を行ってきた。特に代表的な成果として、 「磁気スキルミオン」に関する研究が挙げられる。磁気スキルミオンとは、特殊な磁性体の中で生じる、電子スピンの渦巻き構造のことを指しており、トポロジーによって守られた安定なナノサイズの粒子としての性質を持つことから、次世代の磁気記憶素子のための新しい情報担体の候補として、近年大きな注目を集めている。関氏は、この磁気スキルミオン に関して、(a)世界最小サイズ (世界最高の情報密度)のスキルミオンを実現する新物質の発見、(b)電場を利用した高効率なスキルミオン制御手法の開拓、(c)スキルミオンの3次元形状を可視化する新しい観測手法の開拓、といった複数の画期的な成果を上げており、スキルミオンの超高密度・超低消費電力な情報担体としての応用展開を目指す上で、極めて重要な貢献をしてきた。 これらの業績は、関氏を筆頭・責任著者とする原著論文としてScience誌やNature姉妹誌に掲載され、国際的にも高い評価を得ており、船井学術賞にふさわしいと考えられる。
関真一郎せきしんいちろう東京大学大学院工学系研究科准教授磁気スキルミオンの物質設計と機能開拓関氏はこれまで、系の対称性やトポロジーといった、幾何学的な特徴に基づく物質設計を行うことで、様々な革新的な電子機能の開拓・実証を行ってきた。特に代表的な成果として、 「磁気スキルミオン」に関する研究が挙げられる。磁気スキルミオンとは、特殊な磁性体の中で生じる、電子スピンの渦巻き構造のことを指しており、トポロジーによって守られた安定なナノサイズの粒子としての性質を持つことから、次世代の磁気記憶素子のための新しい情報担体の候補として、近年大きな注目を集めている。関氏は、この磁気スキルミオン に関して、(a)世界最小サイズ (世界最高の情報密度)のスキルミオンを実現する新物質の発見、(b)電場を利用した高効率なスキルミオン制御手法の開拓、(c)スキルミオンの3次元形状を可視化する新しい観測手法の開拓、といった複数の画期的な成果を上げており、スキルミオンの超高密度・超低消費電力な情報担体としての応用展開を目指す上で、極めて重要な貢献をしてきた。 これらの業績は、関氏を筆頭・責任著者とする原著論文としてScience誌やNature姉妹誌に掲載され、国際的にも高い評価を得ており、船井学術賞にふさわしいと考えられる。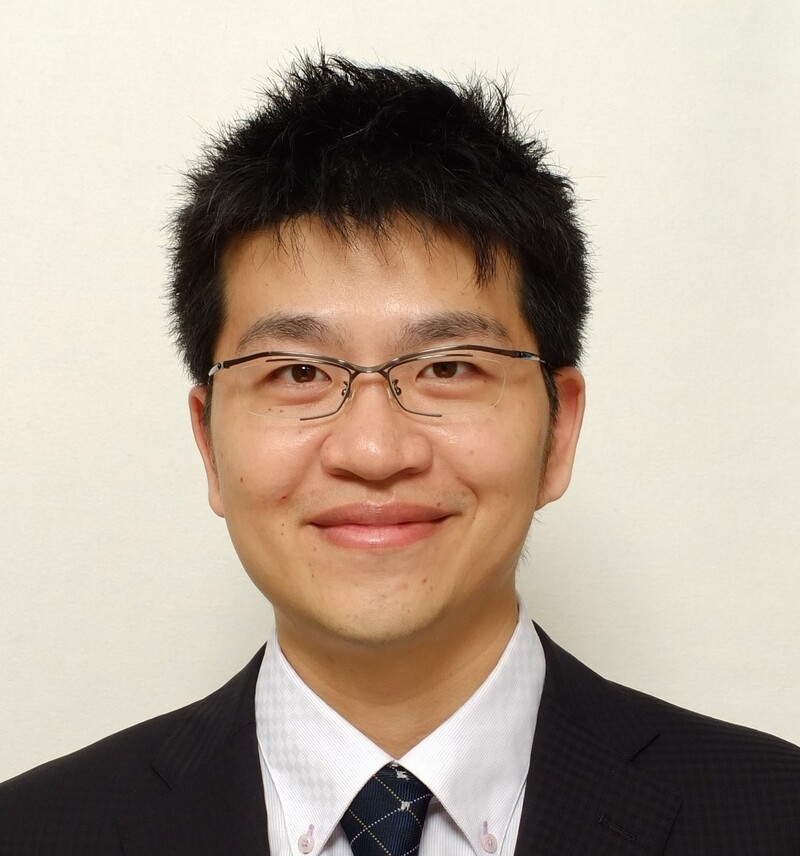 董冕雄とうめんゆう室蘭工業大学大学院工学研究科准教授IoT技術を用いた次世代耐災害システムの研究開発候補者は、これまで無線センサネットワークやサイバーフィジカルシステムといったIoTの研究に一貫して従事し、ネットワーク資源の効率化や伝送遅延を最小化する通信技術の創出、 さらに大規模loTネットワークの技術などの基盤的研究に取り組んでいる。関連成果は、難関国際論文誌やトップ国際会議などで発表し、国内外で著名な賞を受賞している。その中で得られた知見を防災分野の研究に応用し、IoT技術である端末間通信(D2D)、省電力広域通信規格(LPWAN)、ドローン(UAV)を独創的に組み合わせ、臨時ネットワ ー クを構築するといった新たアプローチを試みた。 ドローンによるWi-Fiシステムを実装し、2019年には自治体主催の防災訓練にて実証実験を行った。この一連の取り組みは新聞各紙でこれまでに多数報道されたほか、文部科学大臣表彰ならびに知事表彰されるなど、学術的な研究成果が高く評価されただけでなく、広く社会に寄与すると期待されている。
董冕雄とうめんゆう室蘭工業大学大学院工学研究科准教授IoT技術を用いた次世代耐災害システムの研究開発候補者は、これまで無線センサネットワークやサイバーフィジカルシステムといったIoTの研究に一貫して従事し、ネットワーク資源の効率化や伝送遅延を最小化する通信技術の創出、 さらに大規模loTネットワークの技術などの基盤的研究に取り組んでいる。関連成果は、難関国際論文誌やトップ国際会議などで発表し、国内外で著名な賞を受賞している。その中で得られた知見を防災分野の研究に応用し、IoT技術である端末間通信(D2D)、省電力広域通信規格(LPWAN)、ドローン(UAV)を独創的に組み合わせ、臨時ネットワ ー クを構築するといった新たアプローチを試みた。 ドローンによるWi-Fiシステムを実装し、2019年には自治体主催の防災訓練にて実証実験を行った。この一連の取り組みは新聞各紙でこれまでに多数報道されたほか、文部科学大臣表彰ならびに知事表彰されるなど、学術的な研究成果が高く評価されただけでなく、広く社会に寄与すると期待されている。 堀﨑遼一ほりさきりょういち東京大学大学院情報理工学系研究科准教授情報科学駆動によるイメージング技術の革新カメラに代表されるイメージングシステムにおいて、光学系と信号処理系を協調してデザインする 研究分野はコンピュテーショナルイメージングと呼ばれ、計算機の高速化や情報科学分野の進展と歩調を合わせ、その発展と重要性拡大が急速に進んでいる。応募者は、当該分野において、近年、情報科学分野で活発に研究が行われているコンプレッシブセンシングや機械学習を利用した革新的な イメージングシステムの研究開発に取り組んでおり、多次元イメージング、位相イメージング、散乱イメージング等において、これまで困難であったシステムの簡素化や高機能化を実現している。 また、レンズレスイメージングを含む、信号処置を前提にした光学系のミニマル化を推進しており、これらの研究は世界的にも高い評価を得ている、すでに80報の論文業績を有し、近年では有力国際会議における招待講演も多く、関連分野の中でも傑出した成果を挙げている。
堀﨑遼一ほりさきりょういち東京大学大学院情報理工学系研究科准教授情報科学駆動によるイメージング技術の革新カメラに代表されるイメージングシステムにおいて、光学系と信号処理系を協調してデザインする 研究分野はコンピュテーショナルイメージングと呼ばれ、計算機の高速化や情報科学分野の進展と歩調を合わせ、その発展と重要性拡大が急速に進んでいる。応募者は、当該分野において、近年、情報科学分野で活発に研究が行われているコンプレッシブセンシングや機械学習を利用した革新的な イメージングシステムの研究開発に取り組んでおり、多次元イメージング、位相イメージング、散乱イメージング等において、これまで困難であったシステムの簡素化や高機能化を実現している。 また、レンズレスイメージングを含む、信号処置を前提にした光学系のミニマル化を推進しており、これらの研究は世界的にも高い評価を得ている、すでに80報の論文業績を有し、近年では有力国際会議における招待講演も多く、関連分野の中でも傑出した成果を挙げている。 森本雄矢もりもとゆうや東京大学大学院情報理工学系研究科准教授デバイスと培養組織を融合したバイオマシン技術の開拓応募者は、工学技術とバイオ技術の組み合わせにより、細胞の凝集にて形成される培養組織の高機能化を実現するとともに、培養組織とデバイスを融合したバイオマシン技術の開拓に成功した。 マイクロ加工技術を駆使して細胞含有ハイドロゲルの形状を制御することで、従来よりも高い収縮能を有する筋組織など高機能な培養組織の構築法を確立した。さらに、タンパク質パターニングによる培養組織とデバイスの融合方法を確立し、培養組織の「機能で働く」・「機能を測る」バイオマシンを実現した。 その結果、伸筋と屈筋の2つの骨格筋組織とロボット骨格を融合した“腕のように関節駆動するバイオロボット”やヒト臨床薬に対する筋収縮特性の変化を評価可能なヒト心筋組織チップなど、培養組織の独特な機能とデバイスの頑強性・定量性といった両者の利点を活かした融合システムの創出を世界に先駆けて実現した。 上記成果は数々のトップ国際論文誌への結実に加え、国内外で著名な賞を受賞するなど高く評価されている。
森本雄矢もりもとゆうや東京大学大学院情報理工学系研究科准教授デバイスと培養組織を融合したバイオマシン技術の開拓応募者は、工学技術とバイオ技術の組み合わせにより、細胞の凝集にて形成される培養組織の高機能化を実現するとともに、培養組織とデバイスを融合したバイオマシン技術の開拓に成功した。 マイクロ加工技術を駆使して細胞含有ハイドロゲルの形状を制御することで、従来よりも高い収縮能を有する筋組織など高機能な培養組織の構築法を確立した。さらに、タンパク質パターニングによる培養組織とデバイスの融合方法を確立し、培養組織の「機能で働く」・「機能を測る」バイオマシンを実現した。 その結果、伸筋と屈筋の2つの骨格筋組織とロボット骨格を融合した“腕のように関節駆動するバイオロボット”やヒト臨床薬に対する筋収縮特性の変化を評価可能なヒト心筋組織チップなど、培養組織の独特な機能とデバイスの頑強性・定量性といった両者の利点を活かした融合システムの創出を世界に先駆けて実現した。 上記成果は数々のトップ国際論文誌への結実に加え、国内外で著名な賞を受賞するなど高く評価されている。
第20回 2020年度
 武田俊太郎たけだしゅんたろう東京大学大学院工学系研究科准教授量子テレポーテーションの高性能化とそのループ型光量子コンピュータへの応用武田氏は日本発・世界初の量子コンピュータへとつながる独創的な研究業績を残しています。量子コンピュータは、新しい原理で動作する次世代の超高速コンピュータです。武田氏は、光を用いた量子コンピュータに着目し、その演算機能を担う「量子テレポーテーション回路」を新手法により100倍以上高効率化しました。さらに、それを用いてどれほど大規模な計算も最小規模の回路で実行できる「ループ型光量子コンピュータ」を発明し、その心臓部の開発にも成功しました。これらの成果は、光量子コンピュータの飛躍的な大規模化を可能とし、その開発に必要なリソースやコストを大幅に減少させるもので、光量子コンピュータにイノベーションをもたらすと期待されます。以上の成果はNature誌やScience Advances誌をはじめとする一流紙に掲載され、NHKニュース等で報道された他、文部科学大臣表彰若手科学者賞など11件の受賞につながっています。
武田俊太郎たけだしゅんたろう東京大学大学院工学系研究科准教授量子テレポーテーションの高性能化とそのループ型光量子コンピュータへの応用武田氏は日本発・世界初の量子コンピュータへとつながる独創的な研究業績を残しています。量子コンピュータは、新しい原理で動作する次世代の超高速コンピュータです。武田氏は、光を用いた量子コンピュータに着目し、その演算機能を担う「量子テレポーテーション回路」を新手法により100倍以上高効率化しました。さらに、それを用いてどれほど大規模な計算も最小規模の回路で実行できる「ループ型光量子コンピュータ」を発明し、その心臓部の開発にも成功しました。これらの成果は、光量子コンピュータの飛躍的な大規模化を可能とし、その開発に必要なリソースやコストを大幅に減少させるもので、光量子コンピュータにイノベーションをもたらすと期待されます。以上の成果はNature誌やScience Advances誌をはじめとする一流紙に掲載され、NHKニュース等で報道された他、文部科学大臣表彰若手科学者賞など11件の受賞につながっています。 肥後芳樹ひごよしき大阪大学大学院情報科学研究科准教授ソースコード解析に基づくソフトウェア開発支援に関する研究ソフトウェア開発者は50%以上の時間をデバックに費やしているともいわれている。肥後氏は、ソフトウェア開発におけるデバック支援に関する研究を行ってきている。デバックを困難にする原因の一つとしてソフトウェアのソースコード中に存在する重複コードの存在がある。肥後氏はこれまでに、検出能力が高いが検出速度が遅かったプログラム依存グラフを利用した検出法について研究を行い、検出の精度を保ったまま大幅に速度を向上させることに成功した。これにより、大規模なソフトウェアに対してもプログラム依存グラフを利用した検出法が適用できるようになった。また、ソースコード中の潜在的な問題個所を自動検出する研究において、従来はプログラミング言語に起因した問題の検出しか行えていなかったが、肥後氏は対象ソースコードの開発履歴を利用した検出法を開発し、そのソースコード固有の問題個所を自動検出できる手法を開発した。
肥後芳樹ひごよしき大阪大学大学院情報科学研究科准教授ソースコード解析に基づくソフトウェア開発支援に関する研究ソフトウェア開発者は50%以上の時間をデバックに費やしているともいわれている。肥後氏は、ソフトウェア開発におけるデバック支援に関する研究を行ってきている。デバックを困難にする原因の一つとしてソフトウェアのソースコード中に存在する重複コードの存在がある。肥後氏はこれまでに、検出能力が高いが検出速度が遅かったプログラム依存グラフを利用した検出法について研究を行い、検出の精度を保ったまま大幅に速度を向上させることに成功した。これにより、大規模なソフトウェアに対してもプログラム依存グラフを利用した検出法が適用できるようになった。また、ソースコード中の潜在的な問題個所を自動検出する研究において、従来はプログラミング言語に起因した問題の検出しか行えていなかったが、肥後氏は対象ソースコードの開発履歴を利用した検出法を開発し、そのソースコード固有の問題個所を自動検出できる手法を開発した。
肥後氏はこれまでに学術論文誌70報、国際会議禄102報(全て査読有り)の研究業績を有しており、各種学会より14賞、国際会議において3賞、国内シンポジウムおよび研究会において19賞、所属組織である大阪大学より5賞の受賞歴がある。 前川卓也まえかわたくや大阪大学大学院情報科学研究科准教授人間・生物の行動ビッグデータ認識技術の研究前川氏はセンサにより観測されたビッグデータを用いて実世界を認識・理解する人工知能の研究開発を推進してきた。特に、人間や動物に添付された小型でリソース制約が大きいセンサデバイス上での行動認識技術に関して国際的に顕著な成果を達成している。これらの技術をもとに世界で初めて野生動物に人工知能を搭載した研究者であり、人工知能を備えた動物装着型小型センサデバイスや説明可能な深層学習に基づく動物行動分析手法を用いて、これまでに知られていなかった動物の生態を次々と明らかにした。また、10年以上前からスマートウォッチ等の普及を予見し、小型身体装着センサ用いた行動認識を世界的にリードし続けており、工場や物流センタ等での作業行動認識に適用している。前川氏の成果は、野生生物との共生、コロナウイルス等の人獣共通感染症の伝搬経路の解明、労働人口減少社会における生産性の向上、独居高齢者の見守りといった持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための要素技術であり、社会的重要性も高い。
前川卓也まえかわたくや大阪大学大学院情報科学研究科准教授人間・生物の行動ビッグデータ認識技術の研究前川氏はセンサにより観測されたビッグデータを用いて実世界を認識・理解する人工知能の研究開発を推進してきた。特に、人間や動物に添付された小型でリソース制約が大きいセンサデバイス上での行動認識技術に関して国際的に顕著な成果を達成している。これらの技術をもとに世界で初めて野生動物に人工知能を搭載した研究者であり、人工知能を備えた動物装着型小型センサデバイスや説明可能な深層学習に基づく動物行動分析手法を用いて、これまでに知られていなかった動物の生態を次々と明らかにした。また、10年以上前からスマートウォッチ等の普及を予見し、小型身体装着センサ用いた行動認識を世界的にリードし続けており、工場や物流センタ等での作業行動認識に適用している。前川氏の成果は、野生生物との共生、コロナウイルス等の人獣共通感染症の伝搬経路の解明、労働人口減少社会における生産性の向上、独居高齢者の見守りといった持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための要素技術であり、社会的重要性も高い。 松田信幸まつだのぶゆき東北大学大学院工学研究科准教授光導波路回路を用いた小型・高機能量子情報デバイスの開発量子情報処理は、究極的に安全な暗号通信や、組み合わせ最適化や創薬等の重要分野における複雑な問題の効率的な計算を可能とするため、次世代の情報処理技術として注目を集めている。松田氏は光の量子である光子用い、量子情報処理のためのデバイスの研究開発を行ってきた。特に、光導波路集積回路や光ファイバといった先端光学素子を量子技術へと先駆的に適用し、システムの小型化、大規模化、高機能化を目的としながら、光量子情報処理技術の発展に向けた研究に取り組んだ。結果、回路構成を高速かつ自在に書き換え可能な光量子コンピュータ演算回路、光子の波長を効率100%で変換する光ファイバ型デバイス、シリコンチップ上に小型集積された量子もつれ光源等、独創的かつ革新的な数々の量子光デバイスを世界に先駆けて実現した。松田氏はこれらの成果により、光通信等の他分野を巻き込みながら、量子情報処理研究の飛躍的進展に大きく貢献した。
松田信幸まつだのぶゆき東北大学大学院工学研究科准教授光導波路回路を用いた小型・高機能量子情報デバイスの開発量子情報処理は、究極的に安全な暗号通信や、組み合わせ最適化や創薬等の重要分野における複雑な問題の効率的な計算を可能とするため、次世代の情報処理技術として注目を集めている。松田氏は光の量子である光子用い、量子情報処理のためのデバイスの研究開発を行ってきた。特に、光導波路集積回路や光ファイバといった先端光学素子を量子技術へと先駆的に適用し、システムの小型化、大規模化、高機能化を目的としながら、光量子情報処理技術の発展に向けた研究に取り組んだ。結果、回路構成を高速かつ自在に書き換え可能な光量子コンピュータ演算回路、光子の波長を効率100%で変換する光ファイバ型デバイス、シリコンチップ上に小型集積された量子もつれ光源等、独創的かつ革新的な数々の量子光デバイスを世界に先駆けて実現した。松田氏はこれらの成果により、光通信等の他分野を巻き込みながら、量子情報処理研究の飛躍的進展に大きく貢献した。 安井隆雄やすいたかお名古屋大学大学院工学研究科准教授尿中microRNAの網羅解析による無侵襲がん早期検知の実現安井氏は「がん」の克服を志向して、ナノ空間制御技術と機械学習解析技術を駆使する「尿中microRNAの網羅解析による無侵襲がん早期検知」を実現し、尿リキッドバイオプシーの開拓を行った(Science Adv., 2017)。ナノ空間制御技術により、尿1mLから1300種類以上の発現microRNAを世界で初めて発見した(従来技術:尿20mLから200種類程度)。また、機械技術学習により、microRNAの発現パターン解析によってがん因子microRNA群の同定を達成し、診断率98%・感度98%・特異度99%の早期肺がん検知の実現と、その他がん種への展開を達成した。現行法にて尿からがんを高確度で判定できる手法は存在せず、本研究の成果が世界初の成果となった。これら安井氏の研究の意義は、世界で初めて、尿1mLより1300種類以上のmicroRNAを発見したこと、その発現パターンより98%の高確度で無侵襲な早期がん検知を実現したことにある。
安井隆雄やすいたかお名古屋大学大学院工学研究科准教授尿中microRNAの網羅解析による無侵襲がん早期検知の実現安井氏は「がん」の克服を志向して、ナノ空間制御技術と機械学習解析技術を駆使する「尿中microRNAの網羅解析による無侵襲がん早期検知」を実現し、尿リキッドバイオプシーの開拓を行った(Science Adv., 2017)。ナノ空間制御技術により、尿1mLから1300種類以上の発現microRNAを世界で初めて発見した(従来技術:尿20mLから200種類程度)。また、機械技術学習により、microRNAの発現パターン解析によってがん因子microRNA群の同定を達成し、診断率98%・感度98%・特異度99%の早期肺がん検知の実現と、その他がん種への展開を達成した。現行法にて尿からがんを高確度で判定できる手法は存在せず、本研究の成果が世界初の成果となった。これら安井氏の研究の意義は、世界で初めて、尿1mLより1300種類以上のmicroRNAを発見したこと、その発現パターンより98%の高確度で無侵襲な早期がん検知を実現したことにある。 矢谷浩司やたにこうじ東京大学大学院工学系研究科准教授知的作業支援モバイルプラットフォームを実現するインタフェース研究矢谷氏はモバイルデバイス・スマートフォンを知的作業支援プラットフォームへと変革させる技術の開発とその評価を多角的に行ってきた。より知的作業に適したインタフェースを提供するため、ペンとタッチ入力の組み合わせに着目し、ペンとタッチの位置や動作の関係性により様々な機能を実現した。これにより、一般的なメニューなどを使用せずとも、様々な機能を即座、かつユーザにとって自然な形で実行でき、ペンとタッチ入力の重要性を示した。さらに、アプリケーションを指向した研究を推し進め、モバイルデバイスの使いすぎを抑制するシステムを提案した。これら研究成果は計6編の論文として発表され、2件の受賞があり、矢谷氏の学術的貢献は大変顕著である。産業界においては26件の特許や、現在市場に流通しているモバイルデバイスのインタフェースデザインへの応用がなされており、実社会への影響も非常に大きい。
矢谷浩司やたにこうじ東京大学大学院工学系研究科准教授知的作業支援モバイルプラットフォームを実現するインタフェース研究矢谷氏はモバイルデバイス・スマートフォンを知的作業支援プラットフォームへと変革させる技術の開発とその評価を多角的に行ってきた。より知的作業に適したインタフェースを提供するため、ペンとタッチ入力の組み合わせに着目し、ペンとタッチの位置や動作の関係性により様々な機能を実現した。これにより、一般的なメニューなどを使用せずとも、様々な機能を即座、かつユーザにとって自然な形で実行でき、ペンとタッチ入力の重要性を示した。さらに、アプリケーションを指向した研究を推し進め、モバイルデバイスの使いすぎを抑制するシステムを提案した。これら研究成果は計6編の論文として発表され、2件の受賞があり、矢谷氏の学術的貢献は大変顕著である。産業界においては26件の特許や、現在市場に流通しているモバイルデバイスのインタフェースデザインへの応用がなされており、実社会への影響も非常に大きい。 横田知之よこたともゆき東京大学大学院工学系研究科准教授超柔軟な有機エレクトロニクスの開発と生体・医療応用横田氏は、有機集積回路やセンサなどの様々な複合素子を極薄基板上に集積化し、世界に先駆けて、システムレベルで超柔軟なエレクトロニクスを実現した。特に、極薄基板上に有機発光素子と有機受光素子を集積化することで、指に巻きつけることが可能な血中酸素濃度計を開発した。さらに、光センサと低温ポリシリコンを用いた集積回路の技術を組み合わせることで、生体認識に必要な高解像度、脈拍などのバイタルサインを計測するのに必要な高速撮像が可能なシート型のイメージセンサを実現しました。このシート型イメージセンサを用いることで、生体認証データとバイタルサインを世界で初めて同時に計測することに成功しました。生体認証とウェラブル機器を組み合わせることで、「なりすまし」などを防ぎながらのヘルスケアモニタリングが可能となる。横田氏は、社会実装に向けて既に産業界と協力することでウェアラブル機器にフレキシブルセンサを集積化し目覚ましい成果をあげている。
横田知之よこたともゆき東京大学大学院工学系研究科准教授超柔軟な有機エレクトロニクスの開発と生体・医療応用横田氏は、有機集積回路やセンサなどの様々な複合素子を極薄基板上に集積化し、世界に先駆けて、システムレベルで超柔軟なエレクトロニクスを実現した。特に、極薄基板上に有機発光素子と有機受光素子を集積化することで、指に巻きつけることが可能な血中酸素濃度計を開発した。さらに、光センサと低温ポリシリコンを用いた集積回路の技術を組み合わせることで、生体認識に必要な高解像度、脈拍などのバイタルサインを計測するのに必要な高速撮像が可能なシート型のイメージセンサを実現しました。このシート型イメージセンサを用いることで、生体認証データとバイタルサインを世界で初めて同時に計測することに成功しました。生体認証とウェラブル機器を組み合わせることで、「なりすまし」などを防ぎながらのヘルスケアモニタリングが可能となる。横田氏は、社会実装に向けて既に産業界と協力することでウェアラブル機器にフレキシブルセンサを集積化し目覚ましい成果をあげている。
第19回 2019年度
 竹井邦晴たけいくにはる大阪府立大学大学院工学研究科教授無機ナノ材料による高性能フレキシブルデバイス技術の開拓竹井氏は、これまで一般的ではなかった無機ナノ材料の優れた特性及び機械的柔軟性に注目し、この大面積印刷・転写技術の新規開発、そしてそれらを用いた高性能フレキシブルデバイス技術の開拓を行ってきた。その成果は無機材料によるフレキシブルデバイスの分野では世界トップレベルを走っている。
竹井邦晴たけいくにはる大阪府立大学大学院工学研究科教授無機ナノ材料による高性能フレキシブルデバイス技術の開拓竹井氏は、これまで一般的ではなかった無機ナノ材料の優れた特性及び機械的柔軟性に注目し、この大面積印刷・転写技術の新規開発、そしてそれらを用いた高性能フレキシブルデバイス技術の開拓を行ってきた。その成果は無機材料によるフレキシブルデバイスの分野では世界トップレベルを走っている。
特に、これまで難しいと言われていた①低消費電力駆動フレキシブルCMOS回路、②多種フレキシブルセンサを溶液プロセスで形成する技術、③健康管理用ウェアラブルデバイス・ソフトロボット応用・IoT応用、といった材料、作製技術、新規応用分野への展開を横断的に遂行し実現してきている。
これらはSi半導体技術及び微細加工技術、無機ナノ材料物性、フレキシブルデバイス、プリンテッドエレクトロニクスといった多分野で研究開発を精力的に行うことで初めて実現できた結果である。また業績としてNature誌を含む112報の査読有学術論文発表、国内外で著名な賞も受賞してきた。 関剛斎せきたけし東北大学金属材料研究所准教授規則合金を基軸としたスピントロニクス機能の創出に関する研究関氏は、これまで一貫してスピントロニクス材料研究に従事しており、新材料の開発や材料特性の改善によってデバイスの機能性向上新機能の創出、さらに物理現象の解明に取り組んでいる。
関剛斎せきたけし東北大学金属材料研究所准教授規則合金を基軸としたスピントロニクス機能の創出に関する研究関氏は、これまで一貫してスピントロニクス材料研究に従事しており、新材料の開発や材料特性の改善によってデバイスの機能性向上新機能の創出、さらに物理現象の解明に取り組んでいる。
特に、「強磁性規則合金」がスピントロニクス材料として有望であることに早くから着想し、研究を継続してきた。具体的には、高磁気異方性を有するL10型FePt規則合金、および高スピン分極を示すL21型ホイスラー合金を研究の基軸とし、新しいスピン偏極源によるデバイスの高集積・多機能化へのブレイクスルーをもたらした。また、超低エネルギー磁化反転技術を開発し、省エネルギー動作に向けた道筋を示した。さらに、スピントルク発振の高性能化に成功し、高感度磁場センサの可能性を実証してきた。
いずれも世界に先駆けた革新的成果であり、産業・社会的貢献は大きい。最近では、規則合金における電流‐スピン流‐熱流間の変換現象について重要な成果を挙げており、基礎および応用の両面で分野を牽引している。 都甲薫とこうかおる筑波大学数理物質系准教授IV族材料薄膜の低温合成技術と新規エネルギーデバイスの研究情報化社会の発展にともない、身の回りの電子デバイス数は急速に増加している。そのような中、エネルギーの確保・供給に関する課題が顕在化している。都甲氏は、既存の電子材料であるSiと親和性の高いIV族材料に着眼するとともに、その結晶薄膜を「好きなところに合成する」研究で世界をリードしてきた。
都甲薫とこうかおる筑波大学数理物質系准教授IV族材料薄膜の低温合成技術と新規エネルギーデバイスの研究情報化社会の発展にともない、身の回りの電子デバイス数は急速に増加している。そのような中、エネルギーの確保・供給に関する課題が顕在化している。都甲氏は、既存の電子材料であるSiと親和性の高いIV族材料に着眼するとともに、その結晶薄膜を「好きなところに合成する」研究で世界をリードしてきた。
特に、薄膜が非晶質状態から結晶に成長する過程について微視的観点から制御を図り、絶縁膜やガラス、プラスチックなどの上に従来最高の機能を持つIV族材料(Si、SiGe、Ge、GeSn、グラフェン)を低温合成することに成功した。さらに合成膜の特徴に応じて、「太陽電池」「熱電変換素子」「トランジスタ」「二次電池」など、創・省・蓄エネルギーの分野を横断した新規デバイスに展開している。各分野において、世界初・世界最高となる顕著な成果を挙げ続けており、国内外で招待講演に招聘されている。
以上の成果について、総被引用件数3000件を超える多くの学術論文に結実しているほか、講演奨励賞・業績賞を受賞するなど高い評価を受けている。 福田憲二郎ふくだけんじろう理化学研究所染谷薄膜素子研究室,創発物性科学研究センター専任研究員超柔軟な有機太陽電池の高性能化とウェアラブルセンサ応用福田氏はこれまでに世界最高のエネルギー変換効率(PCE)を有しながら、伸縮性、水安定性、耐熱性を両立した超薄型有機太陽電池を実現した。PCEや環境に対する安定性は基板膜厚とトレードオフ関係を有しており、テキスタイル分野応用などに必要と考えられる全体厚さが10㎛以下において、これまで最高のPCEは4.2%であり、また耐熱性や水安定性を達成した報告例はなかった。
福田憲二郎ふくだけんじろう理化学研究所染谷薄膜素子研究室,創発物性科学研究センター専任研究員超柔軟な有機太陽電池の高性能化とウェアラブルセンサ応用福田氏はこれまでに世界最高のエネルギー変換効率(PCE)を有しながら、伸縮性、水安定性、耐熱性を両立した超薄型有機太陽電池を実現した。PCEや環境に対する安定性は基板膜厚とトレードオフ関係を有しており、テキスタイル分野応用などに必要と考えられる全体厚さが10㎛以下において、これまで最高のPCEは4.2%であり、また耐熱性や水安定性を達成した報告例はなかった。
福田氏は、総膜厚3㎛、エネルギー変換効率13.0%という、フレキシブル有機太陽電池における世界最高水準のPCEを有した超薄型有機太陽電池を実現した。同時に100℃以上の耐熱性、80日以上の大気安定性などの高い環境安定性も実現した。さらに、この超薄型有機太陽電池を生体センサと集積化させることで、超薄型の自立駆動型ウェアラブルセンサを実現した。
以上の成果はウェアラブルエレクトロニクス分野における電力供給の問題を解決に導く、重要な成果である。 村上隆夫むらかみたかお産業技術総合研究所サイバーフィジカルセキュリティ研究センター主任研究員安全性と有用性を両立するプライバシー保護技術に関する研究村上氏は、位置情報、購買履歴、電力使用量などのパーソナルデータの利活用(母集団分布の推定、ターゲット顧客の解析など)の促進に向けて、パーソナルデータの漏洩を強固に防ぎつつ、かつデータの有用性を一切失わないように加工するための安全性指標を世界で初めて確立した。本指標を満たす技術を幾つか確立し、「データを加工しない場合とほぼ同じ有用性を達成できる」という、従来の常識を覆す結果を、現実的な仮定の下で示すことに成功した。
村上隆夫むらかみたかお産業技術総合研究所サイバーフィジカルセキュリティ研究センター主任研究員安全性と有用性を両立するプライバシー保護技術に関する研究村上氏は、位置情報、購買履歴、電力使用量などのパーソナルデータの利活用(母集団分布の推定、ターゲット顧客の解析など)の促進に向けて、パーソナルデータの漏洩を強固に防ぎつつ、かつデータの有用性を一切失わないように加工するための安全性指標を世界で初めて確立した。本指標を満たす技術を幾つか確立し、「データを加工しない場合とほぼ同じ有用性を達成できる」という、従来の常識を覆す結果を、現実的な仮定の下で示すことに成功した。
本成果は情報セキュリティのトップ国際会議USENIX Security (採択率=15.7%) で発表し、Google が Chrome に実装したデータ加工技術の分布推定誤差を2桁低減するなど、世界の産業界にも大きなインパクトを与えた。
また、関連成果も数々のトップ国際論文誌や難関国際会議などで発表し、難関国際会議の Best Paper やドコモ・モバイル・サイエンス賞を受賞するなど、国内外で評価されている。
第18回 2018年度
 飯塚哲也いいづかてつや東京大学大規模集積システム設計教育研究センター准教授時間領域信号処理による高精度・高効率集積回路設計技術に関する研究現在の先端半導体集積回路技術では1Vを下回る低電圧動作が一般的であり、電圧振幅を用いた従来の信号処理(電圧領域)では信号対雑音比の充分な確保が困難となる。微細集積回路における従来手法の弱点を克服し究極的な高性能・高機能を実現するため、候補者は時間領域信号処理による集積回路設計技術の研究に継続して取り組み、理論・応用の両側面から先駆的な業績をあげてきた。
飯塚哲也いいづかてつや東京大学大規模集積システム設計教育研究センター准教授時間領域信号処理による高精度・高効率集積回路設計技術に関する研究現在の先端半導体集積回路技術では1Vを下回る低電圧動作が一般的であり、電圧振幅を用いた従来の信号処理(電圧領域)では信号対雑音比の充分な確保が困難となる。微細集積回路における従来手法の弱点を克服し究極的な高性能・高機能を実現するため、候補者は時間領域信号処理による集積回路設計技術の研究に継続して取り組み、理論・応用の両側面から先駆的な業績をあげてきた。
具体的な研究業績は主に以下の3つに集約される。(A)時間領域のみならず電圧・電流領域においても重要な構成要素であるスイッチング回路の動作、精度解析を統一的に行う理論体系を世界で初めて構築し、正確にモデル化するとともに設計最適化の指針を示した。(B)時間領域信号処理を実現する上で最も基本的かつ重要な要素である時間-デジタル変換器において、提案当時の時点で世界最高の分解能を達成するフェムト秒オーダーの変換器を提案、実証した。(C)時間領域信号処理を実際の通信に応用し、極低消費電力の待機状態からの即時復帰を可能とする、新規なクイックスタート通信方式を提案・実証した。 内田健一うちだけんいち国立研究開発法人物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点グループリーダースピンカロリトロニクスの基盤原理及び応用技術の開拓内田氏は、スピンと熱の相互作用に基づく新しい物理原理・エネルギーデバイス技術の開拓を行い、スピントロニクスと熱効果の融合研究「スピンカロリトロニクス」において世界を先導してきた。内田氏は、熱流によるスピン流生成現象であるスピンゼーベック効果の発見以来同分野の研究を推進し、その後もスピンゼーベック効果の相反現象であるスピンペルチェ効果の熱イメージング計測の実現や、電流を曲げるだけで熱制御可能な「異方性磁気ペルチェ効果」の世界初の観測など、スピントロニクスや熱電分野に大きなインパクトを与える成果を得てきた。
内田健一うちだけんいち国立研究開発法人物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点グループリーダースピンカロリトロニクスの基盤原理及び応用技術の開拓内田氏は、スピンと熱の相互作用に基づく新しい物理原理・エネルギーデバイス技術の開拓を行い、スピントロニクスと熱効果の融合研究「スピンカロリトロニクス」において世界を先導してきた。内田氏は、熱流によるスピン流生成現象であるスピンゼーベック効果の発見以来同分野の研究を推進し、その後もスピンゼーベック効果の相反現象であるスピンペルチェ効果の熱イメージング計測の実現や、電流を曲げるだけで熱制御可能な「異方性磁気ペルチェ効果」の世界初の観測など、スピントロニクスや熱電分野に大きなインパクトを与える成果を得てきた。
内田氏は独創的な計測手法と実験設計により、これまでは測定することすら困難であった熱電・熱スピン変換現象の観測と解明、“スピンを使わなければ実現できない”新しい熱エネルギー制御機能の実証に次々と成功しており、船井学術賞受賞者に相応しい研究業績を有している。 大関真之おおぜきまさゆき東北大学大学院情報科学研究科准教授量子力学を駆使した計算技術の基盤作りと機械学習への展開半導体の集積技術の限界を迎えようとしているなかで、全く異なるパラダイムによる計算技術として注目を浴びている「量子コンピュータ」の実現が目前に迫っている。そのために必須の課題である誤り訂正技術の理論的基盤を物理学の高度な手法を巧みに利用した解析手法で構築した。また組合せ最適化問題や機械学習への応用が期待される量子アニーリングについて、その発展系であるNon-stoquastic系に対するシミュレーション手法の開発を理論物理学の2大手法である場の理論と統計力学の融合により実現した。基盤づくりのみならず、量子アニーリングを隆盛を極める深層学習の学習過程への導入を行い、未知のデータに対する汎化性能を引き上げる量子機械学習アルゴリズムの開発を産学協同で行い世界に先駆けてその威力を知らしめた。以上のように、大関氏は理論物理学の最先端を情報科学技術の進展に結びつける業績をあげた。
大関真之おおぜきまさゆき東北大学大学院情報科学研究科准教授量子力学を駆使した計算技術の基盤作りと機械学習への展開半導体の集積技術の限界を迎えようとしているなかで、全く異なるパラダイムによる計算技術として注目を浴びている「量子コンピュータ」の実現が目前に迫っている。そのために必須の課題である誤り訂正技術の理論的基盤を物理学の高度な手法を巧みに利用した解析手法で構築した。また組合せ最適化問題や機械学習への応用が期待される量子アニーリングについて、その発展系であるNon-stoquastic系に対するシミュレーション手法の開発を理論物理学の2大手法である場の理論と統計力学の融合により実現した。基盤づくりのみならず、量子アニーリングを隆盛を極める深層学習の学習過程への導入を行い、未知のデータに対する汎化性能を引き上げる量子機械学習アルゴリズムの開発を産学協同で行い世界に先駆けてその威力を知らしめた。以上のように、大関氏は理論物理学の最先端を情報科学技術の進展に結びつける業績をあげた。 太田禎生おおたさだお東京大学先端科学技術研究センター准教授機械学習が駆動する高速蛍光イメージングセルソーター実現太田氏は新規光技術や流体・電気工学技術を、機械学習技術を中心として真に融合する事により、高速蛍光「イメージ」セルソーターを世界で初めて実現した。長い間、高速光イメージ計測とリアルタイム情報処理を両立するという技術課題がイメージセルソーター実現を妨げてきた。太田氏は新しい光計測法の開発に止まらず、人を介さない画像解析に画像形式は必要ないという逆転の発想から、圧縮計測信号を直接機械学習で判別して「画像を見ずに形を見る」ゴーストサイトメトリー法を実現し、上記課題を一挙に解決した。光、流体、バイオ・情報と多分野で重要技術を実現し続けてきた太田氏の知識・経験が成した結果であり、人の限界を超えるデータ爆発の時代に、計測ハード技術も機械学習駆動に適した形に再考する革新的な試みでもある。またアカデミアや組織の枠を越えてベンチャー企業を設立して創り上げた機械学習駆動型の融合テクノロジーがScience誌に掲載され、医薬応用の展開、国際的な実用化に邁進する先駆的な事例である。
太田禎生おおたさだお東京大学先端科学技術研究センター准教授機械学習が駆動する高速蛍光イメージングセルソーター実現太田氏は新規光技術や流体・電気工学技術を、機械学習技術を中心として真に融合する事により、高速蛍光「イメージ」セルソーターを世界で初めて実現した。長い間、高速光イメージ計測とリアルタイム情報処理を両立するという技術課題がイメージセルソーター実現を妨げてきた。太田氏は新しい光計測法の開発に止まらず、人を介さない画像解析に画像形式は必要ないという逆転の発想から、圧縮計測信号を直接機械学習で判別して「画像を見ずに形を見る」ゴーストサイトメトリー法を実現し、上記課題を一挙に解決した。光、流体、バイオ・情報と多分野で重要技術を実現し続けてきた太田氏の知識・経験が成した結果であり、人の限界を超えるデータ爆発の時代に、計測ハード技術も機械学習駆動に適した形に再考する革新的な試みでもある。またアカデミアや組織の枠を越えてベンチャー企業を設立して創り上げた機械学習駆動型の融合テクノロジーがScience誌に掲載され、医薬応用の展開、国際的な実用化に邁進する先駆的な事例である。 鈴木健仁すずきたけひと東京農工大学大学院工学研究院 先端電気電子部門准教授極限屈折率材料の開拓によるテラヘルツ応用システムの研究鈴木氏は材料の屈折率・反射・透過をいかに自由自在に、高周波の電磁波領域で制御するかという問いに取り組んだ。メタサーフェスにより自然界の材料には存在しない、超高屈折率、ゼロ屈折率、負の屈折率を有する無反射で透明な材料を、次々世代の情報通信周波数帯の0.3~3THz帯で開拓した。この極限屈折率材料により、第6世代(Beyond 5G)を想定したIoT用超高速無線通信デバイスの光源の高出力化(4.2倍)を実現した。さらに、従来の計測ツールの検出感度を大幅に超える極限領域に感度(-60dB)を有する光学コンポーネントが実現できることを見出した。超高感度なテラヘルツ波帯偏光子に応用し、特許[特許5626740号,US9964678]を取得した。JSTより国策上重要な特許として認定され、JSTへ譲渡した。企業とライセンス契約し、製品化[商標5769812号]し、2014年度に茨城大学(当時所属機関)単独特許で初の純利益に達成した。
鈴木健仁すずきたけひと東京農工大学大学院工学研究院 先端電気電子部門准教授極限屈折率材料の開拓によるテラヘルツ応用システムの研究鈴木氏は材料の屈折率・反射・透過をいかに自由自在に、高周波の電磁波領域で制御するかという問いに取り組んだ。メタサーフェスにより自然界の材料には存在しない、超高屈折率、ゼロ屈折率、負の屈折率を有する無反射で透明な材料を、次々世代の情報通信周波数帯の0.3~3THz帯で開拓した。この極限屈折率材料により、第6世代(Beyond 5G)を想定したIoT用超高速無線通信デバイスの光源の高出力化(4.2倍)を実現した。さらに、従来の計測ツールの検出感度を大幅に超える極限領域に感度(-60dB)を有する光学コンポーネントが実現できることを見出した。超高感度なテラヘルツ波帯偏光子に応用し、特許[特許5626740号,US9964678]を取得した。JSTより国策上重要な特許として認定され、JSTへ譲渡した。企業とライセンス契約し、製品化[商標5769812号]し、2014年度に茨城大学(当時所属機関)単独特許で初の純利益に達成した。 橋田朋子はしだともこ早稲田大学基幹理工学部表現工学科准教授マテリアル指向プログラマブル・マター技術の創出とその応用本研究は次世代の“現実世界のリアリティ拡張手法”として注目を集めつつも具現化が難しかった“プログラマブル・マター(計算機制御可能な物質)”に関する研究である。従来研究が、電子的・機械的機構による疑似的な実現にとどまっていたのに対し、橋田氏は実世界の物質の色・形・硬さなどの多様な物性を、光・熱・湿気などの計算機制御可能な物理刺激を介して、間接的に制御するマテリアル指向の新手法を考案し、本質的な意味でのプログラマブル・マターの具現化に成功した。このイノベーティブな成果は国内外の学会から高い評価を受け、11件の受賞に至っている。橋田氏はこの成果を次世代の情報メディア・広告空間演出・デジタルファブリケーションといった多様な産業で応用利用することにも力を入れており、開発したアプリケーションシステムは既に国内有数の商業施設や公共空間での中長期の招待展示、広告企業での招待WS、食企業との共同研究などに至っている。
橋田朋子はしだともこ早稲田大学基幹理工学部表現工学科准教授マテリアル指向プログラマブル・マター技術の創出とその応用本研究は次世代の“現実世界のリアリティ拡張手法”として注目を集めつつも具現化が難しかった“プログラマブル・マター(計算機制御可能な物質)”に関する研究である。従来研究が、電子的・機械的機構による疑似的な実現にとどまっていたのに対し、橋田氏は実世界の物質の色・形・硬さなどの多様な物性を、光・熱・湿気などの計算機制御可能な物理刺激を介して、間接的に制御するマテリアル指向の新手法を考案し、本質的な意味でのプログラマブル・マターの具現化に成功した。このイノベーティブな成果は国内外の学会から高い評価を受け、11件の受賞に至っている。橋田氏はこの成果を次世代の情報メディア・広告空間演出・デジタルファブリケーションといった多様な産業で応用利用することにも力を入れており、開発したアプリケーションシステムは既に国内有数の商業施設や公共空間での中長期の招待展示、広告企業での招待WS、食企業との共同研究などに至っている。 三浦正志みうらまさし成蹊大学大学院理工学研究科教授超伝導臨界電流向上技術と情報通信デバイスへの応用近年、データ通信が爆発的に増大し、今以上に周波数資源の逼迫が世界的に見込まれ大きな問題となっている。次世代通信技術においては、高周波数の効率的利用を実現可能な移動体通信基地局用フィルタの開発が急務となっている。液体窒素温度下でも高い超電導特性を示すREBa2Cu3Oy(RE123)超伝導薄膜は、一般的にフィルタに用いられている超電導金属と比べて低い表面抵抗を有するため応用が期待されている。
三浦正志みうらまさし成蹊大学大学院理工学研究科教授超伝導臨界電流向上技術と情報通信デバイスへの応用近年、データ通信が爆発的に増大し、今以上に周波数資源の逼迫が世界的に見込まれ大きな問題となっている。次世代通信技術においては、高周波数の効率的利用を実現可能な移動体通信基地局用フィルタの開発が急務となっている。液体窒素温度下でも高い超電導特性を示すREBa2Cu3Oy(RE123)超伝導薄膜は、一般的にフィルタに用いられている超電導金属と比べて低い表面抵抗を有するため応用が期待されている。
三浦氏は、応用上重要である臨界電流密度(Jc)を向上させるために、Jc低下の要因であった量子化磁束の運動を抑制するため、ナノサイズ非超電導相を結晶性を低下させずに導入させる技術を開発した。その結果、RE123薄膜だけでなく近年発見された鉄系超伝導体においても世界最高レベルのJc特性を得ることに成功した。これらの成果は、Nature系論文を含む78件の査読付論文として発表され、全国発明表彰21世紀発明賞、文部科学大臣表彰若手科学者賞など18件受賞し、国内外から高く評価されている。
第17回 2017年度
 伊藤健洋いとうたけひろ東北大学大学院情報科学研究科准教授解空間の遷移性に関するアルゴリズム理論の先駆的研究伊藤氏は、解空間の遷移性に関する画期的なアルゴリズム理論を確立および体系化し、従来は解析が難しかった「持続的システム」に対し、 アルゴリズムの数理的解析を可能とした。伊藤氏は、現代の理論計算機科学の源流ともいえるKarpの21問題に着目し網羅的な解析を進めることで、数多の組合せ問題に対して理論の拡張と波及を可能とした。この理論体系化は、その後、世界的な新しい研究潮流を生み出す起点となっている。一般に、解空間は指数サイズとなるが、伊藤氏の開発した斬新なアルゴリズム手法は、計算時間の指数的な高速化を実現している。また伊藤氏は、解空間の遷移性の観点から、組合せ問題の新しい分類法を提唱し、従来型の解析では得られない分類事例を複数挙げることに成功している。さらに、産学連携を通して、開発したアルゴリズムの実社会システムへの適用を進めており、応用面からも伊藤氏の理論の有効性を実証している。
伊藤健洋いとうたけひろ東北大学大学院情報科学研究科准教授解空間の遷移性に関するアルゴリズム理論の先駆的研究伊藤氏は、解空間の遷移性に関する画期的なアルゴリズム理論を確立および体系化し、従来は解析が難しかった「持続的システム」に対し、 アルゴリズムの数理的解析を可能とした。伊藤氏は、現代の理論計算機科学の源流ともいえるKarpの21問題に着目し網羅的な解析を進めることで、数多の組合せ問題に対して理論の拡張と波及を可能とした。この理論体系化は、その後、世界的な新しい研究潮流を生み出す起点となっている。一般に、解空間は指数サイズとなるが、伊藤氏の開発した斬新なアルゴリズム手法は、計算時間の指数的な高速化を実現している。また伊藤氏は、解空間の遷移性の観点から、組合せ問題の新しい分類法を提唱し、従来型の解析では得られない分類事例を複数挙げることに成功している。さらに、産学連携を通して、開発したアルゴリズムの実社会システムへの適用を進めており、応用面からも伊藤氏の理論の有効性を実証している。 梅津信二郎うめづしんじろう早稲田大学創造理工学部准教授高精度3Dプリンタの開発と高機能デバイスへの応用本研究は、最近話題になっている3Dプリンタに関する内容である。既存の3Dプリンタでは、試作品やサンプルの作製はできるが、これらの試作品を実際に医療分野やエレクトロニクスなどの精密機器分野で利用するには、精度や材料の面で問題があった。梅津氏はこの問題を解決するにあたり、静電力をミクロにコントロールすることで、高粘性な液体から微小なサブミクロン~数ミクロンの液滴をプリントする技術を確立した。さらに、インクやペーストだけでなく、生きた細胞を含むバイオ溶液のような時間経過を伴い、形態が変わる材料でも、精密に3Dプリントできる装置の開発を行った。複雑な3次元状組織を作製できることを実証した。さらに、この装置は、有機太陽電池の作製にも応用できることを実証した。また、既存のFDM方式の3Dプリンタでは、加工精度が高くない。これを解決するにあたり、化学溶解仕上げを援用する手法(3D-CMF)を開発し、広範な領域における様々なデバイスを高精度に作製する手法を確立した。
梅津信二郎うめづしんじろう早稲田大学創造理工学部准教授高精度3Dプリンタの開発と高機能デバイスへの応用本研究は、最近話題になっている3Dプリンタに関する内容である。既存の3Dプリンタでは、試作品やサンプルの作製はできるが、これらの試作品を実際に医療分野やエレクトロニクスなどの精密機器分野で利用するには、精度や材料の面で問題があった。梅津氏はこの問題を解決するにあたり、静電力をミクロにコントロールすることで、高粘性な液体から微小なサブミクロン~数ミクロンの液滴をプリントする技術を確立した。さらに、インクやペーストだけでなく、生きた細胞を含むバイオ溶液のような時間経過を伴い、形態が変わる材料でも、精密に3Dプリントできる装置の開発を行った。複雑な3次元状組織を作製できることを実証した。さらに、この装置は、有機太陽電池の作製にも応用できることを実証した。また、既存のFDM方式の3Dプリンタでは、加工精度が高くない。これを解決するにあたり、化学溶解仕上げを援用する手法(3D-CMF)を開発し、広範な領域における様々なデバイスを高精度に作製する手法を確立した。 杉本宜昭すぎもとよしあき東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授半導体表面の個々の原子の識別と操作全ての物質は原子から構成されている。そして原子と原子は化学結合力により結びついている。杉本氏は、原子間力顕微鏡を用いて、2つの原子の間に働く1本の化学結合力を精密に計測する技術を開発した。それにより、L. Paulingが1932年に提唱した化学結合の基本概念を個々の原子レベルで検証することに初めて成功した。またその知見を応用することで、個々の原子の元素同定や電気陰性度の計測という究極的な分析手法への道を切り拓いた。さらに、化学結合力を制御することにより、表面の1つひとつの原子を操作して、室温で初めてナノ構造体を組み立てることにも成功している。そして、そのナノ構造体を室温でデバイスとして機能させる実証実験にも成功した。化学結合力の精密計測とその制御によって、様々な物質の性質を単原子レベルで分析し、新ナノ材料・デバイスを創成する方法論が確立した。
杉本宜昭すぎもとよしあき東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授半導体表面の個々の原子の識別と操作全ての物質は原子から構成されている。そして原子と原子は化学結合力により結びついている。杉本氏は、原子間力顕微鏡を用いて、2つの原子の間に働く1本の化学結合力を精密に計測する技術を開発した。それにより、L. Paulingが1932年に提唱した化学結合の基本概念を個々の原子レベルで検証することに初めて成功した。またその知見を応用することで、個々の原子の元素同定や電気陰性度の計測という究極的な分析手法への道を切り拓いた。さらに、化学結合力を制御することにより、表面の1つひとつの原子を操作して、室温で初めてナノ構造体を組み立てることにも成功している。そして、そのナノ構造体を室温でデバイスとして機能させる実証実験にも成功した。化学結合力の精密計測とその制御によって、様々な物質の性質を単原子レベルで分析し、新ナノ材料・デバイスを創成する方法論が確立した。 水野洋輔みずのようすけ東京工業大学未来産業技術研究所助教光ファイバを用いた分布計測技術の機能進化:世界最高速度・最高空間分解能の実現近年、インフラの経年劣化や地震等の自然災害による損傷が大きな社会問題となっており、構造物に光ファイバを埋め込むことで、その変形を正確に監視する技術の研究が精力的に推進されている。水野氏は、光ファイバ中のブリルアン散乱に基づき、歪(ひずみ=伸び)と温度の分布を検出できる新たな光ファイバセンサ「ブリルアン光相関領域反射計(BOCDR)」を提案し、性能向上に取り組んできた。大きな成果として、従来法の5000倍以上となる100kHzのサンプリングレートを達成し、片端からの光入射とリアルタイム動作の両立に世界で初めて成功した。また、分布型光ファイバセンサとして世界最高となる2mmの空間分解能(検出可能な歪印加区間の長さが世界最短)を実証した。本技術の提案から超高速化・超空間分解能化に至るまでの成果は、光ファイバセンサの新たな応用領域を開拓するものである。一連の業績は、すでにNature系列誌を含む120件以上の査読付学術論文や国内外のメディアによる多数の記事となっている。
水野洋輔みずのようすけ東京工業大学未来産業技術研究所助教光ファイバを用いた分布計測技術の機能進化:世界最高速度・最高空間分解能の実現近年、インフラの経年劣化や地震等の自然災害による損傷が大きな社会問題となっており、構造物に光ファイバを埋め込むことで、その変形を正確に監視する技術の研究が精力的に推進されている。水野氏は、光ファイバ中のブリルアン散乱に基づき、歪(ひずみ=伸び)と温度の分布を検出できる新たな光ファイバセンサ「ブリルアン光相関領域反射計(BOCDR)」を提案し、性能向上に取り組んできた。大きな成果として、従来法の5000倍以上となる100kHzのサンプリングレートを達成し、片端からの光入射とリアルタイム動作の両立に世界で初めて成功した。また、分布型光ファイバセンサとして世界最高となる2mmの空間分解能(検出可能な歪印加区間の長さが世界最短)を実証した。本技術の提案から超高速化・超空間分解能化に至るまでの成果は、光ファイバセンサの新たな応用領域を開拓するものである。一連の業績は、すでにNature系列誌を含む120件以上の査読付学術論文や国内外のメディアによる多数の記事となっている。 三輪真嗣みわしんじ大阪大学大学院基礎工学研究科准教授ナノ磁性体における電気的スピン制御のデバイス応用に関する研究三輪氏は金属の原子層成長技術を駆使して特徴的な異種材料接合を有する新物質を創成し、スピントロニクスと呼ばれる物性研究を開拓してきた。具体的にはナノ磁性体の磁極(スピン)を電気的に制御し、応用に資する新機能創成に注力した。主な業績のひとつはナノ磁性体の電気応答に対する非線形効果の発見である。これにより半導体ショットキーダイオードのマイクロ波検波感度の3倍を有するスピントロニクスデバイスを室温で実現した。もうひとつの業績はスピントロニクスデバイスの中枢であるナノ磁性体における電界効果の放射光による機構解明である。デバイスの電界効果への放射光適用は実験設計の困難さから皆無であったが、三輪氏はこれを可能にして新分野を切り拓いた。結果として電界効果の起源が金属中の多極子自由度誘起であることを見出し、現状比10倍の電界効果を示す材料開発指針を打ち立てた。三輪氏の研究はスピントロニクスデバイスの応用に期待を与え、界面物性開拓および新規応用物性発見に貢献している。
三輪真嗣みわしんじ大阪大学大学院基礎工学研究科准教授ナノ磁性体における電気的スピン制御のデバイス応用に関する研究三輪氏は金属の原子層成長技術を駆使して特徴的な異種材料接合を有する新物質を創成し、スピントロニクスと呼ばれる物性研究を開拓してきた。具体的にはナノ磁性体の磁極(スピン)を電気的に制御し、応用に資する新機能創成に注力した。主な業績のひとつはナノ磁性体の電気応答に対する非線形効果の発見である。これにより半導体ショットキーダイオードのマイクロ波検波感度の3倍を有するスピントロニクスデバイスを室温で実現した。もうひとつの業績はスピントロニクスデバイスの中枢であるナノ磁性体における電界効果の放射光による機構解明である。デバイスの電界効果への放射光適用は実験設計の困難さから皆無であったが、三輪氏はこれを可能にして新分野を切り拓いた。結果として電界効果の起源が金属中の多極子自由度誘起であることを見出し、現状比10倍の電界効果を示す材料開発指針を打ち立てた。三輪氏の研究はスピントロニクスデバイスの応用に期待を与え、界面物性開拓および新規応用物性発見に貢献している。 山川雄司やまかわゆうじ東京大学生産技術研究所講師実時間センサフィードバックによる高速ロボットの制御とその応用山川氏は、従来困難とされていたロボットによる柔軟物の操りに着目し、高速ロボットシステムを用いて動的紐結び操作や布の折りたたみ操作を高速に実現する手法を提案し、実際に数百ミリ秒オーダでの柔軟物の高速操りを実現している。加えて、ミリ秒オーダでの人間の運動の認識とその認識結果に基づくロボット制御を実現する、人間の動作に完全反応可能な人間機械協調システムを開発するとともに、その一例として「勝率100%じゃんけんロボット」を実現し、その実験動画は動画投稿サイトYouTube において500万回以上の再生回数に達し、世界中に注目され高い評価を得ている。加えて、高速ロボットハンド・アームの協調制御、ロボットハンドによる物体回転操りによる3次元形状復元、高速二足歩行ロボット、高速ビジョンによるビジュアルエンコーダの開発とその応用としての回転制御や、Dynamic Compensation による新しいロボット制御法の研究等にも尽力し、多くの研究業績を創出している。これらの成果が認められ、27個の受賞歴がある。
山川雄司やまかわゆうじ東京大学生産技術研究所講師実時間センサフィードバックによる高速ロボットの制御とその応用山川氏は、従来困難とされていたロボットによる柔軟物の操りに着目し、高速ロボットシステムを用いて動的紐結び操作や布の折りたたみ操作を高速に実現する手法を提案し、実際に数百ミリ秒オーダでの柔軟物の高速操りを実現している。加えて、ミリ秒オーダでの人間の運動の認識とその認識結果に基づくロボット制御を実現する、人間の動作に完全反応可能な人間機械協調システムを開発するとともに、その一例として「勝率100%じゃんけんロボット」を実現し、その実験動画は動画投稿サイトYouTube において500万回以上の再生回数に達し、世界中に注目され高い評価を得ている。加えて、高速ロボットハンド・アームの協調制御、ロボットハンドによる物体回転操りによる3次元形状復元、高速二足歩行ロボット、高速ビジョンによるビジュアルエンコーダの開発とその応用としての回転制御や、Dynamic Compensation による新しいロボット制御法の研究等にも尽力し、多くの研究業績を創出している。これらの成果が認められ、27個の受賞歴がある。 山田崇恭やまだたかゆき京都大学大学院工学研究科助教トポロジー最適化法の拡張と展開及び製造工程を考慮した最適設計法の構築山田氏は、トポロジー最適化の未解決課題を本質的に解決する方法論の構築に世界に先駆けて成功した。すなわち、レベルセット法に基づいた明瞭な外形形状表現をしながら幾何学的な複雑さを制御可能な方法論を数学理論に基づいて構築した。その方法論は、電磁気学、熱流体力学などの様々な領域の設計問題、均質化理論に基づいた材料設計問題設計問題への展開に成功している。さらには、最適設計法を利用した新たな現象の創成法の確立、製造生産工程を考慮可能な方法論の基本的な考え方の提唱等、当該分野における先駆的かつ独創的な成果がある。また、境界要素法や粒子法、格子ボルツマン法等の様々な数値解析方法へ展開により、これらの特徴を利用した方法論の開発にも成功し構造最適化分野の新しい領域を開拓した。特筆すべきことは、既に103報の学術論文を執筆しており、ISSMO Springer Prizeや文部科学大臣表彰(若手科学者賞)をはじめとして、内外から極めて高く評価されている。
山田崇恭やまだたかゆき京都大学大学院工学研究科助教トポロジー最適化法の拡張と展開及び製造工程を考慮した最適設計法の構築山田氏は、トポロジー最適化の未解決課題を本質的に解決する方法論の構築に世界に先駆けて成功した。すなわち、レベルセット法に基づいた明瞭な外形形状表現をしながら幾何学的な複雑さを制御可能な方法論を数学理論に基づいて構築した。その方法論は、電磁気学、熱流体力学などの様々な領域の設計問題、均質化理論に基づいた材料設計問題設計問題への展開に成功している。さらには、最適設計法を利用した新たな現象の創成法の確立、製造生産工程を考慮可能な方法論の基本的な考え方の提唱等、当該分野における先駆的かつ独創的な成果がある。また、境界要素法や粒子法、格子ボルツマン法等の様々な数値解析方法へ展開により、これらの特徴を利用した方法論の開発にも成功し構造最適化分野の新しい領域を開拓した。特筆すべきことは、既に103報の学術論文を執筆しており、ISSMO Springer Prizeや文部科学大臣表彰(若手科学者賞)をはじめとして、内外から極めて高く評価されている。
第16回 2016年度
 桂誠一郎かつらせいいちろう慶應義塾大学理工学部准教授波動制御に基づく応用抽象化の創成および人間支援ネットワーク応用技術の開拓桂氏はこれまでに、波動方程式に基づく分布定数モデリングを導入することで、無限の共振モードすべてを安定化させる波動制御を確立してきた。従来の制御系は単純化されたバネーマスモデルに基づく制御系設計であるため、高次共振を考慮する際には高次微分を必要としており、工学的な実装が困難となっていた。提案する手法は、むだ時間要素を用いることで、等価的に無限階の微分を達成することが可能であるため、無限次元のモデリングが達成できる。特に、純粋微分ができないという工学実装における問題を解決するもので、ロボットによるフレキシブルかつ高速なモーションの獲得に向けて必要不可欠な理論を構築している。このことは、モデルの抽象化が工学の限界突破に極めて重要であることを示唆するものとなっている。桂氏は波動制御理論を振動抑制制御、温熱感覚の呈示、新型アクチュエータの開発、無線電力伝送の高効率化など、今後の人間支援に資する分野への応用展開を進めている。
桂誠一郎かつらせいいちろう慶應義塾大学理工学部准教授波動制御に基づく応用抽象化の創成および人間支援ネットワーク応用技術の開拓桂氏はこれまでに、波動方程式に基づく分布定数モデリングを導入することで、無限の共振モードすべてを安定化させる波動制御を確立してきた。従来の制御系は単純化されたバネーマスモデルに基づく制御系設計であるため、高次共振を考慮する際には高次微分を必要としており、工学的な実装が困難となっていた。提案する手法は、むだ時間要素を用いることで、等価的に無限階の微分を達成することが可能であるため、無限次元のモデリングが達成できる。特に、純粋微分ができないという工学実装における問題を解決するもので、ロボットによるフレキシブルかつ高速なモーションの獲得に向けて必要不可欠な理論を構築している。このことは、モデルの抽象化が工学の限界突破に極めて重要であることを示唆するものとなっている。桂氏は波動制御理論を振動抑制制御、温熱感覚の呈示、新型アクチュエータの開発、無線電力伝送の高効率化など、今後の人間支援に資する分野への応用展開を進めている。 桜庭裕弥さくらばゆうや国立研究開発法人物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点主任研究員高スピン分極ホイスラー合金材料のスピントロニクスデバイス応用に関する研究「ハーフメタル」は伝導電子が完全スピン分極する特殊な電子構造をもつ物質であり、磁気ランダムアクセスメモリなどあらゆるスピントロニクスデバイスの性能を飛躍的に向上させる究極的材料として期待される。しかし、その存在が理論予測された1980年代以降、膨大な研究が行われたにも関わらず、室温でハーフメタル性に由来する高いデバイス性能が実現された例は皆無であった。桜庭氏は、ホイスラー合金系ハーフメタル材料の開発とそのスピントロニクスデバイス応用の研究に長年に渡り従事し、2005年にCo2MnSiのスピン分極率が90%を超えることを世界で初めて実証し、ハーフメタルホイスラー合金のブレークスルーを起こした。さらに桜庭氏は、実デバイス応用に向けた研究を重ね、2009年にCo2MnSiを用いた磁気抵抗素子で、従来素子よりも一桁大きい磁気抵抗出力を室温で実現した。これはハーフメタルの性能を室温で観測した世界初の成果であり、今後、あらゆるスピントロニクスデバイス発展に貢献することが強く期待される。
桜庭裕弥さくらばゆうや国立研究開発法人物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点主任研究員高スピン分極ホイスラー合金材料のスピントロニクスデバイス応用に関する研究「ハーフメタル」は伝導電子が完全スピン分極する特殊な電子構造をもつ物質であり、磁気ランダムアクセスメモリなどあらゆるスピントロニクスデバイスの性能を飛躍的に向上させる究極的材料として期待される。しかし、その存在が理論予測された1980年代以降、膨大な研究が行われたにも関わらず、室温でハーフメタル性に由来する高いデバイス性能が実現された例は皆無であった。桜庭氏は、ホイスラー合金系ハーフメタル材料の開発とそのスピントロニクスデバイス応用の研究に長年に渡り従事し、2005年にCo2MnSiのスピン分極率が90%を超えることを世界で初めて実証し、ハーフメタルホイスラー合金のブレークスルーを起こした。さらに桜庭氏は、実デバイス応用に向けた研究を重ね、2009年にCo2MnSiを用いた磁気抵抗素子で、従来素子よりも一桁大きい磁気抵抗出力を室温で実現した。これはハーフメタルの性能を室温で観測した世界初の成果であり、今後、あらゆるスピントロニクスデバイス発展に貢献することが強く期待される。 冨岡克広とみおかかつひろ北海道大学大学院情報科学研究科准教授半導体ナノワイヤ集積技術と次世代トランジスタ応用展開に関する研究パソコンなどの集積回路の性能は、回路を構成する電界効果トランジスタ(FET)の微細化と低電圧化を牽引力として向上してきた。しかしながら、近年、微細化によるリーク電流の増加や低電圧化によるスイッチのオン・オフ比の低下などが性能劣化要因として顕在化しており、単純な素子の微細化による性能向上が困難になってきている。この問題に対して、冨岡氏は独創的な方法で、シリコン基板上に高性能半導体材料であるⅢ-V族化合物半導体ナノワイヤを垂直に均一性よく結晶成長させる方法を開発した。さらにこのナノワイヤ構造を用いることで、縦型FETや縦型トンネルFETを作製し、リーク電流が極めて低く、低電圧においてもオン・オフ比が充分に高い優れたトランジスタ特性を実証することに成功しました。これらのFETは、従来の半導体集積回路の消費電力を90%以上低減できる可能性を有しており、FET素子の微細化限界を打破する素子として、今後の発展が期待できる。
冨岡克広とみおかかつひろ北海道大学大学院情報科学研究科准教授半導体ナノワイヤ集積技術と次世代トランジスタ応用展開に関する研究パソコンなどの集積回路の性能は、回路を構成する電界効果トランジスタ(FET)の微細化と低電圧化を牽引力として向上してきた。しかしながら、近年、微細化によるリーク電流の増加や低電圧化によるスイッチのオン・オフ比の低下などが性能劣化要因として顕在化しており、単純な素子の微細化による性能向上が困難になってきている。この問題に対して、冨岡氏は独創的な方法で、シリコン基板上に高性能半導体材料であるⅢ-V族化合物半導体ナノワイヤを垂直に均一性よく結晶成長させる方法を開発した。さらにこのナノワイヤ構造を用いることで、縦型FETや縦型トンネルFETを作製し、リーク電流が極めて低く、低電圧においてもオン・オフ比が充分に高い優れたトランジスタ特性を実証することに成功しました。これらのFETは、従来の半導体集積回路の消費電力を90%以上低減できる可能性を有しており、FET素子の微細化限界を打破する素子として、今後の発展が期待できる。 西山大樹にしやまひろき東北大学大学院情報科学研究科准教授移動端末間通信技術の研究ならびにスマホdeリレーの開発通信機を搭載した移動体の例としては人、自動車、船舶、航空機に加えてドローンやロボットなど様々あるが、従来の移動端末間通信技術の多くは、異なる種類の移動端末が混在する環境下ではその性能が著しく低下してしまう。そのため、一対一の近接ペア通信を除き、実用化・普及展開にまで至った事例は存在していない。
西山大樹にしやまひろき東北大学大学院情報科学研究科准教授移動端末間通信技術の研究ならびにスマホdeリレーの開発通信機を搭載した移動体の例としては人、自動車、船舶、航空機に加えてドローンやロボットなど様々あるが、従来の移動端末間通信技術の多くは、異なる種類の移動端末が混在する環境下ではその性能が著しく低下してしまう。そのため、一対一の近接ペア通信を除き、実用化・普及展開にまで至った事例は存在していない。
これに対し西山氏は、同一空間内に存在する移動特性の異なる多数の移動端末間で効率的に通信を行うことを可能にする技術を確立することに成功した。同技術をスマートフォンに実装したプロトタイプ27台を用いた実証実験にも成功しており、当該成果は国際電気通信連合電気通信標準化部門(ITU-T)にも寄与文書として入力されている。なお、同技術については国際特許出願中であり、商標登録と民間企業への技術移転も完了しており、2016年には「スマホdeリレー®」として商用化され、テレビ・新聞等のメディアでも多数報道されるに至っている。 細井厚志ほそいあつし早稲田大学理工学術院准教授繊維強化複合材料の長期信頼性評価技術の確立とその応用地球温暖化防止及びCO2排出削減、省エネルギー化を推進するために、次世代電気自動車やエネルギーデバイス、電子デバイス等に軽量で機械的・電気的・熱的特性に優れる炭素系複合材料の適用が期待されている。細井氏は実験及び電磁気学、破壊力学、損傷力学に基づき、情報科学を応用した学際的な研究を推進し、繊維強化複合材料(FRP)の(Ⅰ)マイクロ波による非接触・非破壊損傷評価技術の構築、(Ⅱ)超高サイクル疲労特性評価技術及び寿命予測シミュレーション技術の構築、について取り組み機械・構造材料に向けた寿命評価基盤技術を構築した。非破壊損傷評価技術については、マイクロ波を用いた評価装置を構築し、FRP積層板中の7.5µmの剥離を検出することに成功した。疲労寿命評価技術について、独自に加速試験手法を確立し、世界で初めて炭素繊維強化複合材料(CFRP)積層板の超高サイクル特有の疲労損傷進展挙動を明らかにし、損傷発生寿命を予測できる技術を構築した。これらの成果は非破壊検査製品や潮流発電ブレードの設計技術、ジェットエンジン部材の材料開発技術に応用されている。
細井厚志ほそいあつし早稲田大学理工学術院准教授繊維強化複合材料の長期信頼性評価技術の確立とその応用地球温暖化防止及びCO2排出削減、省エネルギー化を推進するために、次世代電気自動車やエネルギーデバイス、電子デバイス等に軽量で機械的・電気的・熱的特性に優れる炭素系複合材料の適用が期待されている。細井氏は実験及び電磁気学、破壊力学、損傷力学に基づき、情報科学を応用した学際的な研究を推進し、繊維強化複合材料(FRP)の(Ⅰ)マイクロ波による非接触・非破壊損傷評価技術の構築、(Ⅱ)超高サイクル疲労特性評価技術及び寿命予測シミュレーション技術の構築、について取り組み機械・構造材料に向けた寿命評価基盤技術を構築した。非破壊損傷評価技術については、マイクロ波を用いた評価装置を構築し、FRP積層板中の7.5µmの剥離を検出することに成功した。疲労寿命評価技術について、独自に加速試験手法を確立し、世界で初めて炭素繊維強化複合材料(CFRP)積層板の超高サイクル特有の疲労損傷進展挙動を明らかにし、損傷発生寿命を予測できる技術を構築した。これらの成果は非破壊検査製品や潮流発電ブレードの設計技術、ジェットエンジン部材の材料開発技術に応用されている。 山﨑俊彦やまさきとしひこ東京大学大学院情報理工学系研究科准教授ビッグ・マルチメディア・データを用いた「魅力工学」の先駆的研究山﨑氏は画像・映像・テキスト・メタデータなどのビッグ・マルチメディア・データを用いた「魅力工学」という研究領域を新たに提唱し、機械学習・深層学習、統計処理、グラフ信号処理、最適化技術を駆使した先駆的な研究を行っている。人間は、人やモノ・コトに対して魅力を感じたり好みがあったりする。魅力とは個人の趣味・嗜好の問題でありそれを解析することはできないと考えられてきた。逆に魅力的な人・モノ・コトを作り上げるのも経験や勘、センスによるもので方法論的なアプローチは難しいとされてきた。「魅力工学」では魅力度に関連する数値を予測するだけでなく、どのパラメータがどの程度寄与してその数値に至っているかを工学的に明らかにし、さらにその魅力を向上・増強させるためにはどのようにしたらよいかまでをも支援する試みを行っている。これまでに、婚活・妊活、プレゼン、MOOC、不動産、テレビ・CM、SNS、観光、マーケティングなど様々な分野の企業と共同研究や産学連携に至っている。
山﨑俊彦やまさきとしひこ東京大学大学院情報理工学系研究科准教授ビッグ・マルチメディア・データを用いた「魅力工学」の先駆的研究山﨑氏は画像・映像・テキスト・メタデータなどのビッグ・マルチメディア・データを用いた「魅力工学」という研究領域を新たに提唱し、機械学習・深層学習、統計処理、グラフ信号処理、最適化技術を駆使した先駆的な研究を行っている。人間は、人やモノ・コトに対して魅力を感じたり好みがあったりする。魅力とは個人の趣味・嗜好の問題でありそれを解析することはできないと考えられてきた。逆に魅力的な人・モノ・コトを作り上げるのも経験や勘、センスによるもので方法論的なアプローチは難しいとされてきた。「魅力工学」では魅力度に関連する数値を予測するだけでなく、どのパラメータがどの程度寄与してその数値に至っているかを工学的に明らかにし、さらにその魅力を向上・増強させるためにはどのようにしたらよいかまでをも支援する試みを行っている。これまでに、婚活・妊活、プレゼン、MOOC、不動産、テレビ・CM、SNS、観光、マーケティングなど様々な分野の企業と共同研究や産学連携に至っている。 山本倫久やまもとみちひさ東京大学大学院工学系研究科講師固体中の電子相関と量子力学的自由度の制御と伝送の研究山本氏は、半導体微細構造やグラフェンにおける量子力学的な自由度や電子相関状態の精密な制御と検出の技術を確立し、それを基盤とする独自の方法によってこれまで伝送が不可能であった量子力学的な自由度を固体の電気回路で伝送、制御することに成功した。特に、情報伝送のチャネルとなる一次元量子細線における電子相関効果を、量子細線を2本並べた独創的な実験で明らかにし、電子の波動関数(電子波)の位相、単一電子の量子力学的なスピン情報を、一次元チャネルを介して長距離伝送させることに成功した。さらに、結晶性が高い2層グラフェンにおいて電子波の回転に相当する自由度“バレー”の流れを電気的に生成、検出することに成功した。これらは、いずれも世界初の快挙である。この成果は、原理的にエネルギー散逸のない量子回路を用いた量子情報処理や、スピントロニクスに次ぐ次世代の非電荷系低消費電力エレクトロニクスとして期待されるバレークトロニクスの新概念の創出、発展に大きく寄与するものである。
山本倫久やまもとみちひさ東京大学大学院工学系研究科講師固体中の電子相関と量子力学的自由度の制御と伝送の研究山本氏は、半導体微細構造やグラフェンにおける量子力学的な自由度や電子相関状態の精密な制御と検出の技術を確立し、それを基盤とする独自の方法によってこれまで伝送が不可能であった量子力学的な自由度を固体の電気回路で伝送、制御することに成功した。特に、情報伝送のチャネルとなる一次元量子細線における電子相関効果を、量子細線を2本並べた独創的な実験で明らかにし、電子の波動関数(電子波)の位相、単一電子の量子力学的なスピン情報を、一次元チャネルを介して長距離伝送させることに成功した。さらに、結晶性が高い2層グラフェンにおいて電子波の回転に相当する自由度“バレー”の流れを電気的に生成、検出することに成功した。これらは、いずれも世界初の快挙である。この成果は、原理的にエネルギー散逸のない量子回路を用いた量子情報処理や、スピントロニクスに次ぐ次世代の非電荷系低消費電力エレクトロニクスとして期待されるバレークトロニクスの新概念の創出、発展に大きく寄与するものである。
第15回 2015年度
 千葉大地ちばだいち東京大学大学院工学系研究科准教授磁性の電界効果のデバイス応用に関する研究千葉氏は、「一度作った磁石の性質は後から変えられない」という常識を覆す、数多くの先駆的かつ革新的な成果をあげてきた。第一の成果は、磁界や温度を変えることなく、磁性体の磁化方向や磁力を電界でリバーシブルにスイッチすること(電界誘起磁化ベクトル制御・電界誘起磁性相転移)に世界で初めて成功したことである。磁性を帯びた半導体だけでなく、すでに研究しつくされたかに思われている鉄・コバルト・ニッケルなど極めてポピュラーな磁性金属の潜在能力を大きく引き出すことに貢献した。また、当該技術を磁気記録の超省エネルギ書込み技術へ応用展開するという、今日こそ数多くの研究者が取り組みはじめているテーマにいち早く注目し、世界を牽引する成果を数多く示してきた。磁性をオン・オフするという取り組みは、磁気記録のみにとどまらず、その枠を超えた新たな応用展開にもつながる可能性が期待される点も注目される。
千葉大地ちばだいち東京大学大学院工学系研究科准教授磁性の電界効果のデバイス応用に関する研究千葉氏は、「一度作った磁石の性質は後から変えられない」という常識を覆す、数多くの先駆的かつ革新的な成果をあげてきた。第一の成果は、磁界や温度を変えることなく、磁性体の磁化方向や磁力を電界でリバーシブルにスイッチすること(電界誘起磁化ベクトル制御・電界誘起磁性相転移)に世界で初めて成功したことである。磁性を帯びた半導体だけでなく、すでに研究しつくされたかに思われている鉄・コバルト・ニッケルなど極めてポピュラーな磁性金属の潜在能力を大きく引き出すことに貢献した。また、当該技術を磁気記録の超省エネルギ書込み技術へ応用展開するという、今日こそ数多くの研究者が取り組みはじめているテーマにいち早く注目し、世界を牽引する成果を数多く示してきた。磁性をオン・オフするという取り組みは、磁気記録のみにとどまらず、その枠を超えた新たな応用展開にもつながる可能性が期待される点も注目される。 伊藤康一いとうこういち東北大学大学院情報科学研究科助教高精度画像マッチングに基づく生体認証に関する研究伊藤氏は、画像の位相情報を用いた超高精度画像マッチング技術である「位相限定相関法」および各種高精度化手法に関する研究を行ってきた。その中で、画像間の類似性を高精度に評価するために「局所位相特徴」を考案するとともに、生体認証の各種問題に応用して、多大なインパクトを与えている。これまでに、指紋・顔‣交際・虹彩・掌紋・指関節紋・歯科Ⅹ線画像を用いた個人認証に局所位相特徴を応用し、公開されている評価用データベースを用いた実験により世界最高水準の認証性能を有することを実証している。また、スマートフォン向け手のひら認証アプリ、個人認証機能搭載ドアレバー、歯牙情報に基づく身元確認支援ソフトなどの実用化研究を行っている。
伊藤康一いとうこういち東北大学大学院情報科学研究科助教高精度画像マッチングに基づく生体認証に関する研究伊藤氏は、画像の位相情報を用いた超高精度画像マッチング技術である「位相限定相関法」および各種高精度化手法に関する研究を行ってきた。その中で、画像間の類似性を高精度に評価するために「局所位相特徴」を考案するとともに、生体認証の各種問題に応用して、多大なインパクトを与えている。これまでに、指紋・顔‣交際・虹彩・掌紋・指関節紋・歯科Ⅹ線画像を用いた個人認証に局所位相特徴を応用し、公開されている評価用データベースを用いた実験により世界最高水準の認証性能を有することを実証している。また、スマートフォン向け手のひら認証アプリ、個人認証機能搭載ドアレバー、歯牙情報に基づく身元確認支援ソフトなどの実用化研究を行っている。 岡崎直観おかざきなおあき東北大学大学院情報科学研究科准教授自然言語処理による知識の自動獲得と社会観測に関する研究自然言語処理、すなわち言葉を理解する計算機を真に実現するには、人間の持つ常識的な知識を大量の言語データから自動的に学習する研究が欠かせない。岡崎氏は、単語や句の分散表現の学習、関係知識や因果関係知識の自動獲得、言い換え知識の自動獲得、知識の柔軟な検索に関する研究で顕著な成果を上げた。さらにこうした研究をデータからの社会観測、すなわち人々の文脈や意見をデータから分析するという重要課題に応用し、東日本大震災後にTwitter上で拡散したデマ・誤情報の大規模解析、福島県の農産物の風評被害に関する大規模言語データ解析など、学際的研究を展開した。研究成果はソフトウェアやサービスとして実用化されただけでなく、データ駆動型ジャーナリズムなど、社会貢献の新しい形を切り拓いた。
岡崎直観おかざきなおあき東北大学大学院情報科学研究科准教授自然言語処理による知識の自動獲得と社会観測に関する研究自然言語処理、すなわち言葉を理解する計算機を真に実現するには、人間の持つ常識的な知識を大量の言語データから自動的に学習する研究が欠かせない。岡崎氏は、単語や句の分散表現の学習、関係知識や因果関係知識の自動獲得、言い換え知識の自動獲得、知識の柔軟な検索に関する研究で顕著な成果を上げた。さらにこうした研究をデータからの社会観測、すなわち人々の文脈や意見をデータから分析するという重要課題に応用し、東日本大震災後にTwitter上で拡散したデマ・誤情報の大規模解析、福島県の農産物の風評被害に関する大規模言語データ解析など、学際的研究を展開した。研究成果はソフトウェアやサービスとして実用化されただけでなく、データ駆動型ジャーナリズムなど、社会貢献の新しい形を切り拓いた。 加地範匡かじのりただ名古屋大学大学院工学研究科准教授ナノ空間制御による遺伝子情報抽出手法の開発と医療デバイスへの展開加地氏はこれまで分子の自己組織化とナノテクノロジーに立脚することで、超微細加工技術によりナノメートルレベルで精密にサイズ・構造制御されたナノ構造体やナノマテリアルの作製法と、これらのナノ構造体により形成されるナノ空間を用いた超高速遺伝子情報抽出法であるDNA分離技術を確立し、そのデバイス化と高性能化を実現した。さらに遺伝子以外の生体情報抽出技術、具体的には疾病やがんの状態を判断する際の目安となるバイオマーカーを血液1滴から数分で診断するデバイス技術を確立するとともに臨床現場への展開を推進することで、医療デバイスとしての実用化を行った。この成果により、国民が自身の生体情報に基づいて簡便かつ科学的に健康状態を判断することが可能となり、国民の健康に資することが期待できる。
加地範匡かじのりただ名古屋大学大学院工学研究科准教授ナノ空間制御による遺伝子情報抽出手法の開発と医療デバイスへの展開加地氏はこれまで分子の自己組織化とナノテクノロジーに立脚することで、超微細加工技術によりナノメートルレベルで精密にサイズ・構造制御されたナノ構造体やナノマテリアルの作製法と、これらのナノ構造体により形成されるナノ空間を用いた超高速遺伝子情報抽出法であるDNA分離技術を確立し、そのデバイス化と高性能化を実現した。さらに遺伝子以外の生体情報抽出技術、具体的には疾病やがんの状態を判断する際の目安となるバイオマーカーを血液1滴から数分で診断するデバイス技術を確立するとともに臨床現場への展開を推進することで、医療デバイスとしての実用化を行った。この成果により、国民が自身の生体情報に基づいて簡便かつ科学的に健康状態を判断することが可能となり、国民の健康に資することが期待できる。 関谷毅せきたにつよし大阪大学産業科学研究所教授柔軟なシート型エレクトロニクスシステムの開発と応用関谷氏は、「有機材料の柔らかさを活かしたフレキシブル有機トランジスタ」の作製プロセスを確立し、世界に先駆けて、その大規模集積化に成功した。この技術により、大面積センサや大面積アクチュエータを実現し、柔らかいエレクトロニクスの有用性を世界に先駆けて実証してきた。特に、世界で初めて伸縮自在な大面積集積回路、伸縮性有機ディスプレイの開発に成功するなど、大面積エレクトロニクス、伸縮エレクトロニクスという新しい分野を切り拓くなど、エレクトロニクス分野の重要な業績を挙げている。最近では、額に貼り付けるだけで脳状態を可視化できるウェアラブルセンサを開発し、認知症患者と健常者を見分けることに成功している。さらに東京電力㈱とともに、構造物ヘルスケア用大面積センサの開発に成功するなど、柔軟かつ大面積である利点を生かした新しいIoTセンサの開発とその社会実装を産業界と提携し進めている。
関谷毅せきたにつよし大阪大学産業科学研究所教授柔軟なシート型エレクトロニクスシステムの開発と応用関谷氏は、「有機材料の柔らかさを活かしたフレキシブル有機トランジスタ」の作製プロセスを確立し、世界に先駆けて、その大規模集積化に成功した。この技術により、大面積センサや大面積アクチュエータを実現し、柔らかいエレクトロニクスの有用性を世界に先駆けて実証してきた。特に、世界で初めて伸縮自在な大面積集積回路、伸縮性有機ディスプレイの開発に成功するなど、大面積エレクトロニクス、伸縮エレクトロニクスという新しい分野を切り拓くなど、エレクトロニクス分野の重要な業績を挙げている。最近では、額に貼り付けるだけで脳状態を可視化できるウェアラブルセンサを開発し、認知症患者と健常者を見分けることに成功している。さらに東京電力㈱とともに、構造物ヘルスケア用大面積センサの開発に成功するなど、柔軟かつ大面積である利点を生かした新しいIoTセンサの開発とその社会実装を産業界と提携し進めている。 田辺克明たなべかつあき京都大学大学院工学研究科准教授半導体接合技術およびそれを用いた新規高性能光電子デバイスの創出田辺氏は、ウェハ接合技術の検討を行い、機械的、熱的に安定でかつ高導電性のGaAs/InP、GaAs/Si、および、InP/Si接合を得た。なお、化合物半導体とシリコンの直接接合によるオーミック接合の実現は、世界で初めてである。この技術を用いて高速大容量光通信・演算用途のシリコン基板上InAs/GaAs量子ドットレーザを作製し、シリコン上のあらゆる種類の半導体レーザとして世界最小の発振閾値電流密度、最高の発振温度、および、最高の特性温度を達成した。さらに、超高密度光集積回路の実現に向け、世界初のシリコン上ナノレーザとなる、シリコン基板上に集積されたInAs/GaAs量子ドット・フォトニック結晶ナノ共振器レーザの作製にも成功すると同時に、世界最小の発振閾値電力を達成している。また、格子不整合GaAs/InGaAsニ接合太陽電池、シリコン基板上のInGaAs太陽電池、GaAs/Ag/Si接合による表面プラズモン利用型太陽電池、AlGaAs/Siニ接合太陽電池、フレキシブルInAs/GaAs量子ドット太陽電池といった多岐に亘る新規太陽電池の作製に成功した。特に、GaAs/InGaAsニ接合太陽電池は世界初のウェハ接合による多接合太陽電池の実現である。
田辺克明たなべかつあき京都大学大学院工学研究科准教授半導体接合技術およびそれを用いた新規高性能光電子デバイスの創出田辺氏は、ウェハ接合技術の検討を行い、機械的、熱的に安定でかつ高導電性のGaAs/InP、GaAs/Si、および、InP/Si接合を得た。なお、化合物半導体とシリコンの直接接合によるオーミック接合の実現は、世界で初めてである。この技術を用いて高速大容量光通信・演算用途のシリコン基板上InAs/GaAs量子ドットレーザを作製し、シリコン上のあらゆる種類の半導体レーザとして世界最小の発振閾値電流密度、最高の発振温度、および、最高の特性温度を達成した。さらに、超高密度光集積回路の実現に向け、世界初のシリコン上ナノレーザとなる、シリコン基板上に集積されたInAs/GaAs量子ドット・フォトニック結晶ナノ共振器レーザの作製にも成功すると同時に、世界最小の発振閾値電力を達成している。また、格子不整合GaAs/InGaAsニ接合太陽電池、シリコン基板上のInGaAs太陽電池、GaAs/Ag/Si接合による表面プラズモン利用型太陽電池、AlGaAs/Siニ接合太陽電池、フレキシブルInAs/GaAs量子ドット太陽電池といった多岐に亘る新規太陽電池の作製に成功した。特に、GaAs/InGaAsニ接合太陽電池は世界初のウェハ接合による多接合太陽電池の実現である。 湯川正裕ゆかわまさひろ慶應義塾大学理工学部電子工学科准教授新世代情報通信システムのための適応信号処理アルゴリズムの研究適応信号処理は、情報通信システムを支える最も重要な基盤技術の一つとして、音響・通信・画像・レーダーを初めとする広範な目的に応用されている。適応アルゴリズムの高性能化への期待は、近年の目覚ましい情報通信技術の発達とともに高まる一方であるが、従来のアルゴリズムはいずれも、①収束の高速性、②雑音への頑健性、③低計算コスト性の間に深刻なトレードオフを抱えており、ブレークスルーを阻む大きな要因となっていた。
湯川正裕ゆかわまさひろ慶應義塾大学理工学部電子工学科准教授新世代情報通信システムのための適応信号処理アルゴリズムの研究適応信号処理は、情報通信システムを支える最も重要な基盤技術の一つとして、音響・通信・画像・レーダーを初めとする広範な目的に応用されている。適応アルゴリズムの高性能化への期待は、近年の目覚ましい情報通信技術の発達とともに高まる一方であるが、従来のアルゴリズムはいずれも、①収束の高速性、②雑音への頑健性、③低計算コスト性の間に深刻なトレードオフを抱えており、ブレークスルーを阻む大きな要因となっていた。
湯川氏の業績として
1.凸解析・不動点理論を駆使した独創的な技術の開発に2001年から継続的に取り組み、長年未解決だったトレードオフ問題の解消に成功した。
2.再生核理論とスパース最適化を融合することで、非線形モデル選択と関数推定を同時に実行し、モデルと辞書の適応的精錬機能を持つ革新的な適応アルゴリズムを世界に先駆けて提案した。これによって、上記1.の成果を非線形システムに拡張することが可能となり、応用範囲の裾野が格段に広がった。
第14回 2014年度
 杉浦慎哉すぎうらしんや東京農工大学大学院工学研究院准教授次世代高速無線通信方式のための符号化および変復調アルゴリズムに関する研究無線通信の分野では周波数資源が限られている中、5年ごとに10倍以上の無線リンク通信速度の向上が求められているが、杉浦氏は次世代高速無線通信システムのための符号化及び変復調技術に従事し、この重要課題の解決手法となりうる技術を提案してきた。代表的成果として、シングルRF送信機で動作可能な高速レートマルチアンテナ伝送技術である空間変調方式があり、主要開発者として専門家に評価されている。特に提案技術はRF一系統で動作可能なためアンテナ数に対する実用上スケーラビリティが高い。したがって、移動端末や簡易基地局などにおいて現実的な大規模マルチアンテナ伝送が可能となり、これまで鋭意研究されてきたMIMO技術に新しい展開を与えるものといえる。
杉浦慎哉すぎうらしんや東京農工大学大学院工学研究院准教授次世代高速無線通信方式のための符号化および変復調アルゴリズムに関する研究無線通信の分野では周波数資源が限られている中、5年ごとに10倍以上の無線リンク通信速度の向上が求められているが、杉浦氏は次世代高速無線通信システムのための符号化及び変復調技術に従事し、この重要課題の解決手法となりうる技術を提案してきた。代表的成果として、シングルRF送信機で動作可能な高速レートマルチアンテナ伝送技術である空間変調方式があり、主要開発者として専門家に評価されている。特に提案技術はRF一系統で動作可能なためアンテナ数に対する実用上スケーラビリティが高い。したがって、移動端末や簡易基地局などにおいて現実的な大規模マルチアンテナ伝送が可能となり、これまで鋭意研究されてきたMIMO技術に新しい展開を与えるものといえる。 青井伸也あおいしんや京都大学大学院工学研究科講師生物の適応的歩行制御機序の解明と脚ロボット制御への応用青井氏は、頑健で適応的な歩行能力を有する脚ロボットの開発を目指し、生物の歩行制御機序の解明と脚ロボットへの応用を目指した研究を行ってきた。生物は多様な感覚情報を統合し、冗長多自由度な筋骨格系を巧みに操ることで適応的に歩行する。生物の運動制御における冗長性の問題はベルンシュタイン問題と呼ばれ、半世紀以上にわたる実験的・理論的考察にも関わらず未解決であったが、ヒトからムカデまで様々な生物を対象に、神経筋骨格系の計測に基づく解析的手法と数理モデルを用いた構成論的手法を統合し、運動学・筋シナジーと呼ばれる低次元構造や足の接地に関する感覚運動協調に着目することで、生物が冗長性の問題を解決し、適応的な歩行を実現する脳情報処理機能の解明に貢献してきた。そして得られる知見を工学的に具現化することで、適応機能を示す脚ロボットの開発に成功してきた。これらの成果は、生物学からロボット工学まで幅広い学術分野に貢献し、それぞれで高い評価を受けている。
青井伸也あおいしんや京都大学大学院工学研究科講師生物の適応的歩行制御機序の解明と脚ロボット制御への応用青井氏は、頑健で適応的な歩行能力を有する脚ロボットの開発を目指し、生物の歩行制御機序の解明と脚ロボットへの応用を目指した研究を行ってきた。生物は多様な感覚情報を統合し、冗長多自由度な筋骨格系を巧みに操ることで適応的に歩行する。生物の運動制御における冗長性の問題はベルンシュタイン問題と呼ばれ、半世紀以上にわたる実験的・理論的考察にも関わらず未解決であったが、ヒトからムカデまで様々な生物を対象に、神経筋骨格系の計測に基づく解析的手法と数理モデルを用いた構成論的手法を統合し、運動学・筋シナジーと呼ばれる低次元構造や足の接地に関する感覚運動協調に着目することで、生物が冗長性の問題を解決し、適応的な歩行を実現する脳情報処理機能の解明に貢献してきた。そして得られる知見を工学的に具現化することで、適応機能を示す脚ロボットの開発に成功してきた。これらの成果は、生物学からロボット工学まで幅広い学術分野に貢献し、それぞれで高い評価を受けている。 今出完いまでまもる大阪大学大学院工学研究科助教大口径高品質GaNウエハを実現するNaフラックスポイントシード法の開発窒化ガリウム(GaN)は、白色発光ダイオードだけでなく、電力損失がSiの1/10以下のパワーデバイスや、携帯電話の1000倍以上の通信速度・容量を有する超高速動作トランジスタ用材料として期待されている。しかしながら、Siのように無欠陥で大口径な単結晶成長は極めて困難であるため、大口径高品質GaNウエハは実現していない。今出氏は、Naフラックス法と呼ばれるGaN結晶液相成長法において、欠陥終端メカニズムを有するポイントシード法を発見し、世界で初めて無欠陥GaN単結晶を実現した。さらに、多数のGaN単結晶同士を欠陥の発生を抑制しながら結合できる結合成長法を開発し、短時間で大口径(4インチ)な低欠陥GaN単結晶の作製に世界で初めて成功した。これらの業績により、これまで実用化の障壁とされていた6インチサイズの低欠陥GaNウエハの実現が期待されており、我が国におけるGaNデバイス研究開発の加速に大きく貢献した。
今出完いまでまもる大阪大学大学院工学研究科助教大口径高品質GaNウエハを実現するNaフラックスポイントシード法の開発窒化ガリウム(GaN)は、白色発光ダイオードだけでなく、電力損失がSiの1/10以下のパワーデバイスや、携帯電話の1000倍以上の通信速度・容量を有する超高速動作トランジスタ用材料として期待されている。しかしながら、Siのように無欠陥で大口径な単結晶成長は極めて困難であるため、大口径高品質GaNウエハは実現していない。今出氏は、Naフラックス法と呼ばれるGaN結晶液相成長法において、欠陥終端メカニズムを有するポイントシード法を発見し、世界で初めて無欠陥GaN単結晶を実現した。さらに、多数のGaN単結晶同士を欠陥の発生を抑制しながら結合できる結合成長法を開発し、短時間で大口径(4インチ)な低欠陥GaN単結晶の作製に世界で初めて成功した。これらの業績により、これまで実用化の障壁とされていた6インチサイズの低欠陥GaNウエハの実現が期待されており、我が国におけるGaNデバイス研究開発の加速に大きく貢献した。 大林武おおばやしたけし東北大学大学院情報科学研究科准教授遺伝子発現量データに基づく遺伝子機能予測手法の開発と大規模実装高等生物の半数以上の遺伝子機能は未知であり、また機能の判明している遺伝子でも多面的な機能の一部が判明しているにしか過ぎない。そのため遺伝子機能を大規模推定するための情報科学的アプローチが不可欠になる。大林氏はまず、モデル植物シロイヌナズナの網羅的遺伝子発現量解析を行い、従来発現変化を示さないと考えられてきた遺伝子を含めて、ほぼ全ての遺伝子が組織特異的なパターンを示すことを見いだした。発現プロファイルが類似している遺伝子(共発現遺伝子)の機能は類似しているため、この共発現遺伝子ペアを大規模に同定することで、遺伝子機能の網羅的推定を行うフレームワークを開発した。そこでは、類似性に基づく遺伝子機能分類に留まらず、環境特異性、進化保存性を取り込んだ遺伝子ネットワークとして多様な遺伝子機能を理解することを考案し、この手法を統計的有意性に基づく検証のみならず、実験系研究者が直接利用できるプラットフォーム(遺伝子共発現データーベースATTED-II, COXPRESdb)として実用化した。
大林武おおばやしたけし東北大学大学院情報科学研究科准教授遺伝子発現量データに基づく遺伝子機能予測手法の開発と大規模実装高等生物の半数以上の遺伝子機能は未知であり、また機能の判明している遺伝子でも多面的な機能の一部が判明しているにしか過ぎない。そのため遺伝子機能を大規模推定するための情報科学的アプローチが不可欠になる。大林氏はまず、モデル植物シロイヌナズナの網羅的遺伝子発現量解析を行い、従来発現変化を示さないと考えられてきた遺伝子を含めて、ほぼ全ての遺伝子が組織特異的なパターンを示すことを見いだした。発現プロファイルが類似している遺伝子(共発現遺伝子)の機能は類似しているため、この共発現遺伝子ペアを大規模に同定することで、遺伝子機能の網羅的推定を行うフレームワークを開発した。そこでは、類似性に基づく遺伝子機能分類に留まらず、環境特異性、進化保存性を取り込んだ遺伝子ネットワークとして多様な遺伝子機能を理解することを考案し、この手法を統計的有意性に基づく検証のみならず、実験系研究者が直接利用できるプラットフォーム(遺伝子共発現データーベースATTED-II, COXPRESdb)として実用化した。 佐藤琢哉さとうたくや九州大学大学院理学研究院准教授超短光パルスを用いたマグノニクスの開拓磁性体中のスピン波を情報媒体として生成・制御・検出するマグノニクスが近年になって注目されるようになった。これまでスピン波はマイクロ波やスピン偏極電流によって生成されていたが、電極等の微細加工による空間的制約がスピン波の任意な制御の妨げとなっていた。佐藤氏はフェムト秒光パルスの偏光自由度を駆使し、光スポットを空間整形することで、スピン波の生成・伝播方向の制御・位相を含めた時間空間分解イメージングを成し遂げた。これらは3つとも世界初の快挙である。また、光パルスの任意の偏光状態を反磁性体のテラヘルツ・磁化振動モードとして1対1で転写し、そのモードを別の光パルスを用いて読み取ることに成功した。この成果は、光が持つ偏光自由度を用いた多重度・偏光メモリーの研究開発につながると期待される。このような光パルスを用いた超高速かつ非熱的なスピン制御によって、光マグノニクスという全く新しい分野を切り開き、新しい光磁気デバイスの可能性を見出した。
佐藤琢哉さとうたくや九州大学大学院理学研究院准教授超短光パルスを用いたマグノニクスの開拓磁性体中のスピン波を情報媒体として生成・制御・検出するマグノニクスが近年になって注目されるようになった。これまでスピン波はマイクロ波やスピン偏極電流によって生成されていたが、電極等の微細加工による空間的制約がスピン波の任意な制御の妨げとなっていた。佐藤氏はフェムト秒光パルスの偏光自由度を駆使し、光スポットを空間整形することで、スピン波の生成・伝播方向の制御・位相を含めた時間空間分解イメージングを成し遂げた。これらは3つとも世界初の快挙である。また、光パルスの任意の偏光状態を反磁性体のテラヘルツ・磁化振動モードとして1対1で転写し、そのモードを別の光パルスを用いて読み取ることに成功した。この成果は、光が持つ偏光自由度を用いた多重度・偏光メモリーの研究開発につながると期待される。このような光パルスを用いた超高速かつ非熱的なスピン制御によって、光マグノニクスという全く新しい分野を切り開き、新しい光磁気デバイスの可能性を見出した。 高見剛たかみつよし大阪大学大学院理学研究科助教多自由度結合による環境調和型エレクトロニクス情報科学技術の進歩を担っている半導体エレクトロニクスは、電子の持つ電荷の自由度のみを用いて大発展を遂げてきた。高見氏は、電子に電荷以外の内部自由度(スピン、軌道)や外部自由度(フォノン、原子核)を結合させるとさらなる飛躍が期待できるとの着想のもと、電荷のみを用いていた従来のエレクトロニクスでは現れなかった新しい電子物性や機能を創出することを目的としている。
高見剛たかみつよし大阪大学大学院理学研究科助教多自由度結合による環境調和型エレクトロニクス情報科学技術の進歩を担っている半導体エレクトロニクスは、電子の持つ電荷の自由度のみを用いて大発展を遂げてきた。高見氏は、電子に電荷以外の内部自由度(スピン、軌道)や外部自由度(フォノン、原子核)を結合させるとさらなる飛躍が期待できるとの着想のもと、電荷のみを用いていた従来のエレクトロニクスでは現れなかった新しい電子物性や機能を創出することを目的としている。
おもな業績として、(1)スピン・軌道結合の熱電変換への役割、(2)スピン・フォノン結合によるスピンポーラロンの形成、(3)電子・水素原子核結合による水素代替エネルギーへの展開、があげられる。特に、今後ますます発展する情報科学の根幹を担うエネルギーの需要増大が見込まれる中、環境負荷の少ないエネルギー変換や貯蔵にも直結するエレクトロニクスに関する成果を上げた。 野﨑隆行のざきたかゆき産業技術総合研究所ナノスピントロニクス研究センター主任研究員電界による高速スピン制御技術の確立とスピントロニクスデバイスへの応用野﨑氏は、金属磁石の磁化(電子スピン)を電界によって操作する新しい制御技術を確立し、スピントロニクスデバイスの超低駆動電力化に新たな道を拓いた。スピントロニクスの特徴は磁石の情報不揮発を利用した低待機電力性にあるが、一方で情報の操作に必要となる磁化の向きや運動の制御には大きな電流の通電を必要とし、駆動電力低減の弊害となっている。これに対して候補者は、数原子層まで超薄膜化した金属磁石の磁化の向きやすい方向(磁気異方性)を電界で制御する新しい技術開発に取り組み、実用上重要なトンネル磁気抵抗素子での実現に成功した。さらに、電界による高速スピン運動制御の実証にも世界で初めて成功し、電界スピントロニクスの実現に重要な進展をもたらした。
野﨑隆行のざきたかゆき産業技術総合研究所ナノスピントロニクス研究センター主任研究員電界による高速スピン制御技術の確立とスピントロニクスデバイスへの応用野﨑氏は、金属磁石の磁化(電子スピン)を電界によって操作する新しい制御技術を確立し、スピントロニクスデバイスの超低駆動電力化に新たな道を拓いた。スピントロニクスの特徴は磁石の情報不揮発を利用した低待機電力性にあるが、一方で情報の操作に必要となる磁化の向きや運動の制御には大きな電流の通電を必要とし、駆動電力低減の弊害となっている。これに対して候補者は、数原子層まで超薄膜化した金属磁石の磁化の向きやすい方向(磁気異方性)を電界で制御する新しい技術開発に取り組み、実用上重要なトンネル磁気抵抗素子での実現に成功した。さらに、電界による高速スピン運動制御の実証にも世界で初めて成功し、電界スピントロニクスの実現に重要な進展をもたらした。
これらの成果は待機電力だけでなく駆動電力も省エネルギーな新規スピントロニクスデバイスの開発に寄与し、高速応答性・大容量性・高信頼性を兼ね備えたグリーンITの実現につながると期待される。 山内利宏やまうちとしひろ岡山大学大学院自然科学研究科准教授OS構成要素の独立化によるプロセス実行制御機構と安全なシステムソフトウェアに関する研究山内氏はオペレーティングシステム(OS)のプログラムの実行単位であるプロセスからプロセッサ割当内容を分離する機構を確立した。これにより、プロセスグループ単位でのサービスの性能保証を実現する新しい実行制御機構を実現し、かつプロセッサ資源を対象とするアクセス制御モデルを初めて提案した。この機構を研究開発し、プロセス実行速度を自由に調整できる方式を実現した。また、プロセス構成要素の新たな管理手法を示し、高速なプロセスの生成と削除の処理を実現した。これにより、従来OSのプロセス生成処理の限界を超える高速化を実現した。さらに、不正アクセスなどが起こった場合、攻撃者が侵入の痕跡を消去することを防止する仮想化技術を用いたログの確実な保護機構を提案し、攻撃内容を解析可能にする技術を初めて実現した。近年非常に多く悪用されているUse-After-Free脆弱性を既存のプログラムを修正することなく防止できる新しい手法も確立し、高い安全性を実現するシステムソフトウェアの構成法を開拓した。
山内利宏やまうちとしひろ岡山大学大学院自然科学研究科准教授OS構成要素の独立化によるプロセス実行制御機構と安全なシステムソフトウェアに関する研究山内氏はオペレーティングシステム(OS)のプログラムの実行単位であるプロセスからプロセッサ割当内容を分離する機構を確立した。これにより、プロセスグループ単位でのサービスの性能保証を実現する新しい実行制御機構を実現し、かつプロセッサ資源を対象とするアクセス制御モデルを初めて提案した。この機構を研究開発し、プロセス実行速度を自由に調整できる方式を実現した。また、プロセス構成要素の新たな管理手法を示し、高速なプロセスの生成と削除の処理を実現した。これにより、従来OSのプロセス生成処理の限界を超える高速化を実現した。さらに、不正アクセスなどが起こった場合、攻撃者が侵入の痕跡を消去することを防止する仮想化技術を用いたログの確実な保護機構を提案し、攻撃内容を解析可能にする技術を初めて実現した。近年非常に多く悪用されているUse-After-Free脆弱性を既存のプログラムを修正することなく防止できる新しい手法も確立し、高い安全性を実現するシステムソフトウェアの構成法を開拓した。
第13回 2013年度
 安藤和也あんどうかずや慶應義塾大学理工学部専任講師動的スピン流生成現象の開拓とスピントロニクスへの応用電子の電荷自由度と電流だけでは実現困難なデバイス機能創出の指導原理として、スピン自由度とスピン流に基づくスピントロニクスがある。安藤氏は、スピン流と磁化ダイナミクスとの相関現象という新境地を切り拓くことでスピン流生成・検出の物理・技術体系を明らかにし、近代スピントロニクスの基盤を構築した。特に著しい業績として、磁化ダイナミクスからのスピン流生成「動的スピン流生成」手法の確立がある。これにより歴史上初めてあらゆる物質・環境中のスピン流研究のルートが示され、シリコン中のスピンホール効果定量へと繋がったことで、世界中の研究者に衝撃を与えた。また動的スピン流生成を絶縁体へと応用することで非線形スピントロニクス機能を見出し、更にこれまでの常識を覆す導電性高分子中の巨大スピン流-電流変換の発見はスピン軌道散乱増幅による新時代のスピントロニクスへの扉を開いた。
安藤和也あんどうかずや慶應義塾大学理工学部専任講師動的スピン流生成現象の開拓とスピントロニクスへの応用電子の電荷自由度と電流だけでは実現困難なデバイス機能創出の指導原理として、スピン自由度とスピン流に基づくスピントロニクスがある。安藤氏は、スピン流と磁化ダイナミクスとの相関現象という新境地を切り拓くことでスピン流生成・検出の物理・技術体系を明らかにし、近代スピントロニクスの基盤を構築した。特に著しい業績として、磁化ダイナミクスからのスピン流生成「動的スピン流生成」手法の確立がある。これにより歴史上初めてあらゆる物質・環境中のスピン流研究のルートが示され、シリコン中のスピンホール効果定量へと繋がったことで、世界中の研究者に衝撃を与えた。また動的スピン流生成を絶縁体へと応用することで非線形スピントロニクス機能を見出し、更にこれまでの常識を覆す導電性高分子中の巨大スピン流-電流変換の発見はスピン軌道散乱増幅による新時代のスピントロニクスへの扉を開いた。 伊野文彦いのふみひこ大阪大学 大学院情報科学研究科准教授GPUにおける細粒度サイクル共有技術とその応用に関する研究伊野氏はGPU(Graphics Processing Unit)におけるミリ秒単位(刹那)の遊休時間を遠隔から活用し、ユーザの対話的な操作を妨げることなく大量の独立タスクを高速処理するための細粒度サイクル共有技術を確立した。本来、GPUの用途は画面表示であり、その設計は共有を考慮していない。従って、遠隔から投入された計算がGPUを専有してしまい、画面表示の滞りが共有の実用化を妨げていた。そこで伊野氏はGPUプログラミングモデルと親和性の高い強調マルチタスク技術を開発し、滑らかな画面表示と計算の高速化を実現した。また、遊休時間の長さの分布を数理的にモデル化し、高い性能を期待できる遊休GPUを選択する手法を開発した。これらにより、単一ユーザに専有されてきたGPUを、ネットワーク上の計算アクセラレータとして活用する道を拓いた。また、バイオ情報学や医用画像工学への応用により、企業や大学における遊休GPUの潜在的な計算性能を定量的に明らかにした。
伊野文彦いのふみひこ大阪大学 大学院情報科学研究科准教授GPUにおける細粒度サイクル共有技術とその応用に関する研究伊野氏はGPU(Graphics Processing Unit)におけるミリ秒単位(刹那)の遊休時間を遠隔から活用し、ユーザの対話的な操作を妨げることなく大量の独立タスクを高速処理するための細粒度サイクル共有技術を確立した。本来、GPUの用途は画面表示であり、その設計は共有を考慮していない。従って、遠隔から投入された計算がGPUを専有してしまい、画面表示の滞りが共有の実用化を妨げていた。そこで伊野氏はGPUプログラミングモデルと親和性の高い強調マルチタスク技術を開発し、滑らかな画面表示と計算の高速化を実現した。また、遊休時間の長さの分布を数理的にモデル化し、高い性能を期待できる遊休GPUを選択する手法を開発した。これらにより、単一ユーザに専有されてきたGPUを、ネットワーク上の計算アクセラレータとして活用する道を拓いた。また、バイオ情報学や医用画像工学への応用により、企業や大学における遊休GPUの潜在的な計算性能を定量的に明らかにした。 金井俊光かないとしみつ横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門准教授高品質チューナブルコロイドフォトニック結晶の作製と応用に関する研究フォトニック結晶は光の半導体とも呼ばれ、情報通信分野や映像分野などに革命をもたらす材料として注目されている。金井氏は安価で大量生産が期待でき、また従来のハードなフォトニック結晶では難しいチューニング特性を有した有機系コロイドフォトニック結晶を、大面積で高品質で作製できる画期的な方法を確立した。マイクロ流路内にコロイド分散液をパルス流動させることにより、c㎡サイズの単結晶コロイド結晶を形成させ、引き続き紫外線照射による光重合を行うことにより、大面積単結晶体をゲルフィルム内に固定化するプロセスを確立した。本結晶は外場や外部刺激により、フォトニックバンドギャップ周波数を大幅にチューニングすることができ、ブラッグ反射色による発色をフルカラーで制御できる。またマイクロ流体技術と光重合プロセスを組み合わせることにより、球状やカプセル状のチューナブルコロイドフォトニック結晶の作製にも成功し、形状由来の新しい応用を見出した。
金井俊光かないとしみつ横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門准教授高品質チューナブルコロイドフォトニック結晶の作製と応用に関する研究フォトニック結晶は光の半導体とも呼ばれ、情報通信分野や映像分野などに革命をもたらす材料として注目されている。金井氏は安価で大量生産が期待でき、また従来のハードなフォトニック結晶では難しいチューニング特性を有した有機系コロイドフォトニック結晶を、大面積で高品質で作製できる画期的な方法を確立した。マイクロ流路内にコロイド分散液をパルス流動させることにより、c㎡サイズの単結晶コロイド結晶を形成させ、引き続き紫外線照射による光重合を行うことにより、大面積単結晶体をゲルフィルム内に固定化するプロセスを確立した。本結晶は外場や外部刺激により、フォトニックバンドギャップ周波数を大幅にチューニングすることができ、ブラッグ反射色による発色をフルカラーで制御できる。またマイクロ流体技術と光重合プロセスを組み合わせることにより、球状やカプセル状のチューナブルコロイドフォトニック結晶の作製にも成功し、形状由来の新しい応用を見出した。 河野行雄かわのゆきお東京工業大学・量子ナノエレクトロニクス研究センター准教授ナノ構造を用いたテラヘルツ電磁波の画像化技術の開拓と応用テラヘルツ(THz)電磁波の検出・イメージング技術は、基礎科学から医療・産業応用に至る幅広い分野での活用が期待されている。ところが、従来よく使用される技術(ボロメータやレンズなど)では感度が低く、空間分解能が波長程度に限定されるという問題があった。河野氏は、低次元ナノ電子材料が持つ特徴を活かした新しいTHz計測技術開拓、並びに電子材料・デバイス研究への応用を行った。具体的には以下に要約される。
河野行雄かわのゆきお東京工業大学・量子ナノエレクトロニクス研究センター准教授ナノ構造を用いたテラヘルツ電磁波の画像化技術の開拓と応用テラヘルツ(THz)電磁波の検出・イメージング技術は、基礎科学から医療・産業応用に至る幅広い分野での活用が期待されている。ところが、従来よく使用される技術(ボロメータやレンズなど)では感度が低く、空間分解能が波長程度に限定されるという問題があった。河野氏は、低次元ナノ電子材料が持つ特徴を活かした新しいTHz計測技術開拓、並びに電子材料・デバイス研究への応用を行った。具体的には以下に要約される。
①検出器:半導体電子構造、カーボンナノチューブを用いた新型の超高感度・周波数可変THz検出器を開発
②イメージング:検出に必要な全要素が半導体ワンチップに集積化された、回折限界を超える近接場THzイメージングを 開発、外部光源を用いないパッシブ近接場顕微計測を達成
③電子材料・デバイス研究応用:以上のTHz計測を用いて、半導体量子構造電子の空間ダイナミクスを解明、グラフェン 中ディラックフェルミオンとの広帯域THz共鳴の観測に成功、高分子の高次構造を直接観察 木寺正平きでらしょうへい電気通信大学 大学院情報理工学研究科助教超広帯域レーダを用いた超分解能・不可視領域立体像再構成法の研究木寺氏は、超広帯域電磁波を用いた近距離センシング分野において、全く新しい画像化原理を構築し、再現精度、空間分解能、処理時間において従来性能を超える革新的立体像再構成手法を提案してきた。更に多重散乱波を積極的に用いることで、従来では再現不可能であった領域(影領域)を高精度に推定する独自の手法を提案し、その有効性を実証してきた。卓越した同画像化性能は、国内外の当該分野で注目され、これを基盤とした研究開発が国内外の複数の研究機関で進められている。更に木寺氏は、誘電体内部画像化問題にも本手法の原理を導入し、独自の誘電率推定法を併用することで、超分解能・精度が達成されることを実証している。上記手法は多様な波長帯域に拡張可能であり、災害救助ロボットセンサ、非信襲生体計測及び非破壊計測等の幅広い応用分野で革新的計測技術を創出することが期待されている。
木寺正平きでらしょうへい電気通信大学 大学院情報理工学研究科助教超広帯域レーダを用いた超分解能・不可視領域立体像再構成法の研究木寺氏は、超広帯域電磁波を用いた近距離センシング分野において、全く新しい画像化原理を構築し、再現精度、空間分解能、処理時間において従来性能を超える革新的立体像再構成手法を提案してきた。更に多重散乱波を積極的に用いることで、従来では再現不可能であった領域(影領域)を高精度に推定する独自の手法を提案し、その有効性を実証してきた。卓越した同画像化性能は、国内外の当該分野で注目され、これを基盤とした研究開発が国内外の複数の研究機関で進められている。更に木寺氏は、誘電体内部画像化問題にも本手法の原理を導入し、独自の誘電率推定法を併用することで、超分解能・精度が達成されることを実証している。上記手法は多様な波長帯域に拡張可能であり、災害救助ロボットセンサ、非信襲生体計測及び非破壊計測等の幅広い応用分野で革新的計測技術を創出することが期待されている。 浜屋宏平 はまやこうへい九州大学 大学院システム情報科学研究院准教授強磁性合金・半導体界面の超高品質形成技術の開拓と半導体スピンデバイス技術への応用浜屋氏は、次世代の情報通信機器における超低消費電力半導体素子として最有力視されている「スピントランジスタ」の基盤技術を開発した。具体的には、大規模集積回路(LSI)の根幹を支えるCMOS技術と整合する「シリコン(Si)およびゲルマニウム(Ge)」というIV属元素系半導体材料に対して、高性能強磁性合金材料を原子層レベルで接合する新しい技術を開発し、スピントランジスタ専用の超高品質ソース・ドレイン構造の基礎を構築した。その結果、この高品質接合界面を介した高効率スピン注入・検出を半導体SiおよびGeにおいて世界で世界で初めて実証した。更に、半導体Si-電界効果トランジスタ構造に対して上記のスピン注入・検出技術を適用し、世界で初めて「スピン信号のゲート電圧制御」を室温で実証した。これらの成果は、スピントランジスタの実用化を指向した独創性の高い新技術であり、産業界との共同研究開発においても大きく貢献している。
浜屋宏平 はまやこうへい九州大学 大学院システム情報科学研究院准教授強磁性合金・半導体界面の超高品質形成技術の開拓と半導体スピンデバイス技術への応用浜屋氏は、次世代の情報通信機器における超低消費電力半導体素子として最有力視されている「スピントランジスタ」の基盤技術を開発した。具体的には、大規模集積回路(LSI)の根幹を支えるCMOS技術と整合する「シリコン(Si)およびゲルマニウム(Ge)」というIV属元素系半導体材料に対して、高性能強磁性合金材料を原子層レベルで接合する新しい技術を開発し、スピントランジスタ専用の超高品質ソース・ドレイン構造の基礎を構築した。その結果、この高品質接合界面を介した高効率スピン注入・検出を半導体SiおよびGeにおいて世界で世界で初めて実証した。更に、半導体Si-電界効果トランジスタ構造に対して上記のスピン注入・検出技術を適用し、世界で初めて「スピン信号のゲート電圧制御」を室温で実証した。これらの成果は、スピントランジスタの実用化を指向した独創性の高い新技術であり、産業界との共同研究開発においても大きく貢献している。 林将光はやしまさみつ独立行政法人物質・材料研究機構主任研究員省エネルギースピントロニクス素子開発に向けた革新的磁化制御技術の確立林氏はこれまでに、スピントルクと呼ばれる電子力学的効果を利用して、微細化した磁性ナノ構造における磁化構造を電流で制御する基盤技術を確立した。磁壁移動メモリと呼ばれるストレージクラス個体メモリの開発を目指した研究では、スピントルク効果を利用して強磁性体量子細線中の磁壁の位置を電流パルスを使って操作し、その基本動作を世界に先駆けて実証するなどの大きな成果を挙げた。さらに、スピン・軌道相互作用が大きい金属膜を組み合わせた磁性ナノヘテロ構造において、膜厚がわずか数原子層厚(~1nm以下)の非磁性金属膜に電流を流すことで、大きなスピンホール効果が発現し、隣接する強磁性層の磁化を低電流で反転できることを見出した。このような電子のスピン・軌道相互作用を利用した新たな磁化制御技術は、スピンオービトロニクスと呼ばれるスピントロニクスの次の展開として期待されており、林氏はその開拓に大きく貢献した。
林将光はやしまさみつ独立行政法人物質・材料研究機構主任研究員省エネルギースピントロニクス素子開発に向けた革新的磁化制御技術の確立林氏はこれまでに、スピントルクと呼ばれる電子力学的効果を利用して、微細化した磁性ナノ構造における磁化構造を電流で制御する基盤技術を確立した。磁壁移動メモリと呼ばれるストレージクラス個体メモリの開発を目指した研究では、スピントルク効果を利用して強磁性体量子細線中の磁壁の位置を電流パルスを使って操作し、その基本動作を世界に先駆けて実証するなどの大きな成果を挙げた。さらに、スピン・軌道相互作用が大きい金属膜を組み合わせた磁性ナノヘテロ構造において、膜厚がわずか数原子層厚(~1nm以下)の非磁性金属膜に電流を流すことで、大きなスピンホール効果が発現し、隣接する強磁性層の磁化を低電流で反転できることを見出した。このような電子のスピン・軌道相互作用を利用した新たな磁化制御技術は、スピンオービトロニクスと呼ばれるスピントロニクスの次の展開として期待されており、林氏はその開拓に大きく貢献した。
第12回 2012年度
 木村崇きむらたかし九州大学稲盛フロンティア研究センター教授革新的純スピン流の制御技術の開発と高性能スピンデバイスへの応用木村氏は積層型が主流であったスピンデバイスの素子構造を面内型に展開し、電気を流さずスピン角運動量のみを伝える電子の流れ“純スピン流”を生成する技術をいち早く確立した。更にスピン吸収効果に代表される革新的な高効率純スピン流制御技術を次々と開発し、それらの要素技術を基盤として、純スピン流によるナノ磁性体の磁化反転、白金細線を用いた室温スピンホール効果の電気的検出など、今後のスピントロニクスの展開において、極めて重要となる基礎物理現象の観測に世界で初めて成功した。更にプレーナー構造の柔軟性を最大限利用した外に類を見ない高機能スピンデバイスを次々に提案・実証すると共に、高スピン偏極ホイスラー合金による純スピン流の生成効率の飛躍的改善、積層型と面内型を組み合わせた新奇な純スピン流生成構造による巨大スピン流の生成などにも成功しており、純スピン流の実用化に向けても大きく貢献した。
木村崇きむらたかし九州大学稲盛フロンティア研究センター教授革新的純スピン流の制御技術の開発と高性能スピンデバイスへの応用木村氏は積層型が主流であったスピンデバイスの素子構造を面内型に展開し、電気を流さずスピン角運動量のみを伝える電子の流れ“純スピン流”を生成する技術をいち早く確立した。更にスピン吸収効果に代表される革新的な高効率純スピン流制御技術を次々と開発し、それらの要素技術を基盤として、純スピン流によるナノ磁性体の磁化反転、白金細線を用いた室温スピンホール効果の電気的検出など、今後のスピントロニクスの展開において、極めて重要となる基礎物理現象の観測に世界で初めて成功した。更にプレーナー構造の柔軟性を最大限利用した外に類を見ない高機能スピンデバイスを次々に提案・実証すると共に、高スピン偏極ホイスラー合金による純スピン流の生成効率の飛躍的改善、積層型と面内型を組み合わせた新奇な純スピン流生成構造による巨大スピン流の生成などにも成功しており、純スピン流の実用化に向けても大きく貢献した。 稲邑哲也いなむらてつなり国立情報学研究所准教授身体運動と言語を用いた人間ロボット間の適応的社会的インタラクションシステムの研究ロボットが人間の活動する日常生活空間で共に活動し、ユーザからの指示に従って的確にタスクを実行するには、人間との自然な対話機能、未知の環境への適応的な対応など、数多くの機能が必要となる。稲邑氏はこのような知的な行動実現の基幹となっているのは、他者の行動を模倣し対話する能力であるという点に着目し、ロボットに人間の行動を模倣させながら、曖昧性や不確実性に遭遇した時に対話でその問題に対応し、経験から学習する知能システムの基盤を構築してきた。この基盤システムの応用例として、スポーツの初心者に対してロボットが実演と言語による説明を行いインストラクターとして接するシステムの開発や、インターネット上で身体運動を伴った言語的インタラクション実験に誰もが簡単に参加することのできるシステムを通じたスキル学習などの研究を発展させている。
稲邑哲也いなむらてつなり国立情報学研究所准教授身体運動と言語を用いた人間ロボット間の適応的社会的インタラクションシステムの研究ロボットが人間の活動する日常生活空間で共に活動し、ユーザからの指示に従って的確にタスクを実行するには、人間との自然な対話機能、未知の環境への適応的な対応など、数多くの機能が必要となる。稲邑氏はこのような知的な行動実現の基幹となっているのは、他者の行動を模倣し対話する能力であるという点に着目し、ロボットに人間の行動を模倣させながら、曖昧性や不確実性に遭遇した時に対話でその問題に対応し、経験から学習する知能システムの基盤を構築してきた。この基盤システムの応用例として、スポーツの初心者に対してロボットが実演と言語による説明を行いインストラクターとして接するシステムの開発や、インターネット上で身体運動を伴った言語的インタラクション実験に誰もが簡単に参加することのできるシステムを通じたスキル学習などの研究を発展させている。 岩瀬英治いわせえいじ早稲田大学基幹理工学部専任講師マイクロ3次元構造体の形成技術とそのデバイス応用岩瀬氏は、数μm~数百μmサイズのMEMSデバイスに関して、磁場の力を用いて2次元の展開図構造を折り紙のように起き上げる手法、異なる基板で作成したマイクロデバイスを積み木のように組み立てる手法によるマイクロ3次元構造体の形成技術を提案し、実現した。これは通常のMEMSプロセスは2次元精密加工が得意であるのに対し、その利点を生かしつつ微小な3次元構造体の形成する技術を実現したものである。また、理論的な基礎研究のみならずデバイスなどの応用研究まで行っており、幅広い成果を挙げている。
岩瀬英治いわせえいじ早稲田大学基幹理工学部専任講師マイクロ3次元構造体の形成技術とそのデバイス応用岩瀬氏は、数μm~数百μmサイズのMEMSデバイスに関して、磁場の力を用いて2次元の展開図構造を折り紙のように起き上げる手法、異なる基板で作成したマイクロデバイスを積み木のように組み立てる手法によるマイクロ3次元構造体の形成技術を提案し、実現した。これは通常のMEMSプロセスは2次元精密加工が得意であるのに対し、その利点を生かしつつ微小な3次元構造体の形成する技術を実現したものである。また、理論的な基礎研究のみならずデバイスなどの応用研究まで行っており、幅広い成果を挙げている。 大友明おおともあきら東京工業大学大学院理工学研究科教授透明酸化物半導体界面の高品質化と量子化伝導に関する研究大友氏は、ZnOやSrTiO₃などのありふれた金属酸化物を用いて、極めて高品質の透明酸化物半導体界面を作製し、量子伝導現象を観測した。従来、GaAsやSiなどのクリーンな半導体界面だけで量子ホール効果のような量子伝導の実現が可能であり、金属酸化物のようなダーティな系では量子伝導が実現するとは全く予想もされていなかった。大友氏の行った研究は、酸化物の多様な機能を活用する新しいエレクトロニクス誕生への貴重なマイルストーンであると世界的に広く認知されている。また、このようなクリーンな界面を作製するために、大友氏は材料開発や薄膜技術の向上に非常に多大な貢献をしている。さらに、界面に電子を閉じ込め2次元電子を形成する原理が、通常の半導体ヘテロ構造とは全く異なっており、酸化物に特徴的な新原理を開拓した。
大友明おおともあきら東京工業大学大学院理工学研究科教授透明酸化物半導体界面の高品質化と量子化伝導に関する研究大友氏は、ZnOやSrTiO₃などのありふれた金属酸化物を用いて、極めて高品質の透明酸化物半導体界面を作製し、量子伝導現象を観測した。従来、GaAsやSiなどのクリーンな半導体界面だけで量子ホール効果のような量子伝導の実現が可能であり、金属酸化物のようなダーティな系では量子伝導が実現するとは全く予想もされていなかった。大友氏の行った研究は、酸化物の多様な機能を活用する新しいエレクトロニクス誕生への貴重なマイルストーンであると世界的に広く認知されている。また、このようなクリーンな界面を作製するために、大友氏は材料開発や薄膜技術の向上に非常に多大な貢献をしている。さらに、界面に電子を閉じ込め2次元電子を形成する原理が、通常の半導体ヘテロ構造とは全く異なっており、酸化物に特徴的な新原理を開拓した。 鹿島久嗣かしまひさし東京大学大学院情報理工学系研究科准教授ビッグデータの多様性に立ち向かう機械学習手法の研究ビッグデータのもつ多様性に対処するための機械学習に基づく予測手法を開発したことが鹿島氏の主要な業績である。ソーシャルネットワークや化合物などの複雑なネットワーク構造を有するデータ、加速度センサー等のセンサー時系列データ、ソーシャルメディアなど人間の手によって生み出される属人生の高いデータなど、世の中は多種多様なデータで溢れている。これまでの解析手法が苦手としていたネットワーク構造を有するデータ(データ形式の多様性)に対する予測手法を予測手法を鹿島氏は大きく発展させた。また最近では人間の個性や不確実性等の多様性[人間の多様性)を扱う予測手法に関する数々の業績を挙げている。
鹿島久嗣かしまひさし東京大学大学院情報理工学系研究科准教授ビッグデータの多様性に立ち向かう機械学習手法の研究ビッグデータのもつ多様性に対処するための機械学習に基づく予測手法を開発したことが鹿島氏の主要な業績である。ソーシャルネットワークや化合物などの複雑なネットワーク構造を有するデータ、加速度センサー等のセンサー時系列データ、ソーシャルメディアなど人間の手によって生み出される属人生の高いデータなど、世の中は多種多様なデータで溢れている。これまでの解析手法が苦手としていたネットワーク構造を有するデータ(データ形式の多様性)に対する予測手法を予測手法を鹿島氏は大きく発展させた。また最近では人間の個性や不確実性等の多様性[人間の多様性)を扱う予測手法に関する数々の業績を挙げている。 下馬場朋禄しもばばともよし千葉大学大学院工学研究科准教授コンピュータホログラフィによる3次元動画像・撮像に関する研究コンピュータホログラフィを用いれば理論的には3次元動画表示(3次元ディスプレイ)や3次元構造の動的計測(3次元顕微鏡)が可能になる。しかしホログラフィ方式の3次元ディスプレイは、ホログラム生成に要する計算時間が膨大であり実用化へのネックとなっている。下馬場氏はコンピュータホログラフィの実時間処理に向けたアルゴリズムや高速計算ハードウェアの研究、及び実際の光学系と組み合わせた3次元ディスプレイと顕微鏡システムの構築を行っている。これまでに3種類のホログラム高速計算アルゴリズムを開発、従来のものよりも1000倍以上の性能を達成。従来の手法では不可能だと思われた10万点を超える複雑な形状の3次元物体データから数1000万画素のホログラムをリアルタイム生成に成功した。また撮影物を任意の奥行き距離で広い観察領域・高分解能で複数同時にリアルタイム再生できる、新しいコンセプトの顕微鏡システムを開発した。
下馬場朋禄しもばばともよし千葉大学大学院工学研究科准教授コンピュータホログラフィによる3次元動画像・撮像に関する研究コンピュータホログラフィを用いれば理論的には3次元動画表示(3次元ディスプレイ)や3次元構造の動的計測(3次元顕微鏡)が可能になる。しかしホログラフィ方式の3次元ディスプレイは、ホログラム生成に要する計算時間が膨大であり実用化へのネックとなっている。下馬場氏はコンピュータホログラフィの実時間処理に向けたアルゴリズムや高速計算ハードウェアの研究、及び実際の光学系と組み合わせた3次元ディスプレイと顕微鏡システムの構築を行っている。これまでに3種類のホログラム高速計算アルゴリズムを開発、従来のものよりも1000倍以上の性能を達成。従来の手法では不可能だと思われた10万点を超える複雑な形状の3次元物体データから数1000万画素のホログラムをリアルタイム生成に成功した。また撮影物を任意の奥行き距離で広い観察領域・高分解能で複数同時にリアルタイム再生できる、新しいコンセプトの顕微鏡システムを開発した。 坂東幸浩ばんどうゆきひろNTTアドバンステクノロジ㈱アプリケーションソリューション事業本部担当課長高臨場感通信の実現に向けたナチュラルクオリティ映像符号化に関する先駆的研究高臨場感通信を実現する上で高性能な符号化方法の実現は欠くことができないものであり、その実現が強く望まれている。坂東氏は高画質化の要素として、時間解像度、ビット深度、空間解像度の3つに着目。まず映像の高画質化における時間解像度の重要性を実証すると共に、時間解像度を高めた高フレームレート映像の符号化を世界に先駆け検討し、高フレームレート映像の符号化に対する理論的指針を与えた。また、画素あたりの表現ビット長を高めた高ビット深度映像に対する符号化検討において、従来手法を大幅に上回る符号化効率を実現。さらに、空間解像度を高めた高精細映像に対して、直交変換符号化の理論的設計指針を量子情報理論に基づく数理的考察により解明すると共に、高能率・高速なスケーラブル符号化を検討し、4K映像対応SVCリアルタイムソフトウェアコーデックの開発に世界で初めて成功した。
坂東幸浩ばんどうゆきひろNTTアドバンステクノロジ㈱アプリケーションソリューション事業本部担当課長高臨場感通信の実現に向けたナチュラルクオリティ映像符号化に関する先駆的研究高臨場感通信を実現する上で高性能な符号化方法の実現は欠くことができないものであり、その実現が強く望まれている。坂東氏は高画質化の要素として、時間解像度、ビット深度、空間解像度の3つに着目。まず映像の高画質化における時間解像度の重要性を実証すると共に、時間解像度を高めた高フレームレート映像の符号化を世界に先駆け検討し、高フレームレート映像の符号化に対する理論的指針を与えた。また、画素あたりの表現ビット長を高めた高ビット深度映像に対する符号化検討において、従来手法を大幅に上回る符号化効率を実現。さらに、空間解像度を高めた高精細映像に対して、直交変換符号化の理論的設計指針を量子情報理論に基づく数理的考察により解明すると共に、高能率・高速なスケーラブル符号化を検討し、4K映像対応SVCリアルタイムソフトウェアコーデックの開発に世界で初めて成功した。 平田晃正ひらたあきまさ名古屋工業大学大学院工学研究科准教授人体に対する高速・高精度な電磁界解析アルゴリズムの開発と医療応用人体に対する電気刺激療法において、対象部位を効率的に刺激する技術は十分確立されていない。これは、人体は多数の組織から構成され、かつ複雑に入り組んでいることによるものであり、ゆえに中枢神経による電気刺激閾値は十分特定されていなかった。平田氏は医用画像に基づき開発した精緻な人体モデルに対して、刺激装置により対象部位に誘導される電流を高速かつ高精度に推定するための電磁界解析アルゴリズムを開発した。この技術により、刺激対象となる神経部位における閾値を推定可能となった。その結果、患者個々人で大きく異なる組織構造を考慮し、刺激部位に誘導される電流の最適化が可能となった。以上の成果は、多数ある電気刺激療法のオーダーメイド化、在宅化へのパラダイムシフトに多大な貢献をするものである。
平田晃正ひらたあきまさ名古屋工業大学大学院工学研究科准教授人体に対する高速・高精度な電磁界解析アルゴリズムの開発と医療応用人体に対する電気刺激療法において、対象部位を効率的に刺激する技術は十分確立されていない。これは、人体は多数の組織から構成され、かつ複雑に入り組んでいることによるものであり、ゆえに中枢神経による電気刺激閾値は十分特定されていなかった。平田氏は医用画像に基づき開発した精緻な人体モデルに対して、刺激装置により対象部位に誘導される電流を高速かつ高精度に推定するための電磁界解析アルゴリズムを開発した。この技術により、刺激対象となる神経部位における閾値を推定可能となった。その結果、患者個々人で大きく異なる組織構造を考慮し、刺激部位に誘導される電流の最適化が可能となった。以上の成果は、多数ある電気刺激療法のオーダーメイド化、在宅化へのパラダイムシフトに多大な貢献をするものである。 古海誓一ふるみせいいち独立行政法人物質・材料研究機構主幹研究員有機フォトニック結晶の自己組織化と次世代情報通信に向けた高密度レーザーへの展開周期構造を持った透明な媒質の中に、その繰返し周期と同じ程度の波長を有する光が入射すると、光と媒質の相互作用が極めて大きくなることがある。これは、フォトニック結晶のフォトニックバンドギャップが起因している。多くのフォトニック結晶は、半導体デバイス作製のために開発された微細加工技術を駆使してトップダウン的に作製されているが、その製造プロセスは煩雑なので、簡便に得ることができない。そこで古海氏は有機材料がボトムアップ的に形成する数百nmの周期配列構造に着目して、フォトニックバンドギャップによるレーザー発振に関する研究を遂行した。キラル液晶とコロイド結晶の2種類の有機フォトニック結晶を取り扱い、ソフトマテリアルである液晶やコロイド微粒子の特徴を最大限引き出すことで、レーザーの外部制御、円偏光レーザー、波長可変レーザー、フレキシブルレーザー、マイクロパターンレーザーといった次世代情報通信に向けた新しい高密度レーザーの作製に成功することができた。
古海誓一ふるみせいいち独立行政法人物質・材料研究機構主幹研究員有機フォトニック結晶の自己組織化と次世代情報通信に向けた高密度レーザーへの展開周期構造を持った透明な媒質の中に、その繰返し周期と同じ程度の波長を有する光が入射すると、光と媒質の相互作用が極めて大きくなることがある。これは、フォトニック結晶のフォトニックバンドギャップが起因している。多くのフォトニック結晶は、半導体デバイス作製のために開発された微細加工技術を駆使してトップダウン的に作製されているが、その製造プロセスは煩雑なので、簡便に得ることができない。そこで古海氏は有機材料がボトムアップ的に形成する数百nmの周期配列構造に着目して、フォトニックバンドギャップによるレーザー発振に関する研究を遂行した。キラル液晶とコロイド結晶の2種類の有機フォトニック結晶を取り扱い、ソフトマテリアルである液晶やコロイド微粒子の特徴を最大限引き出すことで、レーザーの外部制御、円偏光レーザー、波長可変レーザー、フレキシブルレーザー、マイクロパターンレーザーといった次世代情報通信に向けた新しい高密度レーザーの作製に成功することができた。
第11回 2011年度
 小森雅晴こもりまさはる京都大学大学院工学研究科准教授精密回転伝達機構の普遍的特性解明と精密計測技術、変則技術の開発精密回転伝達機構に用いる歯車の普遍的な振動特性について長きに渡り解明することができなかったが、小森氏は歯車歯面の三次元幾何曲面の表現方法に着目し、これを量と形に分解して表現する独創的手法を導入した結果、従来のように量と形を混在して扱う場合には不可能であった歯車振動の定式化に成功し、どのような歯車にも共通してあてはまる普遍的な振動特性を議論することが可能になった。また、歯車振動の大きさは、弾性変形する幾何曲面の凸の量(量的要素)と質的要素の積で表現できることを明らかにし、複雑現象と考えられてきた歯車振動においてシンプルな関係が存在することを明らかにした。この成果は歯車振動を抑えるための設計指針を明確に示すものであり、経験や勘に頼らない理論的裏付けのある設計に貢献した。
小森雅晴こもりまさはる京都大学大学院工学研究科准教授精密回転伝達機構の普遍的特性解明と精密計測技術、変則技術の開発精密回転伝達機構に用いる歯車の普遍的な振動特性について長きに渡り解明することができなかったが、小森氏は歯車歯面の三次元幾何曲面の表現方法に着目し、これを量と形に分解して表現する独創的手法を導入した結果、従来のように量と形を混在して扱う場合には不可能であった歯車振動の定式化に成功し、どのような歯車にも共通してあてはまる普遍的な振動特性を議論することが可能になった。また、歯車振動の大きさは、弾性変形する幾何曲面の凸の量(量的要素)と質的要素の積で表現できることを明らかにし、複雑現象と考えられてきた歯車振動においてシンプルな関係が存在することを明らかにした。この成果は歯車振動を抑えるための設計指針を明確に示すものであり、経験や勘に頼らない理論的裏付けのある設計に貢献した。 石鍋隆宏いしなべたかひろ東北大学大学院工学研究科助教液晶を用いた偏光制御技術の確立と低電力・高機能ディスプレイへの応用に関する研究石鍋氏は液晶デバイスの高性能化において最も重要とされる偏光の精密な解析理論と制御技術を確立し、液晶ディスプレイの光学設計技術を学術的に体系化すると共に反射型フルカラー液晶ディスプレイ、フィールドシーケンシャルカラーディスプレイ等の高性能液晶ディスプレイの実現とその実用化に貢献し、現在のディスプレイ技術の発展に不可欠な数多くの成果を収めてきた。またこの理論を応用した液晶材料の物性パラメータの高精度測定手法を考案し、計算機による液晶デバイスの定量評価技術を確立した。この偏光制御技術は現在の液晶ディスプレイの光学設計技術の基盤となっており、液晶ディスプレイの高性能化に大きく貢献している。
石鍋隆宏いしなべたかひろ東北大学大学院工学研究科助教液晶を用いた偏光制御技術の確立と低電力・高機能ディスプレイへの応用に関する研究石鍋氏は液晶デバイスの高性能化において最も重要とされる偏光の精密な解析理論と制御技術を確立し、液晶ディスプレイの光学設計技術を学術的に体系化すると共に反射型フルカラー液晶ディスプレイ、フィールドシーケンシャルカラーディスプレイ等の高性能液晶ディスプレイの実現とその実用化に貢献し、現在のディスプレイ技術の発展に不可欠な数多くの成果を収めてきた。またこの理論を応用した液晶材料の物性パラメータの高精度測定手法を考案し、計算機による液晶デバイスの定量評価技術を確立した。この偏光制御技術は現在の液晶ディスプレイの光学設計技術の基盤となっており、液晶ディスプレイの高性能化に大きく貢献している。 岡田健一おかだけんいち東京工業大学大学院理工学研究科准教授リコンフィギュラブルアナログ回路設計技術の研究岡田氏は、これまで個別の用途や機能ごとに設計されてきたアナログ回路の設計技術において、柔軟な機能可変を実現するための先駆的研究を行い、リコンフィギュラブルアナログ回路という新しい分野を切り拓いた。リコンフィギュラブルアナログ回路は、製造後に機能を変更することのできるアナログ回路であり、柔軟に機能の変更や追加を行うことができる汎用性を備えている。通常、集積回路として実現されたアナログ回路は設計時にその機能や特性が定まるが、調整機構を自身に備えることにより、製造後においても回路に可変性を持たせることが可能である。岡田氏の研究成果は、あらゆる通信方式に対応可能な無線機等、様々なアナログ回路に適用可能なものであり、応用範囲も広い。学術的にも産業的にも今後の更なる発展が期待できる。
岡田健一おかだけんいち東京工業大学大学院理工学研究科准教授リコンフィギュラブルアナログ回路設計技術の研究岡田氏は、これまで個別の用途や機能ごとに設計されてきたアナログ回路の設計技術において、柔軟な機能可変を実現するための先駆的研究を行い、リコンフィギュラブルアナログ回路という新しい分野を切り拓いた。リコンフィギュラブルアナログ回路は、製造後に機能を変更することのできるアナログ回路であり、柔軟に機能の変更や追加を行うことができる汎用性を備えている。通常、集積回路として実現されたアナログ回路は設計時にその機能や特性が定まるが、調整機構を自身に備えることにより、製造後においても回路に可変性を持たせることが可能である。岡田氏の研究成果は、あらゆる通信方式に対応可能な無線機等、様々なアナログ回路に適用可能なものであり、応用範囲も広い。学術的にも産業的にも今後の更なる発展が期待できる。 杉山将すぎやままさし東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授確率密度比に基づく統計的機械学習の新手法の開発とその実世界応用コンピュータによる知識の自動発見や学習能力は複雑なデータに対して学習の質はまだ十分でなく、より高度な知的情報処理技術が切望されている。杉山氏はこの課題に対し、「確率密度比推定」を基盤とする独自のデータ解析パラダイムを提唱した。確率密度比とは確率密度関数の比の関数であり、それを直接推定することにより、困難な確率分布の直接的な推定を回避しつつ、これまで困難とされていた高次元かつ複雑な確率構造を持つ情報源に対しても、精度良く学習を行うことが可能となった。杉山氏はこの確率密度比推定パラダイムによる機械学習法を独自に考案し、密度比推定アルゴリズムの開発、密度比推定の数理的性質の解明、更には音声・画像・脳波・金融・ロボット・自然言語・生命情報などの様々な実問題への応用研究を行い、有効性を実証した。
杉山将すぎやままさし東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授確率密度比に基づく統計的機械学習の新手法の開発とその実世界応用コンピュータによる知識の自動発見や学習能力は複雑なデータに対して学習の質はまだ十分でなく、より高度な知的情報処理技術が切望されている。杉山氏はこの課題に対し、「確率密度比推定」を基盤とする独自のデータ解析パラダイムを提唱した。確率密度比とは確率密度関数の比の関数であり、それを直接推定することにより、困難な確率分布の直接的な推定を回避しつつ、これまで困難とされていた高次元かつ複雑な確率構造を持つ情報源に対しても、精度良く学習を行うことが可能となった。杉山氏はこの確率密度比推定パラダイムによる機械学習法を独自に考案し、密度比推定アルゴリズムの開発、密度比推定の数理的性質の解明、更には音声・画像・脳波・金融・ロボット・自然言語・生命情報などの様々な実問題への応用研究を行い、有効性を実証した。 住井英二郎すみいえいじろう東北大学大学院情報科学研究科准教授環境双模倣によるプログラム等価性証明手法住井氏は、再帰・高階関数・データ抽象・並行計算などの高度な機能を備えた言語における「プログラム等価性」の一般的証明手法を、世界で初めて確立した。プログラム等価性は情報処理システムの安全性や機能的正当性に直結する重要な問題であり、1960年代から現在に至るまで盛んに研究されているが、住井氏のような証明手法の確立は非常に難しいと考えられていた。住井氏の証明手法は健全・完全かつ一般的・初等的で、プログラム理論におけるブレークスルーとして、コンピュータサイエンス最高峰の論文誌Journal of the ACMなどに採録される等、極めて高い国際的評価を得ている。
住井英二郎すみいえいじろう東北大学大学院情報科学研究科准教授環境双模倣によるプログラム等価性証明手法住井氏は、再帰・高階関数・データ抽象・並行計算などの高度な機能を備えた言語における「プログラム等価性」の一般的証明手法を、世界で初めて確立した。プログラム等価性は情報処理システムの安全性や機能的正当性に直結する重要な問題であり、1960年代から現在に至るまで盛んに研究されているが、住井氏のような証明手法の確立は非常に難しいと考えられていた。住井氏の証明手法は健全・完全かつ一般的・初等的で、プログラム理論におけるブレークスルーとして、コンピュータサイエンス最高峰の論文誌Journal of the ACMなどに採録される等、極めて高い国際的評価を得ている。 前田雄介まえだゆうすけ横浜国立大学大学院工学研究院准教授ロボットの物体ハンドリングの基礎理論および応用技術開発に対する貢献前田氏はロボットによる物体ハンドリングについて、その基礎となるマニピュレーション理論の発展のほか、ロボット教示という単体ロボットレベルでの応用技術開発、更に複数ロボットからなる組立システムの新しいアーキテクチャの提案というシステムレベルの技術提案にいたるまで、幅広いレベルで研究業績をあげており、かつ、それぞれのレベルでいずれも高い評価を受けている。
前田雄介まえだゆうすけ横浜国立大学大学院工学研究院准教授ロボットの物体ハンドリングの基礎理論および応用技術開発に対する貢献前田氏はロボットによる物体ハンドリングについて、その基礎となるマニピュレーション理論の発展のほか、ロボット教示という単体ロボットレベルでの応用技術開発、更に複数ロボットからなる組立システムの新しいアーキテクチャの提案というシステムレベルの技術提案にいたるまで、幅広いレベルで研究業績をあげており、かつ、それぞれのレベルでいずれも高い評価を受けている。 水口将輝みずぐちまさき東北大学金属材料研究所准教授磁性ナノ超構造の創製とスピントロニクスデバイスへの応用水口氏は、原子レベルで表面・界面形態を制御した金属・半導体・酸化物単結晶の組み合わせにより強磁性金属ナノ超構造を創製し、それらが呈する様々な機能性を巧みに利用してスピントロニクスデバイスへの応用研究を展開することにより、多くの成果を挙げてきた。特に水口氏が得意とする分子線エピタキシー法およびスパッタリング法による高度な結晶成長技術と表面・界面制御技術を駆使し、新機能構造体開発あるいは新規材料開発を行うと同時に、様々な手法を用いてそれらの特性評価及び付随する物理現象の解明に関する研究を行ってきた。その結果、表面修飾法利用したナノ超構造体における高い磁気抵抗効果の発見、トンネル磁気抵抗素子の表面構造直接観察及び磁気輸送特性との相関の解明、エピタキシャル成長技術に立脚した新規磁性材料の人口創製など、磁性材料・スピントロニクス分野において一連の重要な成果を挙げた。
水口将輝みずぐちまさき東北大学金属材料研究所准教授磁性ナノ超構造の創製とスピントロニクスデバイスへの応用水口氏は、原子レベルで表面・界面形態を制御した金属・半導体・酸化物単結晶の組み合わせにより強磁性金属ナノ超構造を創製し、それらが呈する様々な機能性を巧みに利用してスピントロニクスデバイスへの応用研究を展開することにより、多くの成果を挙げてきた。特に水口氏が得意とする分子線エピタキシー法およびスパッタリング法による高度な結晶成長技術と表面・界面制御技術を駆使し、新機能構造体開発あるいは新規材料開発を行うと同時に、様々な手法を用いてそれらの特性評価及び付随する物理現象の解明に関する研究を行ってきた。その結果、表面修飾法利用したナノ超構造体における高い磁気抵抗効果の発見、トンネル磁気抵抗素子の表面構造直接観察及び磁気輸送特性との相関の解明、エピタキシャル成長技術に立脚した新規磁性材料の人口創製など、磁性材料・スピントロニクス分野において一連の重要な成果を挙げた。 柳田剛やなぎたたけし大阪大学産業科学研究所准教授自己組織化ナノワイヤを用いた超Tbit級不揮発性メモリ素子に関する研究電子デバイス・モバイルデバイス情報通信量の増大化・高性能化に伴い、不揮発性メモリ素子の大容量化が大きな技術課題となっている。その次世代超Tbit級不揮発性メモリの本命として、絶縁体の金属酸化物を電極で挟み込んだ極めてシンプルな抵抗変化素子が大きな注目を集めている。しかしながら、メモリ素子集積化の際に必ず問題となる極微ナノ領域における素子動作特性とその基本的な動作メカニズムが不明なために、抵抗変化素子の展開には大きな障壁が存在していた。柳田氏の研究は、2-10nmのサイズに制御可能な自己組織化ナノワイヤ構造体を用いた極めて独創的なアプローチで、抵抗変化不揮発性メモリ素子の最も本質的な問題を解決することに成功した。
柳田剛やなぎたたけし大阪大学産業科学研究所准教授自己組織化ナノワイヤを用いた超Tbit級不揮発性メモリ素子に関する研究電子デバイス・モバイルデバイス情報通信量の増大化・高性能化に伴い、不揮発性メモリ素子の大容量化が大きな技術課題となっている。その次世代超Tbit級不揮発性メモリの本命として、絶縁体の金属酸化物を電極で挟み込んだ極めてシンプルな抵抗変化素子が大きな注目を集めている。しかしながら、メモリ素子集積化の際に必ず問題となる極微ナノ領域における素子動作特性とその基本的な動作メカニズムが不明なために、抵抗変化素子の展開には大きな障壁が存在していた。柳田氏の研究は、2-10nmのサイズに制御可能な自己組織化ナノワイヤ構造体を用いた極めて独創的なアプローチで、抵抗変化不揮発性メモリ素子の最も本質的な問題を解決することに成功した。
第10回 2010年度
 河原林健一かわらばしけんいち国立情報学研究所教授アルゴリズム的グラフマイナー理論の研究とその応用河原林氏は、離散数学の最先端の理論を駆使し応用することで、離散数学・理論計算機両分野において数多くの未解決問題を解決し、多方面にブレークスルーを与えてきた。離散数学分野においては、最も深遠な理論とみなされている「グラフマイナー理論」を発展させることにより、Hadwiger予想に代表されるグラフ彩色問題や4色定理の周辺問題、曲面上のグラフに関する彩色問題等の問題で数多くの成果を収めてきた。さらに理論計算機分野においては、これらの理論を応用することによって多数の画期的な高速アルゴリズムの開発に成功してきた。
河原林健一かわらばしけんいち国立情報学研究所教授アルゴリズム的グラフマイナー理論の研究とその応用河原林氏は、離散数学の最先端の理論を駆使し応用することで、離散数学・理論計算機両分野において数多くの未解決問題を解決し、多方面にブレークスルーを与えてきた。離散数学分野においては、最も深遠な理論とみなされている「グラフマイナー理論」を発展させることにより、Hadwiger予想に代表されるグラフ彩色問題や4色定理の周辺問題、曲面上のグラフに関する彩色問題等の問題で数多くの成果を収めてきた。さらに理論計算機分野においては、これらの理論を応用することによって多数の画期的な高速アルゴリズムの開発に成功してきた。 圓道知博えんどうともひろ名古屋大学大学院工学研究科助教全周囲の光線を再現する三次元画像表示の研究三次元テレビの現在主流の方式である両眼視差方式は立体視用メガネ等を利用し、左右眼に視差のある画像を見せる方式であるが、不自然な見え方や不快感・眼精疲労等の問題が指摘されている。これを解決するものとして光学的な像そのものを立体的に光線再現型の表示方式が注目されている。圓道氏は長年同方式による表示技術の研究に取り組んできたが、中でも多人数が360度自由な方向から観察できる円筒型の光線再現型3Dディスプレイは極めてユニークで画期的な提案であり、本分野に大きなインパクトを与えた。
圓道知博えんどうともひろ名古屋大学大学院工学研究科助教全周囲の光線を再現する三次元画像表示の研究三次元テレビの現在主流の方式である両眼視差方式は立体視用メガネ等を利用し、左右眼に視差のある画像を見せる方式であるが、不自然な見え方や不快感・眼精疲労等の問題が指摘されている。これを解決するものとして光学的な像そのものを立体的に光線再現型の表示方式が注目されている。圓道氏は長年同方式による表示技術の研究に取り組んできたが、中でも多人数が360度自由な方向から観察できる円筒型の光線再現型3Dディスプレイは極めてユニークで画期的な提案であり、本分野に大きなインパクトを与えた。 小林研介こばやしけんすけ京都大学化学研究所准教授量子多体効果に基づく半導体デバイスの開発とそのダイナミクスの研究小林氏は高純度で制御性の高い半導体素子において、量子効果と多体効果が電子伝導に果たす役割に注目することによって、量子輸送ダイナミクスの研究に新局面を切り拓いてきた。小林氏の主たる業績は、「量子輸送におけるファノ効果」「量子系における『揺らぎの定理』の検証」「シリコンにおける巨大磁気抵抗効果」の3つである。これらは半導体の制御性を活かして成し遂げられた普遍性の高い独創的な成果であり、量子情報技術を含めた半導体デバイスの更なる発展につながるものである。
小林研介こばやしけんすけ京都大学化学研究所准教授量子多体効果に基づく半導体デバイスの開発とそのダイナミクスの研究小林氏は高純度で制御性の高い半導体素子において、量子効果と多体効果が電子伝導に果たす役割に注目することによって、量子輸送ダイナミクスの研究に新局面を切り拓いてきた。小林氏の主たる業績は、「量子輸送におけるファノ効果」「量子系における『揺らぎの定理』の検証」「シリコンにおける巨大磁気抵抗効果」の3つである。これらは半導体の制御性を活かして成し遂げられた普遍性の高い独創的な成果であり、量子情報技術を含めた半導体デバイスの更なる発展につながるものである。 齊藤英治さいとうえいじ東北大学金属材料研究所教授スピン流の伝送技術と基礎物理の開拓「スピン流」は電子のスピンの流れであり、ジュール熱を伴わない超省電力での情報伝送や不揮発・高密度情報記憶を可能にするなどの画期的な性質により、その研究は近年世界的規模で進められている。その源流となるのが、齊藤氏によるスピン流の直接検出手法の発見である。従来スピン流はその検出すら不可能であったが、この状況を一気に打破したのは齊藤氏による逆スピンホール効果(スピン流を電圧に変換する現象)の発見とその系統的研究である。斉藤氏自身もこの手法を利用して「絶縁体中のスピン流伝送(電気信号伝送)」やスピンゼーベック効果等の画期的なスピントロニクス現象の発見を次々と成功させた。
齊藤英治さいとうえいじ東北大学金属材料研究所教授スピン流の伝送技術と基礎物理の開拓「スピン流」は電子のスピンの流れであり、ジュール熱を伴わない超省電力での情報伝送や不揮発・高密度情報記憶を可能にするなどの画期的な性質により、その研究は近年世界的規模で進められている。その源流となるのが、齊藤氏によるスピン流の直接検出手法の発見である。従来スピン流はその検出すら不可能であったが、この状況を一気に打破したのは齊藤氏による逆スピンホール効果(スピン流を電圧に変換する現象)の発見とその系統的研究である。斉藤氏自身もこの手法を利用して「絶縁体中のスピン流伝送(電気信号伝送)」やスピンゼーベック効果等の画期的なスピントロニクス現象の発見を次々と成功させた。 渋谷哲朗しぶやてつお東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター准教授大規模高次元構造データベース検索のための革新的アルゴリズム設計パラダイムの創造渋谷氏はこれまで大規模データベース、特に生物分野におけるデータベースに対する検索アルゴリズムの研究を中心にバイオインフォマティクスの研究を行っており、情報科学、生物学にわたる多数の高ランクの国際学術雑誌・国際会議において数多くの発表を行ってきた。渋谷氏の研究は生物分野にとどまらない様々な産業的応用がある。特に最近創造した大規模高次元構造データベース検索のための新しいアルゴリズム設計パラダイムSMADは非常に独創的かつ革新的なものであり、それをもとに開発したタンパク質立体構造データベース高速検索技術は、きわめて革新的な大きな学術的価値をもつものである。
渋谷哲朗しぶやてつお東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター准教授大規模高次元構造データベース検索のための革新的アルゴリズム設計パラダイムの創造渋谷氏はこれまで大規模データベース、特に生物分野におけるデータベースに対する検索アルゴリズムの研究を中心にバイオインフォマティクスの研究を行っており、情報科学、生物学にわたる多数の高ランクの国際学術雑誌・国際会議において数多くの発表を行ってきた。渋谷氏の研究は生物分野にとどまらない様々な産業的応用がある。特に最近創造した大規模高次元構造データベース検索のための新しいアルゴリズム設計パラダイムSMADは非常に独創的かつ革新的なものであり、それをもとに開発したタンパク質立体構造データベース高速検索技術は、きわめて革新的な大きな学術的価値をもつものである。 林正人はやしまさひと東北大学大学院情報科学研究科准教授ユニバーサル量子情報プロトコルの構築と量子暗号への応用林氏は、量子通信におけるユニバーサル符号の理論的構成と実現という画期的な成果をあげた。量子通信は超高速かつ完全な暗号化通信ができる未来の夢の通信システムであるが、量子情報の完全な保持が難しく、情報源の性質に依存しないユニバーサルな誤り訂正符号の構築が実用化への大きな難関であった。林氏はこの難関の突破に世界で初めて成功し、日本が情報通信技術の世界最先端を走るために必要不可欠な要素技術を与えた。
林正人はやしまさひと東北大学大学院情報科学研究科准教授ユニバーサル量子情報プロトコルの構築と量子暗号への応用林氏は、量子通信におけるユニバーサル符号の理論的構成と実現という画期的な成果をあげた。量子通信は超高速かつ完全な暗号化通信ができる未来の夢の通信システムであるが、量子情報の完全な保持が難しく、情報源の性質に依存しないユニバーサルな誤り訂正符号の構築が実用化への大きな難関であった。林氏はこの難関の突破に世界で初めて成功し、日本が情報通信技術の世界最先端を走るために必要不可欠な要素技術を与えた。 山下淳やましたあつし静岡大学 工学部准教授見え難い情報を見るセンサ情報処理に関する研究山下氏は、水中や雨天時に撮影された画質の劣化した画像からのノイズ除去や画像センシング、背景と同じ色の人物を抽出可能な画像処理、分厚い書籍を撮影した時の歪んだ画像から正常画像を構築する手法など、コンピュータにとっては「見え難い」情報を見るセンサ情報処理技術の開発に長年携わり、多数の論文賞等を受賞するなど数々の革新的な研究業績を上げ、国内外の情報処理技術の学術的発展に広く貢献している。
山下淳やましたあつし静岡大学 工学部准教授見え難い情報を見るセンサ情報処理に関する研究山下氏は、水中や雨天時に撮影された画質の劣化した画像からのノイズ除去や画像センシング、背景と同じ色の人物を抽出可能な画像処理、分厚い書籍を撮影した時の歪んだ画像から正常画像を構築する手法など、コンピュータにとっては「見え難い」情報を見るセンサ情報処理技術の開発に長年携わり、多数の論文賞等を受賞するなど数々の革新的な研究業績を上げ、国内外の情報処理技術の学術的発展に広く貢献している。 四方博之よもひろゆき関西大学 システム理工学部准教授無線通信システムにおけるクロスレイヤ最適化に関する研究従来、無線通信システムの物理層・MAC層・ネットワーク層は、階層化の概念に基づき、各層別に設計されてきた。これに対し、四方氏はこれらの階層を統合的に設計するクロスレイヤ最適化に関する研究を行い、セルラシステムから無線LAN、さらにはアドホックネットワークなど多様な無線システムを対象としたクロスレイヤプロトコルを世に送り出すとともに、その理論的・実験的評価を行ってきた。特に、無線ネットワークコーディング技術に関しては、その基本伝送方式を世界に先駆けて発表した。これを受け国内外で、その基本伝送方式の拡張・評価に関する研究が盛んになるなど、無線通信の研究分野に大きなインパクトを与えた。
四方博之よもひろゆき関西大学 システム理工学部准教授無線通信システムにおけるクロスレイヤ最適化に関する研究従来、無線通信システムの物理層・MAC層・ネットワーク層は、階層化の概念に基づき、各層別に設計されてきた。これに対し、四方氏はこれらの階層を統合的に設計するクロスレイヤ最適化に関する研究を行い、セルラシステムから無線LAN、さらにはアドホックネットワークなど多様な無線システムを対象としたクロスレイヤプロトコルを世に送り出すとともに、その理論的・実験的評価を行ってきた。特に、無線ネットワークコーディング技術に関しては、その基本伝送方式を世界に先駆けて発表した。これを受け国内外で、その基本伝送方式の拡張・評価に関する研究が盛んになるなど、無線通信の研究分野に大きなインパクトを与えた。
第9回 2009年度
 五十嵐健夫いがらしたけお東京大学大学院情報理工学系研究科准教授コンピュータグラフィクスのためのユーザインタフェースに関する研究五十嵐氏は、従来は専門家が膨大な時間をかけて作成するものであった 3次元CGの製作を初心者でも簡単に行えるようにしたことである。具体的な成果として、 2次元のスケッチを描くことで簡単に 3次元形状を作成する手法、画面に表示された絵を両手でつかんで動かすことによる2次元アニメーション作成手法、 3次元キャラクタと 2次元的な服の間の対応関係を指定することで簡単に服を着せ付ける手法等がある。これらの成果は、スケッチインタフェースという新しい研究分野を切り開くものとして高く評価されており、開発した技術のいくつかはすでに実用化され広く使われている。
五十嵐健夫いがらしたけお東京大学大学院情報理工学系研究科准教授コンピュータグラフィクスのためのユーザインタフェースに関する研究五十嵐氏は、従来は専門家が膨大な時間をかけて作成するものであった 3次元CGの製作を初心者でも簡単に行えるようにしたことである。具体的な成果として、 2次元のスケッチを描くことで簡単に 3次元形状を作成する手法、画面に表示された絵を両手でつかんで動かすことによる2次元アニメーション作成手法、 3次元キャラクタと 2次元的な服の間の対応関係を指定することで簡単に服を着せ付ける手法等がある。これらの成果は、スケッチインタフェースという新しい研究分野を切り開くものとして高く評価されており、開発した技術のいくつかはすでに実用化され広く使われている。 戸川望早稲田大学理工学術院基幹理工学研究科教授抽象動作記述からシステムLSIを自動合成するための革新的技術に関する研究戸川氏は、システム LSIの設計技術とりわけ対象アプリケーションをソフトウェアプログラムによって記述した「抽象記述」から、そのハードウェア動作を抽出し「システムLSI」を自動的に合成する技術に関する研究を行い、その成果は国内のみならず米国学会 IEEE/ACMから複数の賞を受賞するなど目覚しい成果を挙げている。
戸川望早稲田大学理工学術院基幹理工学研究科教授抽象動作記述からシステムLSIを自動合成するための革新的技術に関する研究戸川氏は、システム LSIの設計技術とりわけ対象アプリケーションをソフトウェアプログラムによって記述した「抽象記述」から、そのハードウェア動作を抽出し「システムLSI」を自動的に合成する技術に関する研究を行い、その成果は国内のみならず米国学会 IEEE/ACMから複数の賞を受賞するなど目覚しい成果を挙げている。 本間尚文東北大学大学院情報科学研究科准教授ハードウェアアルゴリズムの高水準設計技術とその応用に関する研究本間氏は、複雑化する LSIデータバスの設計問題を解決する新しい設計パラダイムとして、算術演算回路のハードウェアアルゴリズム(算術アルゴリズム)の高水準な記述・検証・合成技術を開拓してきた。特に2進数と非 2進数を統合した数系・数式に基づく算術アルゴリズムの表現手法を発案し、それに基づく算術演算回路の合成・検証システムを世界に先駆けて開発した。同システムは,算術アルゴリズムの検証のために新たに開発した言語を備え,機能が完全に保証された回路のみを高速に合成できる。これは、高度な計算機代数の技法を回路検証に適用することで初めて実現され、国内外から高く評価されている。
本間尚文東北大学大学院情報科学研究科准教授ハードウェアアルゴリズムの高水準設計技術とその応用に関する研究本間氏は、複雑化する LSIデータバスの設計問題を解決する新しい設計パラダイムとして、算術演算回路のハードウェアアルゴリズム(算術アルゴリズム)の高水準な記述・検証・合成技術を開拓してきた。特に2進数と非 2進数を統合した数系・数式に基づく算術アルゴリズムの表現手法を発案し、それに基づく算術演算回路の合成・検証システムを世界に先駆けて開発した。同システムは,算術アルゴリズムの検証のために新たに開発した言語を備え,機能が完全に保証された回路のみを高速に合成できる。これは、高度な計算機代数の技法を回路検証に適用することで初めて実現され、国内外から高く評価されている。 首藤一幸東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授オーバーレイネットワークの基盤・応用ソフトウェアに関する研究オーバレイネットワークは、アンダーレイ、例えばインターネットの上に構築されるアプリケーションレベルのネットワークであり、アンダーレイ自身が持たない様々な機能を提供する。次のインターネットを設計する上でも欠かせない基盤技術となっている。首藤氏は、オーバレイネットワークの研究に欠かせない基盤ソフトウェア (Overlay Weaver)を世に提供するとともに、オーバレイを応用したコンテンツライブ配信技術・ソフトウェア(UG Live)を研究・開発、商用化を達成した。
首藤一幸東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授オーバーレイネットワークの基盤・応用ソフトウェアに関する研究オーバレイネットワークは、アンダーレイ、例えばインターネットの上に構築されるアプリケーションレベルのネットワークであり、アンダーレイ自身が持たない様々な機能を提供する。次のインターネットを設計する上でも欠かせない基盤技術となっている。首藤氏は、オーバレイネットワークの研究に欠かせない基盤ソフトウェア (Overlay Weaver)を世に提供するとともに、オーバレイを応用したコンテンツライブ配信技術・ソフトウェア(UG Live)を研究・開発、商用化を達成した。 原田博司独立行政法人情報通信研究機構 ユビキタスモバイルグループグループリーダーソフトウェア無線・コグニティブ無線技術に関する先駆的研究開発および標準化各種無線通信システムを実現するソフトウェアを切り替えることにより複数の通信システムを l台の無線機で実現するソフトウェア無線技術を用いたマルチモード無線機の小型化に世界初で成功した。さらにこの技術を拡張し、コグニティブ無線技術に展開し、400MHz-6GHz帯の周波数を認識、対応可能なコグニティブ無線機を世界初で開発した。このように原田氏のソフトウェア無線技術、コグニティブ無線技術等の研究成果は国内外を問わず高く評価されている。
原田博司独立行政法人情報通信研究機構 ユビキタスモバイルグループグループリーダーソフトウェア無線・コグニティブ無線技術に関する先駆的研究開発および標準化各種無線通信システムを実現するソフトウェアを切り替えることにより複数の通信システムを l台の無線機で実現するソフトウェア無線技術を用いたマルチモード無線機の小型化に世界初で成功した。さらにこの技術を拡張し、コグニティブ無線技術に展開し、400MHz-6GHz帯の周波数を認識、対応可能なコグニティブ無線機を世界初で開発した。このように原田氏のソフトウェア無線技術、コグニティブ無線技術等の研究成果は国内外を問わず高く評価されている。 牧野和久まきのかずひさ東京大学大学院情報理工学系研究科准教授列挙アルゴリズムの設計と解析に関する研究牧野氏は,列挙アルゴリズムの設計と解析に関する研究、ならびにそれらを人工知能、データマイニングなどの分野へ応用する研究を行い国内外で非常に高い評価を受けている。中でも顕著な業績は「推論補完」と「論理関数の双対化」であり,コンピューターサイエンス分野、特に発見科学の中心的課題に関する世界的なブレークスルーであり、国際的に大きなインパクトを与えた。そしてこれらの成果は発見科学における日本の先進性を計算理論の面から支える大きな成果である。
牧野和久まきのかずひさ東京大学大学院情報理工学系研究科准教授列挙アルゴリズムの設計と解析に関する研究牧野氏は,列挙アルゴリズムの設計と解析に関する研究、ならびにそれらを人工知能、データマイニングなどの分野へ応用する研究を行い国内外で非常に高い評価を受けている。中でも顕著な業績は「推論補完」と「論理関数の双対化」であり,コンピューターサイエンス分野、特に発見科学の中心的課題に関する世界的なブレークスルーであり、国際的に大きなインパクトを与えた。そしてこれらの成果は発見科学における日本の先進性を計算理論の面から支える大きな成果である。
船井振興賞受賞者
第9回2009年度から、船井学術賞に名称変更し、褒賞の対象を39歳以下の若手研究者に変更しました。
第8回 2008年度
 青木孝文あおきたかふみ東北大学大学院情報科学研究科教授位相情報に基づく超高精度画像マッチングとその応用に関する研究画像マッチングは,画像センシング,映像信号処理,コンピュータビジョンなどのさまざまな分野で重要になる基本処理である。 青木氏は,画像の位相情報に基づく一連の超高精度画像マッチング技術を『位相限定相関法(POC:Phase-On1y Corre1ation)』として体系化するとともに, 産学連携研究を通して広範囲の応用に適用してきた。まず1990年代に,バイオメトリクス認証のための生体画像の照合技術として位相限定相関法の研究開発に着手し, 指紋照合システムを実用化している。この基本原理は特許庁の「標準技術集」に登録され,従来の特徴点方式に代わる新方式としてその有効性が広く認知されている。 その後,同技術の拡張を行い,1/100ピクセル級の位置合わせ精度を有する超高精度画像マッチング手法を考案するとともに,工業市場向け超高速画像認識システムを実用化している. これは,ピクセル分解能の壁を突破できる新しい画像センシング技術へ道を拓く成果であり,バイオメトリクス認証や工業用マシンビジョンのみならず,顕微鏡画像解析,レーザースペックル計測, 受動型3次元計測,車載カメラ,映像信号処理,LSI動作解析などの広範な応用において多大なインパクトを与えつつある。
青木孝文あおきたかふみ東北大学大学院情報科学研究科教授位相情報に基づく超高精度画像マッチングとその応用に関する研究画像マッチングは,画像センシング,映像信号処理,コンピュータビジョンなどのさまざまな分野で重要になる基本処理である。 青木氏は,画像の位相情報に基づく一連の超高精度画像マッチング技術を『位相限定相関法(POC:Phase-On1y Corre1ation)』として体系化するとともに, 産学連携研究を通して広範囲の応用に適用してきた。まず1990年代に,バイオメトリクス認証のための生体画像の照合技術として位相限定相関法の研究開発に着手し, 指紋照合システムを実用化している。この基本原理は特許庁の「標準技術集」に登録され,従来の特徴点方式に代わる新方式としてその有効性が広く認知されている。 その後,同技術の拡張を行い,1/100ピクセル級の位置合わせ精度を有する超高精度画像マッチング手法を考案するとともに,工業市場向け超高速画像認識システムを実用化している. これは,ピクセル分解能の壁を突破できる新しい画像センシング技術へ道を拓く成果であり,バイオメトリクス認証や工業用マシンビジョンのみならず,顕微鏡画像解析,レーザースペックル計測, 受動型3次元計測,車載カメラ,映像信号処理,LSI動作解析などの広範な応用において多大なインパクトを与えつつある。 黒橋禎夫くろはしさだお京都大学大学院情報科学研究科教授大規模テキストデータに基づく自然言語処理と情報検索の高度化言語を処理するためには文法的知識だけでなく世界知識、常識が必要となる。これまでの計算機による自然言語 処理では知識の欠落が決定的な問題であった。黒橋氏は,大規模テキストデータと並列計算環境が利用可能となり はじめたことに着自し,大規模テキストデータから述語と名詞の結びつきのパターン(格フレーム)を大規模に学 習することを世界に先駆けて実現した。この格フレーム学習においては,テキストの自動解析結果からまず確から しい情報を抽出し,その情報によって自動解析を高度化し,そこからまた新たな確からしい情報を獲得するという ブートストラップ的手法を考案した。 また,Web情報の利活用において情報の信頼性は重要な課題であるが,計算機でこれを自動的に判断することは 困難なものの,情報を多面的にとらえ組織化するシステムによって利用者のサポートが可能であることを提案し, 自然言語処理技術の統合によって情報発信者や特徴的な言明・意見などから情報にアクセス可能なシステムを構築 した。
黒橋禎夫くろはしさだお京都大学大学院情報科学研究科教授大規模テキストデータに基づく自然言語処理と情報検索の高度化言語を処理するためには文法的知識だけでなく世界知識、常識が必要となる。これまでの計算機による自然言語 処理では知識の欠落が決定的な問題であった。黒橋氏は,大規模テキストデータと並列計算環境が利用可能となり はじめたことに着自し,大規模テキストデータから述語と名詞の結びつきのパターン(格フレーム)を大規模に学 習することを世界に先駆けて実現した。この格フレーム学習においては,テキストの自動解析結果からまず確から しい情報を抽出し,その情報によって自動解析を高度化し,そこからまた新たな確からしい情報を獲得するという ブートストラップ的手法を考案した。 また,Web情報の利活用において情報の信頼性は重要な課題であるが,計算機でこれを自動的に判断することは 困難なものの,情報を多面的にとらえ組織化するシステムによって利用者のサポートが可能であることを提案し, 自然言語処理技術の統合によって情報発信者や特徴的な言明・意見などから情報にアクセス可能なシステムを構築 した。 外林秀之そとばやしひでゆき青山学院大学理工学部電気電子工学科准教授フォトニックネットワーク応用に向けた超高速光エレクトロニクスの先駆的研究多様な形態の情報を、広帯域ネットワークを通じて自由に取り扱えるユビキタス環境の実現は、生活や経済の高度化に大きく寄与するものと考えられている。 情報伝送・転送機能を光領域で行うフォトニックネットワークは、超大容量情報通信技術としてユビキタス社会における不可欠な社会基盤構成要素となっている。 外林氏は、フォトニックネットワーク応用に向けて、光の持つ属性を極限まで活用する多様な超高速光エレクトロニクス技術の提案・実現・実証を行った。具体的には、1)超高速光信号処理サブシステムの実証、2)超テラビット光時分割多重/波長多重ネットワークのシステム実証、3)コヒーレント光符号分割多重技術の開発とシステム応用実証である。研究手法としては、光材料探索・光デバイス開発にとどまらず、サブシステム適用・ネットワーク応用実証まで行い、材料・物理分野の基礎研究から情報通信ネットワーク実証の応用研究に至り、光エレクトロニクス先駆的研究を行った。
外林秀之そとばやしひでゆき青山学院大学理工学部電気電子工学科准教授フォトニックネットワーク応用に向けた超高速光エレクトロニクスの先駆的研究多様な形態の情報を、広帯域ネットワークを通じて自由に取り扱えるユビキタス環境の実現は、生活や経済の高度化に大きく寄与するものと考えられている。 情報伝送・転送機能を光領域で行うフォトニックネットワークは、超大容量情報通信技術としてユビキタス社会における不可欠な社会基盤構成要素となっている。 外林氏は、フォトニックネットワーク応用に向けて、光の持つ属性を極限まで活用する多様な超高速光エレクトロニクス技術の提案・実現・実証を行った。具体的には、1)超高速光信号処理サブシステムの実証、2)超テラビット光時分割多重/波長多重ネットワークのシステム実証、3)コヒーレント光符号分割多重技術の開発とシステム応用実証である。研究手法としては、光材料探索・光デバイス開発にとどまらず、サブシステム適用・ネットワーク応用実証まで行い、材料・物理分野の基礎研究から情報通信ネットワーク実証の応用研究に至り、光エレクトロニクス先駆的研究を行った。 染谷隆夫そめやたかお東京大学大学院工学系研究科准教授有機トランジスターを用いたフレキシブル情報通信デバイスに関する研究新型のフレキシブノレ情報通信デバイスは、有機トランジスタと呼ばれるフレキシブノレな薄膜ト ランジスタを駆使して作製される。染谷君は、有機エレクトロニクス技術の最大の特長である「有 機トランジスタで大面積の集積回路が容易に作れる」ことに着眼し、電子人工皮膚など大面積セ ンサに有機トランジスタを応用する可能性を世界ではじめて立証した。この電子人工皮膚の業績 で、染谷君は、2005年に船井情報科学奨励賞を受賞するなど高い評価を得ている。新デバイス は、電子人工皮膚で鍵となった有機トランジスタの性能を飛躍的に向上し、さらに、大面積セン サシートとアクチュエータシートを集積化することによって始めて実現された。染谷君は、新デ バイスを実現するために、ポリイミドのゲート絶縁膜応用や物理的な切り貼りよる集積回路など 今後の素子化のスタンダードになると期待される数々のブレークスノレーを達成している(特許7 件申請)。また、同君は、有機トランジスタの伝導機構の解明や印刷製造プロセスについても世 界で注目される研究成果を次々と達成している。
染谷隆夫そめやたかお東京大学大学院工学系研究科准教授有機トランジスターを用いたフレキシブル情報通信デバイスに関する研究新型のフレキシブノレ情報通信デバイスは、有機トランジスタと呼ばれるフレキシブノレな薄膜ト ランジスタを駆使して作製される。染谷君は、有機エレクトロニクス技術の最大の特長である「有 機トランジスタで大面積の集積回路が容易に作れる」ことに着眼し、電子人工皮膚など大面積セ ンサに有機トランジスタを応用する可能性を世界ではじめて立証した。この電子人工皮膚の業績 で、染谷君は、2005年に船井情報科学奨励賞を受賞するなど高い評価を得ている。新デバイス は、電子人工皮膚で鍵となった有機トランジスタの性能を飛躍的に向上し、さらに、大面積セン サシートとアクチュエータシートを集積化することによって始めて実現された。染谷君は、新デ バイスを実現するために、ポリイミドのゲート絶縁膜応用や物理的な切り貼りよる集積回路など 今後の素子化のスタンダードになると期待される数々のブレークスノレーを達成している(特許7 件申請)。また、同君は、有機トランジスタの伝導機構の解明や印刷製造プロセスについても世 界で注目される研究成果を次々と達成している。 高木剛たかぎつよし公立はこだて未来大学システム情報学部教授公開鍵暗号の高速実装理論の研究とその応用暗号技術は安全な情撮社会を支える通信インフラとして広く利用されているだけでなく、電子決済方式、著作権保 護システム、電子入札システムなどの情報セキュリティシステムにも応用され始めている。申請者は、公開鍵暗号 の高速実装理論の研究において50編以上の論文を発表するなど優れた業績を上げてきている。1995年~2001年は NTT研究所においてRSA暗号の高速実装の研究、2002年~2005年はドイツ・ダルムシュタット工科大学の助教授と して楕円曲線暗号の研究に従事してきた。2005年からは、公立はこだて未来大学において次世代暗号として注目を 集めているペアリング暗号の研究を行っている。現在までに、情報セキュリティ分野の国際会議のプログラム編集 委員を50件以上務め、海外の大学や研究ワークショップにおいて招待講演を15件行ってきた。また、民間企業 や政府系の研究機関(NIbT,IPA等)と12件の共同/委託研究を実施し10件 の共同特許出願を行った。以上のように、公開鍵暗号の研究において理論および実用の両面から顕著な功績がある。
高木剛たかぎつよし公立はこだて未来大学システム情報学部教授公開鍵暗号の高速実装理論の研究とその応用暗号技術は安全な情撮社会を支える通信インフラとして広く利用されているだけでなく、電子決済方式、著作権保 護システム、電子入札システムなどの情報セキュリティシステムにも応用され始めている。申請者は、公開鍵暗号 の高速実装理論の研究において50編以上の論文を発表するなど優れた業績を上げてきている。1995年~2001年は NTT研究所においてRSA暗号の高速実装の研究、2002年~2005年はドイツ・ダルムシュタット工科大学の助教授と して楕円曲線暗号の研究に従事してきた。2005年からは、公立はこだて未来大学において次世代暗号として注目を 集めているペアリング暗号の研究を行っている。現在までに、情報セキュリティ分野の国際会議のプログラム編集 委員を50件以上務め、海外の大学や研究ワークショップにおいて招待講演を15件行ってきた。また、民間企業 や政府系の研究機関(NIbT,IPA等)と12件の共同/委託研究を実施し10件 の共同特許出願を行った。以上のように、公開鍵暗号の研究において理論および実用の両面から顕著な功績がある。 松岡広成まつおかひろしげ鳥取大学大学院工学研究科准教授液体超薄膜の力学特性の解明と超高密度記録への応用コンピュータ用磁気ディスク装置の超高記録密度化のためのキーテクノロジーの1つであるヘッド・ディスク・インターフェース(HDI)に関し、主に表面間相互作用の観点から多岐にわたる先駆的な研究を行ってきた。具体的には、固体表面近傍の液体超薄膜の構造力による潤滑膜の離散化,液体超薄膜を考慮に入れたファンデルワールスカの汎用的近似式の導出,液体メニスカス架橋の動特性の実験的・理論的解明,超薄膜の表面エネルギーの理論式の導出とその実験的検証,液体超薄膜を介した固体間接触モデルの提案など、将来の超高記録密度ヘッド・ディスク・インターフェース設計の基礎となるだけでなく、ナノテクノロジー全般に適用可能な知見を得ている。これらの業績は、世界的に見ても学術的先導性・発展性に優れたものであり、米国機械学会(ASME),英国機械学会(IMechE),日本機械学会,日本トライボロジー学会など、国内外の学会から高い評価を受けている。
松岡広成まつおかひろしげ鳥取大学大学院工学研究科准教授液体超薄膜の力学特性の解明と超高密度記録への応用コンピュータ用磁気ディスク装置の超高記録密度化のためのキーテクノロジーの1つであるヘッド・ディスク・インターフェース(HDI)に関し、主に表面間相互作用の観点から多岐にわたる先駆的な研究を行ってきた。具体的には、固体表面近傍の液体超薄膜の構造力による潤滑膜の離散化,液体超薄膜を考慮に入れたファンデルワールスカの汎用的近似式の導出,液体メニスカス架橋の動特性の実験的・理論的解明,超薄膜の表面エネルギーの理論式の導出とその実験的検証,液体超薄膜を介した固体間接触モデルの提案など、将来の超高記録密度ヘッド・ディスク・インターフェース設計の基礎となるだけでなく、ナノテクノロジー全般に適用可能な知見を得ている。これらの業績は、世界的に見ても学術的先導性・発展性に優れたものであり、米国機械学会(ASME),英国機械学会(IMechE),日本機械学会,日本トライボロジー学会など、国内外の学会から高い評価を受けている。
第7回 2007年度
 田中克己たなかかつみ京都大学大学院情報学研究科教授Web及びマルチメディア情報システムに関する先駆的研究Web情報システム、マルチメディア情報システム、及び、データベース等の分野における国際的な評価の高いトップコンプライアンスや国際学術論文誌に多数の「先駆性・影響力の高い」研究論文を発表し,我が国の同分野の研究のリーディング役としての大きな貢献をした。特に質問対リンクに基づくハイパーメディア構築法、ビデオ映像検索モデル、Webの受動的視聴システム、Web比較ブラウジング方式、ソーシャルブックマークによるWeb検索結果リランキング方式などの研究は,独創性や新規性が極めて高いとともに、国際的にも多くの注目を集めている。同氏の研究姿勢は,新規性の高いアイデアの創出にもとづき新たな研究分野を開拓するというもので、国際的な論文被引用数も多く,その先駆性が高く評価できる。
田中克己たなかかつみ京都大学大学院情報学研究科教授Web及びマルチメディア情報システムに関する先駆的研究Web情報システム、マルチメディア情報システム、及び、データベース等の分野における国際的な評価の高いトップコンプライアンスや国際学術論文誌に多数の「先駆性・影響力の高い」研究論文を発表し,我が国の同分野の研究のリーディング役としての大きな貢献をした。特に質問対リンクに基づくハイパーメディア構築法、ビデオ映像検索モデル、Webの受動的視聴システム、Web比較ブラウジング方式、ソーシャルブックマークによるWeb検索結果リランキング方式などの研究は,独創性や新規性が極めて高いとともに、国際的にも多くの注目を集めている。同氏の研究姿勢は,新規性の高いアイデアの創出にもとづき新たな研究分野を開拓するというもので、国際的な論文被引用数も多く,その先駆性が高く評価できる。 江崎浩えさきひろし東京大学大学院情報理工学系研究科教授高機能インターネットアーキテクチャの先導的研究超高速・高機能インターネットを実現するための基盤アーキテクチャとプロトコルに関する研究開発を、グローバノレ規模での産学連携体制を確立し推進した。具体的には、インターネットにおけるトラフィックエンジニアリング制御ならびに高品質VPN(Virtual Private Network)構築手法として、現在ではほとんどの主要インターネットサービスプロバイダにおいて導入されているMPLSアーキテクチャと、次世代インターネットプロトコルであるIPv6(IPversion6)技術の実装ソフトウェアアーキテクチャの研究開発とIPv6技術を用いたモパイルネットワークアーキテクチャや経路制御アーキテクチャに関する研究である。両研究成果とも、産学連携の共同研究体制を確立し、その成果を商用システムヘの導入展開に資する研究開発活動へと発展させる先導的な活動を展開した。さらに、その活動を国際的共同研究/協調活動へと発展させ、それらはインターネットにおける国際標準技術として採択されるにいたっている。
江崎浩えさきひろし東京大学大学院情報理工学系研究科教授高機能インターネットアーキテクチャの先導的研究超高速・高機能インターネットを実現するための基盤アーキテクチャとプロトコルに関する研究開発を、グローバノレ規模での産学連携体制を確立し推進した。具体的には、インターネットにおけるトラフィックエンジニアリング制御ならびに高品質VPN(Virtual Private Network)構築手法として、現在ではほとんどの主要インターネットサービスプロバイダにおいて導入されているMPLSアーキテクチャと、次世代インターネットプロトコルであるIPv6(IPversion6)技術の実装ソフトウェアアーキテクチャの研究開発とIPv6技術を用いたモパイルネットワークアーキテクチャや経路制御アーキテクチャに関する研究である。両研究成果とも、産学連携の共同研究体制を確立し、その成果を商用システムヘの導入展開に資する研究開発活動へと発展させる先導的な活動を展開した。さらに、その活動を国際的共同研究/協調活動へと発展させ、それらはインターネットにおける国際標準技術として採択されるにいたっている。 小野輝男おのてるお京都大学化学研究所教授電流による磁化制御技術の開発小野氏は半導体分野で広く用いられてきた微細加工技術を用いてナノメートルスケールの強磁性細線や強磁性ドットを作製し、それらの示す電流と磁気モーメントの直接相互作用に起因する新しい磁化制御技術を開発した。具体的には、強磁性細線中の磁壁を電流で動かして細線の磁化状態を制御する技術、強磁性ドットに存在する磁気コアの向きを電流によって制御する技術の二つを開発した。従来、磁気デバイスの磁化の向きは磁場によって制御されてきたが、小野氏の開発した技術はデバイスを流れる電流のみで磁化の向きを制御することを可能とするものである。この技術によって磁場発生部は不要となり、新規な磁気メモリーや磁気論理回路などのスピントロニクスデバイス開発が可能となった。この開発した技術は、次世代スピントロニクスの基盤となる技術であり、エレクトロニクス分野の可能性を広げ、当分野における波及効果の大きい優れた業績である。
小野輝男おのてるお京都大学化学研究所教授電流による磁化制御技術の開発小野氏は半導体分野で広く用いられてきた微細加工技術を用いてナノメートルスケールの強磁性細線や強磁性ドットを作製し、それらの示す電流と磁気モーメントの直接相互作用に起因する新しい磁化制御技術を開発した。具体的には、強磁性細線中の磁壁を電流で動かして細線の磁化状態を制御する技術、強磁性ドットに存在する磁気コアの向きを電流によって制御する技術の二つを開発した。従来、磁気デバイスの磁化の向きは磁場によって制御されてきたが、小野氏の開発した技術はデバイスを流れる電流のみで磁化の向きを制御することを可能とするものである。この技術によって磁場発生部は不要となり、新規な磁気メモリーや磁気論理回路などのスピントロニクスデバイス開発が可能となった。この開発した技術は、次世代スピントロニクスの基盤となる技術であり、エレクトロニクス分野の可能性を広げ、当分野における波及効果の大きい優れた業績である。 栗村直くりむらすなお独立行政法人 物質・材料研究機構 光材料センター光周波数変換グループ主任研究員擬似位相整合非線形光学の研究栗村氏は非線形光学波長変換を用いて、従来特定の波長で固定されていたレーザーの波長を、自由に高効率変換することを可能にしてきた。擬似位相整合という新しい概念の基に、波長変換デバイスに設計の概念を持ち込んだ。用途に合わせて波長変換した光源を実現し他分野へ大きな波及効果を及ぼしている。バルク、導波路など多彩なデバイス形態を実現して、波長多重通信、分子分光、量子光学、シリコンフォトニクス、など新規分野へも精力的に進出しており、擬似位相整合非線形光学を先導している。光通信用波長変換デバイスでは、世界最高効率を更新し続けている。紫外擬似位相整合波長変換デバイスでは最短波長266nmの記録を有している。産業応用を見据えた新規材料・新規デバイスの開拓にも積極的であり、波長変換デバイスのベンチャーSWINGを設立する傍ら、企業への技術移管も行っているとともに、各学会・協会の委員を歴任しており、学術界における貢献度は非常に大きい。
栗村直くりむらすなお独立行政法人 物質・材料研究機構 光材料センター光周波数変換グループ主任研究員擬似位相整合非線形光学の研究栗村氏は非線形光学波長変換を用いて、従来特定の波長で固定されていたレーザーの波長を、自由に高効率変換することを可能にしてきた。擬似位相整合という新しい概念の基に、波長変換デバイスに設計の概念を持ち込んだ。用途に合わせて波長変換した光源を実現し他分野へ大きな波及効果を及ぼしている。バルク、導波路など多彩なデバイス形態を実現して、波長多重通信、分子分光、量子光学、シリコンフォトニクス、など新規分野へも精力的に進出しており、擬似位相整合非線形光学を先導している。光通信用波長変換デバイスでは、世界最高効率を更新し続けている。紫外擬似位相整合波長変換デバイスでは最短波長266nmの記録を有している。産業応用を見据えた新規材料・新規デバイスの開拓にも積極的であり、波長変換デバイスのベンチャーSWINGを設立する傍ら、企業への技術移管も行っているとともに、各学会・協会の委員を歴任しており、学術界における貢献度は非常に大きい。 小寺秀俊こでらひでとし京都大学大学院工学研究科教授圧電材料の基礎研究とそれを用いたMEMS及びμTASの研究小寺氏は、PZT薄膜を基本とした圧電薄膜の組成と特性に関する基礎研究を行うとともに、基礎研究成果を元に、高速度通信用(60GHz帯)のMEMSスイッチや指向性可変アンテナおよびマイクロポンプを考案し開発した。また、磁性粒子をPDMSに高密度充填する方法を考案し、それを用いてマイクロアクチュエータを作成しマイクロスイッチや可変アンテナの新たな構造として磁性粉体を利用することを提案している。圧電素子の応用としては通信用デバイス以外に圧電駆動型のマイクロミラーデバイス等を開発した。これらの圧電技術・粉体成形技術は企業に引き継がれ多くの企業が利用している。また、細胞内および細胞間の情報伝達を計測するマイクロ流路とオリフィスおよび電極を集積化したマイクロデバイスの構造と加工方法を考案し、心筋細胞を始め様々な細胞機能を計測するとともに、細胞内情報伝達の細胞機能シミュレーションシステム開発に大きく寄与した。
小寺秀俊こでらひでとし京都大学大学院工学研究科教授圧電材料の基礎研究とそれを用いたMEMS及びμTASの研究小寺氏は、PZT薄膜を基本とした圧電薄膜の組成と特性に関する基礎研究を行うとともに、基礎研究成果を元に、高速度通信用(60GHz帯)のMEMSスイッチや指向性可変アンテナおよびマイクロポンプを考案し開発した。また、磁性粒子をPDMSに高密度充填する方法を考案し、それを用いてマイクロアクチュエータを作成しマイクロスイッチや可変アンテナの新たな構造として磁性粉体を利用することを提案している。圧電素子の応用としては通信用デバイス以外に圧電駆動型のマイクロミラーデバイス等を開発した。これらの圧電技術・粉体成形技術は企業に引き継がれ多くの企業が利用している。また、細胞内および細胞間の情報伝達を計測するマイクロ流路とオリフィスおよび電極を集積化したマイクロデバイスの構造と加工方法を考案し、心筋細胞を始め様々な細胞機能を計測するとともに、細胞内情報伝達の細胞機能シミュレーションシステム開発に大きく寄与した。 橋本巨はしもとひろむ東海大学工学部機械工学科教授紙・光学フィルムを対象としたウェブハンドリング理論の体系化とその生産現場への応用紙や光学フィルムなどの連続柔軟媒体はウェブと総称され、記録媒体やディスプレイ用材料と多く用いられ、情報技術の重要な一役を担っている。ウェブの生産工程においてこれらを搬送し途中処理工程を経て最終的に巻き取るウェブハンドリング技術は、ウェブ製造に関わる重要基盤技術である。しかしながら、ウェブハンドリング技術は従来生産現場での経験の積み重ねにより練り上げられたものであり、技術自体は相当高度なレベノレにはあるものの、搬送・巻き取り中に生じるしわ、スリップ、巻きずれなどウェブの品質に深刻なダメージを与える現象を予測・解明するための学術的なバックグラウンドには極めて乏しい状況にあった。本研究においては,従来の経験則をべ一スとしたウェブ搬送並びに巻き取り技術から脱却して、これらの技術のキーとなる生産速度の高速化に伴う周囲からの空気巻込みとそれにともなうウェブとローラ間のトラクション特性の変化を記述し得る新理論モデノレを構築している。さらにこれを応用して、従来予測が不可能であったウェブ搬送中におけるスリップ、しわ、巻きずれなどの不具合現象を予測かつ防止し、ウェブを安定に生産する手法を確立した。
橋本巨はしもとひろむ東海大学工学部機械工学科教授紙・光学フィルムを対象としたウェブハンドリング理論の体系化とその生産現場への応用紙や光学フィルムなどの連続柔軟媒体はウェブと総称され、記録媒体やディスプレイ用材料と多く用いられ、情報技術の重要な一役を担っている。ウェブの生産工程においてこれらを搬送し途中処理工程を経て最終的に巻き取るウェブハンドリング技術は、ウェブ製造に関わる重要基盤技術である。しかしながら、ウェブハンドリング技術は従来生産現場での経験の積み重ねにより練り上げられたものであり、技術自体は相当高度なレベノレにはあるものの、搬送・巻き取り中に生じるしわ、スリップ、巻きずれなどウェブの品質に深刻なダメージを与える現象を予測・解明するための学術的なバックグラウンドには極めて乏しい状況にあった。本研究においては,従来の経験則をべ一スとしたウェブ搬送並びに巻き取り技術から脱却して、これらの技術のキーとなる生産速度の高速化に伴う周囲からの空気巻込みとそれにともなうウェブとローラ間のトラクション特性の変化を記述し得る新理論モデノレを構築している。さらにこれを応用して、従来予測が不可能であったウェブ搬送中におけるスリップ、しわ、巻きずれなどの不具合現象を予測かつ防止し、ウェブを安定に生産する手法を確立した。
第6回 2006年度
 藤田博之ふじたひろゆき東京大学 生産技術研究所教授MEMSとマイクロアクチュエターの研究と情報・通信機器への応用MEMS(micro electoro mechanical system:マイクロマシン)は、半導体微細加工を利用して極微細の立体構造を作り、センサやマイクロアクチュエータをシリコンチップ上に実現する技術である。
藤田博之ふじたひろゆき東京大学 生産技術研究所教授MEMSとマイクロアクチュエターの研究と情報・通信機器への応用MEMS(micro electoro mechanical system:マイクロマシン)は、半導体微細加工を利用して極微細の立体構造を作り、センサやマイクロアクチュエータをシリコンチップ上に実現する技術である。
その応用は自動車や家電用の各種センサから、可動ミラーを利用したディスプレイや光通信用スイッチまで幅広く、現在多くの製品が市場に投入されている。藤田氏は本技術の黎明期であった1980年代半ばから研究を開始し、日本における先駆者として技術の確立、発展、実用化に大きく貢献した。 代表小野浩司おのひろし長岡技術科学大学教授光波電解ベクトル情報記録方式による光記録媒体の高密度化に関する研究小野氏等は、現行光ディスクシステムをできる限り踏襲できる新しい記録方式として、光波電界ベクトル和による多重・多値記録方式を提案すると共に、当該記録方式を実現できる記録材料系を提案している。記録材料系は、偏光照射によって、液晶分子配向を制御・固定化することが可能な、光架橋性高分子液晶であり、①偏光照射によって液晶分子配向方向が制御され大きな位相差を形成できる、②架橋構造を取るため熱的に安定な記録が可能である、③重ね書きした場合にお互い独立に情報記録が可能、といった特徴がある。小野氏等は、これらの特徴を生かし、さらに、405nm波長帯で記録可能な材料を開発し、光波電界ベクトル記録方式による多値・多重記録を実証しており、新しい、実現性の高い高密度記録方式への開発分野を開拓した。
代表小野浩司おのひろし長岡技術科学大学教授光波電解ベクトル情報記録方式による光記録媒体の高密度化に関する研究小野氏等は、現行光ディスクシステムをできる限り踏襲できる新しい記録方式として、光波電界ベクトル和による多重・多値記録方式を提案すると共に、当該記録方式を実現できる記録材料系を提案している。記録材料系は、偏光照射によって、液晶分子配向を制御・固定化することが可能な、光架橋性高分子液晶であり、①偏光照射によって液晶分子配向方向が制御され大きな位相差を形成できる、②架橋構造を取るため熱的に安定な記録が可能である、③重ね書きした場合にお互い独立に情報記録が可能、といった特徴がある。小野氏等は、これらの特徴を生かし、さらに、405nm波長帯で記録可能な材料を開発し、光波電界ベクトル記録方式による多値・多重記録を実証しており、新しい、実現性の高い高密度記録方式への開発分野を開拓した。- 川月 喜弘かわつき のぶひろ兵庫県立大学助教授
 代表根元義章ねもとよしあき東北大学大学院情報科学研究科教授衛星と地上ネットワークの融合を目指した新世代ネットワークプロトコルに関する先駆的研究有線と無線が融合した次世代ネットワークが進む中、ディジタルディハイドを解消し、どこからでも容易にインターネットに接続可能な衛星インターネットが世界的に注目されている。中でも特に低遅延で移動性に優れる低軌道衛星システムが大きな脚光を浴びている。本研究では、低軌道衛星システムとこれまで地上で構築されている有線及び無線ネットワークとのシームレスな接続を目指し、高効率かつ公平性を有する新世代ネットワークプロトコルを世界に先駆けて提案しその有用性を理論とコンピュータシミュレーションにより明らかにした。また、高頻度に移動する利用者を効率的に管理し、管理コストの低い移動管理技術を確立した。
代表根元義章ねもとよしあき東北大学大学院情報科学研究科教授衛星と地上ネットワークの融合を目指した新世代ネットワークプロトコルに関する先駆的研究有線と無線が融合した次世代ネットワークが進む中、ディジタルディハイドを解消し、どこからでも容易にインターネットに接続可能な衛星インターネットが世界的に注目されている。中でも特に低遅延で移動性に優れる低軌道衛星システムが大きな脚光を浴びている。本研究では、低軌道衛星システムとこれまで地上で構築されている有線及び無線ネットワークとのシームレスな接続を目指し、高効率かつ公平性を有する新世代ネットワークプロトコルを世界に先駆けて提案しその有用性を理論とコンピュータシミュレーションにより明らかにした。また、高頻度に移動する利用者を効率的に管理し、管理コストの低い移動管理技術を確立した。
これら新しく提案された技術は、情報ネットワーク分野で権威のある国際学会雑誌であるIEEE/ACM Transaction on Networkingを始め、IEEEJournal on Selected Areas in Communicationsの論文として掲載されている。また、IEEE Wireless Communications Magazineのサーベイ論文、または著名な国際会議の招待論文などで掲載されており、本分野の推進に指導的な役割を果たしており、国内外から高く評価されている。- 加藤寧かとう ねい東北大学大学院情報科学研究科教授
- タレブ タリクたれぶ たりく東北大学大学院情報科学研究科助手
 増永良文ますながよしふみお茶の水女子大学 理学部情報科学科教授データベースシステムとその高度応用に関する先導的研究増永氏はデータベースシステムとその高度応用に関する先導的研究で国際的に評価される研究を行ってきた。 1970年代末から80年代始めにかけてリレーショナルデータベースのビューサポートの研究で顕著な研究成果をあげ、その結果を世界第1級のデータベースの国際会議であるVLDB国際会議で発表する業績 をあげた。その後、マルチメディアデータベースシステムの研究・開発で顕著な成果をあげた。日本の他の研究者に先駆けてその研究・開発に取り組んだ結果、1987年には情報処理学会の会誌である「情報処理」でマルチメディアデータベースシステムの特集号を組み、その巻頭論文を執筆し、その後その論文は多くの研究者に引用されることとなった。1980年代後半から1990年代初頭にかけてはオブジェクト指向データベースシステムに関する研究を行った。特にオブジェクト指向データベースシステムのマルチメディア応用研究で成果をあげた。1990年代中頃からは、リレーショナルデータベースシステムやオブジェクト指向データベースシステムに続くべき次世代データベースシステムの研究・開発に取り組み、バーチャルリアリティとデータベースシステムを統合して仮想世界データベースシステムを実現した。近年はウェブマイニングの研究にも鋭意取り組み、情報科学と社会科学の融合に端緒を切り開くなど、一貫してデータベースシステムとその高度応用に関する研究を先導し続けている。
増永良文ますながよしふみお茶の水女子大学 理学部情報科学科教授データベースシステムとその高度応用に関する先導的研究増永氏はデータベースシステムとその高度応用に関する先導的研究で国際的に評価される研究を行ってきた。 1970年代末から80年代始めにかけてリレーショナルデータベースのビューサポートの研究で顕著な研究成果をあげ、その結果を世界第1級のデータベースの国際会議であるVLDB国際会議で発表する業績 をあげた。その後、マルチメディアデータベースシステムの研究・開発で顕著な成果をあげた。日本の他の研究者に先駆けてその研究・開発に取り組んだ結果、1987年には情報処理学会の会誌である「情報処理」でマルチメディアデータベースシステムの特集号を組み、その巻頭論文を執筆し、その後その論文は多くの研究者に引用されることとなった。1980年代後半から1990年代初頭にかけてはオブジェクト指向データベースシステムに関する研究を行った。特にオブジェクト指向データベースシステムのマルチメディア応用研究で成果をあげた。1990年代中頃からは、リレーショナルデータベースシステムやオブジェクト指向データベースシステムに続くべき次世代データベースシステムの研究・開発に取り組み、バーチャルリアリティとデータベースシステムを統合して仮想世界データベースシステムを実現した。近年はウェブマイニングの研究にも鋭意取り組み、情報科学と社会科学の融合に端緒を切り開くなど、一貫してデータベースシステムとその高度応用に関する研究を先導し続けている。 向井剛輝むかいこうき横浜国立大学大学院 工学研究院助教授半導体量子ドットを用いた光通信素子に関する先導的研究光通信で用いられる1.3ミクロン帯で発光する半導体自己形成量子ドットの作製方法を1994年に世界で初めて見いだすとともに1999年にはこれも世界で初めて、量子ドットを用いた半導体レーザを、発振波長1.3ミクロンで室温連続発振させることに成功した。量子ドットを用いた光素子は、情報トラフイックが飛躍的に増大中の光通信事業において、今後の中核技術となることが期待されている。向井氏は1994年以来現在に至る量子ドット光通信素子の実用化において、量子ドット特有の物理現象の解明や、工学的見地からの量子ドット材料の研究、更にはデバイスの開発といった、非常に広い範囲で先導的役割を果たした。
向井剛輝むかいこうき横浜国立大学大学院 工学研究院助教授半導体量子ドットを用いた光通信素子に関する先導的研究光通信で用いられる1.3ミクロン帯で発光する半導体自己形成量子ドットの作製方法を1994年に世界で初めて見いだすとともに1999年にはこれも世界で初めて、量子ドットを用いた半導体レーザを、発振波長1.3ミクロンで室温連続発振させることに成功した。量子ドットを用いた光素子は、情報トラフイックが飛躍的に増大中の光通信事業において、今後の中核技術となることが期待されている。向井氏は1994年以来現在に至る量子ドット光通信素子の実用化において、量子ドット特有の物理現象の解明や、工学的見地からの量子ドット材料の研究、更にはデバイスの開発といった、非常に広い範囲で先導的役割を果たした。 薮上信やぶかみしん東北学院大学 工学部助教授室温で動作し10-13T台の磁界検出分解能を有する薄膜磁界センサ本研究における磁界センサは磁界印加に伴う磁性薄膜の透磁率変化を高周波インピーダンス変化として取り出すもので、数100%以上の大きなインピーダンス変化が得られる。薮上氏は本センサが室温で動作する薄膜磁界センサとしては原理的に最も高感度になりうる点に着目し、これまで約9年間の研究の中で、2001年には10-11T台、2003年には10-12T台と常に世界記録を更新してきた。薮上氏はこのセンサ特有のカオスによるノイズ発生メカニズムを明らかにするとともに、ノイズを抑制しつつ、大きなインピーダンス変化を得るために、共振型の伝送線路構造のセンサデバイスを開発した。その結果501kHzの交流磁界において7.4×10-13Tの磁界検出分解能を得た。これは室温で動作する薄膜磁界センサとして、世界最高分解能であるとともに、SQUID(超伝導量子干渉素子)に匹敵するものである。これにより従来不可能とされてきた室温で動作する生体磁気信号計測が現実的な課題になりうる成果と考えられる。
薮上信やぶかみしん東北学院大学 工学部助教授室温で動作し10-13T台の磁界検出分解能を有する薄膜磁界センサ本研究における磁界センサは磁界印加に伴う磁性薄膜の透磁率変化を高周波インピーダンス変化として取り出すもので、数100%以上の大きなインピーダンス変化が得られる。薮上氏は本センサが室温で動作する薄膜磁界センサとしては原理的に最も高感度になりうる点に着目し、これまで約9年間の研究の中で、2001年には10-11T台、2003年には10-12T台と常に世界記録を更新してきた。薮上氏はこのセンサ特有のカオスによるノイズ発生メカニズムを明らかにするとともに、ノイズを抑制しつつ、大きなインピーダンス変化を得るために、共振型の伝送線路構造のセンサデバイスを開発した。その結果501kHzの交流磁界において7.4×10-13Tの磁界検出分解能を得た。これは室温で動作する薄膜磁界センサとして、世界最高分解能であるとともに、SQUID(超伝導量子干渉素子)に匹敵するものである。これにより従来不可能とされてきた室温で動作する生体磁気信号計測が現実的な課題になりうる成果と考えられる。
第5回 2005年度
 西田正吾にしだしょうご大阪大学大学院基礎工学研究科教授ヒューマンコンピュータ交流技術の先導的研究西田氏は、認知工学を応用した教育訓練システム、設計意図に着目した知識伝承支援システム、大規模システムの階層型管理方式などいずれも実用化につながった技術開発を行い、人問機械協調型システム技術の発展に貢献した。またソフトウェア開発プロジェクトにおけるコミュニケーション支援方式や大規模災害発生時の情報伝達支援方式の開発を通じて、コミュニケーション支援技術の発展にも貢献した。さらに、感性コミュニケーションや拡張現実感などのメディア関連技術の研究開発にも貢献した。これらの成果は、国内および国際的に各種受賞などの形で評価されている。また、ヒューマンインタフェースエ学、メディアエ学に関する著書を多数執筆し、この分野の学問体系の確立に貢献してきた。さらに、電子情報通信学会のヒューマンコミュニケーショングループ(2003年度運営委員長)やヒューマンインタフェース学会(2004-2005年度会長)など、この分野の学会活動に深く関わり、日本におけるヒューマンインタフェース分野の発展に寄与してきた。
西田正吾にしだしょうご大阪大学大学院基礎工学研究科教授ヒューマンコンピュータ交流技術の先導的研究西田氏は、認知工学を応用した教育訓練システム、設計意図に着目した知識伝承支援システム、大規模システムの階層型管理方式などいずれも実用化につながった技術開発を行い、人問機械協調型システム技術の発展に貢献した。またソフトウェア開発プロジェクトにおけるコミュニケーション支援方式や大規模災害発生時の情報伝達支援方式の開発を通じて、コミュニケーション支援技術の発展にも貢献した。さらに、感性コミュニケーションや拡張現実感などのメディア関連技術の研究開発にも貢献した。これらの成果は、国内および国際的に各種受賞などの形で評価されている。また、ヒューマンインタフェースエ学、メディアエ学に関する著書を多数執筆し、この分野の学問体系の確立に貢献してきた。さらに、電子情報通信学会のヒューマンコミュニケーショングループ(2003年度運営委員長)やヒューマンインタフェース学会(2004-2005年度会長)など、この分野の学会活動に深く関わり、日本におけるヒューマンインタフェース分野の発展に寄与してきた。 代表青木孝憲あおきたかのり大阪産業大学 工学部電気電子工学科相変化型光ディスク材料および新規酸化物光ディスク材料の開発と記録メカニズムの解明現在、光ディスクは情報システムのストレージ部門においてHDD(ハードディスク)や半導体メモリー(フラッシュメモリー)同様に不可欠なメモリーとして存在するが、本グノレープは開発当初から相変化型光ディスクの開発に挑わってきた。研究初期の段階では、今日、主流の材料のGe-Sb-Te系およびAg-In・Sb-Te系については本グループでも深く係わり材料探索に傾注し、特に結晶化メカニズム(結晶化速度の詳細な測定)の追求は実用化へ大きく貢献した。又さらなる高密度化を達成するため半導体レーザーの短波長化に対応する材料の探索を行い。ブルーレイはもちろん紫外光にも感度がある酸化物材料を発見したことは特筆すべき点である。酸化物薄膜は通常のスパヅタリング法などの作製手法では透明な膜しか得られないが、本グループが独自に開発したレーザーアブレーション法で異種の酸化物薄膜を多層積層することにより、短波長に大きく感度がある光ディスク用記録膜の開発に成功した。最近では多層積層膜よりシンプルな構造の単層膜で短波長に対応する金属膜(高純度のFe)および高融点金属(W、Mo)の酸化物薄膜を用いた光ディスクの開発に成功している。これらの記録・再生・消去のメカニズムについて詳細にわたり物性測定を行い明らかにした。
代表青木孝憲あおきたかのり大阪産業大学 工学部電気電子工学科相変化型光ディスク材料および新規酸化物光ディスク材料の開発と記録メカニズムの解明現在、光ディスクは情報システムのストレージ部門においてHDD(ハードディスク)や半導体メモリー(フラッシュメモリー)同様に不可欠なメモリーとして存在するが、本グノレープは開発当初から相変化型光ディスクの開発に挑わってきた。研究初期の段階では、今日、主流の材料のGe-Sb-Te系およびAg-In・Sb-Te系については本グループでも深く係わり材料探索に傾注し、特に結晶化メカニズム(結晶化速度の詳細な測定)の追求は実用化へ大きく貢献した。又さらなる高密度化を達成するため半導体レーザーの短波長化に対応する材料の探索を行い。ブルーレイはもちろん紫外光にも感度がある酸化物材料を発見したことは特筆すべき点である。酸化物薄膜は通常のスパヅタリング法などの作製手法では透明な膜しか得られないが、本グループが独自に開発したレーザーアブレーション法で異種の酸化物薄膜を多層積層することにより、短波長に大きく感度がある光ディスク用記録膜の開発に成功した。最近では多層積層膜よりシンプルな構造の単層膜で短波長に対応する金属膜(高純度のFe)および高融点金属(W、Mo)の酸化物薄膜を用いた光ディスクの開発に成功している。これらの記録・再生・消去のメカニズムについて詳細にわたり物性測定を行い明らかにした。- 奥田 昌宏おくだまさのり奥田技術事務所
 大石進一おおいししんいち早稲田大学理工学部教授線形系の精度保証付き数値計算学の確立と実用化に関する貢献連立一次方程式や固有値問題などの線形代数方程式の数値解法は多様な問題の数値解析でしぱしぱ必要になり、その次元数も原間題の解精度を上げようとすれぱ数百万・数千万次元以上にもなる。したがって、これを高速かつ精度良く解くことが数値解析上極めて重要になりつつあり、この傾向は益々強まっている。大石教授は、連立一次方程式に対して、淳動小数点演算の丸めモードの制御方式を用いることによって、解析プログラムを多少変更するだけで既存の数値計算ライブラリの高遠性を保持したまま計算コストを殆ど増やすことなく精度保証ができることを明らかにし、精度保証は不可能か出来たとしても計算コストが増大しすぎて実用的ではないという常識を打ち破って一挙に実用化のレベル}こ到達させた。このことは数値計算における一種の革命であり、非常に広範囲な分野に多大な影響を与えることが期待できる。
大石進一おおいししんいち早稲田大学理工学部教授線形系の精度保証付き数値計算学の確立と実用化に関する貢献連立一次方程式や固有値問題などの線形代数方程式の数値解法は多様な問題の数値解析でしぱしぱ必要になり、その次元数も原間題の解精度を上げようとすれぱ数百万・数千万次元以上にもなる。したがって、これを高速かつ精度良く解くことが数値解析上極めて重要になりつつあり、この傾向は益々強まっている。大石教授は、連立一次方程式に対して、淳動小数点演算の丸めモードの制御方式を用いることによって、解析プログラムを多少変更するだけで既存の数値計算ライブラリの高遠性を保持したまま計算コストを殆ど増やすことなく精度保証ができることを明らかにし、精度保証は不可能か出来たとしても計算コストが増大しすぎて実用的ではないという常識を打ち破って一挙に実用化のレベル}こ到達させた。このことは数値計算における一種の革命であり、非常に広範囲な分野に多大な影響を与えることが期待できる。 川本広行かわもとひろゆき早稲田大学理工学術院機械工学科教授電磁界中における粒子のダイナミクスとその画像形成技術への応用に関する研究研究のキーワードは、「電磁力」「マイクロ」「画像」であり、対象は、「情報精密機器」である。情報精密機器は、マルチメディアの基盤となるハードウェアであり、なかでもカラープリンタなどの画像形成装置は、視覚を介して情報を記録・伝達するための重要な機器である。わが国が世界で突出して優位な分野でもある。この画像形成装置は、電磁気力や流体カを利用してトナーや液滴などの微粒子の運動や相変化を高速・高精度に制御する技術を基盤としている。このような観点から候補者は、電磁粒体カ学、換言すれば、「電磁気カや流体カによる粒体輸送の精密制御に関する研究」とでも称すべき学際的な研究と、実際の機器の高性能化に寄与する研究を行っている、また、これをセラミックスなどの材料科学、マイクロ加エ、マイクロマシン、生体科学などへ応用する研究も行っている。
川本広行かわもとひろゆき早稲田大学理工学術院機械工学科教授電磁界中における粒子のダイナミクスとその画像形成技術への応用に関する研究研究のキーワードは、「電磁力」「マイクロ」「画像」であり、対象は、「情報精密機器」である。情報精密機器は、マルチメディアの基盤となるハードウェアであり、なかでもカラープリンタなどの画像形成装置は、視覚を介して情報を記録・伝達するための重要な機器である。わが国が世界で突出して優位な分野でもある。この画像形成装置は、電磁気力や流体カを利用してトナーや液滴などの微粒子の運動や相変化を高速・高精度に制御する技術を基盤としている。このような観点から候補者は、電磁粒体カ学、換言すれば、「電磁気カや流体カによる粒体輸送の精密制御に関する研究」とでも称すべき学際的な研究と、実際の機器の高性能化に寄与する研究を行っている、また、これをセラミックスなどの材料科学、マイクロ加エ、マイクロマシン、生体科学などへ応用する研究も行っている。 前野隆司まえのたかし慶應義塾大学工学部機械工学科教授ヒトの触覚情報知覚機構解明とヒト規範型触覚センシングの研究本研究は、ヒトが触覚情報を知覚するメカニズムの解明と、メカトロニクス・ロボティクス機器への得られた知見の応用という二つのフェーズから成る。前野氏は、まず、物体に接触する際のヒト指腹部の変形と触覚情報知覚機構の関係を、有限要素解析および実験により明らかにしている。すなわち、指紋や真皮乳頭は触覚受容感度向上のために有効であること、4種類の触覚受容器はひずみが集中する箇所に配置されていることなどの新たな知見を得ている。
前野隆司まえのたかし慶應義塾大学工学部機械工学科教授ヒトの触覚情報知覚機構解明とヒト規範型触覚センシングの研究本研究は、ヒトが触覚情報を知覚するメカニズムの解明と、メカトロニクス・ロボティクス機器への得られた知見の応用という二つのフェーズから成る。前野氏は、まず、物体に接触する際のヒト指腹部の変形と触覚情報知覚機構の関係を、有限要素解析および実験により明らかにしている。すなわち、指紋や真皮乳頭は触覚受容感度向上のために有効であること、4種類の触覚受容器はひずみが集中する箇所に配置されていることなどの新たな知見を得ている。
次に、ヒト触覚機構に関する知見を応用して、センサが弾性体内に分散配置された分布触覚センサの情報処理機構を提案している。すなわち、重量や摩擦係数が未知の物体の把持力制御や対象物の質感検出のための分布型触覚センサとその制御アルゴリズムを開発し、ヒトの特徴に学ぶ人工物設計法の有効性を示している。
これらのユニークな結果は、学会で高い評価を得るのみならず、メカトロニクス・ロボティクス分野における触覚情報処理研究領域自体の発展に大きく貢献している。 松野文俊まつのふみとし電気通信大学電気通信学部知能機械工学科教授メカニカルシステムのダイナミクスベースト制御とレスキュー工学の構築従来の制御系設計はシステムに有限次元近似や線形近似を導入し、標準問題に帰着することで行なわれていた。
松野文俊まつのふみとし電気通信大学電気通信学部知能機械工学科教授メカニカルシステムのダイナミクスベースト制御とレスキュー工学の構築従来の制御系設計はシステムに有限次元近似や線形近似を導入し、標準問題に帰着することで行なわれていた。
この設計方法ではシステムが本来持つダイナミクスの特徴を失ってしまい、非常に複雑な制御系しか導出されない。
松野氏は近似を導入せず、システム固有の物理特徴を生かした制御系設計重要性を指摘している。その結果として物理法則に適ったシンプルかつロバストな制御器は設計できることを数学的および実験的に示し、その考えをダイナミクスベースト制御として提唱している。この設計法は高遠・軽量化を要求される情報機器や宇宙構造物の制御への適応が可能であり、メカニカルシステムの制御における貢献は非常に大きい。又松野氏は神戸大学在職中の1995年に阪神淡路大震災により教え子を失っている。その体験から工学研究者として災害時にどのように貢献できるかを考え、ITとRT(RobotTechnology)を融合したレスキュー工学を提唱し、11年に渡って新しい分野の開拓のために心血を注いできている。最近では文部科学省のレスキューロボットに関する大型プロジェクトを推進し、災害直後の迅速な情報収集を目的として、様々なレスキューシステムを開発している。また、顕著な業績をあげた若手のレスキュー工学研究者を奨励する賞を創設(競基弘賞:阪神淡路大震災で亡くなった学生の名前を冠にした賞)して、後進の育成にも多大な貢献をなしている。
第4回 2004年度
 松本眞まつもとまこと広島大学大学院理学研究科教授擬似乱数発生法の開発と評価法の研究及び普及活動松本眞氏は当時の指導学生西村氏とともに1998年Mersenne Twister (MT)という高性能擬似乱数発生法を提唱し、世界的に強い反響を受けた。この発生法は有限体や数の幾何などの現代数学理論を用い、現在の計算機アーキテクチャにおいて高速に計算可能な演算のみで擬似乱数を発生するもので、速度や周期などで従来の技術を圧倒するものであった。
松本眞まつもとまこと広島大学大学院理学研究科教授擬似乱数発生法の開発と評価法の研究及び普及活動松本眞氏は当時の指導学生西村氏とともに1998年Mersenne Twister (MT)という高性能擬似乱数発生法を提唱し、世界的に強い反響を受けた。この発生法は有限体や数の幾何などの現代数学理論を用い、現在の計算機アーキテクチャにおいて高速に計算可能な演算のみで擬似乱数を発生するもので、速度や周期などで従来の技術を圧倒するものであった。
現在世界的に普及しており、インターネット検索すると2万件以上ヒットする。同氏はインターネット上でMTのソースコードを配布しており、あらゆる言語での実装が同氏のホームページから入手できる。その後も、独立なMTを動的に生成する並列計算機用擬似乱数Dynamic Creatorの開発、符号理論を用いた擬似乱数の非統計的検定法の開発、MTの初期化法の改良といった研究を精力的に続けている。近年カナダのグループと共同でMTの後継機種を開発中である。 金谷健一かなたにけんいち岡山大学工学部情報工学科教授コンピュータビジョンの数理的方法の提唱コンピュータビジョンとはカメラから入力した画像を計算機で解析して、シーンの3次元状況(物体の識別、位置や3次元形状など)を知る研究であり、1960年代に米国で始まった。当初は人工知能の一部と位置づけられ、発見的知識とプログラミング(if-then-else構造)の組み合わせが中心であった。そして理想化された状況(「積み木世界」を呼ばれた)でのデモが注目を集め、研究が急速に拡大した。しかし、実シーンの解析は困難を極めた。
金谷健一かなたにけんいち岡山大学工学部情報工学科教授コンピュータビジョンの数理的方法の提唱コンピュータビジョンとはカメラから入力した画像を計算機で解析して、シーンの3次元状況(物体の識別、位置や3次元形状など)を知る研究であり、1960年代に米国で始まった。当初は人工知能の一部と位置づけられ、発見的知識とプログラミング(if-then-else構造)の組み合わせが中心であった。そして理想化された状況(「積み木世界」を呼ばれた)でのデモが注目を集め、研究が急速に拡大した。しかし、実シーンの解析は困難を極めた。
それに対して金谷教授は、米国Maryland大学在住中にカメラの撮像の幾何学、不変量や群表現論に基づく物体の幾何学的構造解析、誤差の統計解析を組み合わせた数理的方法をほぼ単独で提唱した。これは当初は反発を受けながら、英国Oxford大学に飛び火して、そこから急速に世界中に拡散し、約10年間の間に世界の研究を一変させるほど影響を与えた。この事実は国内では意外と認知されていないが、海外では周知の事実である。 徳山豪とくやまたけし東北大学大学院情報科学研究科教授計算幾何学の理論研究と、データマイニングにおける先駆的研究への応用徳山氏は計算幾何学(幾何学データ処理理論)を中心とした計算理論と、その応用において高い成果を挙げている。日本の計算理論を代表する存在として、計算理論のフラグシップ国際会議で質の高い論文発表を続け、数学的に洗練された独創的な新技法を数多く提案しており、理論のみの業績でも学術振興への貢献は非常に大きい。
徳山豪とくやまたけし東北大学大学院情報科学研究科教授計算幾何学の理論研究と、データマイニングにおける先駆的研究への応用徳山氏は計算幾何学(幾何学データ処理理論)を中心とした計算理論と、その応用において高い成果を挙げている。日本の計算理論を代表する存在として、計算理論のフラグシップ国際会議で質の高い論文発表を続け、数学的に洗練された独創的な新技法を数多く提案しており、理論のみの業績でも学術振興への貢献は非常に大きい。
しかしながら、徳山氏の最大の特徴は、企業に在籍していた経験から生まれた、現実問題に根付いた理論研究スタイルであり、計算幾何学を中心とした計算理論の技法の多くの適用分野の開拓が最大の貢献である。
特に、近年の情報処理において重要分野となっているデータマイニングにおいては、世界に先駆けて計算幾何学を応用した技法の導入を行なった。1996年のACM-SIGMOD国際会議での成果は「データマイニング分野で初めての理論計算幾何学の本格利用」として注目され、現在世界で活発に行なわれているアルゴリズム理論の研究者によるデータマイニングへの取り組みの国際的な先駆けとなった。この研究では、徳山氏が導入した独自のパラメトリックな計算幾何学の新しい枠組みで開発された手法がベースになっており、アルゴリズムの先端理論での独創性が実用分野でのブレークスルーに結びつくことを示す事により、日本の理論計算機科学分野全体の活性化に繋がった。 寅市和男とらいちかずお筑波大学先端学際領域研究センター教授フルーエンシ情報理論とそのマルチメディアへの応用に関する研究1980年までに寅市教授によって体系付けられたフルーエンシ情報理論は、シャノンのサンプリング定理、ウェーブレット変換を包含する独自の理論であり、ディジタル信号を適応的且つ柔軟にアナログ信号に対応付けて変換する技術に結びついている。この成果は現代システム制御理論で著名なR.E.Kalman教授により最初に高く評価され、以降、当該理論はフルーエンシ理論と名付けられ、それらを搭載した装置はフルーエンシマルチメディアシステムと呼ばれている。それがマルチメディアにおける信号変換の統一的符号化、復号化技術として確立され、各種マルチメディアシステムへ応用されている。
寅市和男とらいちかずお筑波大学先端学際領域研究センター教授フルーエンシ情報理論とそのマルチメディアへの応用に関する研究1980年までに寅市教授によって体系付けられたフルーエンシ情報理論は、シャノンのサンプリング定理、ウェーブレット変換を包含する独自の理論であり、ディジタル信号を適応的且つ柔軟にアナログ信号に対応付けて変換する技術に結びついている。この成果は現代システム制御理論で著名なR.E.Kalman教授により最初に高く評価され、以降、当該理論はフルーエンシ理論と名付けられ、それらを搭載した装置はフルーエンシマルチメディアシステムと呼ばれている。それがマルチメディアにおける信号変換の統一的符号化、復号化技術として確立され、各種マルチメディアシステムへ応用されている。
特に、半導体メーカーと共同で開発したオーディオ装置に応用されているDACのLSIは、国内外のオーディオメーカで採用され、Golden Sound Award他世界に於ける35の賞に輝いており、それはFluencyオーディオと呼ばれるに至っている。
印刷物への応用に関しては画像の関数近似により、高精細、スケーラブルに拡大、縮小が行え、印刷革命が可能な技術として、日本印刷学会論文賞、印刷朝陽会賞を受賞している。また、TV分野においても通常のNTSC信号をハイビジョン並みの高画質な映像に変換することが可能で、信号処理装置は実用段階にある。 代表西尾章治郎にしおしょうじろう大阪大学大学院 情報科学研究科先進ネットワーク環境におけるデータベースの新技術開拓に関する研究グループ代表者らは、データベース分野において、長期に亘り常に先駆的な研究開発を展開している。特に、広帯域ネットワークやモバイルネットワーク、放送通信など、急速に発展するネットワーク技術にいち早く注目し、これらの特性を考慮した分散データベース技術について新たなパラダイムを展開する研究を行なっている。
代表西尾章治郎にしおしょうじろう大阪大学大学院 情報科学研究科先進ネットワーク環境におけるデータベースの新技術開拓に関する研究グループ代表者らは、データベース分野において、長期に亘り常に先駆的な研究開発を展開している。特に、広帯域ネットワークやモバイルネットワーク、放送通信など、急速に発展するネットワーク技術にいち早く注目し、これらの特性を考慮した分散データベース技術について新たなパラダイムを展開する研究を行なっている。
具体的には、近年のネットワークの広帯域化に着目し、データベースをネットワーク上で移動させるという斬新な概念「データベース移動」を提唱し、データベース移動に基づく分散データベースシステムを構築している。さらに、モバイルネットワークやその進化形であるアドホックネットワークやウェアラブルコンピューティング環境において、非常に独創的なデータ共有基盤を確立している。また、放送通信を用いる高度分散データベース環境において、情報フィルタリングや放送スケジューリング・キャッシングなどに関する基盤技術を考案している。
これらの研究成果は国内だけではなく、国際的にも高く評価され、新たな研究分野を開拓した先駆的研究として認識されている。- 塚本 昌彦さかもと まさひこ神戸大学 工学部
- 原 隆浩はらたかひろ大阪大学大学院 情報科学研究科
 山浦弘やまうらひろし東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻教授情報機器の高性能化に関する研究(1)位置決め機構の制振アクセス制御に関する研究
山浦弘やまうらひろし東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻教授情報機器の高性能化に関する研究(1)位置決め機構の制振アクセス制御に関する研究
磁気ディスク装置のヘッド位置決め機構のアクセス制御の高速化・高精度化に必要な、残留振動を生じない制振アクセス制御の原理を明らかにするとともに、最適な入力・軌道の導出法を示している。また、しばしば実機で問題となる固有振動数変動や高次振動モードに対する対策も提案している。
(2)磁気ヘッド位置決め機構のサーボ帯域の向上に関する研究
広サーボ帯域を実現できる磁気ヘッド位置決め機構、センサを使わない振動モードの安定化手法および広サーボ帯域を実現できる制御系設計法を提案している。
(3)紙搬送機構における紙搬送特性の高精度予測
ゴムローラと鋼ローラを用いた紙搬送機構に対して、比較的短い計算時間により高精度に紙搬送特性を予測できる手法を開発している。
また、共同研究者として磁気ディスク装置のヘッドスライダ機構、流体軸受スピンドルの研究なども行なっている。何れの業績も実際の情報機器の設計、制御に既に適用されているか、今後の適用が期待されているものであり、情報機器の高性能化に重要な役割を果たしつつある。
第3回 2003年度
 代表井上光輝いのうえみつてる豊橋技術科学大学電気・電子工学系教授光体積記録のための超高速固体空間光変調デバイスの開発ホログラム光体積情報記録は、1000bits/μ㎡以上の超高密度情報記録が可能であることから、次世代超高密度光ディスク記録を実現するキーテクノロジーとして期待されている。しかし、信号光をページデータで変調する空間光変調器(SLM)の動作速度が遅く、かつ固体形状で高速動作するものが無いために、我国が得意とする光ヘッド技術と融合させた新しい超高密度高速光ディスク装置への展開が困難であった。 本研究は、磁性体中のスピン・スイッチング速度が数ナノ秒と速いことに着目し、スピン方位により偏光面回転符号が反転する磁気光学効果を利用した高速動作可能な固体SLM(Magneto-optic SLM:MOSLM)を開発したものである。既に10mA程度の小さな駆動電流で70ns/ピクセルに達する世界最高速で動作するSLMの開発に成功し、民間企業への技術移転を通じて、市場投入素子の開発が開始されている。更に、これらの成果を踏まえ、小さな光ピックアップに組み込み可能なように、電圧でスピン方位を制御する次世代MOSLMの原理試作にも成功している。これらの研究成果は、世界的に見ても類のない独創性・新規性の高いものであると同時に、我国主導による新しい超高密度光体積記録装置の実現に強いインパクトを与えるものといえる。
代表井上光輝いのうえみつてる豊橋技術科学大学電気・電子工学系教授光体積記録のための超高速固体空間光変調デバイスの開発ホログラム光体積情報記録は、1000bits/μ㎡以上の超高密度情報記録が可能であることから、次世代超高密度光ディスク記録を実現するキーテクノロジーとして期待されている。しかし、信号光をページデータで変調する空間光変調器(SLM)の動作速度が遅く、かつ固体形状で高速動作するものが無いために、我国が得意とする光ヘッド技術と融合させた新しい超高密度高速光ディスク装置への展開が困難であった。 本研究は、磁性体中のスピン・スイッチング速度が数ナノ秒と速いことに着目し、スピン方位により偏光面回転符号が反転する磁気光学効果を利用した高速動作可能な固体SLM(Magneto-optic SLM:MOSLM)を開発したものである。既に10mA程度の小さな駆動電流で70ns/ピクセルに達する世界最高速で動作するSLMの開発に成功し、民間企業への技術移転を通じて、市場投入素子の開発が開始されている。更に、これらの成果を踏まえ、小さな光ピックアップに組み込み可能なように、電圧でスピン方位を制御する次世代MOSLMの原理試作にも成功している。これらの研究成果は、世界的に見ても類のない独創性・新規性の高いものであると同時に、我国主導による新しい超高密度光体積記録装置の実現に強いインパクトを与えるものといえる。- 内田 裕久うちだ ひろなが豊橋技術科学大学電気・電子工学系助教授
- 西村 一寛にしむら かずひろ豊橋技術科学大学電気・電子工学系助手
- 朴 載赫ぱく じぇひひょく豊橋技術科学大学電気・電子工学系博士研究員
 入江満いりえみつる大阪産業大学工学部電気電子工学科助教授光ディスク(DVD)における高密度記録方式の標準化とその環境信頼性に関する研究今日、高密度光ディスク”DVD(Digetal Versatile Disc)”は、デジタルマルチメディア時代の大容量ストレージメディアとして確固たる国際的地位を確立した。この背景には、DVDがデファクト規格として幅広く公開され、光ディスク仕様の互換性を確保するという標準化が行なわれたことがある。候補者はDVDの誕生(1996年)よりデファクト規格策定、特に記録型DVDの主流である追記型DVD(DVD-R)、書換え型DVD(DVD-RW)の物理規格策定に携わり、1999年にはDVD-RW、2000年にはDVD-Rを業界標準規格として制定に貢献した。 さらに、DVD規格の国際標準化活動を行い、DVD-R規格をISO規格として制定すると共に、DVD規格の認証のためのDVD規格管理会社の設立・運営にも参画してきた。その後、DVDの光学素子の研究に従事しながら、DVD-ROMのJIS規格改定(2003年)を行なう一方、ユーザの立場からの光ディスクの環境信頼特性評価の研究にも着手している。2003年には、DVD規格全般にわたる成書も出版するなど、候補者の規格策定者の見識とユーザの視点に立った幅広い光ディスクの研究活動は高く評価されている。
入江満いりえみつる大阪産業大学工学部電気電子工学科助教授光ディスク(DVD)における高密度記録方式の標準化とその環境信頼性に関する研究今日、高密度光ディスク”DVD(Digetal Versatile Disc)”は、デジタルマルチメディア時代の大容量ストレージメディアとして確固たる国際的地位を確立した。この背景には、DVDがデファクト規格として幅広く公開され、光ディスク仕様の互換性を確保するという標準化が行なわれたことがある。候補者はDVDの誕生(1996年)よりデファクト規格策定、特に記録型DVDの主流である追記型DVD(DVD-R)、書換え型DVD(DVD-RW)の物理規格策定に携わり、1999年にはDVD-RW、2000年にはDVD-Rを業界標準規格として制定に貢献した。 さらに、DVD規格の国際標準化活動を行い、DVD-R規格をISO規格として制定すると共に、DVD規格の認証のためのDVD規格管理会社の設立・運営にも参画してきた。その後、DVDの光学素子の研究に従事しながら、DVD-ROMのJIS規格改定(2003年)を行なう一方、ユーザの立場からの光ディスクの環境信頼特性評価の研究にも着手している。2003年には、DVD規格全般にわたる成書も出版するなど、候補者の規格策定者の見識とユーザの視点に立った幅広い光ディスクの研究活動は高く評価されている。 木村浩きむらひろし電気通信大学情報システム学研究科助教授自律不整地適応可能な四脚ロボットの開発ホンダの二足ロボットが注目を集めるなど、歩行ロボットの実用化が近いと一般には思われているが、路面のちょっとした凹凸に適応できないなど、自律的な歩行生成と制御は依然として歩行ロボット実用化への大きな壁となっている。これは、ロボットと環境の厳密なモデルに基づき運動の計画と制御を別々に行なう従来の手法では、多様な外部環境への自律適応を実現することが非常に困難であるためである これに対して、本研究では、神経‐筋骨格系と環境との相互作用により力学系の創発として運動の生成・適応が発生するという考えに基づき、生物学などで提唱されたパターン発生器(CPG:Central Pattern Generator)と反射からなる簡単でかつ自律的な適応能力を持つ歩行生成・制御系を新たに提案した。さらに、このような生物規範型の手法が有効に働く四脚ロボットの機構を開発し、従来概念的であった手法がロボットにおいて実現可能であることを世界で始めて示すことができた。現在、独自に開発したバッテリを搭載した自立型の四脚ロボットにより屋内で1m/s(3.6km/h)での自律走行や屋外(大学キャンパス内)で0.5m/s(1.8km/h)での自律不整地動歩行が実現されている。
木村浩きむらひろし電気通信大学情報システム学研究科助教授自律不整地適応可能な四脚ロボットの開発ホンダの二足ロボットが注目を集めるなど、歩行ロボットの実用化が近いと一般には思われているが、路面のちょっとした凹凸に適応できないなど、自律的な歩行生成と制御は依然として歩行ロボット実用化への大きな壁となっている。これは、ロボットと環境の厳密なモデルに基づき運動の計画と制御を別々に行なう従来の手法では、多様な外部環境への自律適応を実現することが非常に困難であるためである これに対して、本研究では、神経‐筋骨格系と環境との相互作用により力学系の創発として運動の生成・適応が発生するという考えに基づき、生物学などで提唱されたパターン発生器(CPG:Central Pattern Generator)と反射からなる簡単でかつ自律的な適応能力を持つ歩行生成・制御系を新たに提案した。さらに、このような生物規範型の手法が有効に働く四脚ロボットの機構を開発し、従来概念的であった手法がロボットにおいて実現可能であることを世界で始めて示すことができた。現在、独自に開発したバッテリを搭載した自立型の四脚ロボットにより屋内で1m/s(3.6km/h)での自律走行や屋外(大学キャンパス内)で0.5m/s(1.8km/h)での自律不整地動歩行が実現されている。 田村秀行たむらひでよし立命館大学理工学部情報学科教授複合現実感の研究基盤構築と技術普及推進候補者の業績は、世界に先駆けて現実世界と仮想世界と融合する「複合現実感」(Mixed Reality; MR)の研究基盤や技術体系の枠組みを構築し、当該分野の学術振興や技術普及推進にも大きな貢献を果たしたことにある。「複合現実感」の命名者であるとともに、旧通商産業省傘下の「MR研究プロジェクト」(1997-2001年)のリーダーとして、中核となる空間位置合わせ技術や独自のビデオシースルー型表示装置等を開発した。この結果、従来構想レベルや簡単な実験段階に留まっていた技術を、安定して実用化可能な技術水準にまで引き上げ、多くの研究者が参入できる技術領域に育て上げた。 学会活動としては、当該分野の研究委員会を組織して6年間委員長を務め、欧米の学会組織と合併して、わが国が世界を先導し大きな発言力を有する研究交流組織を作り上げた。実用化に関しては、多数の体験可能なデモ・システムの展示や研究成果のリリースを通して、教育・展示・娯楽関連業界の新規事業や、製造業の設計・製造の革新に繋がる道筋を具体的に示した。
田村秀行たむらひでよし立命館大学理工学部情報学科教授複合現実感の研究基盤構築と技術普及推進候補者の業績は、世界に先駆けて現実世界と仮想世界と融合する「複合現実感」(Mixed Reality; MR)の研究基盤や技術体系の枠組みを構築し、当該分野の学術振興や技術普及推進にも大きな貢献を果たしたことにある。「複合現実感」の命名者であるとともに、旧通商産業省傘下の「MR研究プロジェクト」(1997-2001年)のリーダーとして、中核となる空間位置合わせ技術や独自のビデオシースルー型表示装置等を開発した。この結果、従来構想レベルや簡単な実験段階に留まっていた技術を、安定して実用化可能な技術水準にまで引き上げ、多くの研究者が参入できる技術領域に育て上げた。 学会活動としては、当該分野の研究委員会を組織して6年間委員長を務め、欧米の学会組織と合併して、わが国が世界を先導し大きな発言力を有する研究交流組織を作り上げた。実用化に関しては、多数の体験可能なデモ・システムの展示や研究成果のリリースを通して、教育・展示・娯楽関連業界の新規事業や、製造業の設計・製造の革新に繋がる道筋を具体的に示した。 代表山村清隆やまむらきよたけ中央大学理工学部電気電子情報通信工学科教授大規模集積回路の大域的求解法の開発とその実用化に関する研究LSI設計における大きなボトルネックとして世界中の設計者を悩ませていた「非収束問題」を理論面・実用面の両方から解決するアルゴリズムを開発し、アナログ回路としては最大級である一万素子クラスのアナログLSIを世界で初めて収束の保証付きで解くことに成功した。また、業界に先駆けてこのクラスのLSIの製品化にも成功した。それにより、国内ではLSI設計期間の短縮や民生機器の高度化・低価格化、さらにはそれに伴う情報産業の発展に貢献し、また国外でも、欧米で使われている回路シミュレータのプログラムに簡単な修正を施すことにより大域的収束性が保証されることを証明した論文を発表し、国際的な評価を受けた。 本技術を適用して設計・開発・製造した三洋電機のバイポーラアナログLSIの実績は次の通りである。【生産金額】年間約800億円、【生産数量】年間10~12億個、【輸出額】年間約400億円、【開発期間】従来の2年から1年に短縮、【開発技術】世界市場占有率50%以上の各種高性能・高機能1チップLSIの開発に成功。 又上記論文のアルゴリズムはその後IEEE(米国電気電子学会)のNG-SPICEプロジェクトで採用され、全世界に公開されている。それにより世界中の設計者が収束率100%の回路シミュレータを利用できるようになり、長い間多くの設計者を悩ませた「非収束問題」は国内外で完全に解決されることになった。
代表山村清隆やまむらきよたけ中央大学理工学部電気電子情報通信工学科教授大規模集積回路の大域的求解法の開発とその実用化に関する研究LSI設計における大きなボトルネックとして世界中の設計者を悩ませていた「非収束問題」を理論面・実用面の両方から解決するアルゴリズムを開発し、アナログ回路としては最大級である一万素子クラスのアナログLSIを世界で初めて収束の保証付きで解くことに成功した。また、業界に先駆けてこのクラスのLSIの製品化にも成功した。それにより、国内ではLSI設計期間の短縮や民生機器の高度化・低価格化、さらにはそれに伴う情報産業の発展に貢献し、また国外でも、欧米で使われている回路シミュレータのプログラムに簡単な修正を施すことにより大域的収束性が保証されることを証明した論文を発表し、国際的な評価を受けた。 本技術を適用して設計・開発・製造した三洋電機のバイポーラアナログLSIの実績は次の通りである。【生産金額】年間約800億円、【生産数量】年間10~12億個、【輸出額】年間約400億円、【開発期間】従来の2年から1年に短縮、【開発技術】世界市場占有率50%以上の各種高性能・高機能1チップLSIの開発に成功。 又上記論文のアルゴリズムはその後IEEE(米国電気電子学会)のNG-SPICEプロジェクトで採用され、全世界に公開されている。それにより世界中の設計者が収束率100%の回路シミュレータを利用できるようになり、長い間多くの設計者を悩ませた「非収束問題」は国内外で完全に解決されることになった。- 井上 靖秋いのうえ やすあき早稲田大学大学院情報生産システム研究科教授
 山本透やまもととおる広島大学大学院教育学研究科技術・情報教育学講座助教授PID制御系設計の高度化と知能化に関する研究適応制御やロバスト制御などのアドバンスト制御やソフトコンピューティング手法を用いたインテリジェント制御に関する研究が進められる中で、プロセス制御やメカニカルシステムなどの実システムにおいては、制御器の構造が単純であり、制御器に含まれるパラメータの持つ物理的な意味が明確であるなどの理由により、今なおPID制御法が広く用いられている。このような現状に着目し、アドバンスト制御法やインテリジェント制御法を、PID制御器をベースとした形で実現することは、企業等の産業社会に対し有用であると確信し、PID制御系設計の高度化と知能化に関する研究を進めてきた。 制御対象の特性が前もって正確に把握することが困難なものや、特性が時々刻々と変動するもの、あるいは非線形であるものなど、制御対象には常に不確かさが存在している。このような不確かさに十分対処することのできるPID制御手法が産業社会で必要とされており、不確かさに応じてPID制御器を自己調整する方法(ロバストPID制御法)、非線形系に対してニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム、小脳演算モデル(CMAC)などを用いたインテリジェントPID制御法など多くの手法を開発し、実システムにおいてその有用性が高く評価されている。
山本透やまもととおる広島大学大学院教育学研究科技術・情報教育学講座助教授PID制御系設計の高度化と知能化に関する研究適応制御やロバスト制御などのアドバンスト制御やソフトコンピューティング手法を用いたインテリジェント制御に関する研究が進められる中で、プロセス制御やメカニカルシステムなどの実システムにおいては、制御器の構造が単純であり、制御器に含まれるパラメータの持つ物理的な意味が明確であるなどの理由により、今なおPID制御法が広く用いられている。このような現状に着目し、アドバンスト制御法やインテリジェント制御法を、PID制御器をベースとした形で実現することは、企業等の産業社会に対し有用であると確信し、PID制御系設計の高度化と知能化に関する研究を進めてきた。 制御対象の特性が前もって正確に把握することが困難なものや、特性が時々刻々と変動するもの、あるいは非線形であるものなど、制御対象には常に不確かさが存在している。このような不確かさに十分対処することのできるPID制御手法が産業社会で必要とされており、不確かさに応じてPID制御器を自己調整する方法(ロバストPID制御法)、非線形系に対してニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズム、小脳演算モデル(CMAC)などを用いたインテリジェントPID制御法など多くの手法を開発し、実システムにおいてその有用性が高く評価されている。
第2回 2002年度
 安達千波矢あだちちはや千歳科学技術大学光科学部・物質光科学科助教授高効率有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)素子の研究開発研究当初は発光効率が0.0001%と極めて低い値であったが、材料・デバイス構造の最適化により、現在では内部量子効率が100%に達するデバイスを実現した。 有機ELの黎明期である九州大学大学院時代(1987-1990)では、従来にない新しい有機ELデバイス構造の提案を行った。これにより有機EL素子の基本デバイス構造をすべて分類することができた。現在でも安達らが確立したデバイス構造のカテゴリーに基づき素子設計が行われている。また、デバイス構造の設計と共に、新規電子輸送層材料の提案を行った。これは有機半導体材料における電子輸送材料という新しいカテゴリーを創製した。その後、民間企業の研究所及び信州大学(1991-1997)にて材料研究に特化し、高耐久性材料の合成と分子設計指針の確立、また、高分子材料を用いた厚膜有機EL素子等のデバイス実証などの実用化を念頭においた先駆的な研究を行った。また、最近では、米国プリンストン大学(1998-2001)にて超高効率有機EL素子の実現を果たした。ここでは、リン光性有機金属化合物を発光中心に用いたデバイスにより、内部量子効率が100%に達する究極の有機EL素子を実現し、次世代ディスプレーとしての有機ELの確個たる地位を築いた。これらの研究成果は、有機エレクトロニクスの発展に大きく寄与することができたと考える。
安達千波矢あだちちはや千歳科学技術大学光科学部・物質光科学科助教授高効率有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)素子の研究開発研究当初は発光効率が0.0001%と極めて低い値であったが、材料・デバイス構造の最適化により、現在では内部量子効率が100%に達するデバイスを実現した。 有機ELの黎明期である九州大学大学院時代(1987-1990)では、従来にない新しい有機ELデバイス構造の提案を行った。これにより有機EL素子の基本デバイス構造をすべて分類することができた。現在でも安達らが確立したデバイス構造のカテゴリーに基づき素子設計が行われている。また、デバイス構造の設計と共に、新規電子輸送層材料の提案を行った。これは有機半導体材料における電子輸送材料という新しいカテゴリーを創製した。その後、民間企業の研究所及び信州大学(1991-1997)にて材料研究に特化し、高耐久性材料の合成と分子設計指針の確立、また、高分子材料を用いた厚膜有機EL素子等のデバイス実証などの実用化を念頭においた先駆的な研究を行った。また、最近では、米国プリンストン大学(1998-2001)にて超高効率有機EL素子の実現を果たした。ここでは、リン光性有機金属化合物を発光中心に用いたデバイスにより、内部量子効率が100%に達する究極の有機EL素子を実現し、次世代ディスプレーとしての有機ELの確個たる地位を築いた。これらの研究成果は、有機エレクトロニクスの発展に大きく寄与することができたと考える。 代表奥乃博おくのひろし京都大学大学院情報学研究科教授音環境理解研究の提案、および、ロボットを対象とした視聴覚統合による実環境・実時間の 音源定位・分離・認識とそのヒューマンロボットインタフェースへの応用音声認識はPCの標準装備となりつつあるが、入力として音声からなる単一音源を想定しており、聖徳太子のように10人とまではいわれないまでも複数の同時発話を認識することはできない。奥乃らは混合音の認識のために「音環境理解」( Computational Auditory Scene Analysis )研究を提唱し、調波構造と音源方向の抽出による混合音分離の研究を進めてきた。音環境理解の具体的な応用として、ヒューマノイドのための聴覚システムを取り上げ、自分自身が出すモータノイズのキャンセル法、視聴覚情報統合による聴覚処理や画像処理での曖昧性解消法、聴覚と動作を統合し、知覚能力を向上させるアクティブオーディションなどを考案し、4自由度の上半身ヒューマノイドに実装をし、5台にPCによる実時間処理を達成した。この結果、反響のある部屋で、移動する複数音源の定位・追跡、視聴覚情報統合による複数人物の実時間追跡、3話者同時発話の分離認識を達成するとともに、音を使用した自然なヒューマン・ロボットインターラクションを実現した。
代表奥乃博おくのひろし京都大学大学院情報学研究科教授音環境理解研究の提案、および、ロボットを対象とした視聴覚統合による実環境・実時間の 音源定位・分離・認識とそのヒューマンロボットインタフェースへの応用音声認識はPCの標準装備となりつつあるが、入力として音声からなる単一音源を想定しており、聖徳太子のように10人とまではいわれないまでも複数の同時発話を認識することはできない。奥乃らは混合音の認識のために「音環境理解」( Computational Auditory Scene Analysis )研究を提唱し、調波構造と音源方向の抽出による混合音分離の研究を進めてきた。音環境理解の具体的な応用として、ヒューマノイドのための聴覚システムを取り上げ、自分自身が出すモータノイズのキャンセル法、視聴覚情報統合による聴覚処理や画像処理での曖昧性解消法、聴覚と動作を統合し、知覚能力を向上させるアクティブオーディションなどを考案し、4自由度の上半身ヒューマノイドに実装をし、5台にPCによる実時間処理を達成した。この結果、反響のある部屋で、移動する複数音源の定位・追跡、視聴覚情報統合による複数人物の実時間追跡、3話者同時発話の分離認識を達成するとともに、音を使用した自然なヒューマン・ロボットインターラクションを実現した。- 奥乃博Hiroshi Okuno京都大学大学院情報学研究科教授
- 中臺一博Kazuhiro Nakadai科学技術振興事業団 ERATO 北野共生システムプロジェクト研究員
 代表小島政和こじままさかず東京工業大学大学院情報理工学研究科教授数理計画(最適化)問題に対する主双対内点法代表者小島のScience Citation Indexでの論文被引用合計数は1,400に、また、大学院学生を除く7人の平均の論文被引用合計数は400に達し、本グループの業績はComputer Scienceとしても重要な貢献として認識されている。特に、Karmarkar法に双対理論を導入した主双対内点法を初めて提案し、その基礎を築いた業績は国際的に非常に高い評価を受けている。主要な最適化ソフトウェアパッケージには主双対内点法が実装され、大規模な線形計画問題を解くことが可能になっている。この業績により米国INFORMSより受賞している。さらに、主双対内点法をより高度な最適化問題へと拡張し、それに基づいてソフトウェアSDPAを開発、公開、改良・高速化、並列化している。 SDPA は米国 Argone 国立研究所 NEOS System にも登録され、世界中で広く使われている。 また、SDPA Sparse Formatは世界標準にもなっている。
代表小島政和こじままさかず東京工業大学大学院情報理工学研究科教授数理計画(最適化)問題に対する主双対内点法代表者小島のScience Citation Indexでの論文被引用合計数は1,400に、また、大学院学生を除く7人の平均の論文被引用合計数は400に達し、本グループの業績はComputer Scienceとしても重要な貢献として認識されている。特に、Karmarkar法に双対理論を導入した主双対内点法を初めて提案し、その基礎を築いた業績は国際的に非常に高い評価を受けている。主要な最適化ソフトウェアパッケージには主双対内点法が実装され、大規模な線形計画問題を解くことが可能になっている。この業績により米国INFORMSより受賞している。さらに、主双対内点法をより高度な最適化問題へと拡張し、それに基づいてソフトウェアSDPAを開発、公開、改良・高速化、並列化している。 SDPA は米国 Argone 国立研究所 NEOS System にも登録され、世界中で広く使われている。 また、SDPA Sparse Formatは世界標準にもなっている。- 小島政和Masakazu Kojima東京工業大学大学院情報理工学研究科教授
- 進藤晋Susumu Shindo神奈川大学工学部経営工学科教授
- 中田和秀Kazuhide Nakata東京工業大学大学院社会理工学研究科助手
- 原辰次Shinji Hara東京大学大学院情報理工学系研究科教授
- 藤澤克樹Katsuki Fujisawa東京電機大学理工学部数理科学科助教授
- 水野真治Shinji Mizuno東京工業大学大学院社会理工学研究科教授
- 山下真Makoto Yamashita東京工業大学大学院情報理工学研究科
- 吉瀬章子Akiko Yoshise筑波大学社会工学系助教授
 高木友博たかぎともひろ明治大学理工学部情報科学科教授TS Model (Takagi-Sugeno Model)1983年TS Model(Takagi-Sugeno Model)を提唱。現在ファジィ制御の研究は約90%がこの推論法を用いており、提唱論文の引用件数はジャーナルを中心として700件以上。1995年Conceptual Fuzzy Sets を提唱。 ソフトコンピューティングにおける次世代の知識処理パラダイムとして期待されており、これまでにWebインテリジェンス応用やマルチメディアデータの解釈への応用が研究され、その潜在的可能性は極めて大きい。また、知識情報ファジィ学会を中心に新しいリーダーとして潮流を起こしつつあり、今後の学会の方向を明示的に示し引っ張っている世界で数人の一人である。
高木友博たかぎともひろ明治大学理工学部情報科学科教授TS Model (Takagi-Sugeno Model)1983年TS Model(Takagi-Sugeno Model)を提唱。現在ファジィ制御の研究は約90%がこの推論法を用いており、提唱論文の引用件数はジャーナルを中心として700件以上。1995年Conceptual Fuzzy Sets を提唱。 ソフトコンピューティングにおける次世代の知識処理パラダイムとして期待されており、これまでにWebインテリジェンス応用やマルチメディアデータの解釈への応用が研究され、その潜在的可能性は極めて大きい。また、知識情報ファジィ学会を中心に新しいリーダーとして潮流を起こしつつあり、今後の学会の方向を明示的に示し引っ張っている世界で数人の一人である。 代表富田悦次とみたえつじ電気通信大学電気通信学部情報通信工学科教授先進的アルゴリズムと新情報処理パラダイムの開発と応用・評価に関する研究産業界などの実社会で実際に解く必要がある重要な問題には、NP困難問題と呼ばれる、現状では計算量爆発が避けられない非常に難しい問題とが多い、本研究では、そのような問題に対し、コンピュータサイエンスにおける基本アルゴリズムの先進的方式を確立し、それを具体的な問題に応用して解決を得た成果である。 まず、学習理論の基礎になる形式言語・オートマトン等の等価性判定問題について、先駆的なアルゴリズムを確立し、RNAの2次元構造予測などへの応用にも成功している。また、最大クリーク抽出問題を始めとする組合せ最適化問題に対して先進的アルゴリズムを確立することにより、バイオインフォマティクスの主要問題解決などの成果を得ている。一方、様々な新情報処理パラダイムに関して、数理的基礎を与え、革新的な性能解析手法を開発している。特に、NMR量子計算パラダイムの数理的基礎を提示することによってこの領域における理論研究の扉を開け、DNA計算パラダイムにおけるDNA配列の新たな設計手法を開発することによってこの領域の研究を飛躍的に発展させた。またさらに、独創的な性能解析手法を開発することによって、種々の先進的アルゴリズムや新情報処理パラダイムの理論とその応用に関して、従来の予想を覆す革新的成果を確立している。
代表富田悦次とみたえつじ電気通信大学電気通信学部情報通信工学科教授先進的アルゴリズムと新情報処理パラダイムの開発と応用・評価に関する研究産業界などの実社会で実際に解く必要がある重要な問題には、NP困難問題と呼ばれる、現状では計算量爆発が避けられない非常に難しい問題とが多い、本研究では、そのような問題に対し、コンピュータサイエンスにおける基本アルゴリズムの先進的方式を確立し、それを具体的な問題に応用して解決を得た成果である。 まず、学習理論の基礎になる形式言語・オートマトン等の等価性判定問題について、先駆的なアルゴリズムを確立し、RNAの2次元構造予測などへの応用にも成功している。また、最大クリーク抽出問題を始めとする組合せ最適化問題に対して先進的アルゴリズムを確立することにより、バイオインフォマティクスの主要問題解決などの成果を得ている。一方、様々な新情報処理パラダイムに関して、数理的基礎を与え、革新的な性能解析手法を開発している。特に、NMR量子計算パラダイムの数理的基礎を提示することによってこの領域における理論研究の扉を開け、DNA計算パラダイムにおけるDNA配列の新たな設計手法を開発することによってこの領域の研究を飛躍的に発展させた。またさらに、独創的な性能解析手法を開発することによって、種々の先進的アルゴリズムや新情報処理パラダイムの理論とその応用に関して、従来の予想を覆す革新的成果を確立している。- 富田悦次Etsuji Tomita電気通信大学電気通信学部情報通信工学科教授
- 西野哲朗Tetsuro Nishino電気通信大学電気通信学部情報通信工学科助教授
- 小林聡Satoshi Kobayashi電気通信大学電気通信学部情報通信工学科助教授
- 戸田誠之助Seinosuke Toda日本大学文理学部情報システム解析学科教授
 西関隆夫にいそかたかお東北大学大学院情報科学研究科教授離散アルゴリズムと秘密共有法に関する先駆的研究インターネット、交通網、VLSI配線などに関する多くの問題は、点およびそれらを結ぶ辺からなる”グラフ”上の組み合せ問題として定式化される。候補者は、そのような問題を効率よく解くアルゴリズムの統一的な設計法を確立した。また、道路網やVLSI一層配線のモデルとしてよく現れる平面グラフについては、埋め込み、彩色、ハミルトン閉路、多種フローなど重要な組み合せ問題のほとんど全てに対して、効率のよいアルゴリズムの開発に成功し、それらの成果をまとめ英文の成書(添付資料)として出版しており、平面グラフアルゴリズムの唯一の英文著書として高く評価されている。また、グラフ描画アルゴリズムの研究を世界に先駆けて開始し、凸描画、直線格子描画、矩形描画、箱矩形描画などの理論を体系たてるとともに、それらを求める効率のよいアルゴリズムを開発し、グラフ描画アルゴリズムという研究分野を開拓し、毎年1回国際会議が開催されるまでに育てた。また暗号の分野においても、(k,n)しきい値法の分散情報を秘密共有システムの各構成員に複数個割り当てる複数割り当て法を発明し、その方法を用いれば、いかなるアクセス構造も実現できることを示している。このシステムは、画期的な秘密共有システムとして高く評価されている。
西関隆夫にいそかたかお東北大学大学院情報科学研究科教授離散アルゴリズムと秘密共有法に関する先駆的研究インターネット、交通網、VLSI配線などに関する多くの問題は、点およびそれらを結ぶ辺からなる”グラフ”上の組み合せ問題として定式化される。候補者は、そのような問題を効率よく解くアルゴリズムの統一的な設計法を確立した。また、道路網やVLSI一層配線のモデルとしてよく現れる平面グラフについては、埋め込み、彩色、ハミルトン閉路、多種フローなど重要な組み合せ問題のほとんど全てに対して、効率のよいアルゴリズムの開発に成功し、それらの成果をまとめ英文の成書(添付資料)として出版しており、平面グラフアルゴリズムの唯一の英文著書として高く評価されている。また、グラフ描画アルゴリズムの研究を世界に先駆けて開始し、凸描画、直線格子描画、矩形描画、箱矩形描画などの理論を体系たてるとともに、それらを求める効率のよいアルゴリズムを開発し、グラフ描画アルゴリズムという研究分野を開拓し、毎年1回国際会議が開催されるまでに育てた。また暗号の分野においても、(k,n)しきい値法の分散情報を秘密共有システムの各構成員に複数個割り当てる複数割り当て法を発明し、その方法を用いれば、いかなるアクセス構造も実現できることを示している。このシステムは、画期的な秘密共有システムとして高く評価されている。
第1回 2001年度
 大松繁おおまつしげる大阪府立大学大学院工学研究科電気・情報系専攻教授ニューロ技術による音響・画像情報を用いた官能検査システムの研究本研究は、競合型ニューラルネットワークが有している学習・識別能力を用いて、人間の官能評価に替わる高速で高精度な評価を実現する検査システムを開発し、音響、画像、匂いなどの情報に対応した知的評価システムの構築とその実用化としての工業製品の良否検査システムの開発に関する研究である。 工業製品の検査の多くは、音響データや画像データを用いた検査員の官能評価に頼っている。こ方法は人間の高度な知的情報処理を用いており、検査精度の信頼性も高い。しかし、検査員の体調や育った環境または検査員の個人差などによるバラツキが多く、日本での検査結果と中国での検査結果の著しい差異の発生事例に見られるように、製造業の国際化の進展によってこの傾向はますます顕著になっている。このため、官能評価の世界業界標準化の実現は製造業において必須であり、本研究はこれらの様々な環境に適用可能な官能検査システム開発の研究を行ったものである。
大松繁おおまつしげる大阪府立大学大学院工学研究科電気・情報系専攻教授ニューロ技術による音響・画像情報を用いた官能検査システムの研究本研究は、競合型ニューラルネットワークが有している学習・識別能力を用いて、人間の官能評価に替わる高速で高精度な評価を実現する検査システムを開発し、音響、画像、匂いなどの情報に対応した知的評価システムの構築とその実用化としての工業製品の良否検査システムの開発に関する研究である。 工業製品の検査の多くは、音響データや画像データを用いた検査員の官能評価に頼っている。こ方法は人間の高度な知的情報処理を用いており、検査精度の信頼性も高い。しかし、検査員の体調や育った環境または検査員の個人差などによるバラツキが多く、日本での検査結果と中国での検査結果の著しい差異の発生事例に見られるように、製造業の国際化の進展によってこの傾向はますます顕著になっている。このため、官能評価の世界業界標準化の実現は製造業において必須であり、本研究はこれらの様々な環境に適用可能な官能検査システム開発の研究を行ったものである。 金光義彦かねみつよしひこ奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科助教授ナノシリコンオプトエレクトロニクスの開拓的研究本研究は、ナノメートルサイズのシリコンおよびゲルマニュウム半導体微結晶からの強い可視発光を発見するとともに広範かつ系統的な研究を展開し、新しい「光るシリコン」の研究分野を開拓した。 様々な手法を用いてサイズおよび次元構造の制御されたシリコンナノ物質を作製し、それらの量子物性の解明と量子効果による新機能の発見を行った。さらに、シリコンナノ微粒子における高効率の青色エレクトロルミネセンス(EL)発光および大きな光非線形現象と光双安定性の発見、ナノシリコン薄膜を用いた光スイッチ・光演算素子や非線形伝導素子の開発等を世界に先駆けて行った。 金光氏の開拓した「ナノシリコン光エレクトロニクス」の分野は、量子論に基づいたシリコンの新しい機能創出という新しいタイプの研究成果によるものであり、その学術的・工業的意義はきわめて大きい。
金光義彦かねみつよしひこ奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科助教授ナノシリコンオプトエレクトロニクスの開拓的研究本研究は、ナノメートルサイズのシリコンおよびゲルマニュウム半導体微結晶からの強い可視発光を発見するとともに広範かつ系統的な研究を展開し、新しい「光るシリコン」の研究分野を開拓した。 様々な手法を用いてサイズおよび次元構造の制御されたシリコンナノ物質を作製し、それらの量子物性の解明と量子効果による新機能の発見を行った。さらに、シリコンナノ微粒子における高効率の青色エレクトロルミネセンス(EL)発光および大きな光非線形現象と光双安定性の発見、ナノシリコン薄膜を用いた光スイッチ・光演算素子や非線形伝導素子の開発等を世界に先駆けて行った。 金光氏の開拓した「ナノシリコン光エレクトロニクス」の分野は、量子論に基づいたシリコンの新しい機能創出という新しいタイプの研究成果によるものであり、その学術的・工業的意義はきわめて大きい。
船井研究奨励賞受賞者
第24回 2024年度
- 安藤冬希あんどうふゆき国立研究開発法人 物質・材料研究機構特別研究員3次元人工多層構造制御に基づいた量子輸送・エネルギー変換機能の開拓
 伊藤伸志いとうしんじ東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻准教授オンライン学習問題に対するアルゴリズム設計とリグレット解析
伊藤伸志いとうしんじ東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻准教授オンライン学習問題に対するアルゴリズム設計とリグレット解析 岡谷泰佑おかたにたいゆう東北大学 大学院工学研究科 ロボティクス専攻助教次世代ロボット要素技術としてのメタオプティクスの開発
岡谷泰佑おかたにたいゆう東北大学 大学院工学研究科 ロボティクス専攻助教次世代ロボット要素技術としてのメタオプティクスの開発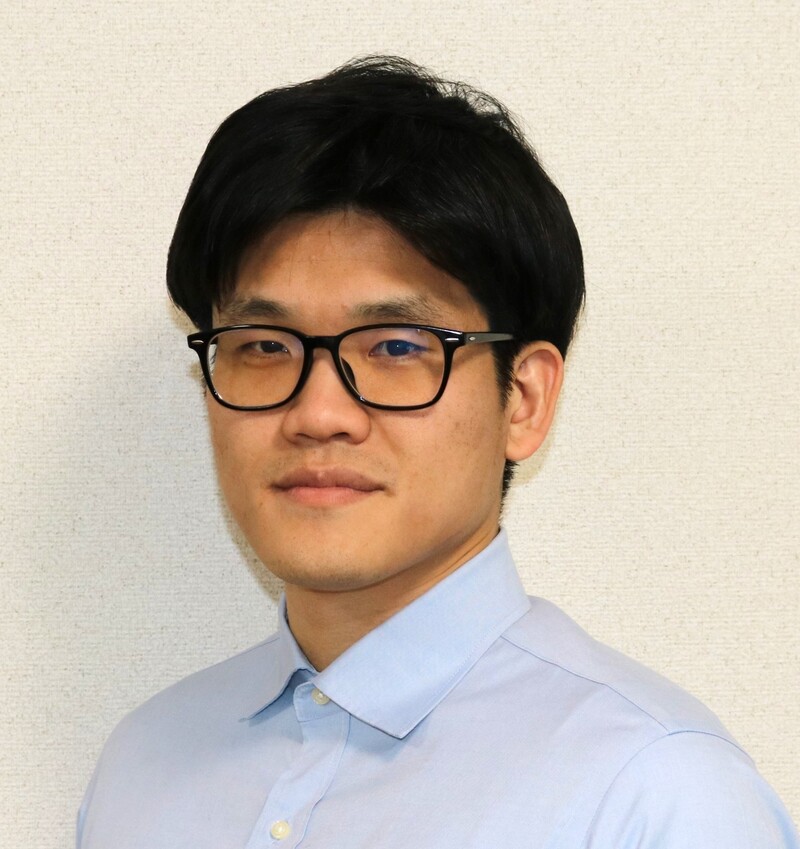 清川拓哉きよかわたくや大阪大学大学院 基礎工学研究科助教設計情報のみからの知能ロボットによる作業計画に関する研究
清川拓哉きよかわたくや大阪大学大学院 基礎工学研究科助教設計情報のみからの知能ロボットによる作業計画に関する研究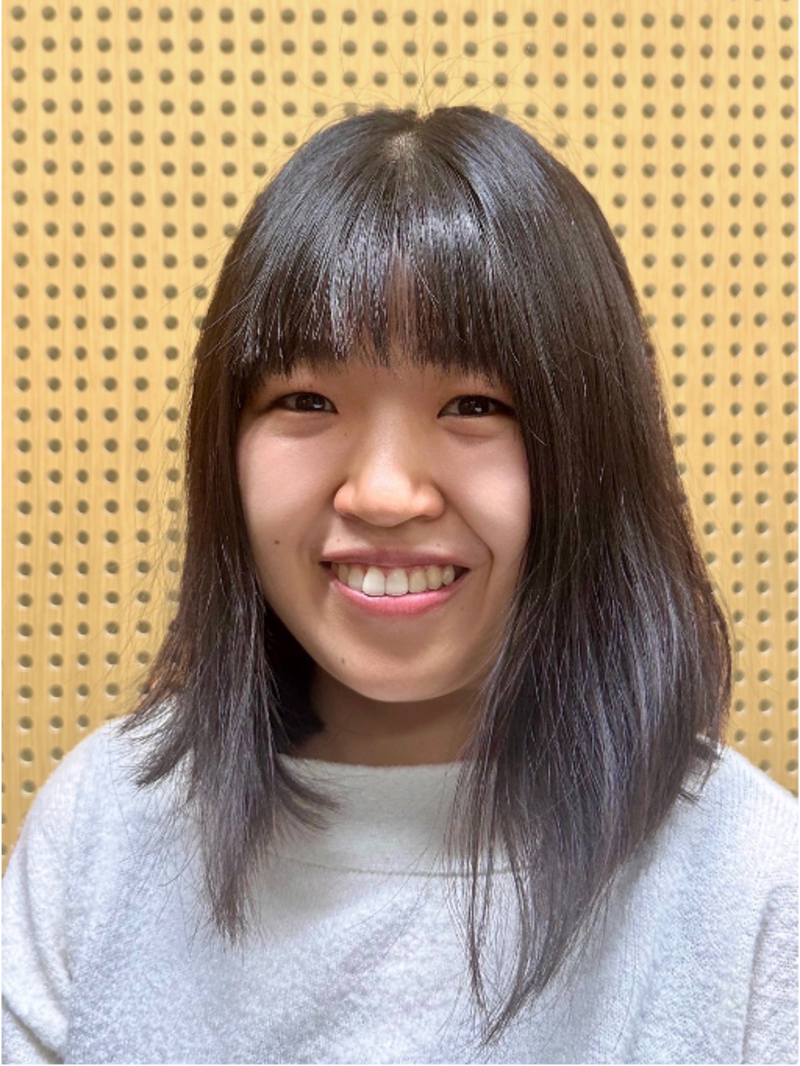 斎藤菜美子さいとうなみこ早稲田大学客員次席研究員ロボットの動作生成のためのマルチモーダル深層学習モデル構築と料理タスクへの応用
斎藤菜美子さいとうなみこ早稲田大学客員次席研究員ロボットの動作生成のためのマルチモーダル深層学習モデル構築と料理タスクへの応用 菅原朔すがわらさく国立情報学研究所助教自然言語理解システムの説明性の高い評価基盤の構築
菅原朔すがわらさく国立情報学研究所助教自然言語理解システムの説明性の高い評価基盤の構築- 土田光つちだひかる埼玉工業大学 工学部 情報システム学科講師マルチパーティ計算の理論と実装
 土肥昂尭どひたかあき国立大学法人 東北大学 電気通信研究所助教反強磁性スキルミオニクスの開拓
土肥昂尭どひたかあき国立大学法人 東北大学 電気通信研究所助教反強磁性スキルミオニクスの開拓 平井孝昌ひらいたかまさ国立研究開発法人 物質・材料研究機構研究員幾何学デザインに基づく構造エンジニアリングによる高性能熱変換・生成機能の創出
平井孝昌ひらいたかまさ国立研究開発法人 物質・材料研究機構研究員幾何学デザインに基づく構造エンジニアリングによる高性能熱変換・生成機能の創出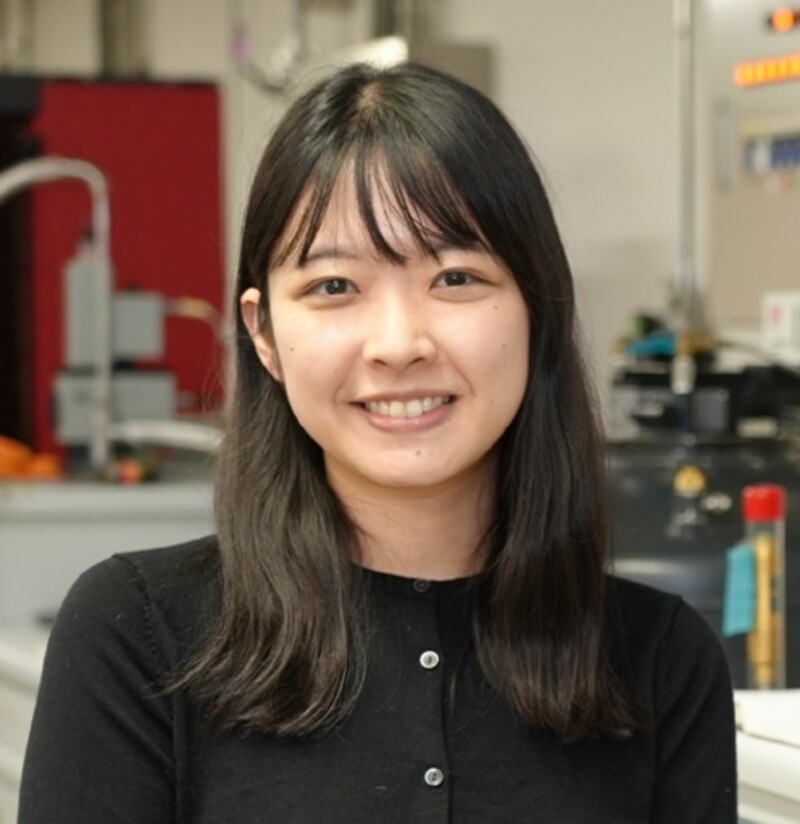 藤代有絵子ふじしろゆかこ理化学研究所 創発物性科学研究センター / 開拓研究本部ユニットリーダーナノスケール磁気構造におけるトポロジー制御と新奇電子物性の開拓
藤代有絵子ふじしろゆかこ理化学研究所 創発物性科学研究センター / 開拓研究本部ユニットリーダーナノスケール磁気構造におけるトポロジー制御と新奇電子物性の開拓 前田拓也まえだたくや東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻講師次世代パワーデバイスに向けた窒化物ワイドギャップ半導体の高電界物性の解明
前田拓也まえだたくや東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻講師次世代パワーデバイスに向けた窒化物ワイドギャップ半導体の高電界物性の解明 村松久圭むらまつひさよし広島大学 先進理工系科学研究科 機械工学プログラム准教授周期/非周期分離に基づく制御と診断
村松久圭むらまつひさよし広島大学 先進理工系科学研究科 機械工学プログラム准教授周期/非周期分離に基づく制御と診断
第23回 2023年度
 有沢洋希ありさわひろき東京大学 工学系研究科 物理工学専攻助教磁気-歪み結合系におけるスピンメカニクス現象の開拓
有沢洋希ありさわひろき東京大学 工学系研究科 物理工学専攻助教磁気-歪み結合系におけるスピンメカニクス現象の開拓 井上智好いのうえともよし広島大学大学院統合生命科学研究科日本学術振興会特別研究員PD光伝播の複数動画像をワンショット記録可能な超高速動画イメージング技術の開発と応用
井上智好いのうえともよし広島大学大学院統合生命科学研究科日本学術振興会特別研究員PD光伝播の複数動画像をワンショット記録可能な超高速動画イメージング技術の開発と応用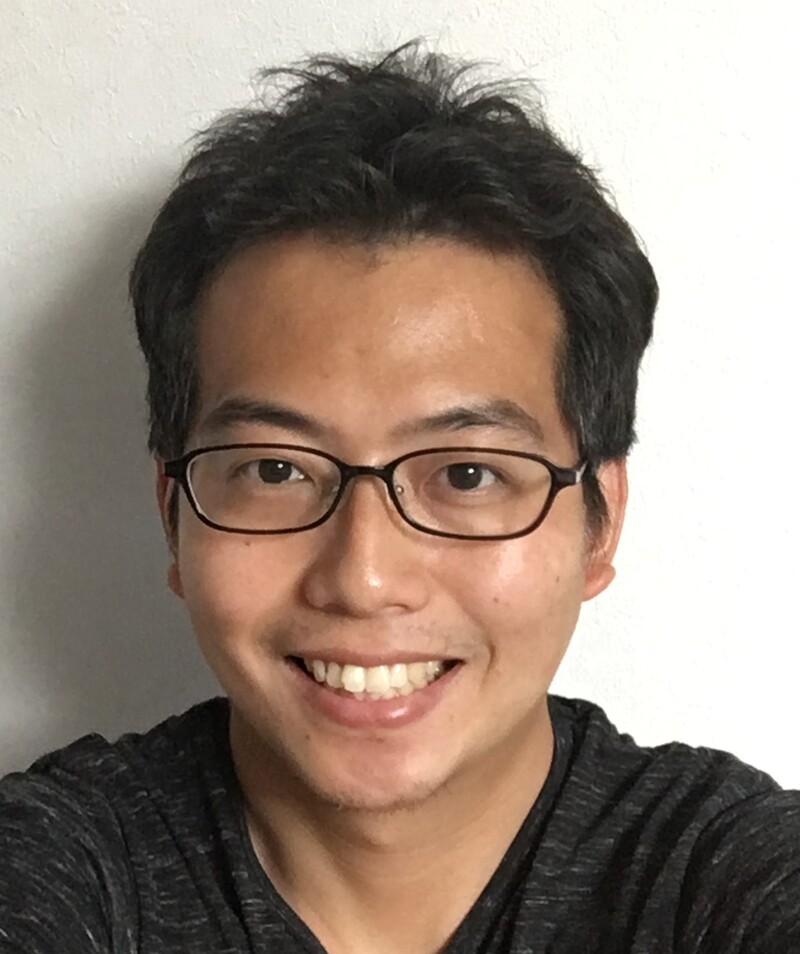 岩崎悠真いわさきゆうま国立研究開発法人 物質・材料研究機構主任研究員マテリアルズ・インフォマティクスによる新材料創製
岩崎悠真いわさきゆうま国立研究開発法人 物質・材料研究機構主任研究員マテリアルズ・インフォマティクスによる新材料創製 甚野裕明じんのひろあき宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所助教高性能な超薄型有機太陽電池を用いた電源内蔵型ウェアラブルエレクトロニクスの創出
甚野裕明じんのひろあき宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所助教高性能な超薄型有機太陽電池を用いた電源内蔵型ウェアラブルエレクトロニクスの創出 神野莉衣奈じんのりえな東京大学助教超ワイドワンドギャップ材料酸化アルミニウムガリウムの熱的安定性に関する研究
神野莉衣奈じんのりえな東京大学助教超ワイドワンドギャップ材料酸化アルミニウムガリウムの熱的安定性に関する研究 鳴海紘也なるみこうや東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻特任講師理論上任意の立体形状に自動で折れる折紙の計算製造技術とその産業応用
鳴海紘也なるみこうや東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻特任講師理論上任意の立体形状に自動で折れる折紙の計算製造技術とその産業応用 久富隆佑ひさとみりゅうすけ京都大学 化学研究所助教マグノン誘起ブリルアン散乱の量子情報処理応用及び新散乱現象の発見
久富隆佑ひさとみりゅうすけ京都大学 化学研究所助教マグノン誘起ブリルアン散乱の量子情報処理応用及び新散乱現象の発見 日比野有岐ひびのゆうき国立研究開発法人 産業技術総合研究所 新原理コンピューティング研究センター研究員スピン軌道トルク磁気メモリのためのスピンホール材料の開拓
日比野有岐ひびのゆうき国立研究開発法人 産業技術総合研究所 新原理コンピューティング研究センター研究員スピン軌道トルク磁気メモリのためのスピンホール材料の開拓 宮原大輝みやはらだいき電気通信大学助教カードベース暗号の理論と実践
宮原大輝みやはらだいき電気通信大学助教カードベース暗号の理論と実践 室賀駿むろがしゅん産業技術総合研究所主任研究員データ駆動型複合材料評価技術に関する研究
室賀駿むろがしゅん産業技術総合研究所主任研究員データ駆動型複合材料評価技術に関する研究 茂木将孝もぎまさたか東京大学 大学院工学系研究科助教磁性トポロジカル絶縁体ヘテロ構造における量子化現象とスピントロニクス機能の開拓
茂木将孝もぎまさたか東京大学 大学院工学系研究科助教磁性トポロジカル絶縁体ヘテロ構造における量子化現象とスピントロニクス機能の開拓 森秀人もりひでと大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点特任准教授 (常勤)ゲノム編集を支援するソフトウェアツール群の開発
森秀人もりひでと大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点特任准教授 (常勤)ゲノム編集を支援するソフトウェアツール群の開発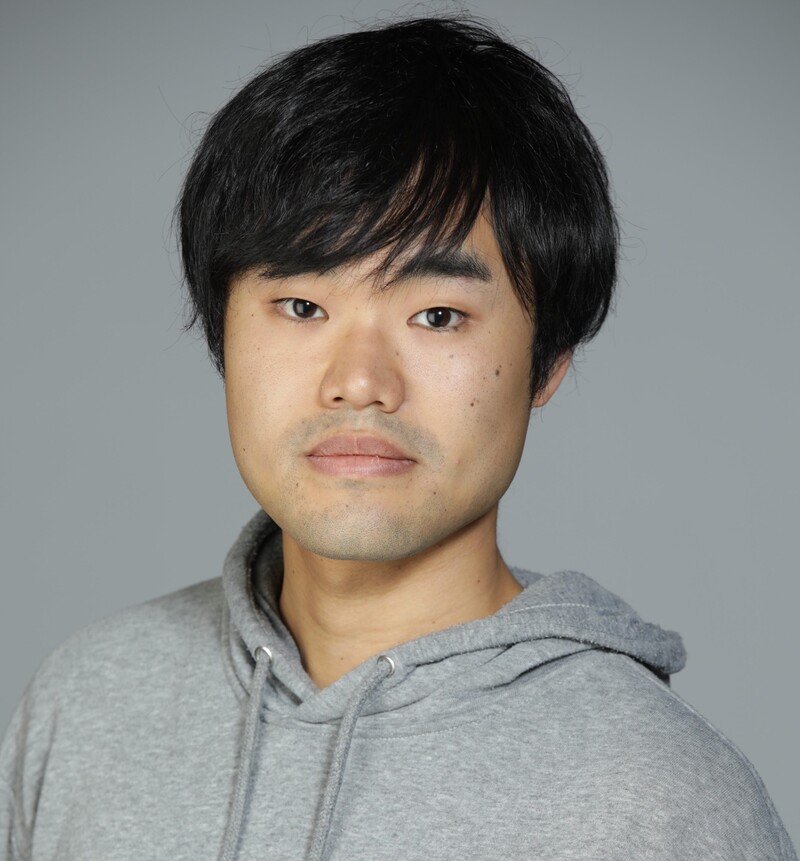 山本和樹やまもとかずき東京工業大学理学院物理学系助教開放量子多体系における超伝導と観測誘起相転移の開拓
山本和樹やまもとかずき東京工業大学理学院物理学系助教開放量子多体系における超伝導と観測誘起相転移の開拓
第22回 2022年度
 石田隆いしだたかし東京大学 大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻講師限られたデータと教師からの高信頼機械学習
石田隆いしだたかし東京大学 大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻講師限られたデータと教師からの高信頼機械学習 岡弘樹おかこうき大阪大学大学院工学研究科テニュアトラック助教高度化する情報技術を支える革新的かつ環境適合な有機電池の開発
岡弘樹おかこうき大阪大学大学院工学研究科テニュアトラック助教高度化する情報技術を支える革新的かつ環境適合な有機電池の開発- 顧玉杰こゆじえ九州大学 システム情報科学研究院助教著作権・プライバシー保護の数理的研究
 小島拓也こじまたくや東京大学大学院情報理工学系研究科助教粗粒度再構成可能ハードウェアCGRAに関する研究
小島拓也こじまたくや東京大学大学院情報理工学系研究科助教粗粒度再構成可能ハードウェアCGRAに関する研究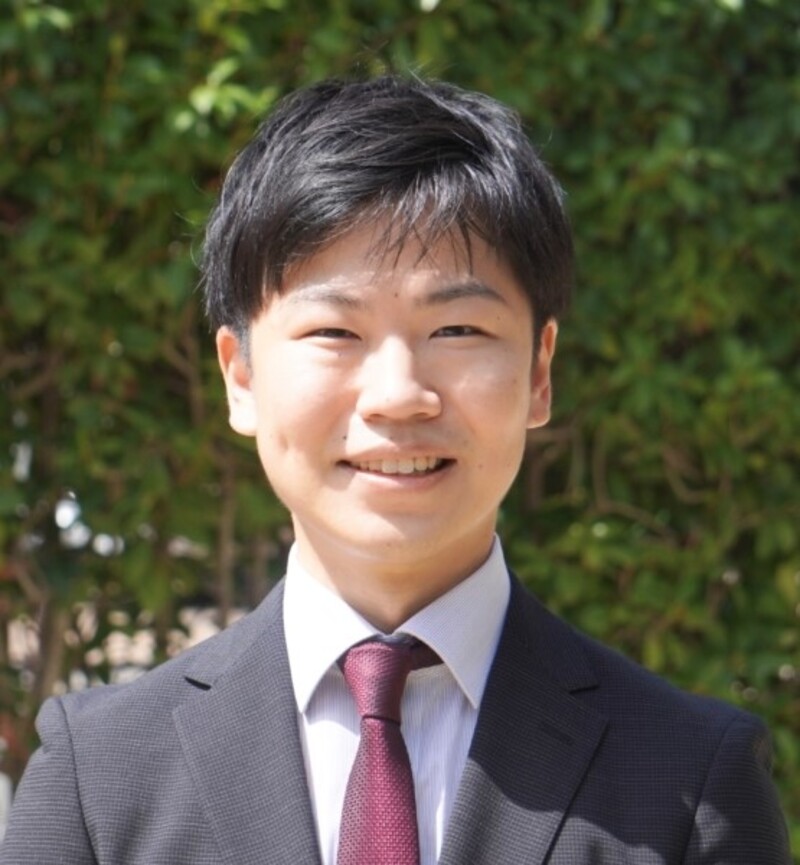 小林拓真こばやしたくま大阪大学 大学院工学研究科 物理学系専攻助教炭化珪素半導体における欠陥の制御と機能開拓
小林拓真こばやしたくま大阪大学 大学院工学研究科 物理学系専攻助教炭化珪素半導体における欠陥の制御と機能開拓 権藤詩織ごんどうしおり産業技術総合研究所研究員少数教師データで構築するデータ駆動型スピニング加工の開発
権藤詩織ごんどうしおり産業技術総合研究所研究員少数教師データで構築するデータ駆動型スピニング加工の開発 齋藤佑樹さいとうゆうき東京大学 大学院情報理工学系研究科特任助教人間と計算機の違いの最小化に基づく音声合成に関する研究
齋藤佑樹さいとうゆうき東京大学 大学院情報理工学系研究科特任助教人間と計算機の違いの最小化に基づく音声合成に関する研究 包含つつみふくむ京都大学白眉センター特定助教信頼性の高い機械学習を目指した損失関数の設計
包含つつみふくむ京都大学白眉センター特定助教信頼性の高い機械学習を目指した損失関数の設計 津村遼介つむらりょうすけ産業技術総合研究所 健康医工学研究部門研究員COVID-19患者トリアージのための遠隔肺超音波検査支援ロボットの開発
津村遼介つむらりょうすけ産業技術総合研究所 健康医工学研究部門研究員COVID-19患者トリアージのための遠隔肺超音波検査支援ロボットの開発- 中村優吾なかむらゆうご九州大学 大学院システム情報科学研究院助教IoTナッジ:生活空間に溶け込むIoTデバイスを用いた行動認識に基づく次世代ナッジの創出
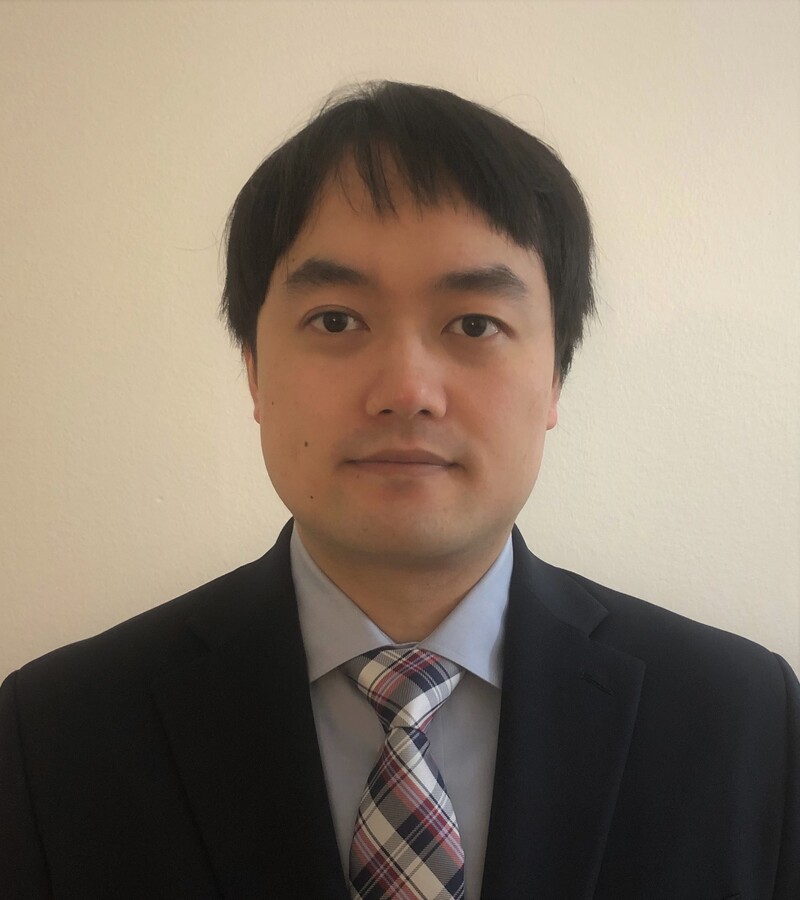 西早辰一にしはやしんいち東京工業大学 理学院物理学系助教高品質トポロジカルディラック半金属薄膜における量子化伝導の開拓
西早辰一にしはやしんいち東京工業大学 理学院物理学系助教高品質トポロジカルディラック半金属薄膜における量子化伝導の開拓 日置友智ひおきともさと東北大学材料科学高等研究所助教スピン波トモグラフィ法の開発とスピン・フォノン変換現象群の研究
日置友智ひおきともさと東北大学材料科学高等研究所助教スピン波トモグラフィ法の開発とスピン・フォノン変換現象群の研究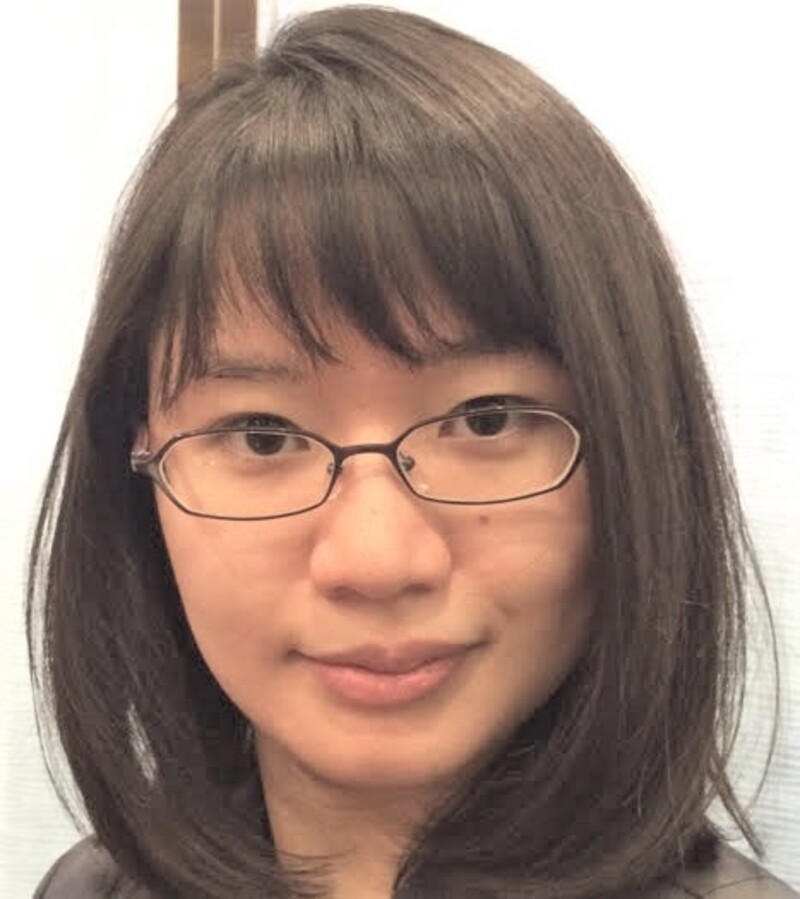 谷中瞳やなかひとみ東京大学大学院 情報理工学系研究科講師形式意味論と自然言語処理の融合による自然言語推論技術と評価ベンチマークの構築
谷中瞳やなかひとみ東京大学大学院 情報理工学系研究科講師形式意味論と自然言語処理の融合による自然言語推論技術と評価ベンチマークの構築
第21回 2021年度
 青木俊介あおきしゅんすけ国立情報学研究所助教完全自動運転のための超人間級AI運転手ソフトウェアの開発
青木俊介あおきしゅんすけ国立情報学研究所助教完全自動運転のための超人間級AI運転手ソフトウェアの開発 安達眞聡あだちまさと京都大学大学院工学研究科助教電磁気力を利用した微小粒子ハンドリング技術の開発と宇宙電磁粒体力学に関する研究
安達眞聡あだちまさと京都大学大学院工学研究科助教電磁気力を利用した微小粒子ハンドリング技術の開発と宇宙電磁粒体力学に関する研究 安部祐一あんべゆういち東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター助教多脚ロボットおよび索状ロボットのための「やわらかさ」を生かした 運動制御に関する研究
安部祐一あんべゆういち東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター助教多脚ロボットおよび索状ロボットのための「やわらかさ」を生かした 運動制御に関する研究 李成薫いそんふん東京大学大学院工学系研究科講師超柔軟かつ伸縮可能なエレクトロニクスによる極薄スキンセンサの実現
李成薫いそんふん東京大学大学院工学系研究科講師超柔軟かつ伸縮可能なエレクトロニクスによる極薄スキンセンサの実現 五十嵐歩美いがらしあゆみ東京大学准教授公平な資源配分メカニズム設計の研究
五十嵐歩美いがらしあゆみ東京大学准教授公平な資源配分メカニズム設計の研究 石部貴史いしべたかふみ大阪大学大学院基礎工学研究科助教通信センサ用新規熱電電源の実現に向けた 電子・フォノン輸送制御方法論の創成
石部貴史いしべたかふみ大阪大学大学院基礎工学研究科助教通信センサ用新規熱電電源の実現に向けた 電子・フォノン輸送制御方法論の創成 井手啓介いでけいすけ東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所助教アモルファス酸化物半導体の欠陥に関する研究と応用技術の開拓
井手啓介いでけいすけ東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所助教アモルファス酸化物半導体の欠陥に関する研究と応用技術の開拓 岩崎悟いわさきさとる大阪大学大学院情報科学研究科助教メトリックグラフ上の偏微分方程式を用いた空間解像度の高いネットワーク解析
岩崎悟いわさきさとる大阪大学大学院情報科学研究科助教メトリックグラフ上の偏微分方程式を用いた空間解像度の高いネットワーク解析 小山裕己こやまゆうき産業技術総合研究所研究員数理最適化に基づくデザイン支援手法の研究
小山裕己こやまゆうき産業技術総合研究所研究員数理最適化に基づくデザイン支援手法の研究 田中一成たなかかずあき早稲田大学理工学術院総合研究所次席研究員(研究院講師)ニューラルネットワーク技術の信頼性向上に資する精度保証付き数値計算法に関する研究
田中一成たなかかずあき早稲田大学理工学術院総合研究所次席研究員(研究院講師)ニューラルネットワーク技術の信頼性向上に資する精度保証付き数値計算法に関する研究 早矢仕晃章はやしてるあき東京大学大学院工学系研究科講師データ利活用知識基盤構築による異分野データ協創と 設計支援システムの開発と応用
早矢仕晃章はやしてるあき東京大学大学院工学系研究科講師データ利活用知識基盤構築による異分野データ協創と 設計支援システムの開発と応用 樋浦諭志ひうらさとし北海道大学大学院情報科学研究院准教授室温で動作するスピン偏極半導体の開発と光スピン変換素子への応用
樋浦諭志ひうらさとし北海道大学大学院情報科学研究院准教授室温で動作するスピン偏極半導体の開発と光スピン変換素子への応用 平原秀一ひらはらしゅういち国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系助教メタ計算量による平均時計算量の革新的な解析手法
平原秀一ひらはらしゅういち国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系助教メタ計算量による平均時計算量の革新的な解析手法 村田博雅むらたひろまさ産業技術総合研究所研究員フレキシブル全固体薄膜二次電池の実現に向けた多層グラフェンの低温合成に関する研究
村田博雅むらたひろまさ産業技術総合研究所研究員フレキシブル全固体薄膜二次電池の実現に向けた多層グラフェンの低温合成に関する研究 横内智行よこうちともゆき東京大学大学院総合文化研究科助教らせんスピン構造とスキルミオンのダイナミクスに起因した電気伝導現象の研究
横内智行よこうちともゆき東京大学大学院総合文化研究科助教らせんスピン構造とスキルミオンのダイナミクスに起因した電気伝導現象の研究
第20回 2020年度
 周偉男WeinanZhou物質・材料研究機構ポスドク研究員超高密度マイクロ波アシスト磁気記録のための 発振素子及び記録メカニズムに関する研究
周偉男WeinanZhou物質・材料研究機構ポスドク研究員超高密度マイクロ波アシスト磁気記録のための 発振素子及び記録メカニズムに関する研究 伊藤勇太いとうゆうた東京工業大学情報理工学院情報工学系助教拡張現実感技術を用いた視覚支援・機能拡張に関する研究
伊藤勇太いとうゆうた東京工業大学情報理工学院情報工学系助教拡張現実感技術を用いた視覚支援・機能拡張に関する研究 大柳洸一おおやなぎこういち岩手大学理工学部助教常磁性絶縁体における長距離スピン輸送の研究
大柳洸一おおやなぎこういち岩手大学理工学部助教常磁性絶縁体における長距離スピン輸送の研究 新竹純しんたけじゅん電気通信大学大学院情報理工学研究科助教ソフトロボティクスに向けた機能性材料の開発と応用
新竹純しんたけじゅん電気通信大学大学院情報理工学研究科助教ソフトロボティクスに向けた機能性材料の開発と応用 高木優たかぎゆう東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員統計的機械学習を用いた高次元神経活動データからの 効率的な情報抽出手法の提案
高木優たかぎゆう東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員統計的機械学習を用いた高次元神経活動データからの 効率的な情報抽出手法の提案 高道慎之介たかみちしんのすけ東京大学大学院情報理工学系研究科助教統計量補償に基づく音声合成に関する研究
高道慎之介たかみちしんのすけ東京大学大学院情報理工学系研究科助教統計量補償に基づく音声合成に関する研究 常安翔太つねやすしょうた東京工芸大学大学院工学研究科助教分子間相互作用解析による新規機能性ディスプレイデバイス開発
常安翔太つねやすしょうた東京工芸大学大学院工学研究科助教分子間相互作用解析による新規機能性ディスプレイデバイス開発 中野晃佑なかのこうすけ北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科助教革新的信頼性を有する第一原理電子状態計算の理論構築と産業応用
中野晃佑なかのこうすけ北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科助教革新的信頼性を有する第一原理電子状態計算の理論構築と産業応用 野入亮人のいりあきと理化学研究所基礎科学特別研究員半導体量子ドット中の電子スピンを用いた量子計算の基盤技術開発
野入亮人のいりあきと理化学研究所基礎科学特別研究員半導体量子ドット中の電子スピンを用いた量子計算の基盤技術開発 松久直司まつひさなおじ慶應義塾大学理工学部専任講師次世代ウェアラブルデバイスのための伸縮性電子材料・デバイス・システム
松久直司まつひさなおじ慶應義塾大学理工学部専任講師次世代ウェアラブルデバイスのための伸縮性電子材料・デバイス・システム 持山志宇もちやまじう京都大学大学院工学研究科助教電力のパケット化によるパワープロセッシングと そのモーションコントロールへの応用
持山志宇もちやまじう京都大学大学院工学研究科助教電力のパケット化によるパワープロセッシングと そのモーションコントロールへの応用 山田駿介やまだしゅんすけ東北大学大学院工学研究科助教生分解性イオンゲルの開発とそのウェラブルデバイスへの応用
山田駿介やまだしゅんすけ東北大学大学院工学研究科助教生分解性イオンゲルの開発とそのウェラブルデバイスへの応用 和佐泰明わさやすあき早稲田大学理工学術院講師複数エージェントの意思決定と集団合意形成に関する制度設計と工学的応用
和佐泰明わさやすあき早稲田大学理工学術院講師複数エージェントの意思決定と集団合意形成に関する制度設計と工学的応用
第19回 2019年度
 唐楓梟FengxiaoTang東北大学大学院情報科学研究科特任助教深層学習を用いた無線と有線ネットワーク制御に関する研究
唐楓梟FengxiaoTang東北大学大学院情報科学研究科特任助教深層学習を用いた無線と有線ネットワーク制御に関する研究 上野嶺うえのれい東北大学電気通信研究所助教ガロア体算術アルゴリズムの形式的設計手法の開発と その暗号ハードウェア設計への応用
上野嶺うえのれい東北大学電気通信研究所助教ガロア体算術アルゴリズムの形式的設計手法の開発と その暗号ハードウェア設計への応用 金子光顕かねこみつあき京都大学大学院工学研究科助教界面不整転位導入による歪み制御窒化アルミニウム結晶の成長と物性解明
金子光顕かねこみつあき京都大学大学院工学研究科助教界面不整転位導入による歪み制御窒化アルミニウム結晶の成長と物性解明 後藤穣ごとうみのり大阪大学大学院基礎工学研究科助教磁気トンネル接合における高効率熱スピン制御とマイクロ波増幅効果の発見
後藤穣ごとうみのり大阪大学大学院基礎工学研究科助教磁気トンネル接合における高効率熱スピン制御とマイクロ波増幅効果の発見 寺川達郎てらかわたつろう京都大学大学院工学研究科助教車輪式移動装置における一般化運動学モデルの構築と新メカニズムの創出
寺川達郎てらかわたつろう京都大学大学院工学研究科助教車輪式移動装置における一般化運動学モデルの構築と新メカニズムの創出 中山悠なかやまゆう東京農工大学工学研究院准教授適応的メトロアクセスネットワークに関する研究
中山悠なかやまゆう東京農工大学工学研究院准教授適応的メトロアクセスネットワークに関する研究 早川智彦はやかわともひこ東京大学大学院情報理工学系研究科助教高速移動環境下における高速モーションブラー補償技術の開発と 点検の高度化への応用
早川智彦はやかわともひこ東京大学大学院情報理工学系研究科助教高速移動環境下における高速モーションブラー補償技術の開発と 点検の高度化への応用 坂野遼平ばんのりょうへい東京工業大学情報理工学院研究員IoTに適したスケーラブルなメッセージング技術の研究
坂野遼平ばんのりょうへい東京工業大学情報理工学院研究員IoTに適したスケーラブルなメッセージング技術の研究 久野大介ひさのだいすけ大阪大学大学院工学研究科助教時間制約型ネットワークにおけるネットワークリソース制御手法に関する研究
久野大介ひさのだいすけ大阪大学大学院工学研究科助教時間制約型ネットワークにおけるネットワークリソース制御手法に関する研究 藤原邦夫ふじわらくにお大阪大学大学院工学研究科助教原子スケールの局所物理量に基づく界面輸送現象の解明に関する研究
藤原邦夫ふじわらくにお大阪大学大学院工学研究科助教原子スケールの局所物理量に基づく界面輸送現象の解明に関する研究 村松大陸むらまつだいろく東京理科大学理工学部 電気電子情報工学科助教生体と電磁波の相互作用の解明と人体通信技術への応用に関する研究
村松大陸むらまつだいろく東京理科大学理工学部 電気電子情報工学科助教生体と電磁波の相互作用の解明と人体通信技術への応用に関する研究 矢地謙太郎やじけんたろう大阪大学大学院工学研究科助教流体場のトポロジー最適化による革新的工学設計に関する研究
矢地謙太郎やじけんたろう大阪大学大学院工学研究科助教流体場のトポロジー最適化による革新的工学設計に関する研究
第18回 2018年度
 謝浩然HaoranXie北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科助教複雑流体影響下における物体のダイナミックス表現に関する研究
謝浩然HaoranXie北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科助教複雑流体影響下における物体のダイナミックス表現に関する研究 NGUYEN THANHVINHNGUYEN THANHVINH東京大学IRT研究機構特任研究員MEMS力センサを利用したマルチスケールの力計測に関する研究
NGUYEN THANHVINHNGUYEN THANHVINH東京大学IRT研究機構特任研究員MEMS力センサを利用したマルチスケールの力計測に関する研究 井手上敏也いでうえとしや東京大学大学院工学系研究科助教空間反転対称性の破れた結晶における量子流の制御技術開拓
井手上敏也いでうえとしや東京大学大学院工学系研究科助教空間反転対称性の破れた結晶における量子流の制御技術開拓 上田健太郎うえだけんたろう東京大学大学院工学系研究科助教強相関トポロジカル物質における新奇な相転移現象の開拓と量子輸送現象の解明
上田健太郎うえだけんたろう東京大学大学院工学系研究科助教強相関トポロジカル物質における新奇な相転移現象の開拓と量子輸送現象の解明 吉川貴史きっかわたかし東北大学 材料科学高等研究所、 金属材料研究所助教磁性絶縁体におけるスピンゼーベック効果と熱電変換応用に関する研究
吉川貴史きっかわたかし東北大学 材料科学高等研究所、 金属材料研究所助教磁性絶縁体におけるスピンゼーベック効果と熱電変換応用に関する研究 定本知徳さだもととものり電気通信大学大学院情報理工学研究科助教大規模システムに対する推定・制御理論
定本知徳さだもととものり電気通信大学大学院情報理工学研究科助教大規模システムに対する推定・制御理論 杉元紘也すぎもとひろや東京工業大学工学院電気電子系助教回転機の省エネルギー化を実現する革新的ベアリングレス技術に関する研究
杉元紘也すぎもとひろや東京工業大学工学院電気電子系助教回転機の省エネルギー化を実現する革新的ベアリングレス技術に関する研究 大門俊介だいもんしゅんすけ東京大学大学院工学系研究科助教動的サーモグラフィ法を用いた熱流・スピン流・電流変換現象の開拓
大門俊介だいもんしゅんすけ東京大学大学院工学系研究科助教動的サーモグラフィ法を用いた熱流・スピン流・電流変換現象の開拓 藤田高史ふじたたかふみ大阪大学産業科学研究所助教1次元量子ドット配列における単一電子スピンのコヒーレントシャトル
藤田高史ふじたたかふみ大阪大学産業科学研究所助教1次元量子ドット配列における単一電子スピンのコヒーレントシャトル 松尾貞茂まつおさだしげ東京大学大学院工学系研究科助教グラフェンおよびInAsナノ構造の接合における弾道的な電子の分配と非局所伝導の研究
松尾貞茂まつおさだしげ東京大学大学院工学系研究科助教グラフェンおよびInAsナノ構造の接合における弾道的な電子の分配と非局所伝導の研究 三浦智みうらさとし早稲田大学創造理工学部助教操作者の脳機能解析を用いた手術支援ロボットの構造最適化
三浦智みうらさとし早稲田大学創造理工学部助教操作者の脳機能解析を用いた手術支援ロボットの構造最適化 宮下令央みやしたれお東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教マーカレス・モデルレス高速計測技術と質感提示システムの開発
宮下令央みやしたれお東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教マーカレス・モデルレス高速計測技術と質感提示システムの開発 山本詠士やまもとえいじ慶應義塾大学理工学部助教分子動力学シミュレーションによる生体膜近傍における分子輸送現象に関する研究
山本詠士やまもとえいじ慶應義塾大学理工学部助教分子動力学シミュレーションによる生体膜近傍における分子輸送現象に関する研究
第17回 2017年度
 井之上直也いのうえなおや東北大学大学院情報科学研究科助教仮説推論に基づく行間理解計算モデルの構築
井之上直也いのうえなおや東北大学大学院情報科学研究科助教仮説推論に基づく行間理解計算モデルの構築 今泉允聡いまいずみまさあき情報・システム研究機構統計数理研究所日本学術振興会特別研究員(PD)現代の複雑データのための適応的解析手法の開発
今泉允聡いまいずみまさあき情報・システム研究機構統計数理研究所日本学術振興会特別研究員(PD)現代の複雑データのための適応的解析手法の開発 今西正幸いまにしまさゆき大阪大学大学院工学研究科助教低欠陥・大口径・厚膜GaN結晶を実現するハイブリット成長法の開発
今西正幸いまにしまさゆき大阪大学大学院工学研究科助教低欠陥・大口径・厚膜GaN結晶を実現するハイブリット成長法の開発 大上雅史おおうえまさひと東京工業大学情報理工学院情報工学系助教立体構造情報に基づく網羅的なタンパク質間相互作用予測技術に関する研究
大上雅史おおうえまさひと東京工業大学情報理工学院情報工学系助教立体構造情報に基づく網羅的なタンパク質間相互作用予測技術に関する研究 小山翔一こやましょういち東京大学大学院情報理工学系研究科助教音場再現のための時空間周波数領域信号変換法およびスパースモデリングによる超解像化
小山翔一こやましょういち東京大学大学院情報理工学系研究科助教音場再現のための時空間周波数領域信号変換法およびスパースモデリングによる超解像化 佐藤丈博さとうたけひろ京都大学大学院情報学研究科助教省電力かつ高信頼な光メトロ・アクセスネットワークの実現に向けた研究開発
佐藤丈博さとうたけひろ京都大学大学院情報学研究科助教省電力かつ高信頼な光メトロ・アクセスネットワークの実現に向けた研究開発 末石智大すえいしともひろ東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教高速光軸制御を用いた画像計測の研究
末石智大すえいしともひろ東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教高速光軸制御を用いた画像計測の研究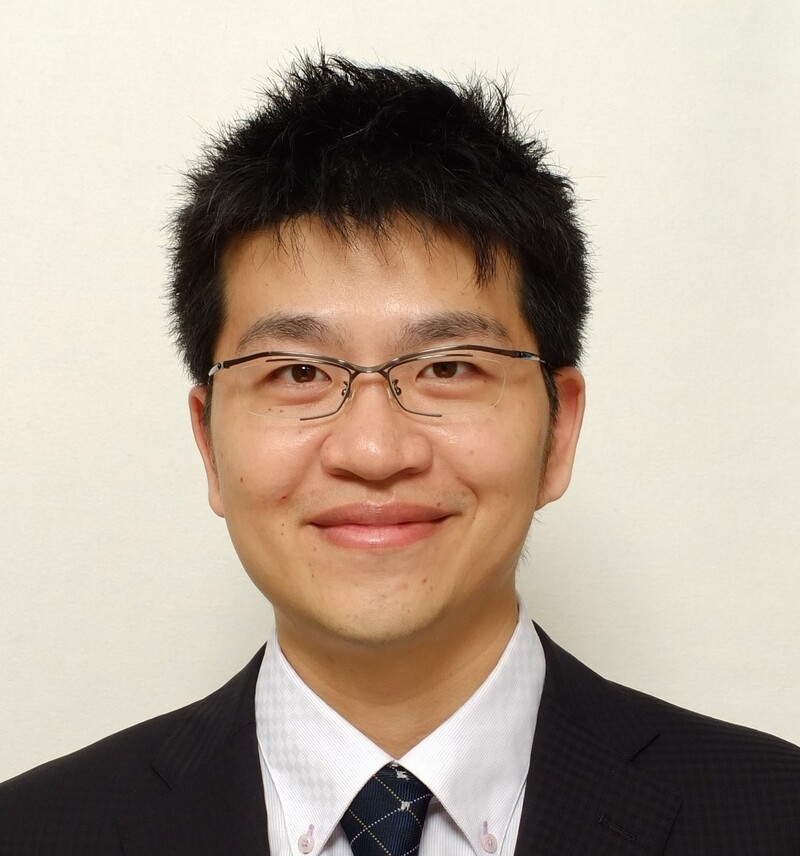 董冕雄とうめんゆう室蘭工業大学大学院工学研究科准教授IoTにおけるモデリング・解析・最適化に関する研究
董冕雄とうめんゆう室蘭工業大学大学院工学研究科准教授IoTにおけるモデリング・解析・最適化に関する研究 野崎貴裕のざきたかひろ慶應義塾大学理工学部助教人に優しい電動機駆動技術に基づく汎用双腕型ロボットの研究
野崎貴裕のざきたかひろ慶應義塾大学理工学部助教人に優しい電動機駆動技術に基づく汎用双腕型ロボットの研究 藤井浩光ふじいひろみつ東京大学大学院工学系研究科特任講師インフラ自動点検のための遠隔操作ロボットシステムと自動診断アルゴリズムの研究開発
藤井浩光ふじいひろみつ東京大学大学院工学系研究科特任講師インフラ自動点検のための遠隔操作ロボットシステムと自動診断アルゴリズムの研究開発 松井勇佑まついゆうすけ国立情報学研究所特任研究員直積量子化コードに対する探索とクラスタリング
松井勇佑まついゆうすけ国立情報学研究所特任研究員直積量子化コードに対する探索とクラスタリング 横田信英よこたのぶひで東北大学電気通信研究所助教マッハツェンダ変調器を用いた新奇光パルス制御技術の研究
横田信英よこたのぶひで東北大学電気通信研究所助教マッハツェンダ変調器を用いた新奇光パルス制御技術の研究 若生将史わかいきまさし神戸大学大学院システム情報学研究科講師通信ネットワークを含む制御システムの解析・設計
若生将史わかいきまさし神戸大学大学院システム情報学研究科講師通信ネットワークを含む制御システムの解析・設計
第16回 2016年度
 張亜ZhangYa東京大学 生産技術研究所特任助教単一自己組織化InAs量子ドットにおける量子準位構造のテラヘルツ分光に関する研究
張亜ZhangYa東京大学 生産技術研究所特任助教単一自己組織化InAs量子ドットにおける量子準位構造のテラヘルツ分光に関する研究 奥田貴史おくだたかふみ京都大学大学院工学研究科助教炭化珪素パワー半導体の物性制御およびデバイス性能の向上
奥田貴史おくだたかふみ京都大学大学院工学研究科助教炭化珪素パワー半導体の物性制御およびデバイス性能の向上 小野峻佑おのしゅんすけ東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所助教凸最適化と単調写像理論に基づく革新的画像復元技術に関する研究
小野峻佑おのしゅんすけ東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所助教凸最適化と単調写像理論に基づく革新的画像復元技術に関する研究 木山治樹きやまはるき大阪大学 産業科学研究所助教量子ホールエッジ状態-量子ドット結合系におけるスピン依存電子輸送の研究
木山治樹きやまはるき大阪大学 産業科学研究所助教量子ホールエッジ状態-量子ドット結合系におけるスピン依存電子輸送の研究 小山知弘こやまともひろ東京大学大学院工学系研究科助教強磁性ナノ細線における磁壁電流駆動に関する研究
小山知弘こやまともひろ東京大学大学院工学系研究科助教強磁性ナノ細線における磁壁電流駆動に関する研究 佐保賢志さほけんし立命館大学理工学部電子情報工学科助教マイクロドップラーレーダを軸としたセンサ融合による移動体計測の理論構築及び実証
佐保賢志さほけんし立命館大学理工学部電子情報工学科助教マイクロドップラーレーダを軸としたセンサ融合による移動体計測の理論構築及び実証 白松知世しらまつともよ東京大学 先端科学技術研究センター特任助教聴皮質における音の質感情報の神経表現の解明
白松知世しらまつともよ東京大学 先端科学技術研究センター特任助教聴皮質における音の質感情報の神経表現の解明 常木澄人つねぎすみと国立研究開発法人産業技術総合研究所 スピントロニクス研究センター研究員トンネル磁気抵抗素子の応用化研究
常木澄人つねぎすみと国立研究開発法人産業技術総合研究所 スピントロニクス研究センター研究員トンネル磁気抵抗素子の応用化研究 中島康貴なかしまやすたか九州大学大学院工学研究院機械工学部門助教理学療法士・片麻痺患者の相互作用に基づいた介助動作のモデル化とロボットの制御
中島康貴なかしまやすたか九州大学大学院工学研究院機械工学部門助教理学療法士・片麻痺患者の相互作用に基づいた介助動作のモデル化とロボットの制御 真栄城正寿まえきまさとし北海道大学大学院工学研究院助教マイクロデバイスを用いたタンパク質立体構造解析法に関する研究
真栄城正寿まえきまさとし北海道大学大学院工学研究院助教マイクロデバイスを用いたタンパク質立体構造解析法に関する研究 増田貴史ますだたかし北陸先端科学技術大学院大学助教液体シリコンの直接インプリントによるシリコン微細加工技術の創出
増田貴史ますだたかし北陸先端科学技術大学院大学助教液体シリコンの直接インプリントによるシリコン微細加工技術の創出 吉見龍太郎よしみりゅうたろう国立研究開発法人理化学研究所創発物性科学研究センター基礎科学特別研究員トポロジカル絶縁体薄膜における量子輸送現象の観測と素子構造開発
吉見龍太郎よしみりゅうたろう国立研究開発法人理化学研究所創発物性科学研究センター基礎科学特別研究員トポロジカル絶縁体薄膜における量子輸送現象の観測と素子構造開発
第15回 2015年度
 秋葉拓哉あきばたくや国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系特任助教大規模ネットワークに向けた高速アルゴリズムのための体系的アプローチの確立と実証
秋葉拓哉あきばたくや国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系特任助教大規模ネットワークに向けた高速アルゴリズムのための体系的アプローチの確立と実証 安琪あんち東京大学大学院工学系研究科特任助教筋の協同発揮に基づくヒト起立動作のモデル化とそのアシストシステムの開発
安琪あんち東京大学大学院工学系研究科特任助教筋の協同発揮に基づくヒト起立動作のモデル化とそのアシストシステムの開発 金井駿かないしゅん東北大学電気通信研究所助教強磁性体/酸化物接合における電界による磁性制御の記録素子応用
金井駿かないしゅん東北大学電気通信研究所助教強磁性体/酸化物接合における電界による磁性制御の記録素子応用 河野佑かわのゆう京都大学大学院情報学研究科特定研究員実用化に向けた代数的非線形システム制御理論の構築
河野佑かわのゆう京都大学大学院情報学研究科特定研究員実用化に向けた代数的非線形システム制御理論の構築 塩田陽一しおたよういち産業技術総合研究所スピントロニクス研究センター研究員電圧による高速磁化反転技術の研究開発
塩田陽一しおたよういち産業技術総合研究所スピントロニクス研究センター研究員電圧による高速磁化反転技術の研究開発 中野和也なかのかずや東京理科大学理学部第二部助教光情報処理に基づいた光学的暗号化イメージングの提案
中野和也なかのかずや東京理科大学理学部第二部助教光情報処理に基づいた光学的暗号化イメージングの提案 中山裕康なかやまひろやす慶應義塾大学理工学部特任助教スピン流-電流相互変換とスピンホール磁気抵抗効果に関する研究
中山裕康なかやまひろやす慶應義塾大学理工学部特任助教スピン流-電流相互変換とスピンホール磁気抵抗効果に関する研究 西尾理志にしおたかゆき京都大学大学院情報学研究科助教コンピュータビジョン技術融合による新たな通信制御の研究
西尾理志にしおたかゆき京都大学大学院情報学研究科助教コンピュータビジョン技術融合による新たな通信制御の研究 長谷川圭介はせがわけいすけ東京大学大学院新領域創成科学研究科特任助教連結型超音波フェーズドアレイによる空中触感の生成
長谷川圭介はせがわけいすけ東京大学大学院新領域創成科学研究科特任助教連結型超音波フェーズドアレイによる空中触感の生成
第14回 2014年度
 打田正輝うちだまさき東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター助教強相関遷移金属酸化物における低エネルギー電子構造の直接観測と機能応用
打田正輝うちだまさき東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター助教強相関遷移金属酸化物における低エネルギー電子構造の直接観測と機能応用 金井康かないやすし大阪大学 産業科学研究所助教InAs量子ドットにおけるスピン軌道相互作用の制御と超伝導と近藤効果の競合の解明
金井康かないやすし大阪大学 産業科学研究所助教InAs量子ドットにおけるスピン軌道相互作用の制御と超伝導と近藤効果の競合の解明 金子健太郎かねこけんたろう京都大学大学院工学研究科助教新規機能性コランダム構造酸化物混晶の作製とその物性開拓
金子健太郎かねこけんたろう京都大学大学院工学研究科助教新規機能性コランダム構造酸化物混晶の作製とその物性開拓 金崎朝子かねざきあさこ東京大学大学院情報理工学系研究科助教対象毎の負例クラスの導入による実世界からの多クラス物体認識
金崎朝子かねざきあさこ東京大学大学院情報理工学系研究科助教対象毎の負例クラスの導入による実世界からの多クラス物体認識 櫻井庸明さくらいつねあき大阪大学大学院工学研究科助教絶縁体-半導体界面における電荷キャリア輸送特性の非接触評価技術の開発
櫻井庸明さくらいつねあき大阪大学大学院工学研究科助教絶縁体-半導体界面における電荷キャリア輸送特性の非接触評価技術の開発 鈴木顕すずきあきら東北大学大学院情報科学研究科助教エネルギーを制限したしきい値回路の計算限界の解明
鈴木顕すずきあきら東北大学大学院情報科学研究科助教エネルギーを制限したしきい値回路の計算限界の解明 髙瀬英希たかせひでき京都大学大学院情報学研究科助教多階層の協調による組込みシステムの消費エネルギー最適化技術に関する研究
髙瀬英希たかせひでき京都大学大学院情報学研究科助教多階層の協調による組込みシステムの消費エネルギー最適化技術に関する研究 中川桂一なかがわけいいち東京大学大学院理学系研究科日本学術振興会特別研究員PD光学的時空間変換によるサブナノ秒シングルショットイメージング法の考案と実証
中川桂一なかがわけいいち東京大学大学院理学系研究科日本学術振興会特別研究員PD光学的時空間変換によるサブナノ秒シングルショットイメージング法の考案と実証 林浩平はやしこうへい国立情報学研究所特任助教テンソル分解を用いた関係データ解析および機械学習における新しいモデル選択法の開発
林浩平はやしこうへい国立情報学研究所特任助教テンソル分解を用いた関係データ解析および機械学習における新しいモデル選択法の開発 三輪真嗣みわしんじ大阪大学大学院基礎工学研究科准教授磁気トンネル接合を用いた高性能スピントロニクス素子の研究
三輪真嗣みわしんじ大阪大学大学院基礎工学研究科准教授磁気トンネル接合を用いた高性能スピントロニクス素子の研究 門内靖明もんないやすあき東京大学大学院新領域創成科学研究科特任助教構造化表面散乱に基づくテラヘルツ波ビーム制御
門内靖明もんないやすあき東京大学大学院新領域創成科学研究科特任助教構造化表面散乱に基づくテラヘルツ波ビーム制御 山本俊介やまもとしゅんすけ東北大学 多元物質科学研究所助教高分子を用いた有機電子デバイスの動作機構解明と新規作製手法の開発
山本俊介やまもとしゅんすけ東北大学 多元物質科学研究所助教高分子を用いた有機電子デバイスの動作機構解明と新規作製手法の開発
第13回 2013年度
 石井智いしいさとし独立行政法人 情報通信研究機構研究員金属ナノ構造を用いた光の回折と散乱の制御
石井智いしいさとし独立行政法人 情報通信研究機構研究員金属ナノ構造を用いた光の回折と散乱の制御 河村彰星かわむらあきとし東京大学大学院情報理工学系研究科助教高階計算量の応用による実数計算理論の深化
河村彰星かわむらあきとし東京大学大学院情報理工学系研究科助教高階計算量の応用による実数計算理論の深化 境野翔さかいのしょう埼玉大学 工学部助教人間支援ロボットタスクのオブジェクト指向型制御技術
境野翔さかいのしょう埼玉大学 工学部助教人間支援ロボットタスクのオブジェクト指向型制御技術 高橋英俊たかはしひでとし東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教ピエゾ抵抗型シリコン梁を利用したMEMS力センサの研究
高橋英俊たかはしひでとし東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教ピエゾ抵抗型シリコン梁を利用したMEMS力センサの研究 田原樹たはらたつき関西大学 システム理工学部助教ディジタルホログラフィによる微小生体の3次元動画像記録と瞬時多次元画像同時記録
田原樹たはらたつき関西大学 システム理工学部助教ディジタルホログラフィによる微小生体の3次元動画像記録と瞬時多次元画像同時記録 辻本学つじもとまなぶ京都大学大学院工学研究科学振特別研究員SPD超伝導小型テラヘルツ発振器の動作原理実証と広帯域チューニングの達成
辻本学つじもとまなぶ京都大学大学院工学研究科学振特別研究員SPD超伝導小型テラヘルツ発振器の動作原理実証と広帯域チューニングの達成 都甲薫とこうかおる筑波大学数理物質系准教授絶縁体上における高品質Ge薄膜の結晶成長とデバイス応用に関する研究
都甲薫とこうかおる筑波大学数理物質系准教授絶縁体上における高品質Ge薄膜の結晶成長とデバイス応用に関する研究 野田聡人のだあきひと東京大学大学院新領域創成科学研究科特任助教二次元導波路を用いた安全なワイヤレス電力伝送法の研究開発
野田聡人のだあきひと東京大学大学院新領域創成科学研究科特任助教二次元導波路を用いた安全なワイヤレス電力伝送法の研究開発 深見俊輔ふかみしゅんすけ東北大学 省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター助教高性能低消費電力論理集積回路の実現に向けた電流誘起磁壁移動デバイスの研究開発
深見俊輔ふかみしゅんすけ東北大学 省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター助教高性能低消費電力論理集積回路の実現に向けた電流誘起磁壁移動デバイスの研究開発 宮永宜典みやながのりふみ関東学院大学 理工学部専任講師超小型・高速回転用動圧気体軸受システムに関する研究
宮永宜典みやながのりふみ関東学院大学 理工学部専任講師超小型・高速回転用動圧気体軸受システムに関する研究 吉松公平よしまつこうへい東京工業大学大学院理工学研究科助教伝導性酸化物SrVO3による強相関量子化状態の創製と観測
吉松公平よしまつこうへい東京工業大学大学院理工学研究科助教伝導性酸化物SrVO3による強相関量子化状態の創製と観測 若土弘樹わかつちひろき名古屋工業大学 若手研究イノベータ養成センターテニュアトラック助教メタサーフェスを用いた新たな電磁気学的特性「波形依存性」の創出
若土弘樹わかつちひろき名古屋工業大学 若手研究イノベータ養成センターテニュアトラック助教メタサーフェスを用いた新たな電磁気学的特性「波形依存性」の創出
第12回 2012年度
 安藤岳洋あんどうたけひろ東京大学大学院医学系研究科日本学術振興会特別研究員展開型電極アレイと蛍光計測による術中心機能評価システムの開発
安藤岳洋あんどうたけひろ東京大学大学院医学系研究科日本学術振興会特別研究員展開型電極アレイと蛍光計測による術中心機能評価システムの開発 内田健一うちだけんいち国立研究開発法人物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点グループリーダースピン流・熱流・格子ダイナミクス相互作用の基礎物理及び応用技術に関する研究
内田健一うちだけんいち国立研究開発法人物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究拠点グループリーダースピン流・熱流・格子ダイナミクス相互作用の基礎物理及び応用技術に関する研究 角江崇かくえたかし千葉大学大学院工学研究科助教ホログラフィに基づく高速現象のディジタル3次元動画イメージング
角江崇かくえたかし千葉大学大学院工学研究科助教ホログラフィに基づく高速現象のディジタル3次元動画イメージング 杉浦慎哉すぎうらしんや東京農工大学大学院工学研究院准教授次世代無線通信ネットワークのためのディジタル信号処理・符号技術に関する研究
杉浦慎哉すぎうらしんや東京農工大学大学院工学研究院准教授次世代無線通信ネットワークのためのディジタル信号処理・符号技術に関する研究 瀬尾北斗せおほくと日本放送協会 放送技術研究所 撮像・記録デバイス研究部有機光導電膜を積層した垂直色分離型撮像デバイスの研究
瀬尾北斗せおほくと日本放送協会 放送技術研究所 撮像・記録デバイス研究部有機光導電膜を積層した垂直色分離型撮像デバイスの研究 寺島修てらしまおさむ名古屋大学大学院工学研究科助教MEMS技術応用による流体中の高精度な圧力情報取得と乱流現象の動力学的特性の解明
寺島修てらしまおさむ名古屋大学大学院工学研究科助教MEMS技術応用による流体中の高精度な圧力情報取得と乱流現象の動力学的特性の解明 鳴海拓志なるみたくじ東京大学大学院情報理工学系研究科助教感覚間相互作用を利用した五感インタフェースの研究
鳴海拓志なるみたくじ東京大学大学院情報理工学系研究科助教感覚間相互作用を利用した五感インタフェースの研究 橋爪絢子はしずめかずき首都大学東京 システムデザイン学部助教高齢者のICTリテラシーに影響する要因の分析
橋爪絢子はしずめかずき首都大学東京 システムデザイン学部助教高齢者のICTリテラシーに影響する要因の分析 安井隆雄やすいたかお名古屋大学大学院工学研究科准教授ナノバイオデバイスを用いた生体分子解析技術に関する研究
安井隆雄やすいたかお名古屋大学大学院工学研究科准教授ナノバイオデバイスを用いた生体分子解析技術に関する研究 吉田悠一よしだゆういち国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系特任助教制約充足問題に対する定数時間アルゴリズム
吉田悠一よしだゆういち国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系特任助教制約充足問題に対する定数時間アルゴリズム
第11回 2011年度
 崔題恩ChoiJe-Eun千葉大学大学院工学研究科JSPS外国人研究者MPT法によるマイクロ・チャンネル内の微小粒子濃度分布の3次元可視化計測
崔題恩ChoiJe-Eun千葉大学大学院工学研究科JSPS外国人研究者MPT法によるマイクロ・チャンネル内の微小粒子濃度分布の3次元可視化計測 韋冬いどうん東京大学大学院工学系研究科特任研究員多パルス列干渉による飛行時間法の開発
韋冬いどうん東京大学大学院工学系研究科特任研究員多パルス列干渉による飛行時間法の開発 大竹充おおたけみつる中央大学理工学部助教エピタキシャル磁性薄膜の形成と構造制御技術に関する研究
大竹充おおたけみつる中央大学理工学部助教エピタキシャル磁性薄膜の形成と構造制御技術に関する研究 河合吉彦かわいよしひこ日本放送協会放送技術研究所映像アーカイブ用技術の研究
河合吉彦かわいよしひこ日本放送協会放送技術研究所映像アーカイブ用技術の研究 川那子高暢かわなごたかまさ東京工業大学フロンティア研究機構産学官連携研究員希土類酸化物を用いた高誘電率絶縁膜/金属ゲートスタックMOSFETに関する研究
川那子高暢かわなごたかまさ東京工業大学フロンティア研究機構産学官連携研究員希土類酸化物を用いた高誘電率絶縁膜/金属ゲートスタックMOSFETに関する研究 小林佑輔こばやしゆうすけ東京大学大学院情報理工学系研究科助教点素パス問題に対する効率的アルゴリズムの研究
小林佑輔こばやしゆうすけ東京大学大学院情報理工学系研究科助教点素パス問題に対する効率的アルゴリズムの研究 月山陽介つきやまようすけ新潟大学工学部助教炭素系薄膜のマイクロ・ナノトライボロジー
月山陽介つきやまようすけ新潟大学工学部助教炭素系薄膜のマイクロ・ナノトライボロジー 冨中悟史とみなかさとし独立行政法人物質・材料研究機構MANA研究者超小型エレクトロニクス用オンチップ燃料電池の創製
冨中悟史とみなかさとし独立行政法人物質・材料研究機構MANA研究者超小型エレクトロニクス用オンチップ燃料電池の創製 長島一樹ながしまかずき大阪大学産業科学研究所特任助教自己組織化酸化物ナノワイヤを用いた次世代不揮発性メモリに関する研究
長島一樹ながしまかずき大阪大学産業科学研究所特任助教自己組織化酸化物ナノワイヤを用いた次世代不揮発性メモリに関する研究 橋田朋子はしだともこ早稲田大学基幹理工学部表現工学科准教授フォトクロミック材料を用いた発色型映像投影メディアの創出とその応用
橋田朋子はしだともこ早稲田大学基幹理工学部表現工学科准教授フォトクロミック材料を用いた発色型映像投影メディアの創出とその応用 藤原弘将ふじはらひろまさ独立行政法人産業技術総合研究所情報技術研究部門研究員混合音中の歌声の自動理解技術とその音楽情報検索・楽曲鑑賞支援への応用に関する研究
藤原弘将ふじはらひろまさ独立行政法人産業技術総合研究所情報技術研究部門研究員混合音中の歌声の自動理解技術とその音楽情報検索・楽曲鑑賞支援への応用に関する研究 前田佳弘まえだよしひろ名古屋工業大学大学院工学研究科特任助教転がり案内を有する位置決め機構に対する摩擦モデリングと摩擦補償による位置決め制御系の高精度化
前田佳弘まえだよしひろ名古屋工業大学大学院工学研究科特任助教転がり案内を有する位置決め機構に対する摩擦モデリングと摩擦補償による位置決め制御系の高精度化 山川雄司やまかわゆうじ東京大学生産技術研究所講師高速多指ハンドシステムを用いた柔軟物体の高速操り
山川雄司やまかわゆうじ東京大学生産技術研究所講師高速多指ハンドシステムを用いた柔軟物体の高速操り 山田崇恭やまだたかゆき京都大学大学院工学研究科助教レベルセット法に基づくトポロジー最適化法の開発
山田崇恭やまだたかゆき京都大学大学院工学研究科助教レベルセット法に基づくトポロジー最適化法の開発
第10回 2010年度
 安藤和也あんどうかずや慶應義塾大学理工学部専任講師磁化ダイナミクス及び光スピンと結合したスピン流物性に関する研究
安藤和也あんどうかずや慶應義塾大学理工学部専任講師磁化ダイナミクス及び光スピンと結合したスピン流物性に関する研究 五十嵐悠紀いがらしゆうき筑波大学大学院システム情報工学研究科日本学術振興会特別研究員3次元モデリングと力学シミュレーションを融合したインタラクティブデザイン
五十嵐悠紀いがらしゆうき筑波大学大学院システム情報工学研究科日本学術振興会特別研究員3次元モデリングと力学シミュレーションを融合したインタラクティブデザイン 内山彰うちやまあきら大阪大学大学院情報科学研究科特任助教無線ネットワークにおける端末の位置推定法に関する研究
内山彰うちやまあきら大阪大学大学院情報科学研究科特任助教無線ネットワークにおける端末の位置推定法に関する研究 岡本正吾おかもとしょうご名古屋大学大学院工学研究科助教複数触感因子の遠隔伝達技術および通信遅延が知覚へ与える影響に関する研究
岡本正吾おかもとしょうご名古屋大学大学院工学研究科助教複数触感因子の遠隔伝達技術および通信遅延が知覚へ与える影響に関する研究 金子めぐみかねこめぐみ京都大学大学院情報学研究科助教マルチキャリア・マルチリレーを用いた無線通信システムのためのリソース割り当て法
金子めぐみかねこめぐみ京都大学大学院情報学研究科助教マルチキャリア・マルチリレーを用いた無線通信システムのためのリソース割り当て法 鈴木健仁すずきたけひと東京農工大学大学院工学研究院 先端電気電子部門准教授ミリ波大面積平面波励振高効率アンテナの高速高精度電磁界解析の研究
鈴木健仁すずきたけひと東京農工大学大学院工学研究院 先端電気電子部門准教授ミリ波大面積平面波励振高効率アンテナの高速高精度電磁界解析の研究 谷川眞一たにがわしんいち京都大学数理解析研究所日本学術振興会特別研究員剛性理論の数学的基盤とその応用に関する研究
谷川眞一たにがわしんいち京都大学数理解析研究所日本学術振興会特別研究員剛性理論の数学的基盤とその応用に関する研究 新津葵一にいつきいち群馬大学大学院工学研究科助教誘導結合型積層チップ間インタフェースを用いた三次元プロセッサの開発
新津葵一にいつきいち群馬大学大学院工学研究科助教誘導結合型積層チップ間インタフェースを用いた三次元プロセッサの開発 深川弘彦ふかがわひろひこNHK放送技術研究所研究員有機半導体の電子物性解明及びフレキシブルディスプレイ用有機デバイスへの応用に関する研究
深川弘彦ふかがわひろひこNHK放送技術研究所研究員有機半導体の電子物性解明及びフレキシブルディスプレイ用有機デバイスへの応用に関する研究 松嶋徹まつしまとおる京都大学大学院工学研究科助教高速ディジタル回路基板の信号系におけるコモンモード発生メカニズムの解明とその低減法の開発
松嶋徹まつしまとおる京都大学大学院工学研究科助教高速ディジタル回路基板の信号系におけるコモンモード発生メカニズムの解明とその低減法の開発 水野洋輔みずのようすけ東京工業大学未来産業技術研究所助教光ファイバを用いた計測技術に関する研究
水野洋輔みずのようすけ東京工業大学未来産業技術研究所助教光ファイバを用いた計測技術に関する研究 南川丈夫みなみかわたけお大阪大学大学院基礎工学研究科日本学術振興会特別研究員2光子検出器を用いた高精度光パルス同期システムの開発とCARS顕微鏡への応用
南川丈夫みなみかわたけお大阪大学大学院基礎工学研究科日本学術振興会特別研究員2光子検出器を用いた高精度光パルス同期システムの開発とCARS顕微鏡への応用 森勢将雅もりいせまさのり立命館大学情報理工学部助教高品質声質制御を実現する音声合成システムの研究開発
森勢将雅もりいせまさのり立命館大学情報理工学部助教高品質声質制御を実現する音声合成システムの研究開発 渡辺峻わたなべしゅん徳島大学 知能情報工学科助教量子鍵配送プロトコルにおける通信路推定と後処理に関する研究
渡辺峻わたなべしゅん徳島大学 知能情報工学科助教量子鍵配送プロトコルにおける通信路推定と後処理に関する研究
第9回 2009年度
 井尻敬いじりたかし独立行政法人理化学研究所VCADシステム研究プログラム研究員複雑な構造を持つ生物のためのモデリングインタフェースに関する研究
井尻敬いじりたかし独立行政法人理化学研究所VCADシステム研究プログラム研究員複雑な構造を持つ生物のためのモデリングインタフェースに関する研究 稲葉一浩いなばかずひろ国立情報学研究所特別研究員階層構造データ処理プログラムの正当性検証に関する研究
稲葉一浩いなばかずひろ国立情報学研究所特別研究員階層構造データ処理プログラムの正当性検証に関する研究 筧康明かけいやすあき慶應義塾大学環境情報学部専任講師実世界指向インタラクティブメディアの創出とその応用
筧康明かけいやすあき慶應義塾大学環境情報学部専任講師実世界指向インタラクティブメディアの創出とその応用 小林亮太こばやしりょうた立命館大学情報理工学部助教神経細胞のスパイク応答を高精度に予測できるモデルの構築
小林亮太こばやしりょうた立命館大学情報理工学部助教神経細胞のスパイク応答を高精度に予測できるモデルの構築 笹田耕一ささだこういち東京大学大学院情報理工学系研究科講師プログラミング言語Ruby用処理系の開発
笹田耕一ささだこういち東京大学大学院情報理工学系研究科講師プログラミング言語Ruby用処理系の開発 谷口一徹たにぐちいってつ立命館大学理工学部電子情報デザイン学科助教組込み向けプロセッサのための設計最適化に関する研究
谷口一徹たにぐちいってつ立命館大学理工学部電子情報デザイン学科助教組込み向けプロセッサのための設計最適化に関する研究 寺尾京平てらおきょうへい香川大学工学部助教微細加工技術を応用したDNA分子操作技術に関する研究
寺尾京平てらおきょうへい香川大学工学部助教微細加工技術を応用したDNA分子操作技術に関する研究 西山大樹にしやまひろき東北大学大学院情報科学研究科准教授次世代ネットワークのための高機能通信プロトコルに関する研究
西山大樹にしやまひろき東北大学大学院情報科学研究科准教授次世代ネットワークのための高機能通信プロトコルに関する研究 蓮池隆はすいけたかし大阪大学大学院情報科学研究科助教不確実性と不確定性を融合した最適化モデルの開発と資源配分問題への応用
蓮池隆はすいけたかし大阪大学大学院情報科学研究科助教不確実性と不確定性を融合した最適化モデルの開発と資源配分問題への応用 松谷宏紀まつたにひろき東京大学大学院情報理工学系研究科特別研究員チップ内のコア間通信ネットワーク(Network-on-Chip)に関する業績
松谷宏紀まつたにひろき東京大学大学院情報理工学系研究科特別研究員チップ内のコア間通信ネットワーク(Network-on-Chip)に関する業績 宮澤高也みやざわたかや独立行政法人情報通信研究機構研究員次世代および新世代ネットワークの実現に向けた光アクセス技術に関する研究
宮澤高也みやざわたかや独立行政法人情報通信研究機構研究員次世代および新世代ネットワークの実現に向けた光アクセス技術に関する研究 吉井和佳よしいかずよし産業技術総合研究所情報技術研究部門研究員デジタル音楽配信時代における音楽鑑賞支援に関する研究
吉井和佳よしいかずよし産業技術総合研究所情報技術研究部門研究員デジタル音楽配信時代における音楽鑑賞支援に関する研究
第8回 2008年度
 伊藤健洋いとうたけひろ東北大学大学院情報科学研究科准教授需要と供給のグラフ分割問題に関する研究
伊藤健洋いとうたけひろ東北大学大学院情報科学研究科准教授需要と供給のグラフ分割問題に関する研究 井上真杉いのうえますぎ独立行政法人 情報通信研究機構新世代ネットワーク研究センター研究マネージャー異種無線混在環境におけるシームレス通信技術に関する実証的研究
井上真杉いのうえますぎ独立行政法人 情報通信研究機構新世代ネットワーク研究センター研究マネージャー異種無線混在環境におけるシームレス通信技術に関する実証的研究 岡本英二おかもとえいじ名古屋工業大学大学院工学研究科准教授ディジタル変調の高度化による高機能・高品質な通信方式の実現
岡本英二おかもとえいじ名古屋工業大学大学院工学研究科准教授ディジタル変調の高度化による高機能・高品質な通信方式の実現 久保田章亀くぼたあきひさ熊本大学大学院自然科学研究科助教次世代パワーデバイス用基板の超精密加工プロセスに関する研究
久保田章亀くぼたあきひさ熊本大学大学院自然科学研究科助教次世代パワーデバイス用基板の超精密加工プロセスに関する研究 鯉渕道紘こいぶちみちひろ国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系助教メニーコア計算プラットフォームのための省電力・超高信頼インターコネクトに関する研究
鯉渕道紘こいぶちみちひろ国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系助教メニーコア計算プラットフォームのための省電力・超高信頼インターコネクトに関する研究 齊藤普聖さいとうくにまさ北海道大学大学院情報科学研究科准教授フォトニック結晶ファイバの高度利用技術の開発に関する研究
齊藤普聖さいとうくにまさ北海道大学大学院情報科学研究科准教授フォトニック結晶ファイバの高度利用技術の開発に関する研究 杉原真すぎはらまこと豊橋技術科学大学工学部情報工学系講師組込み機器向けマルチコアCPUシステムの高信頼化に関する研究
杉原真すぎはらまこと豊橋技術科学大学工学部情報工学系講師組込み機器向けマルチコアCPUシステムの高信頼化に関する研究 鈴木孝明すずきたかあき香川大学工学部知能機械システム工学科准教授アセンブリフリー3次元露光法の基礎研究とMEMS及びμTASへの応用
鈴木孝明すずきたかあき香川大学工学部知能機械システム工学科准教授アセンブリフリー3次元露光法の基礎研究とMEMS及びμTASへの応用 蘇洲そしゅう早稲田大学理工学術院基幹理工学部助教次世代マルチメディアコンテンツ配信技術に関する研究
蘇洲そしゅう早稲田大学理工学術院基幹理工学部助教次世代マルチメディアコンテンツ配信技術に関する研究 田中正行たなかまさゆき東京工業大学大学院理工学研究科准教授超解像処理に関する研究及び業績
田中正行たなかまさゆき東京工業大学大学院理工学研究科准教授超解像処理に関する研究及び業績 浜屋宏平はまやこうへい九州大学大学院システム情報科学研究院助教強磁性単電子トランジスタにおけるスピン機能の実証
浜屋宏平はまやこうへい九州大学大学院システム情報科学研究院助教強磁性単電子トランジスタにおけるスピン機能の実証 松浦基晴まつうらもとはる電気通信大学電気通信学部情報通信工学科助教フォトニックネットワークのための光信号処理技術に関する研究
松浦基晴まつうらもとはる電気通信大学電気通信学部情報通信工学科助教フォトニックネットワークのための光信号処理技術に関する研究
第7回 2007年度
 郭嵩GooSon会津大学 コンピュータ理工学部准教授安全でエネルギー・コスト効率の優れたコミュニケーションのための無線アドホックセンサネットワークについての研究
郭嵩GooSon会津大学 コンピュータ理工学部准教授安全でエネルギー・コスト効率の優れたコミュニケーションのための無線アドホックセンサネットワークについての研究 金森義明かなもりよしあき東北大学 大学院工学研究科准教授超微細周期構造を用いた光フィルタと情報・通信用MEMSへの応用研究
金森義明かなもりよしあき東北大学 大学院工学研究科准教授超微細周期構造を用いた光フィルタと情報・通信用MEMSへの応用研究 昆陽雅司こんようまさし東北大学 大学院情報科学研究科助教触覚情報の呈示手法およびその応用技術に関する研究
昆陽雅司こんようまさし東北大学 大学院情報科学研究科助教触覚情報の呈示手法およびその応用技術に関する研究 櫻庭裕弥さくらばゆうや東北大学 金属材料研究所助教ホイスラー合金Co2MnSiを用いた強磁性トンネル接合における極高スピン偏極状態の実現
櫻庭裕弥さくらばゆうや東北大学 金属材料研究所助教ホイスラー合金Co2MnSiを用いた強磁性トンネル接合における極高スピン偏極状態の実現 住井英二郎すみいえいじろう東北大学大学院情報科学研究科准教授再帰的高階言語におけるプログラム等価性証明手法
住井英二郎すみいえいじろう東北大学大学院情報科学研究科准教授再帰的高階言語におけるプログラム等価性証明手法 関屋大雄せきやひろお千葉大学 大学院融合科学研究科助教小型・高効率電力変換機の開発およびその設計手法の確立
関屋大雄せきやひろお千葉大学 大学院融合科学研究科助教小型・高効率電力変換機の開発およびその設計手法の確立 武田朗子たけだあきこ東京工業大学 情報理工学研究科助教不確実性を考慮した意思決定法の投資決定問題への適用
武田朗子たけだあきこ東京工業大学 情報理工学研究科助教不確実性を考慮した意思決定法の投資決定問題への適用 竹延大志たけのぶたいし東北大学 金属材料研究所准教授カーボンナノチューブおよび有機材料を用いたフレキシブルエレクトロニクスの研究
竹延大志たけのぶたいし東北大学 金属材料研究所准教授カーボンナノチューブおよび有機材料を用いたフレキシブルエレクトロニクスの研究 野田啓のだけい京都大学 大学院工学研究科助教強誘電低分子薄膜の構造・物性制御および電子デバイスへの応用に関する研究
野田啓のだけい京都大学 大学院工学研究科助教強誘電低分子薄膜の構造・物性制御および電子デバイスへの応用に関する研究 萬代雅希ばんだいまさき静岡大学 情報学部 情報科学科助教アドホックネットワークの効率化および省電力化に関する研究
萬代雅希ばんだいまさき静岡大学 情報学部 情報科学科助教アドホックネットワークの効率化および省電力化に関する研究 藤原宏志ふじわらひろし京都大学 大学院情報学研究科助教次世代の高精度数値シミュレーションのための高速多倍長計算環境の開発
藤原宏志ふじわらひろし京都大学 大学院情報学研究科助教次世代の高精度数値シミュレーションのための高速多倍長計算環境の開発 鷲崎弘宜わしざきひろのり情報・システム研究機構国立情報学研究所助教再利用と品質評価による高品質・高効率ソフトウェア開発に関する研究
鷲崎弘宜わしざきひろのり情報・システム研究機構国立情報学研究所助教再利用と品質評価による高品質・高効率ソフトウェア開発に関する研究
第6回 2006年度
 伊藤浩之いとうひろゆき東京工業大学 精密工学研究所集積回路における高速信号配線技術の研究
伊藤浩之いとうひろゆき東京工業大学 精密工学研究所集積回路における高速信号配線技術の研究 落合秀樹おちあいひでき横浜国立大学大学院 工学研究院助教授周波数および電力利用効率に優れた無線通信システムの研究
落合秀樹おちあいひでき横浜国立大学大学院 工学研究院助教授周波数および電力利用効率に優れた無線通信システムの研究 金井俊光かないとしみつ横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門准教授大面積単結晶コロイドフォトニック結晶の作製に関する研究
金井俊光かないとしみつ横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門准教授大面積単結晶コロイドフォトニック結晶の作製に関する研究 五島洋行ごとうひろゆき長岡技術科学大学経営情報系助教授繰り返し実行型離散事象システムに関する最適制御方法と そのスケジューリング問題への応用
五島洋行ごとうひろゆき長岡技術科学大学経営情報系助教授繰り返し実行型離散事象システムに関する最適制御方法と そのスケジューリング問題への応用 髙田昌忠たかたまさのり静岡大学大学院理工学研究科日本学術振興会特別研究員(DC)指向性アンテナを利用したアドホックネットワークMACプロトコル
髙田昌忠たかたまさのり静岡大学大学院理工学研究科日本学術振興会特別研究員(DC)指向性アンテナを利用したアドホックネットワークMACプロトコル 高橋宏知たかはしひろかず東京大学 先端科学技術研究センター講師聴覚と音声のリハビリテーションに関する先導的研究
高橋宏知たかはしひろかず東京大学 先端科学技術研究センター講師聴覚と音声のリハビリテーションに関する先導的研究 唐山英明とうやまひであき東京大学大学院情報理工学系研究科特任助手バーチャルリアリティ技術を利用した脳-コンピュータインタフェースに関する研究
唐山英明とうやまひであき東京大学大学院情報理工学系研究科特任助手バーチャルリアリティ技術を利用した脳-コンピュータインタフェースに関する研究 平田研二ひらたけんじ長岡技術科学大学 機械系助教授拘束条件を有する制御系の解析・設計および実験検証に関する研究
平田研二ひらたけんじ長岡技術科学大学 機械系助教授拘束条件を有する制御系の解析・設計および実験検証に関する研究 FukudaMituhiroふくだみつひろ東京工業大学グローバルエッジ研究院特任助教最適化ソフトウェアと量子化学への応用
FukudaMituhiroふくだみつひろ東京工業大学グローバルエッジ研究院特任助教最適化ソフトウェアと量子化学への応用 峰野博史みねのひろし静岡大学 情報学部 情報科学科助手次世代IPネットワークにおけるセッション制御遅延の削減に関する研究
峰野博史みねのひろし静岡大学 情報学部 情報科学科助手次世代IPネットワークにおけるセッション制御遅延の削減に関する研究 室谷浩平むろたにこうへい東洋大学計算力学研究センター研究助手拡張SSAの理論と応用の確立
室谷浩平むろたにこうへい東洋大学計算力学研究センター研究助手拡張SSAの理論と応用の確立 和田雅昭わだまさあき公立はこだて未来大学助教授ホタテ養殖支援のための小型海洋観測ブイの開発
和田雅昭わだまさあき公立はこだて未来大学助教授ホタテ養殖支援のための小型海洋観測ブイの開発
第5回 2005年度
 伊藤康一いとうこういち東北大学大学院情報科学研究科助教高性能バイオメトリクス認証システムに関する研究
伊藤康一いとうこういち東北大学大学院情報科学研究科助教高性能バイオメトリクス認証システムに関する研究 内田淳史うちだあつし拓殖大学工学部 情報エレクトロニクス学科専任講師レザーカオスを用いた情報理論的セキュリティに基づく超高速暗号鍵発生方式の開発
内田淳史うちだあつし拓殖大学工学部 情報エレクトロニクス学科専任講師レザーカオスを用いた情報理論的セキュリティに基づく超高速暗号鍵発生方式の開発 内田孝紀うちだたかのり九州大学 応用力学研究所助手風力発電適地選定支援のための風況解析ソフトウエアの開発とその実用化の達成
内田孝紀うちだたかのり九州大学 応用力学研究所助手風力発電適地選定支援のための風況解析ソフトウエアの開発とその実用化の達成 梅津信二郎うめづしんじろう早稲田大学創造理工学部准教授放電場における力学とマイクロ駆動機構への応用に関する研究
梅津信二郎うめづしんじろう早稲田大学創造理工学部准教授放電場における力学とマイクロ駆動機構への応用に関する研究 桂誠一郎かつらせいいちろう慶應義塾大学理工学部准教授実世界触覚情報のマルチラテラル共有技術の研究開発
桂誠一郎かつらせいいちろう慶應義塾大学理工学部准教授実世界触覚情報のマルチラテラル共有技術の研究開発 木口賢紀きぐちたかのり東京工業大学 総合分析支援センター助手リアルタイム構造評価による酸化物エレクトロニクス界面構造制御に関する研究
木口賢紀きぐちたかのり東京工業大学 総合分析支援センター助手リアルタイム構造評価による酸化物エレクトロニクス界面構造制御に関する研究 定兼邦彦さだかねくにひこ九州大学大学院 システム情報科学研究院助教授圧縮データ構造の開発
定兼邦彦さだかねくにひこ九州大学大学院 システム情報科学研究院助教授圧縮データ構造の開発 滝沢寛之たきざわひろゆき東北大学大学院 情報科学研究科階層的並列化による大規模データクラスタリングに関する研究
滝沢寛之たきざわひろゆき東北大学大学院 情報科学研究科階層的並列化による大規模データクラスタリングに関する研究 田端利宏たばたとしひろ岡山大学大学院 自然科学研究科 産業創成工学専攻助教授資源の分離と独立化によるプログラム実行機構に関する研究
田端利宏たばたとしひろ岡山大学大学院 自然科学研究科 産業創成工学専攻助教授資源の分離と独立化によるプログラム実行機構に関する研究 燈明泰成とうみょうひろのり東北大学大学院 工学研究科助手非水浸超音波顕微鏡法に関する研究
燈明泰成とうみょうひろのり東北大学大学院 工学研究科助手非水浸超音波顕微鏡法に関する研究 古海誓一ふるみせいいち独立行政法人物質・材料研究機構主幹研究員キラルフォトニックバンド液晶によるレーザー発振制御に関する研究
古海誓一ふるみせいいち独立行政法人物質・材料研究機構主幹研究員キラルフォトニックバンド液晶によるレーザー発振制御に関する研究 本間道則ほんまみちのり秋田県立大学 システム科学技術学部助教授微細な液晶配向パターン作製法の開発と新規なアクティブ型液晶デバイスへの応用
本間道則ほんまみちのり秋田県立大学 システム科学技術学部助教授微細な液晶配向パターン作製法の開発と新規なアクティブ型液晶デバイスへの応用 和田光司わだこうじ電気通信大学 電気通信学部 電子工学科助教授高周波フィルタの特性改善手法に関する研究
和田光司わだこうじ電気通信大学 電気通信学部 電子工学科助教授高周波フィルタの特性改善手法に関する研究
第4回 2004年度
 井上振一郎いのうえしんいちろう独立行政法人 理化学研究所基礎科学特別研究員高非線形フォトニック結晶の創製とその非線形光学応用に関する研究
井上振一郎いのうえしんいちろう独立行政法人 理化学研究所基礎科学特別研究員高非線形フォトニック結晶の創製とその非線形光学応用に関する研究 岩田哲いわたてつ茨城大学 工学部 情報工学科助手メッセージ認証コードOMACの厳密な安全性解析に関する研究
岩田哲いわたてつ茨城大学 工学部 情報工学科助手メッセージ認証コードOMACの厳密な安全性解析に関する研究 大橋剛介おおはしごうすけ静岡大学工学部 電気・電子工学科助教授スケッチ画像入力による画像内容検索に関する研究
大橋剛介おおはしごうすけ静岡大学工学部 電気・電子工学科助教授スケッチ画像入力による画像内容検索に関する研究 阪本邦夫さかもとくにお島根大学 総合理工学部助教授偏光スリットを利用した新方式立体表示装置の開発に関する研究
阪本邦夫さかもとくにお島根大学 総合理工学部助教授偏光スリットを利用した新方式立体表示装置の開発に関する研究 染谷隆夫そめやたかお東京大学大学院工学系研究科准教授有機トランジスタの大面積センサ応用に関する研究
染谷隆夫そめやたかお東京大学大学院工学系研究科准教授有機トランジスタの大面積センサ応用に関する研究 高橋健志たかはしたけし早稲田大学大学院 国際情報通信研究科Proactive Handover Scheme based on Forwarding Router Discovery for Mobile IP Networks
高橋健志たかはしたけし早稲田大学大学院 国際情報通信研究科Proactive Handover Scheme based on Forwarding Router Discovery for Mobile IP Networks 中田芳樹なかたよしき九州大学大学院 システム情報科学研究院助手干渉フェムト秒レーザー加工装置の開発及び薄膜加工による新ナノマテリアルの創製に関する研究
中田芳樹なかたよしき九州大学大学院 システム情報科学研究院助手干渉フェムト秒レーザー加工装置の開発及び薄膜加工による新ナノマテリアルの創製に関する研究 西川剛樹にしかわつよき奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科ブラインド音源分離に基づくハンズフリー集音インターフェースに関する研究
西川剛樹にしかわつよき奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科ブラインド音源分離に基づくハンズフリー集音インターフェースに関する研究 前田雄介まえだゆうすけ横浜国立大学大学院工学研究院准教授柔軟に再構成可能なマルチエージェント型組立ロボットシステムの開発
前田雄介まえだゆうすけ横浜国立大学大学院工学研究院准教授柔軟に再構成可能なマルチエージェント型組立ロボットシステムの開発 水木敬明みずきたかあき東北大学 情報シナジーセンター助教授無条件に安全な秘密鍵共有に関する研究
水木敬明みずきたかあき東北大学 情報シナジーセンター助教授無条件に安全な秘密鍵共有に関する研究 水口将輝みずぐちまさき東北大学金属材料研究所准教授超巨大磁気抵抗効果材料の開発およびそのデバイス応用
水口将輝みずぐちまさき東北大学金属材料研究所准教授超巨大磁気抵抗効果材料の開発およびそのデバイス応用 森田康之もりたやすゆき九州大学 応用力学研究所助手ICデバイスの微視的熱変位・熱ひずみ分布計測のためのウェッジガラス板を用いた位相シフトモアレ干渉法の開発
森田康之もりたやすゆき九州大学 応用力学研究所助手ICデバイスの微視的熱変位・熱ひずみ分布計測のためのウェッジガラス板を用いた位相シフトモアレ干渉法の開発 廖洪恩りょうこうおん東京大学大学院 工学研究科 精密機械工学専攻特任教員Integral Videography三次元画像誘導手術支援ソフトウェア群の基礎及び展開研究
廖洪恩りょうこうおん東京大学大学院 工学研究科 精密機械工学専攻特任教員Integral Videography三次元画像誘導手術支援ソフトウェア群の基礎及び展開研究
第3回 2003年度
 粟辻安浩あわつじやすひろ京都工芸繊維大学助手光速度動画像記録・再生システムの開発
粟辻安浩あわつじやすひろ京都工芸繊維大学助手光速度動画像記録・再生システムの開発 伊藤一之いとうかずゆき岡山大学 工学部助手冗長多自由度ロボットロボットの知的制御のための人工知能に関する研究
伊藤一之いとうかずゆき岡山大学 工学部助手冗長多自由度ロボットロボットの知的制御のための人工知能に関する研究 井門俊いどしゅん愛媛大学 工学部 情報工学科講師画像の領域切り出しおよび視点視野に基づく画像符号化に関する研究
井門俊いどしゅん愛媛大学 工学部 情報工学科講師画像の領域切り出しおよび視点視野に基づく画像符号化に関する研究 岡田健一おかだけんいち東京工業大学大学院理工学研究科准教授集積回路における性能ばらつき解析に関する研究
岡田健一おかだけんいち東京工業大学大学院理工学研究科准教授集積回路における性能ばらつき解析に関する研究 高橋儀弘たかはしよしひろ長岡技術科学大学COEポストドクトラル研究員結晶化を用いた新規非線形フォトニック・ガラスの創製
高橋儀弘たかはしよしひろ長岡技術科学大学COEポストドクトラル研究員結晶化を用いた新規非線形フォトニック・ガラスの創製 谷山智康たにやまともやす東京工業大学大学院 総合理工学研究科助手人工ナノ磁性体を利用したスピンエレクトロニクスに関する研究
谷山智康たにやまともやす東京工業大学大学院 総合理工学研究科助手人工ナノ磁性体を利用したスピンエレクトロニクスに関する研究 滑川徹なめかわとおる長岡技術科学大学助教授ロバスト性と過渡応答特性を考慮したメカトロニクスシステム制御
滑川徹なめかわとおる長岡技術科学大学助教授ロバスト性と過渡応答特性を考慮したメカトロニクスシステム制御 成田浩久なりたひろひさ名古屋工業大学大学院つくり領域助手次世代の生産システムを志向した自律型・知能型工作機械の開発
成田浩久なりたひろひさ名古屋工業大学大学院つくり領域助手次世代の生産システムを志向した自律型・知能型工作機械の開発 長谷川勝はせがわまさる中部大学 工学部 電気工学科講師ロボット及びモーションコントロールを支える電動機のアドバンスド制御に関する研究
長谷川勝はせがわまさる中部大学 工学部 電気工学科講師ロボット及びモーションコントロールを支える電動機のアドバンスド制御に関する研究 平田晃正ひらたあきまさ名古屋工業大学大学院工学研究科准教授人体の影響を考慮に入れた携帯端末用アンテナの設計に関する研究
平田晃正ひらたあきまさ名古屋工業大学大学院工学研究科准教授人体の影響を考慮に入れた携帯端末用アンテナの設計に関する研究 平塚眞彦ひらつかまさひこ仙台電波工業高等専門学校助手無配線分子コンピューティングに関する研究
平塚眞彦ひらつかまさひこ仙台電波工業高等専門学校助手無配線分子コンピューティングに関する研究 藤本典幸ふじもとのりゆき大阪大学大学院 情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻助教授計算グリッド上でのパラメータ・スィープ型アプリケーションの動的スケジューリングのための近似アルゴリズムに関する研究
藤本典幸ふじもとのりゆき大阪大学大学院 情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻助教授計算グリッド上でのパラメータ・スィープ型アプリケーションの動的スケジューリングのための近似アルゴリズムに関する研究 村田貴広むらたたかひろ九州大学大学院 総合理工学研究院助手遷移金属イオンをドープした無機フォトニクスガラスに関する基礎的研究
村田貴広むらたたかひろ九州大学大学院 総合理工学研究院助手遷移金属イオンをドープした無機フォトニクスガラスに関する基礎的研究 モハマッド・サイドゥ・ラハマンもはまっどさいどぅらはまん東北大学大学院 情報科学研究科助教授グラフ描画アルゴリズムの研究
モハマッド・サイドゥ・ラハマンもはまっどさいどぅらはまん東北大学大学院 情報科学研究科助教授グラフ描画アルゴリズムの研究
第2回 2002年度
 安昌俊あんちゃんじゅん慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 情報通信メディア工学専修嘱託研究助手移動体通信システムにおける周波数有効利用に関する研究
安昌俊あんちゃんじゅん慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 情報通信メディア工学専修嘱託研究助手移動体通信システムにおける周波数有効利用に関する研究 稲邑哲也いなむらてつなり国立情報学研究所准教授統計的手法に基づくヒューマノイドロボットの行動認識、生成、抽象化の研究
稲邑哲也いなむらてつなり国立情報学研究所准教授統計的手法に基づくヒューマノイドロボットの行動認識、生成、抽象化の研究 齋藤滋規さいとうしげき東京工業大学大学院 理工学研究科 国際開発工学専攻助手次世代マイクロ実装のための微小物体マニピュレーション技術の研究
齋藤滋規さいとうしげき東京工業大学大学院 理工学研究科 国際開発工学専攻助手次世代マイクロ実装のための微小物体マニピュレーション技術の研究 佐藤孝雄さとうたかお姫路工業大学大学院 工学研究科機械系工学専攻 機械知能工学部門助手セルフチューニングPID制御
佐藤孝雄さとうたかお姫路工業大学大学院 工学研究科機械系工学専攻 機械知能工学部門助手セルフチューニングPID制御 杉山将すぎやままさし東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授知能を持った学習機械のためのモデル選択に関する研究
杉山将すぎやままさし東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授知能を持った学習機械のためのモデル選択に関する研究 手島裕詞てしまゆうじ大阪工業大学 情報科学部 情報メディア学科嘱託助手ボクセルモデルによる Mathematical Morphology の基礎研究とその応用
手島裕詞てしまゆうじ大阪工業大学 情報科学部 情報メディア学科嘱託助手ボクセルモデルによる Mathematical Morphology の基礎研究とその応用 中西義孝なかにしよしたか大分大学 工学部福祉環境工学科助教授力覚提示装置による歩行者用ナビゲーションシステムの開発
中西義孝なかにしよしたか大分大学 工学部福祉環境工学科助教授力覚提示装置による歩行者用ナビゲーションシステムの開発 野口健太郎のぐちけんたろう豊橋技術科学大学 情報工学系助手サンプリング制御に基づくディジタル信号処理の基礎研究
野口健太郎のぐちけんたろう豊橋技術科学大学 情報工学系助手サンプリング制御に基づくディジタル信号処理の基礎研究 福山敦彦ふくやまあつひこ宮崎大学 工学部材料物理工学科助手非輻射電子遷移検出による半導体中深い準位の高感度インラインプロセス評価技術の開発
福山敦彦ふくやまあつひこ宮崎大学 工学部材料物理工学科助手非輻射電子遷移検出による半導体中深い準位の高感度インラインプロセス評価技術の開発 星野准一ほしのじゅんいち筑波大学 機能工学系専任講師ビデオ映像からのデジタルヒューマンの自動生成と対話型ストーリー環境への応用
星野准一ほしのじゅんいち筑波大学 機能工学系専任講師ビデオ映像からのデジタルヒューマンの自動生成と対話型ストーリー環境への応用 牧野和久まきのかずひさ東京大学大学院情報理工学系研究科准教授離散構造を有する列挙問題に対するアルゴリズムの研究
牧野和久まきのかずひさ東京大学大学院情報理工学系研究科准教授離散構造を有する列挙問題に対するアルゴリズムの研究 水柿義直みずがきよしなお電気通信大学 電気通信学部 電子工学科助教授単一量子を制御する情報処理電子デバイスの研究
水柿義直みずがきよしなお電気通信大学 電気通信学部 電子工学科助教授単一量子を制御する情報処理電子デバイスの研究
第1回 2001年度
 大槻知明おおつきともあき東京理科大学 理工学部電気工学科講師有線・無線通信における高効率通信方式の研究
大槻知明おおつきともあき東京理科大学 理工学部電気工学科講師有線・無線通信における高効率通信方式の研究 五味健二ごみけんじ東京電機大学 工学部機械工学科助手走査型レーザー光弾性法の開発と半導体ウエハおよび光学部品の応力測定への応用
五味健二ごみけんじ東京電機大学 工学部機械工学科助手走査型レーザー光弾性法の開発と半導体ウエハおよび光学部品の応力測定への応用 斎木敏治さいきとしはる東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻講師ナノイメージング分光技術の開発とその応用分野の開拓
斎木敏治さいきとしはる東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻講師ナノイメージング分光技術の開発とその応用分野の開拓 千葉滋ちばしげる東京工業大学数理・計算科学専攻講師リフレクションを用いたプログラムの自動生成法の研究
千葉滋ちばしげる東京工業大学数理・計算科学専攻講師リフレクションを用いたプログラムの自動生成法の研究 波多伸彦はたのぶひこ東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻講師画像誘導手術支援ソフトウェア群の基礎及び展開研究
波多伸彦はたのぶひこ東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻講師画像誘導手術支援ソフトウェア群の基礎及び展開研究 桧垣博章ひがきひろあき東京電機大学 理工学部情報システム工学科助教授柔軟なコンピューターネットワークのためのプロトコルとシステムソフトウェアの研究
桧垣博章ひがきひろあき東京電機大学 理工学部情報システム工学科助教授柔軟なコンピューターネットワークのためのプロトコルとシステムソフトウェアの研究